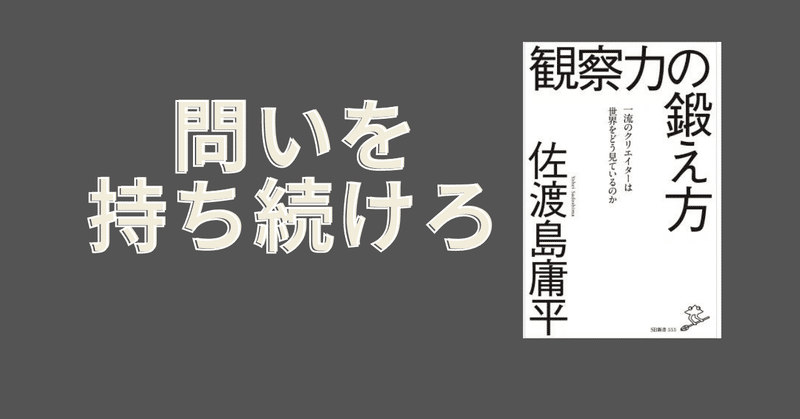
【読書録】観察力の鍛え方
概要
著者は「宇宙兄弟」や「ドラゴン桜」を担当し、社会現象を巻き起こした編集者の方です。現在は講談社を退社し、起業して作家のエージェント業を行う会社を経営しています。
本書では観察を以下のように定義しています。
・いい観察
ある主体が、物事に対して仮説を持ちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す
・悪い観察
仮説と物事の状態に差がないと感じ、分かった状態になり、仮説の更新が止まる
そんな本書から特に勉強になったと感じた部分を4つ紹介します!!
平凡すぎる問いを世紀の発見にまで導く力、それが観察力
観察力を磨くということは日常の解像度を上げることであると思います。ほかの人が疑問に思わないことについて疑問を抱くには、一つの事柄に対して複数の視点から考える必要があります。常に普通や当たり前を疑う姿勢を忘れずにしたいと感じました。
「観察」は自分で見つけたがゆえに解きたくなる「問い」とセットでモチベーションになる
この部分には強く共感しました。自分でひらめいた仮説をすぐに検証したくなるのは多くの人が経験していることであると思います。観察には仮説が伴うため、検証したくなるのだと感じました。いつでも仮説を立てるために常にあらゆることに興味を持ち、前提を疑う姿勢を忘れないようにして行きたいです。
「常識・偏見」が観察を阻む者の代表だ
年齢を重ねれば重ねるほど常識や普通という言葉のあいまいさを感じるようになりました。常識というのは主観でしかなく、他人と完全に一致することなどありません。しかしながら、自分の考え方と合わない価値観の人に出会った時にはつい使ってしまう言葉であると思います。今後、常識や普通といった言葉を使わないことを意識して行きたいですね。
分からない状態に身を置き続けるとは、思考を停止しないということ
思考を停止しないことは私も常に意識しています。どんなにいい結果が出せたとしてももっといい方法はないのか?と自分に問い続けることは技術者として最も重要な姿勢であると思います。これからも「分からない状態」であることを維持できるような仕事の進め方をしていきたいです。
さいごに
複数のヒット作を世に出して来た著者の本だけあって、非常に本質を突いた内容であると感じました。科学者とは全く異なるジャンルの人が捉える「観察」でもここまで納得感のある内容であるとは思っていなかったです。どんな分野でも一流の人はインプットの質が高いからこそアウトプットの質が高いのだとことを痛感させられました。これからもインプットとアウトプットの質を上げられるよう、noteへの投稿を続けていきたいです。
参考文献
佐渡島庸平(2021) 「観察力の鍛え方」 SBクリエイティブ株式会社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
