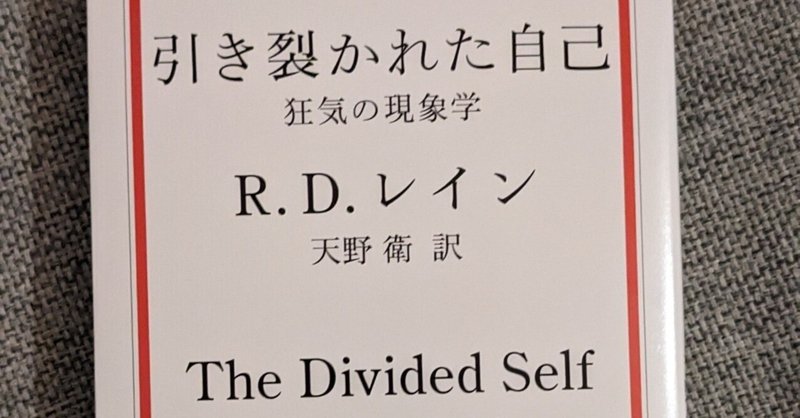
レインとカフカとシェイクスピア【引き裂かれた自己(R.D.Laing)から見るカフカの魅力】
レインの『狂気の現象学』の改訳版である、『引き裂かれた自己』天野衛訳を読んでいて目にとまった箇所があったので紹介させてほしい。
ロナルド・ディヴィッド・レインは20世紀イギリスの精神科医。
狂気を了解可能なものとして認識する論文を数々発表。統合失調症をメインに、" 人が狂気を作りだし、しかし人との関係が患者を治療する" いう寛解モデルを実際の臨床を通して世間に伝えた。
レインの研究はざっくり言えば、
(自己/肉体) ⇆ 他者 【つまり正常】
自己 ⇆ (肉体=他者) 【異常とされる】
この過程を行き来する過程で何が起こっているのか、実は完全に説明できるのではないのか。
というものである。
そのレインが本書では珍しく、文芸評論家のライオネル・トリリングを引用し文学と狂気の関係について論じている。
シェイクスピアもカフカも、残酷な不条理を被るという点で作品は似ており、「世は牢獄」という描写に変わりはない。
しかし、カフカがあれほどにも強烈な印象を与えるのは何故だろう。それは以下の通りである。
事実、シェイクスピアの不快の描写ほど残酷なものはない。しかし、シェイクスピアの牢獄では、囚人たちはカフカの場合よりはずっとましである。
つまり彼の名将や王様や恋人や道化師は、死ぬまで生きており完全である。
シェイクスピアといえば悲劇。
子供っぽい神々の遊びに巻き込まれる人間たち。
残酷で、不条理なものごとが降りかかり、破滅に向かう。
カフカについてはあの、『変身』を思い浮かべてもらうだけで充分だろう。
起きたら虫になっていた。家族や人々は自分を怖がり、だんだんすべてが虫そのものになる。
つまりこういうことだ。
一方カフカにおいては、判決が執行されるはるか以前に、あるいは悪意の訴訟手続が起こされる以前ですら、被告に対して何か恐ろしいことが執行されてしまっているのだ。
それがどういうことか、我々は知っている。
それはつまり、「自己の喪失」というのである。
シェイクスピアの描く人物は、いかに疑惑にまどい 葛藤に引き裂かれようとも、明らかに現実的な生きた完全なものとして自己を経験できる人間である。
しかしカフカにおいてはそうではない。事実、このような確信なしに生きるとはどういうことなのかを伝えようとする努力こそ、現代の多くの作家、芸術家の作品を 特徴づけているように思われる。
生きていることを実感できない生。
なんて分かりやすく、興味深い。
本書でレインはこういった説明を駆使し、" 自己喪失への過度の恐怖が、自己喪失へつながる" と論じている。
ウィキペディアなんかでカフカを調べてみると、彼の『変身』とカミュの『ペスト』が不条理文学として同系分類されている。
レインの視点で見れば、カミュのペストはあきらかにシェイクスピアの悲劇と同じ構造である。
つまりこの不条理文学というのは、まったく異なった性質を持ち、カフカの描く死はさらに恐ろしい、まったく異なったものであると言えるだろう。
結論、この恐ろしい自己喪失の構造がカフカの強烈なイメージとをさらに強調しているといえる。
恐怖を抱いている対象は同時にいつも魅力的なのだ。
言いかえれば、カフカの小説は人類が最も恐れた、「死」のかたちを書いたものと言えるだろう。
ナチス統治下の収容所やソ連の収容所で囚人はいつも、どうしたら自己を喪失できるか論じあっていたらしい。
自己を殺して苦しみから解放される手はずは、肉体が死んでいない彼らに残された唯一の解放の方法で、誰もがそれを望んでいた。
(なにかで読んだ一説だったけど何だったかなー)
人類最大の恐怖を欲する場面も歴史にはあるのだ。
現にこうしてそれらの記録を読み漁り嗜んでいる現代のわたしたちがいる。
【余談】
引っ越しを終え、ネットが通りました。
そういえば光文社古典新訳文庫でカフカの新訳がいくつか出版されたなぁ。
次の給料日には日本のアマゾンでほしい本をいくつか買う予定。
誕生日に叔母に買ってもらった、フーコーの『監獄の誕生』新装版を読んでいます。
彷彿されるのはジュネとユゴー。フランスの死刑がきらびやかで、憧れで、誰もが羨むエンターテインメントだったあの時代のフランス文学が好き。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
