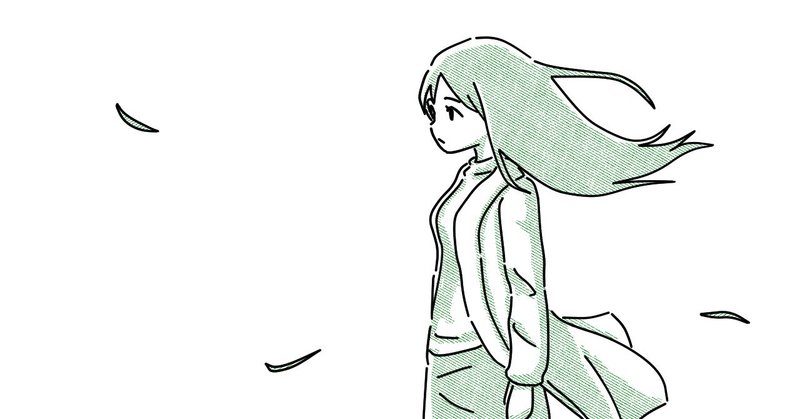
心をさらして
酒瓶を手にしたその人が私の隣に座ると、静かに晩酌を始めた。
居心地が悪くなる前に立ち去ろうとして「そんなに慌てないでさ、一緒に飲もうよ」そっと手に渡されたお猪口に日本酒を注がれた。
「かんぱーい」
甘い声が響くこともなく停滞するままに落ちて、それは日本酒に染み渡ったかのように思えた。
特に、何か話しをするわけではなかった。静かに酒を飲み、私のお猪口の中がなくなるタイミングでそっと注ぐ。いらない、とも言えずに、付き合った。
月は瞼を閉じるような目つきで私たちを見下ろして、夢の続きを眺めるようにあたり一面は闇に包まれ、星がところどころ輝く。そのひとつひとつがゆりかごを思わせて、どんな夢を見ているのか、気になった。いや、私たちも、同じように夢を見ているのかもしれない。それとも、夢を見たくて、酔いしれたいのかもしれない。少なくとも、この人はーー
「わたしは別に、夢なんて見たくないよ」
ぐい お猪口を一気に傾けて、再び注ぐ。にやり 私を見つめる瞳が薄く濁り、それでも奥には輝きも感じられ、凝視しながら動けない。
いつの間にか口から漏れていた言葉に気を悪くするでもなく、それ以上何を言うでもなかった。
ときおり、こうして思考が心の内ではなく言語を介して口から漏れ出してしまうことがある。「正直ねぇ」疎ましくも思い、何も考えないほうがよい、というのも、そこから生まれたものだった。それでも、何も考えないで生きるなんて、そうできるものではない。何も考えていない、と言いつつ、それは単に計画性がないだけで、何かしら思考している人がいるように、心を無にするなんて、どんな達人ならできることであろう。
お酒のせいもあるのか、私は余計に饒舌になってしまっているような気もした。やっぱり帰ろう、と思い立ち「そんなこと、あるのねぇ」礼を言ってお猪口を渡そうとする前に、その人から話しかけられた。
「おもしろいわねぇ。心、というものが、見えてくるようじゃない?」
何のことかわからずに、私は口をつぐむ。その人は笑って、私が差し出したように見えたお猪口に酒を入れた。
すなおにそれを受けた私は、ゆれる酒の水面を見ながら、押し黙る。いや、これまでも、口をつぐんでいたはずだった。
耳から入る言葉を受けても、私自身の声が耳に届くことはなかった。けれど、私の「声」か「言葉」は相手の耳に届いているらしい。それとも
「心に、聞こえているかもしれないね」
その人は にかっ きれいな笑みを見せると、再び盃でも交わすようにお猪口を向けてくる。反射的にそれに合わせると、
「どうして、でしょう、ね。本当、嫌に、なります」
言葉に、してみた。
本当に、嫌になる。どうしてだろう、と、いつも、思う。
それでも、どうしようもなくて、どうすることもできなくて、諦めてしまう。諦めてしまっていた。
もう、疲れてしまって、疲れて、しまって。途方に暮れるくらい、嫌になって。ずっと、悩んでいるけれど、それでも、何にもできなくて。なんで、こんなふうに、考えていることなのに、それが滲み出てしまうのだろう。考えるな、ということなのだろうか。考えなければ、何にも思わなければ、何も感じなければ、こんなことにはならないのかしら。そんなこと、できない。私は、私だって、生きているのだから。からっぽになりたいけれど、こんなこと感じたくないから、無になりたいけれど。それでも、私は、生きて、いる、から。達人ではない、とか、そんなことではない。そんなこと、本当は、望んでもいない。自然に、いたい。自然に、ありたい。どうしたら、いい、のだろう。
それが口からこぼれているのか、思考がこぼれているのか、わからなかった。それでも、その人には届いていたのだろう。私は、気がつけば、抱きしめられていた。抱きしめられて、頭を撫でられて、力いっぱい、ぎゅーって、された。
「あなたこそ、自然なのだと思う。裏のない、忖度のない、自然なかかわりが、できているんだと。それは、たしかに、怖いこと、心が見えてしまうようで、怖い、よね。でも、本当は、それが自然なんだよ。裏のない、自然なんだよ」
ごめんね、つらい、のにね。
私は瞼を閉じて、そのぬくもりにもたれかかった。身を任せられるそれは安心そのもので、あぁ、こうやって、温かいものに包まれながらだったらいいのになぁ、と。そう、感じた。
そうではないから、それだけではないから。私は、つらい、のかもしれない。だから、思考が漏れてしまうのが、怖い、のだと思う。
心を曝け出しても、いいと思える。そんな、関係。それは、どれだけ尊いことだろう。
抱きしめていた腕の力がゆるむと、その人はじっと私の瞳を見つめた。酒の残る、少しのゆらぎと輝き。それが輝いて見えるのは、たぶん、澄んでいるから、なのだろう。純粋な、瞳。酒でゆらいでいたとしても、その奥に光るものは、覆われない。
夢なんて、見たくない、とその人は言っていた。
あぁ、そうなんだ。
私の悩みが、私以外の人に、本当のところわからないように、誰の悩みも、その人以外、本当のところはわからない。同じ痛みなんてないし、同じ感じ方なんてない。それに、どう感じているかなんて、推し量る以外にはないのだから。
同じように、別のことで悩んでいても、それでも、こうして話し合える。寄り添え合える。互いが、互いの、救いになりうる。
その人ははにかみながら、恥ずかしそうにしている。それを見て、私も何だか、頬が熱い。うん、きっと、酔いが回ってきたに違いない。
「うん、そうだよ。そうしておこう」
それを聞いて、久しぶりに、たぶん、本当に、久しぶりに、自然に、笑った気がした。ううん。笑い合えた、気がした。
そうして、その人はお猪口を掲げると、
「かんぱーい」
と、一緒に、声を、出した。
いつも、ありがとうございます。 何か少しでも、感じるものがありましたら幸いです。
