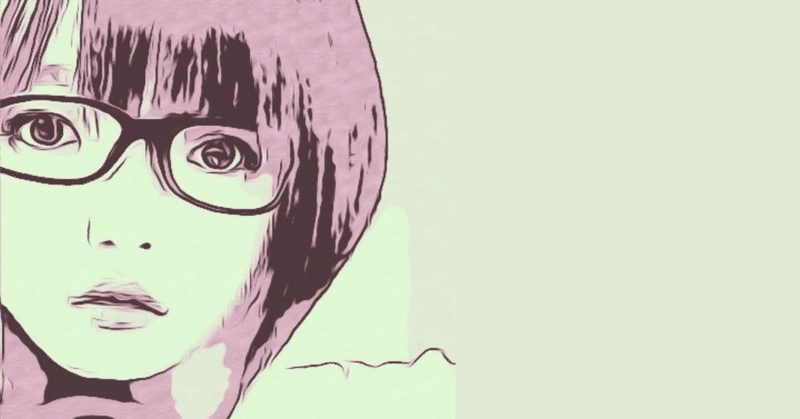
仮面をつけるということ
私たちは何らかの仕方で仮面をつけてコミュニケーションをすることがある。実際に、私の知っている哲学者のなかでジル・ドゥルーズという人は、役者という存在について言及することで、私たちが役を演じている時にはどのような状態にあるのかということについて思考を促している。
コメディアンが演ずるのは、決して人物ではなく、出来事の要素が構成するテーマ(複雑なテーマあるいは意味)、つまり、個体と人格の限界から実効的に解放されて交流し合う特異性が構成するテーマである。役者は、非人称的で前個体的な役割に自らを開くために、常にまだ分割可能な瞬間へ、その人格性のすべてを差し出してしまう。だから、役者は別の役を演ずる役を演ずる状態にあるわけである。
私たちはこのような状態に関する思考をすることができる。実際に自分は何らかの役割を演じる時は、このように個体と人格という2つのカテゴリーから独立したような特異性を表現するそうした役割に対して自らを開くのである。それは「非人称的で前個体的な役割」というように言われるものでもある。私はこの問題に関してこれ以上言うことは難しいのかもしれない。
しかし、この内容に関して前置きとすることで、私が感じている違和感について報告したい。
それは、自分は「ありのままの自分」というものを持っているはずなのだが、それは心理学的にはtrue selfと言うことのできるものなのだが、それをなかなか表現することができないということである。
私が読んだ漫画のなかで、『明日、私は誰かのカノジョ』というものがあり、そこでレンタル彼女をしている雪は、ある場面において(これはネタバレになるのでネタバレな苦手な方はこの部分は飛ばしてください)客の人から告白を受けるのであるが、彼女がその人に見せているのは「レンタル彼女」としての雪であって、「ありのままの私」としての雪ではないという理由で断るのである。そうしたことがなぜ理由として言われるのかというと、彼女はもちろんその客に接する時は「レンタル彼女」としてのペルソナをつけてコミュニケーションしているからである。
その「レンタル彼女」としてのペルソナというものが、実際には「前個体的で非人称的な役割」なのかもしれない。
その役割というものが、その客にとってはまさに求めている役割なのであった。しかしおそらくその「前個体的で非人称的な役割」というのは、実際にその雪という個体からは離れたところにあるあるいはその個体が本来は実現するポテンシャルを持っていながらも何らかの事情で表現していないポテンシャルを「レンタル彼女」という役割において表現している、いわば「アルターエゴ」としての雪がそこに出てきているのである。
「アルターエゴ」、それは必ずしも悪いものではないかもしれない。しかし、私は例えば次の記事のなかで「アルターエゴ」について読んだのだが、こうした「アルターエゴ」を通してのコミュニケーションにおいては、実際にはそこで抑圧された「エゴ」があるのかもしれない、そうしたことについてはもちろん思いを馳せるが、先ほどのドゥルーズへの言及をここでもう一度想起するのであれば、私たちは常に「前個体的で非人称的な役割」に自らを開く可能性を、あるいは役者になる可能性を秘めていると思われる。
私には葛藤がある。そうした役割を演じる時、どうしても「エゴ」との間に乖離が生じるからだ。それは、例えば、感情労働をする際に、表出している態度と本心が乖離してしまう現象が起きることと関連しているのかもしれない。
私たちはまた常に自己呈示をしながら生きていると思われるが、そこで自己呈示することに失敗するケースももちろんあるだろう。
つまり「より良く見せる」のではなく「より悪く見せる」ことになってしまったというケースである。
それは実際に起こり得ることである。
「より悪く見せる」というのはいわば自分を黒塗りしてしまうことでもある。普通にはホワイトウォッシングと言ったように、自分を白く塗って呈示することはあるかもしれないが、そこで黒く塗って呈示してしまうことはあまりないと思われる。
しかし、実際に黒く塗って呈示してしまうそうしたケースもあるだろう。
私たちは「エゴ」というものをそのまま社会空間において見せることはできないのだろうか。
しかし、私には疑問がある。私は時々人が独り言を言っているのを公共的なスペースで聞くことがあるのだが、私自身は公共空間で言えるような独り言というのを持っていない(に等しい)。私自身はおそらく何らかの役割を演じている状態で、つまり「非人称的で前個体的な役割」を演じている状態で社会空間を生きているのであり、自分の個体的な自己というものをその場で表出することが許されていないそうしたケースになる。
その意味で、私自身の心は非常に壊れているのかもしれない。
そこまで壊れた心を持っていて、人には言えないような独り言を自分は潜在的には発することができてしまう、もちろんここにある記事のなかでそれぞれの記事ごとに書き方を変えているし、また自分自身医者とコミュニケーションを取り、今回については一応「話しながら書く」ということも「私がそれを通じてより混乱することがないのであれば」良いという許可をもらったうえでしていることであり、今回についてはその許可が降りた上でのnoteの執筆ということになっている。
私自身はこうした仕方で言葉を書いているけれども、もちろん医者による許可がなければ書いていなかっただろう。
私自身はここに書く記事は自分に対する思索をいわばホワイトボックスのようにして見せる(もちろんそこでもすべてを見せているわけではないと思われるが)ことを一応趣旨としており、精神疾患を抱えている自分が、その精神疾患との格闘のなかで実際にどのようにして文章を書いたら良いのか、文章を通したテキストコミュニケーションはどのようにしたら取れるのかということを自分なりになんとか体得しようとして、書いているものになってくる。私は時々昔のブログやウェブ日記が主流だった頃を懐かしく思う。私はその頃のウェブももちろん知っているが、そこには「いいね」に相当するものがなかったと思う。「いいね」がないそうしたウェブにおいて、自分を「良く見せる」ということとは少し違った仕方での「自己のエクリチュール」があったのかもしれない。
もちろん、私自身は私の内面を抱えており、その内面に基づいて書くことが誠実の証ではないかと考えたことはあったのだが(そしてその言葉に関して誠実という言葉を頂いたことももちろんあった)、私は現在、いつかこのnoteでも出した「暗い自我」に基づいて言語化できない環境にあり、それは自分の暗い部分を社会平面において登記できないということでもある。
それは、いつか言及した『ニーア・レプリカント』というゲームの世界のようである。これも前に言及したはずであるが、実際ネタバレになってしまうのであるが、レプリカント体とゲシュタルト体という仕方で自分が分裂して世界に存在してしまうそうした話であった。
私は前回のブログでアルタと莉子という名前を出した。現時点においてアルタというアイデンティティに関しては主人格であった時間が長かったのであるが、現在それを社会空間において表出させることが難しい状況になっており、主人格であるにもかかわらず、出ることのできる時間はとても少ない。
主人格と基本人格、それをとりあえず、アルタと莉子としている。いつかここでも論じた「植民地化された魂」と「脱植民地化された魂」という組み合わせは、それぞれ基本人格と主人格という風に対応することができるかもしれない。
私がいつか言及した『女子高生に殺されたい』という映画のなかでも二重人格の女子生徒が登場していた。
私は分人主義という言葉についてももちろんこのブログで言及しているが、私が感じている解離の問題、また内面のいわば亢進していく思考に関して精神疾患という観点から考えた方が良いかもしれないと私は思ったのであった。
人は文脈において何かを理解しているのかもしれないし、また自分自身、とりあえず基本人格と主人格と書いたが、実際にはそれ以上にも人格があるように感じているという事実、
私の単なる自分用のメモのなかでは次のように人格を分けていた。
1、ユキ ♀ 基本人格 高校までの自分を延長として形成されている
2、アルタ ♂ 主人格 大学および大学院の学業のなかで培われた自分(元はと言えば、家のなかの自分を延長としている)
3、ハナ ♀ 交代人格 内面的にもっとも思考している。しかし、自分のことをもしかしたら人前に言えないようなことを考えている自分と思っている節がある
4、セラ ♀ 交代人格 もっとも感覚的に鋭い。ただいわゆる破壊者人格と言われる(確かこれは町沢静夫さんの本で読んだ)要素を持ち合わせている
こうした4人格に自分を分けるということを自分ではすでにしている。
こうした解離性障害を持っている自分というものを人と共有できる空間において提示することは難しかったが、今回なんとかしてみた。
そして「非人称的で前個体的な役割」という点について、おそらく私にとってエゴと言えば、2か3のことを意味しており、より3はエゴの要素が強いが、現在は1でおそらく語っていて、その1の自分においてほとんどエゴの要素はないかもしれない。
ただ内面において思考することはもちろんそれは咎められることではない。
3の自分は色々考えている。
考えることはもちろん「思想の自由」であり、内面において何かを考える権利が私たちにはあるし(この理解が怪しければ指摘してほしい)、私たちは何かを思うそうした「余白としての自由」があるとは思っている。
私たちは実際には何かを思い、何かを社会平面において言語化していく。
私は承認というものはもうこれまでのようにはもらえないと心のどこかで思っている。
しかし、これを社会平面に登記していくことには意味があると思っている。
それは、学部の時の指導教員の人の思考の影響である。
今回のnoteはここまでにします。
また考察を続けたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
