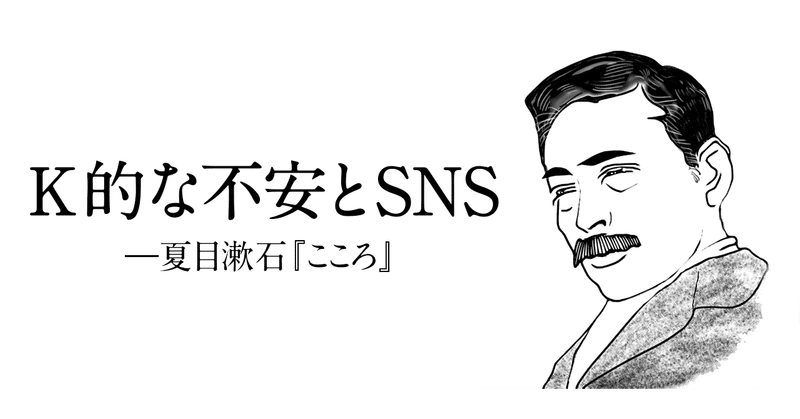
K的な不安とSNS―夏目漱石『こころ』
「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト篇
内藤理恵子(哲学者、宗教学者)
哲学者、宗教学者であり『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』を著した“内藤仙人”こと内藤理恵子氏。その後の編集者との対話の中で、「文学が描く自死」というテーマへの関心を自覚します。
内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」、第1回は夏目漱石『こころ』を取り上げます。
※関連記事『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』幻のあとがき
ある出来事から
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』を上梓して1か月。編集部から「いま書いてみたいこと、掘り下げてみたいことはありますか?」と聞かれました。しばし考えますと、書きたいことが明確に見えてきました。それはある出来事がきっかけ(トリガー)でした。
拙著発売から1週間後のこと。インターネット上に私に関する中傷(デマ)が書かれていたのを見つけたのです。調べてみたら、それを書き込んだのは20年来の知り合いでした。私は、怒りよりも疑問が先に湧いてきて、「どうしてこんなことを書いたの?」と本人に聞いてみると、原因は意外にもSNSにおけるほんの少しのすれ違いでした。「嫌われたと勘違いしたので腹いせに荒らした。申しわけなかった」と謝罪されました。
こう振り返ってみると、「ネットあるあるエピソード」のひとつのようにも思えますが、問題解決までの時間は相当に憂鬱なものでした。知人からの身に覚えのない中傷に見知らぬ人が6人も賛同していたことにもショックを受け、ネットの「シンジツ」というものが“爆誕”する瞬間を、身をもって知ったのでした。
新刊が出たタイミングで、昔からの知り合いにネットを荒らされたことは不気味としか言いようがありません。問題の渦中、憂鬱な気分に支配された私は「死にたい」と、思わず反射的に呟いていました。が、その瞬間「アッ」と声が出ました。
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』という、まさに「死」についてどう考えるか、そしてどう生きるかをテーマとした本を書き上げたばかり。しかも、その最終章では宇宙観と死生観を結びつけた壮大なフィナーレを描いたその著者の脳裏を、ちょっとしたボタンのかけ違いによる憂鬱から「死にたい」などという思いがかすめたのです。自身の弱さを含めた「人間の弱さ」というものを改めて考えてみなければいけない、そう気づきました。
今『こころ』を再読する理由
そんなことがあって、最初に思い浮かんだのは夏目漱石の小説『こころ』に登場する「K」という人物でした。多くの読者には不要かもしれませんが、『こころ』のあらすじを述べておきましょう。
舞台は明治時代。主人公の「私」は鎌倉に海水浴に来ていた大学生。ある人物(主人公がのちに「先生」と呼ぶ)と、その鎌倉の海で知り合います。
「先生」は謎めいた人物で、美しい奥さんと暮らしています。いつしか主人公は、「先生」に年齢を超えた尊敬と友情がない交ぜになった感情を抱きます。やがて「先生」からの長い手紙(実は遺書)が主人公に届きます。手紙の内容は、「先生」とその友人「K」のエピソードでした。
かつて若き「先生」と「K」は友人関係にあり、同じ下宿のお嬢さん(「先生」の奥さん)をめぐって恋のさや当てのような関係にあったこと。さらに「先生」の抜け駆けで「先生」のお嬢さんとの結婚が成立したこと。その結婚をきっかけに「K」が自死を選んだ(らしい)こと……が綿々と綴られた遺書なのです。しかも、主人公が手紙を受け取った時には、差出人の「先生」はもうこの世にはいない――「先生」がそのように計画的に主人公に送った手紙なのでした。
このように『こころ』では、Kだけでなく「先生」も自死します。「先生」はもともと親族の裏切りにより傷ついていた上に、「K」の一件が重なり、とうに生きる力は尽きていたのでしょう。「先生」にとっての自死へのトリガーは、「明治天皇の崩御」と「乃木大将の自死(殉死)」でした。「先生」の死をそれら(史実)とじかに結びつける分析もありますが、これらはあくまでも「トリガー」だと私は思います。
『こころ』で漱石は、「K」と「先生」が自死を選ぶまでの「長期間の葛藤」と「トリガー」の両方を描くことで、最終的に人が自死を選ぶまでの普遍性のようなものを描き出そうとしています。そしてその普遍性は、個別事例と個別事例を重ね合わせた上に輪郭がかろうじて見えてくる類の分析不能のもので、その輪郭をトレースできるのはフィクションだけなのです。
例えば学問上の記述では、「トラウマ」「ストレス」などとラベリングして事態を説明したことにします。それは血の通わない概念であって、仮にそういうものがあるとして、その結果として生じる「何か」。それを文学では、人間たちの具体的なドラマとして再現することができます。
学問はメニュー化した概念を大雑把に整理するための便宜的な手法であり、生きている感情、すなわち「こころ」をありありと描くには文学という手法以外にないのです。

イラスト:内藤理恵子
「K」という人物像を再度あぶり出す
今回『こころ』を再読してみて、「K」が相当に興味深い人物であることを再認識しました。「K」は真宗寺院の次男ですが、彼の思想は真宗のそれとは違います。中学の頃から哲学と宗教に興味を持っていた「K」は、聖書も読んでいたのです。また、聖書ばかりか、神秘主義思想家のスウェーデンボルグについて語り、それを知らなかった「先生」を焦らせたこともありました。
「K」は実家(真宗寺院)から養子に出され、養子先では医師になることを期待されていたものの嘘をついて人文系の学問を専攻しています。その事実が明らかになると、今度は仕送りを止められて経済的に困窮するという事情もありました。
「先生」より「K」の方が女性に好かれる容貌(性格)であったという「先生」の証言も気になります。おそらく「K」は現代風に言えば「影のあるイケメン」で、相当に魅力的な人物だったに違いありません。それでいてどこか抜けていて、純粋なところがありました。他方で、これと決めたら実行に移す意志の強さもあるように見受けられます。
「イケメン」と「ギャップ萌え」を併せ持つ優秀な男、それが「K」です。彼の学問的な専攻が何であったのか、「先生」は「自分とは専門が違う」というだけで明らかにしていませんが、おそらくは哲学か、もしくはそれに近い人文系の学問だったように思います。彼の興味の対象(聖書、スウェーデンボルグ、日蓮)などを重ね合わせると、専門は宗教哲学ではないだろうか、と推察されます。
「K」は学問の道を行くか、もしくは「お嬢さん」との恋愛を取るか、非常に悩み、「先生」に相談します。「先生」はそれにどう答えたか? そこにこの小説の葛藤、対立、すれ違い、懐柔、裏切りといった弁証法的なドラマ構造があります。
ただし、「K」の最終目的は学問を修めることではなかったようです。学問探求の艱難辛苦を通じて「強い人」になることが、彼の最終目的であったと「先生」の証言からわかります。そのためにも、なるべく窮屈な環境を「K」は自ら望んでいた節があります。
それらを総合的に考えると、「K」は宗教哲学を探究しながら、実存主義を実践しようとする人物だったのではないかと私は思います。
「K」と現代のポスドク問題の共通点
「K」の場合、養子先からも実家の寺からも経済的援助が望めないため、「お嬢さん」との結婚を選べば、学問の道は諦めざるを得ないでしょう。これは現代の若手研究者も同じ問題を抱えており、結婚を取って就職するか、すべてを棄てる覚悟でポスドク(博士号を取得しても多くは正規雇用が望めないため、非正規雇用で生活をする博士号取得者のこと。日本では多くの場合、文系科目の単位取得退学者も含まれる)の道を進むか、選択を迫られます。
実際、研究者への道を諦めて恋人のために就職した大学院生を知っていますし、逆に、経済的な困難と孤独の末に研究室を爆破し、自死した大学非常勤講師のニュースも記憶に新しいところです。
学問上の苦悩については、私にも「K」の気持ちが理解できるところがあります。私には「K」という人物像が、私自身を含め、周りに実在する人々のモンタージュ写真に見えて仕方ない時があるのです。
真宗寺院の次男に生まれながらも、他宗教への強い興味・関心を示していること(イエ単位の信仰を持つのではなく、個として神仏との1対1の関係にある)。ポスドク研究者のような「二択」を迫られていたこと。そして宗教や哲学を専攻し、それを道とすることの根本的な難しさ。「K」はまるで現代日本の人文系研究者の苦悩のモザイク画に思えるのです。
「K」の自死までの経緯
「K」と先生が同居するようになった理由は、「K」が今でいうポスドク研究者のような生活をしていたためです。そのような苦況にある「K」を見るに見かねた「先生」は自らの下宿先に招き入れ、その結果、「K」と自分の想い人である「お嬢さん」が「いい感じ」になってしまった、という経緯があったのは先に書いた通りです。
そのあたりの状況を、再度、詳しく分析してみましょう。
「K」は養子先からも実家からも勘当されており、どのようにして学究と生活を両立させていたかは、先生の証言から推察することができます。「K」は「夜学校の教師」をしたいと述べており、それがその通りになったとされていますから、おそらく「K」は昼間は大学に通い、夜は教師として働いていたのでしょう。その苦しい生活によって、心身ともに衰弱しているように見えた「K」に「先生」は同居を提案したわけです。
その結果、「K」と下宿先の「お嬢さん」とはお互いに気持ちが通じ合うようになったように「先生」には見えます。「お嬢さん」に淡い恋愛感情を持っていた「先生」は焦って抜け駆け行動に出た、という流れになります。友人と想い人を同時に失った「K」は驚くほどアッサリと自死を選びました。
しかしそれは「トリガー」であって、もともと「K」の寿命は尽きていたのかもしれません。作中に、旅先で「先生」が「K」を突き落とそうとふざけると「丁度好い、遣ってくれ」と、「K」が答えるシーンがあります。生きていたくもないが死ぬきっかけがない、そんな心持ちで「K」は生きていたのかもしれません。
「K」に近い心持ちで人生を送った哲学者を挙げるとすれば、婚約者よりも自身の「道」を選んだものの、その後に精神的な煩悶を繰り返したキルケゴールということになるでしょう(詳細は『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』)。
違いは、キルケゴールが強固なキリスト教への信仰に支えられて最期を迎えたのに、「K」が選んだ道は道なき道の絶望でした。キルケゴールのいう「絶望」はキリスト者としての道をまっとうできないことへの絶望でしたが、「K」の絶望は、シンプルな「人間という存在」への絶望だったように思います。
そして、それはのちの「先生」の人生をも支配する「シンプルだけれども強固な絶望」で、それゆえに、「先生」は一生、誰とも心を通わせることができませんでした。「先生」は「K」の死後、「K」との仲違いの原因となった「奥さん(お嬢さん)」とも心を通わせることができなかったのです。
「K的な不安」なるもの
本稿では近代文学における唯一無二の存在、夏目漱石の代表作を借りて「自死」について見てきました。「K」の苦悩は、漱石作品に通底するテーマ、 “近代化の苦悩”の一つの側面かもしれません。畏るべし漱石、彼の慧眼は21世紀の今日も古くなっていません。
『こころ』は、朝日新聞に連載され、単行本化するに当たっては岩波書店創業の最初の書籍となりました。弟子の岩波茂雄に対する創業祝いとして、漱石が提供したものです。
「K」が失恋ともいえぬ失恋に傷つき、友人(「先生」)の裏切り行為で自死した一連の流れは、SNSが一般化したいまこそ、再注目されるべきでしょう。0.2ミリの悪意で人は死んでしまうという弱さ。それは哲学ではなく文学でしか描けぬ心の機微だと思いました。
その一方で、メディアの革新は人間の心を大きく変える場合があります。それは単なる道具(媒体=メディア)ではなく、使いよう一つのモノではありません。それは、個々の死生観や社会通念、人間関係を根底から覆しかねない「ある力」であり、そのスピード感と相互依存性、拡散力は、人間の意識を変えてしまうのです。
それゆえに、現代には「先生」と「K」の物語の舞台となった明治期よりも、はるかに多くの「隠されたトリガー」が日常に溢れています。フェイスブック上で、あいつに「いいね!」がついたのに自分にはつかなかった。ツイッターの少しのすれ違いで嫌われたのではないかと思い込む。LINEで既読がついたのに返信がこない。着信が拒否された。デマを流された。SNSの友達を横から取られた気がして悔しい……。それらは「些細な出来事」のようでいて、「最後の一押し(トリガー)」になりかねません。
こうした状況に対する定義や、言葉を私たちの社会はまだ見つけていないようです。もし、その状況を命名するとすれば、「K的な不安」とでもいいましょうか。こうした「不安」は学問的な概念規定が難しい。まさに小説でしか描けないものです。
かつて、マスコミで「知の巨人」とまで呼ばれた人気ノンフクション作家が、「フィクション(=小説)はもう読まない」と宣言したことに、ある種の認識が欠落していると感じたことがあるのを思い出しました。「ちょっとした心の機微で人は簡単に死ぬ」ということ、そしてそれを描くことができるのは、小説によってでしかありえないのにと思うからです。
人間にとって本質的な物事は、「些細なもの」であったりします。そして、それが些細であればあるほど、小説からしか学べない、とも言えるのです。そこに、小説を読む意味があります。
次回の『「死」の哲学入門』スピンアウト篇では、この「自死」について、そして「K的な不安」との関連から、「ぼんやりとした不安」という言葉を残して自らの命を絶った芥川龍之介を採り上げたいと思います。芥川は夏目漱石の弟子でもありました。
<写真は古書店で入手した昭和29年版『こころ』>
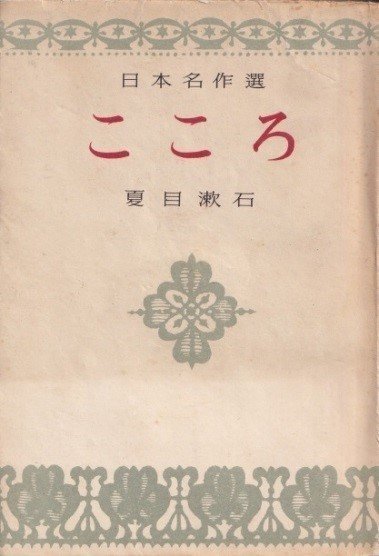
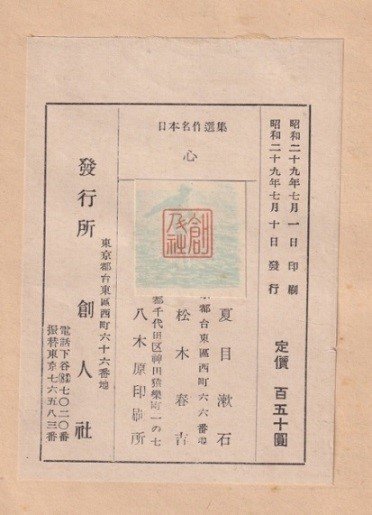
著者プロフィール
内藤理恵子
1979年愛知県生まれ。
南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。
南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了,博士(宗教思想)。
現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
