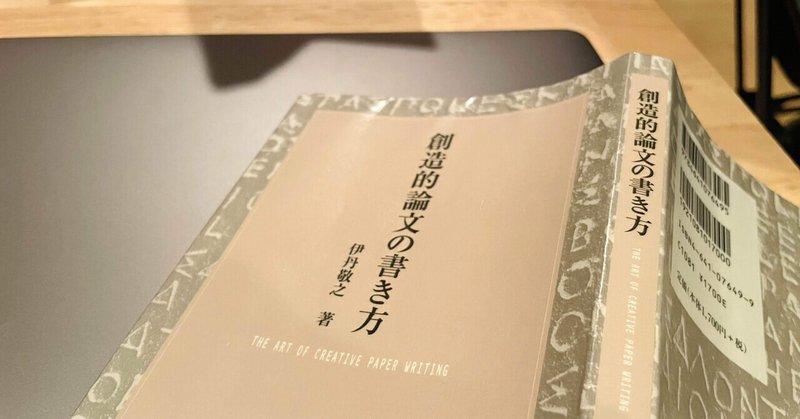
研究や論文は、自分だけのクリエイティブな表現になりうる。
大学院の授業で、アカデミックライティング(論文など学術的な形式を踏まえた表現方法)について学んでいるのですが、その中で読んだ書籍について1200字(3分くらいで読めます)で書評してみます。
題材は、一橋大学名誉教授で経済学者の伊丹敬之さんの『創造的論文の書き方』という2001年に発行された書籍です。
「論文とは。」
その硬派なトピックの本質に対し、靭やかに向き合った一冊です。論文という表現を創造的なものにするための心構えや方法論が記されているのが特徴的で、研究や論文との前向きな付き合い方のヒントが得られます。
4つのポイントに絞ってご紹介します。
①「いい研究」「いい論文」をイメージできる
論文という表現技法を、どのようなものにしたいか。論文作成というプロセスを、自分にとって意味があり面白いものにするには、どのような道のりにしていくのが良いのか。その大まかな道筋や類型が提示されており、「よしやってみよう」という気持ちにさせられます。
その際に、やはり「いい」ものにしたいと思うのが人間の心情です。その「いい」ポイントについても、シンプルに提示されています。
②「知的好奇心」を原動力に
研究や論文には、「我こそはこの点について論じよう」という知的情熱を向けることができる論点を発見することが求められます。同時に、突飛な意見ではなく、既に論じられている大きなアカデミックワールドの中でどこに位置するのかを論証する必要性が示されています。このバランスが肝なのでしょう。
また、研究という長い道のりを進み続けるには、「知的好奇心」を寄せられる対象の存在が重要という点も、興味深いものでした。
③論文を通じて自分を「育てる」
研究を通じて、自己の成長と社会への還元を果たすというイメージがクリアになります。
これは、テクニックとしての研究や論文への向き合い方だけでない、続けていくための自分だけの理由を見つける上で、とても示唆的です。
自分だけが持つ問題意識に向き合い、その定点観測としてのアウトプットが論文であり、それを踏まえて新たな問いを発見する流れをイメージできます。
④創造的論文は「作品」
論文は、技術と意図を両立させた作品・著作であることを再認識させられました。思えば「著作物とは、創造的な表現」であることが、著作権法上でも定義されています。
論文というフォーマットやレトリックを踏まえながら、仮説と論証による言語表現をすることで、自立した作品として成り立たせることができるのではないかと思いました。
画家が絵を描くように、茶人がお茶をたてるように、ジャズミュージシャンが即興するように、研究者もまた、論文を書くのでしょう。
さいごに
本書の冒頭に「いい論文は、ジャズの名盤ビル・エヴァンスの『ワルツ・フォー・デビー』※ と本質的に似たところがある。」とあります。
※1961年発表。日本では累計100万枚のセールスという人気作。
過去の優れた楽曲に新たな解釈を含ませて再演することは、ジャズの名演の一つの典型です。上記作品は、古典から続く音楽史と個人史の交差点を感じさせ、それは創造的な論文の特徴と共通するのかもしれません。
本書を読み終えたとき、「研究や論文というものは、クリエイティブでおもしろいものなのだ」と感じ、また立ち帰りたくなる一冊になっていました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
