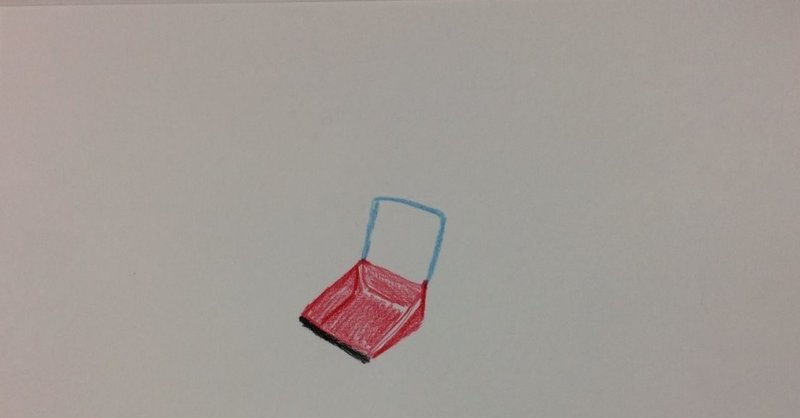
読んでない本の書評76「小川未明童話集 赤いろうそくと人魚」
148グラム。著者名を見ててっきり早熟で薄幸そうな文学少女だと思い込んでいたのに、カバーの折り返しに印刷された写真が坊主頭のおじさんだったのでものすごく驚いた。未明さん、あなたでしたか。

生粋の北国育ちで「ママさんダンプ」という言葉が、積雪地帯でしか通用しないことを知ったのは大人になってからだった。
大雪が降った日にはどこの家でも真っ赤なプラスチック製の除雪用ダンプが翻る。面白いことに、ママさんダンプはどれもこれも真っ赤だ。視界の悪い吹雪の中で作業をしても目立ちやすくて安全だから、と考えれば一応説明はつくのだが、それならオレンジや黄色や緑くらいまでバリエーションがありそうなものだ。どうしてママさんダンプは赤いのか。
寒さの中の赤はひときわあざやかに見える。
「赤いろうそくと人魚」という話は、北の寒い海に住む人魚のはなしだ。あまり海が寒々としてるのを寂しくおもった人魚が、人間に育ててもらうために自分の子を人里で産み落とす。
ろうそく屋の老夫婦が赤ちゃん人魚をひろい、大切に育てた。美しく育った人魚は、赤い絵の具でろうそくに絵を描くようになり、それが評判になってろうそく屋は繁盛する。
ある日、遠くからきた香具師が老夫婦を言いくるめ高い値で人魚を買い取ってしまう。人魚は「一生懸命働きますから」と老夫婦に懇願するが、お金で心が変わってしまった夫婦は聞き入れない。泣く泣く最後のろうそくを真っ赤にそめ、人魚は檻に入れられて香具師に連れ去られる。
ろうそく屋に、母人魚が最後の赤いろうそくを買いに来る。それ以来、赤いろうそくをともすと必ず海が荒れて事故が起こるようになり、やがてその村は滅んでしまう。
ずいぶんな話だ。差別される悲しみ、怨み。地味に働くことへの賛美、地方への貨幣経済の拡大にたいする不安も感じられるのは時代性なのだろうか。
それでも悲しい中にかわいらしい印象も残すのは、赤い印象を残して消える人魚が、何か金魚めいて幼い姿で想像されるからだ。
年の瀬のせわしない中、ずいぶん雪が降った。
冷たい夜空の下をよく目立つ赤いダンプでせっせと雪をかたずけていく。年末の通りはしんと静かである。あちらの遠くと、こちらの遠くにも白い景色の中に浮かびあがるように雪をかいている人がいる。声は聞こえないけれど、同じ雪を運んでいる人たちとのほんの少しの連帯感が好きだ。今日は冷えるので、雪もさらさらと軽いですね。
寒い海で生まれた人魚は、なぜ赤が好きだったのか。 人魚であれば、老夫婦のかわりに肉体労働をうけもつということもできなかっただろう。ずっとひと目をしのぶように座って絵を描いていたに違いない。寒い空、寒い海の中でも、赤い色が見えたら寂しくない。そんなふうに、彼女もひとりで思っただろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
