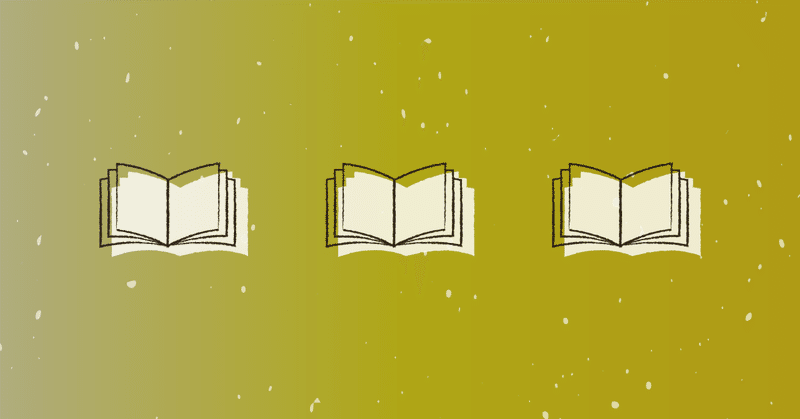
基本情報技術者試験用のまとめメモ
こんにちは、Kenです。
こちらの記事は、基本情報技術者試験を受けた際に使用していた僕の勉強用のメモです。
参考書の内容をまとめたり、ネットから情報を拾ってきたりして自分なりにわかりやすくまとめたものです。
ほぼ午前試験対策用になっていますが、参考書代わりにはなるのではないかと思います。
よければご活用ください。内容は2022年11月現在のものです。
メモを使った学習も載せていますので、興味のある方はこちらから。
学習用まとめメモ
基本情報
CP構成:制御装置(CPU)、演算装置(CPU)、記憶装置、入力装置、出力装置
クロック周波数:クロック信号のサイクルが一秒間に繰り返される回数。周波数が高いほど処理能力は高くなるが、発熱などの問題も出てくる
レジスタ:CPU内蔵の高速記憶装置。
逐次制御方式:1命令づつ順番に繰り返し行う方式
パイプライン方式:複数の命令を1ステージずつヅラしながら並行処理することで高速化を図る
スーパーパイプライン方式:パイプラインをさらに細分化したもの
スーパースカラ方式:複数のパイプラインを使い、同時に複数の命令を実行する
マルチコアプロセッサ:1つのCPU内に複数のコアを内蔵
GPU:3D画像処理を高速に実行する画像処理装置。数千個のコアがあり並列処理する。
ラウンドロビン方式:実行可能状態となった順に従って、タスクに一定のCPU時間(タイムクウォンタム)ずつ与えていくタスクスケジューリング方式
傾向分析:資源の使用状況やサービスのパフォーマンスに関するデータを収集し、それらの推移を分析することで将来予測を行おうとする手法
バス:データの送受信をする伝送路
半導体メモリ
RAM:揮発性メモリで読み書きができる。
DRAM(Dynamic RAM):主記憶に用いられ、SRAMよりも低速だが大容量で安価。コンデンサに電荷を与えており、一定時間ごとに記憶内容を維持するリフレッシュ動作が必要になる。
SRAM(Static RAM):キャッシュメモリに使われ、DRAMよりも容量は小さく高価だがフリップフロップ回路で構成されているので処理が高速。リフレッシュ動作がは不要。
ROM:不揮発性メモリで、読み取り専用。
キャッシュメモリ:CPUと主記憶の間に配置されるメモリで主記憶よりも高速。
フラッシュメモリ:電気的に一部または全部を消去して内容を書き直せる。SDカードやUSBメモリ。
大容量でアクセス速度が良くコンパクト。数十Kバイトから数Mバイトのブロック単位で書き換えを行う。
メモリインタリーブ:主記憶装置を複数の区画に分けて、連続するアドレスの内容を並列アクセスすることで高速化を図る
補助記憶装置(ストレージ)
HDD:磁性体を塗った円板のディスクにデータを記録する。アクセス速度とデータ転送が高速で大容量。
SDD:フラッシュメモリを用いて、HDDの代わりになる。アクセス速度が速く、機械部分も少ないので静音で消費電力も小さい。
光ディスク:レーザ光を使ってデータを読み書きする記憶媒体。CD,DVDなど。
ジョブとタスク
ジョブ:利用者から見た仕事の単位。
タスク:OSから見た仕事の単位。
ディスパッチ:OSによるタスク管理の制御機能の1つで、実行可能状態のタスクの中から優先度順などによって次に実行すべきタスクを選択して、CPUの使用権を割り当てること
スプーリング:プリンタなどの低速な入出力装置に対するデータの転送を磁気ディスク装置などを介して実行する機能
実記憶管理
スワッピング方式:主記憶の容量が不足したときに、実行中のプログラムで優先度の低いものを一時中断して磁気ディスクに退避(スワップ)させる方式
オーバーレイ方式:予めプログラムを同時に実行しないセグメントに分けて、必要な部分だけ主記憶に配置して実行する方式。
仮想記憶方式:プログラムを仮想記憶空間に格納し、実行時に必要なデータを動的に主記憶に配置する方式。補助記憶領域を見かけの主記憶領域として使うので、主記憶よりも大きなプログラムも実行できる。
ページング方式:主記憶とプログラムを固定長(ページ)に分割して一つの単位として管理する。主記憶を効率よく使える。
ページフォールト:プログラムの実行に必要なページが主記憶に存在していないときに発生する割込み
フラグメンテーション:OSが主記憶領域の獲得と解放を繰り返すことで、細切れの未使用領域が発生する現象
メモリリーク:使用可能な主記憶の容量が減ること。プログラムやOSのバグにより、実行中に確保した主記憶領域が解放されないことが原因。ガーベジコレクションや再起動して解放する。実行するページが主記憶に存在しないページフォルトが発生すると、処理効率が悪くなるスラッシングが発生する。
リエントラント(再入可能):同時に複数のタスクが共有して実行しても、正しい結果が得られるプログラムの性質
システム構成
デュプレックスシステム:運用とバックアップの2系統で構成され、障害時に切り替える
ホットスタンバイ:バックアップも常に起動しておき、障害時に速やかにシステムを切り替える。
コールドスタンバイ:バックアップにバッチ処理などを行い、現用のシステム障害時に、処理を中断し業務システムを起動して処理を行う。
※バッチ処理:一括処理とも言われ、データを溜めてからまとめて処理する
デュアルシステム:処理を2系統で独立して行い、結果を照合する
ここから先は
¥ 100
よろしければサポートお願いします!よりいい情報を発信します。
