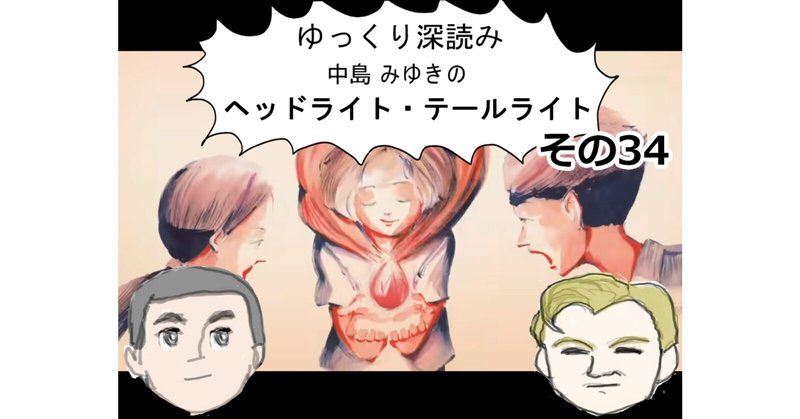
ゆっくり深読み 中島みゆきの『ヘッドライト・テールライト』その34「大林宣彦&横溝正史の 金田一耕助の冒険」
前回はこちら
A MOUSOU
(本作品は著者の身体に憑依した横溝正史の霊が世間で駄作の烙印を押されている大林宣彦の映画『金田一耕助の冒険』を種明かしするという妄想です。ネタバレどころか横溝文学の秘密の核心部分にも踏み込みますので予め御了承ください)

それでは落語『宮戸川』の「霊岸島の伯父さん」とは…

決まってるだろう。
私が短篇集『金田一耕助の冒険』の『瞳の中の女』で「百円紙幣」に喩えた人物だ。
肖像画の板垣退助と同じく、立派な二又あごひげをしている。


預言者イザヤ…

それでは『宮戸川』の本編を translate、翻訳しようか。


小網町に住む幼馴染の半七とお花は…
同じ日の夜の、同じ時刻、つまり、まったく同じタイミングで親から勘当され、家を追い出された…
おそらくこれは…
フラ・アンジェリコ『受胎告知』に描かれた、アダムとイヴの楽園追放、つまり「失楽園」のこと…


その通り。冒頭場面はアダムとイブの失楽園。
だから二人は「締め出しを食った」について議論する。
一見どうでもいいような「食った/食べた」のやり取りを繰り広げるわけだ。
なぜだかわかるかな?

閉め出しを食ったことに拘る二人… なぜだろう…

ヒント。
♬ああ、哀しいね~え、哀しいね~♬

あっ… そうか…
神との約束を破って「食ってしまった」禁断の果実…

William Blake(ウィリアム・ブレイク)

その禁断の果実とは「知恵の実」。
だから半七とお花が締め出された原因も、悪い遊びではなく「知的なもの」だった。

半七は碁将棋、お花は絵カルタ(百人一首)…
どちらも「知恵」が必要な遊び…

ではなぜ「碁将棋」と「絵カルタ」なのかわかるかな?

なぜ? 当時はその2つが遊びの定番だったから?

違う。
半七は「もう一番、もう一局」と言って遅くなり、お花は絵カルタ(百人一首)に「熱を入れ過ぎて」遅くなった。
あの天使ガブリエルと聖母マリアは、そういう風に見えるだろう?


人差し指を1本立てて何かを言っているガブリエル…
そしてマリアの膝にある旧約聖書から立ち昇る熱気…
もう、そうとしか思えない…

だから『宮戸川』に出て来る地名は「小網町」と「霊岸島」そして「肥後熊本」なのだよ。
この意味わかるかな?


おじさんの家が「霊岸島」なのは、おそらく預言者イザヤと「聖霊」のこと…


その通り。まさに「霊」岸島の「おじさん」だな。
では「小網町」が意味するものは?

小網町か…
ウィキペディアによると「小網」とは白魚(シラウオ)漁で使う小さな網「四つ手網」のことらしいですね…
江戸時代、ここで獲れた白魚をお上に献上していたことから、町の入り口にシンボルとして四つ手網を飾るようになり、小網町と呼ばれるようになったとか…
でも、フラ・アンジェリコの『受胎告知』とは何も関係なさそうだ…


何も関係ない? そうかな?


えっ!?

あの天井は「白魚漁」とよく似ていると思わないか?

こ、これは、いったい…

そして白魚は産卵期に入る春が旬。
その透き通るような白さが穢れの無い縁起物として貴ばれ、春告魚(春を告げる魚)として武家から庶民までとても愛されていた。

産卵期とは、排卵期だったマリア…
春を告げる魚とは、告知された子キリストのシンボル…
穢れの無い白さとは、白い鳩に喩えられる聖霊…

白魚を詠んだ有名な俳句を知ってるかな?

白魚の有名な句? もしかして松尾芭蕉の?

その通り。
あけぼのや 白魚白きこと 一寸
春の早朝、水面に差し込む陽の光に照らされた白魚を詠んだものだ。

それが何か?

もう一度言う。
春の早朝、水面に差し込む陽の光に照らされた白魚を詠んだもの。


あっ!
しかしなぜ松尾芭蕉と『宮戸川』に関係が…

落語『宮戸川』には芭蕉の俳句が出て来る。
実際は芭蕉の弟子 島崎又玄が師を偲んで詠んだものなのだが、昔は芭蕉の作だとされていた。
木曽殿と 背中合わせの 寒さかな

ああ、お花と半七が同衾する場面…
背中合わせで寝ていると心にも体にも隙間風が入ってくることを説明する際に、引き合いに出された句ですね…

ちなみに松尾芭蕉の「芭蕉」とは、バナナと同じバショウ科バショウ属の植物「バショウ(ジャパニーズ・バナナ)」のこと。
細長い葉が特徴的で、高さが3メートルくらいになる木だ。
厳密には木ではないのだが。


ん? これって… まさか…

よく似ているだろう。
フラ・アンジェリコの『受胎告知』に描かれた木とバショウは。


そ、そんなバナナ… いや、バカな…

『宮戸川』と松尾芭蕉の話は「木曽殿と背中合わせの寒さかな」の場面で改めて解説するとしよう。
今は「小網町」に関する重要な話をしなければならない。

まだ小網町に何かあるのですか?

小網町といえば、東京屈指のパワースポット小網神社だ。
大川沿いの小さな漁村に過ぎなかった小網町が江戸時代に大きく栄えるようになったのも、この霊験あらたかな小網神社の御利益による。

その小網神社と『宮戸川』に何の関係が?
落語には一切出て来ませんが。

小網神社のシンボルは「昇り龍」と「降り龍」だ。


昇り龍と降り龍?
昇龍はよく縁起物として有難がられますが、降龍なんて初めて聞いた。
「こうりゅう」で変換しても出て来ないですし。

小網神社に「昇り龍」だけでなく「降り龍」がいるのは、この龍が「天の使い・神の使い」だからだ。
地上の人間に、神から授かった大切な何かを伝えるためには、天から降りて来なければならないだろう?

龍は天の使い、神の使い?
かつて小網町に空から龍が降りてきた伝説でもあるのですか?

そう。しかし実際に降りてきたのは「龍」ではなく「僧」だ。

僧?

神のメッセージを携えて天から地上へ降りてきた「僧」を「龍」の姿に喩えているんだよ。
小網神社の「天の使いの龍」とは「天の使いの僧」を意味する。

い、いったいどういうことなのですか?

むかしむかし、今から千年くらい前、江戸周辺は恐ろしい疫病に襲われていた…
そんなある日の夜のこと…
大川沿いの漁村にあった小さな庵に、稲をもった男がやって来て、一晩泊めてほしいとお願いをした…

ん?

普通なら夜中に突然「稲男」が現れたら怪しむだろう…
しかしこの庵の主人はとても物分かりのいい人で、詳しい事情はあえて聞かず、快く「稲男」を受け入れた…

んん?

そして庵の主人が再び床について眠ると、夢の中にひとりの僧が現れた…
その僧は恵信僧都源信(えしんそうずげんしん)と名乗った…

恵信僧都源信?
紫式部『源氏物語』の「手習」と「夢浮橋」に出て来る「横川の僧都」のモデルになった僧ですか?

そう。
そして恵心僧都は、自分が神の使いとして天から降りてきたと言った…
庵の主人が何の神ですかと尋ねると、それは稲荷神だと答えた…

稲荷神?

夢の中とはいえ、あまりの事態に驚き戸惑う庵の主人に対し、恵心僧都はこう告げた…
「先程やって来た稲男は人の姿になった稲荷神です。この場所に稲荷神を祀った祠を建てて篤く信仰すれば、この地から災禍は跡形もなく消え、子孫代々にわたって栄えるでしょう」と…
庵の主人が「そんなことがあるでしょうか?」と疑うと、恵心僧都は最後に「神に出来ないことは何もないのです」と言った…
その言葉を聞いた庵の主人は、こう答えた…
「わかりました。お言葉通りにいたします」

俺の気のせいかもしれないが…
この話は別の話に聞こえる…

気のせいではない。
稲荷はINARI、つまりINRIの四文字で表されるイエス・キリスト。
この小網神社誕生の話は、まるで「受胎告知」のように聞こえるんだな。


INARIはINRI?

志賀直哉『小僧の神様』でも使われたトリックだな。
最後に小僧が親切なおじさんAの住所を訪ねたら、そこにはAは住んでいなくて稲荷の祠があるだけだった。
AのいないINARIだからINRI。
つまり「小僧の神様」とはイエス・キリストのこと。

Andrea Mantegna(アンドレア・マンテーニャ)

なるほど…
そして小網神社誕生物語は、落語『宮戸川』そっくりだった…
夜中にやって来て泊めてくださいと願うのが男女じゃなくて稲男ひとりだったけど…

稲男の「稲」を「居ね」に掛けたのだよ。
半七はお花に「ついて来るな、あっち行け」と何度も言うだろう?

稲(いね)と居ね(いね)の駄洒落…
そういうことか…

そして残るは「肥後熊本」だな。

肥後熊本は『あんたがたどこさ』だったのでは?
あんたがたどこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ、熊本どこさ、船場さ…
小網町は船場であり、お花は船宿の娘…

それは「表向き」の理由で、本当は違う。

ええっ!?どういうことですか?

『受胎告知』を描いた画家グイード・ディ・ピエトロは、日本など諸外国では Fra Angelico(フラ・アンジェリコ)と呼ばれているけど、本場イタリアでは Beato Angelico(ベアート・アンジェリコ)と呼ばれている話をしたよね?

ええ。イタリア語の「Fra」には「修道士」の他に「~間・~後」という意味もあるから紛らわしいと。

Fra Angelico の「Fra」は「~後」…
Beato Angelico の「Beato」は「ベアート」…

え?

そして「Beato」はイタリア語で「神の庇護のもとにある」という意味…
つまり、~後、庇護、ベアート…

ああ… 肥後熊本…

そういうこと。
このギャグを考えた者は、かなりのインテリジェンスの持ち主だな。
ジョークのセンスだけでなく、外国語の知識も豊富だった。

信じられない…
古典落語にこんな秘密が…

ふふふ。まだ落語『宮戸川』は始まったばかりだよ。
ここからが本番だ。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
