
元日と元旦の違いは?成り立ちを理解して漢字が好きになる話
『元日』と『元旦』の意味の違いを30秒でわかるように説明します。
ポイントは、『日』と『旦』の【成り立ち】の違いです。
まず、『日』についてです。
―――――――――――――――
◆日
◆【成り立ち】太陽の形。
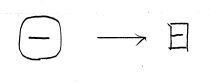

―――――――――――――――
【+αの知識】
『日』の中にある中点(横棒)は、“中味があること”を意味しています。
(空っぽの丸い輪ではない、ということを)
次は、『旦』についてです。
―――――――――――――――
◆旦
◆【成り立ち】雲の上に日が半ば姿を表した様子
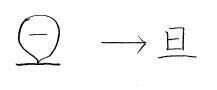

―――――――――――――――
つまり、『旦』は【朝】を意味します。
したがって、
―――――――――――――――
◆元日・・・・・・正月の第1日
◆元旦・・・・・・元日の朝
―――――――――――――――
と、なるわけです。
漢字を成り立ちから理解すると、以下のメリットがあります。
―――――――――――――――
◆漢字の意味が今まで以上にわかる。
◆書き間違いがなくなる。
◆楽しい!漢字が好きになる。
―――――――――――――――
この記事で、漢字の成り立ちについて勉強しませんか?
1.漢字の成り立ち
漢字は【物の形を絵画的に切り取ってできたものが多い】です。
(誤解を恐れず大胆に表現するなら)
たとえば、
―――――――――――――――
◆魚
◆【成り立ち】さかなの形
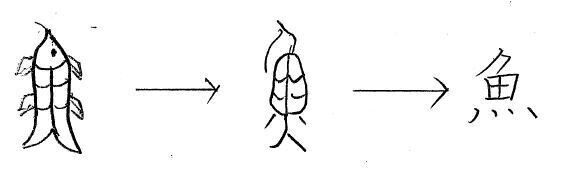
―――――――――――――――
―――――――――――――――
◆生
◆【成り立ち】草の生え出る形
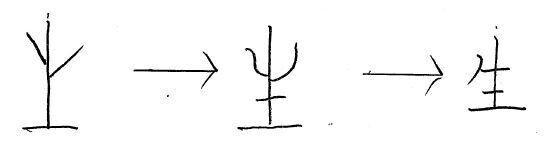
―――――――――――――――
―――――――――――――――
◆赤
◆【成り立ち】人と火(罪人を焼く火の色)
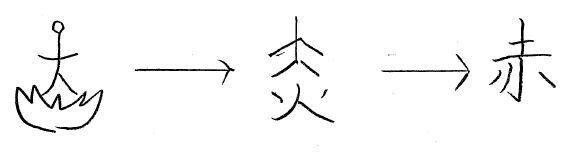
―――――――――――――――
です。
「noteで記事を書く」の『書』は、
―――――――――――――――
◆書
◆【成り立ち】紙に筆で字を書く
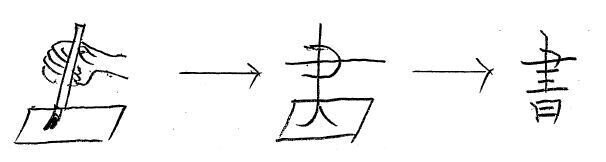
―――――――――――――――
です。
どうですか?
楽しくなってきませんか??
2.祐と被
『祐と被』など、『示偏(しめすへん)』と『衣偏』の漢字が混同してしまう人、いらっしゃいませんか?
私も大学で国語を勉強するまでは、そうでした。
この混同も、成り立ちを覚えれば解決します。
まず、『示偏』です。
もともとはその名のとおり、『示』の形をしていました。

👆👆『示偏』の『神』と『社』👆👆
(画像出典:茨城県神栖市日川の蚕霊神社)
そして、この『示』の成り立ちは、
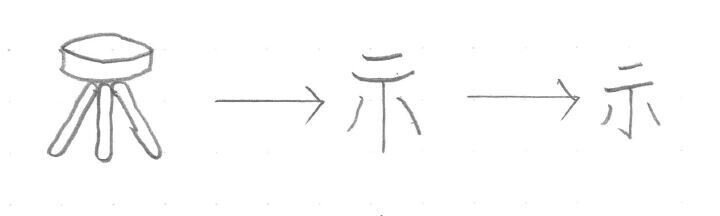
です。
これは、神様に捧げものをするときに使う台(机)なのです。
その証拠に、『示偏』の漢字は神様に関わる意味を持つものばかりです。
―――――――――――――――
◆神
◆社
◆祝
◆福
◆祉(福も祉も、”しあわせ”という意味)
◆禍(神が下すわざわい)
◆祠(ほこら)
◆禅
◆祈
◆祐(神の助け)
―――――――――――――――

【+αの知識】
なぜ、『示偏』を『ネ』と書くようになったのか?
👉『示』を書き崩して『ネ』となりました。
次に、『衣偏』です。
成り立ちは以下のとおりです。
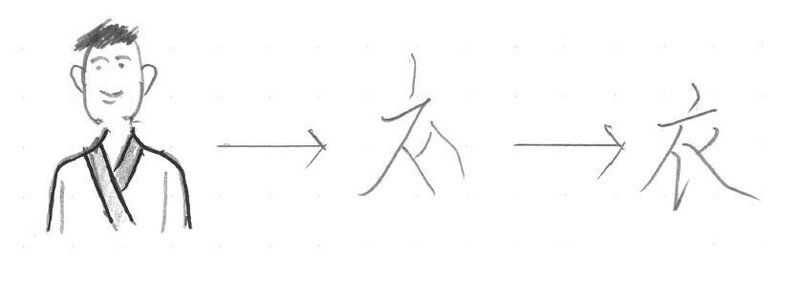
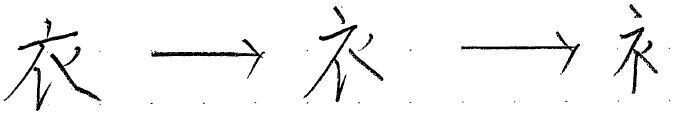
したがって、『衣偏』の漢字は衣服に関する意味を持ちます。
―――――――――――――――
◆被(カブる)
◆袖(ソデ)
◆襟(エリ)
◆裸
◆補(衣服のほころびを他の布でふさぐ)
◆複(裏地のある衣服=何枚か重ねる)
◆初(刀で衣を裁ち切る。初めての衣を作ること)
―――――――――――――――
つまり、
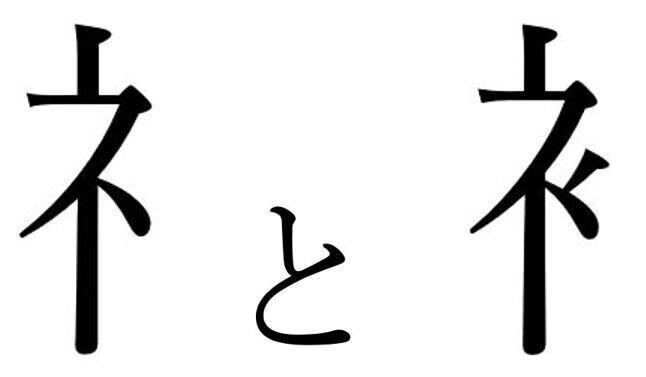
は、形は似ているが、意味はまったく違うのです。
もし、実生活で漢字を書くとき、『示偏』か『衣偏』か迷ったら、意味を考えてください。
そうすれば、
「『祈る』は、神様に関する意味だから、『示偏』だな」
と、書き分けることができるはずですよ。
3.『集』←何が、何をしている様子?
次は、『集』です。
この話をすると、生徒はたいてい楽しんでくれます。
『集』は、もともと、次のような字でした。

そして、

の部分は、【尾が短い鳥】です。
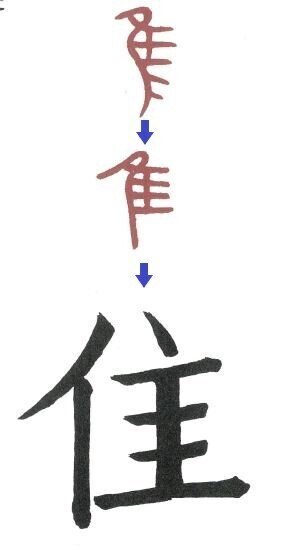
です。(ちなみに、『フルトリ』と読みます)
つまり、『集』の成り立ちは、

という具合。
そう、『集』という漢字の成り立ちは、【鳥が木に集まっている】様子なのです。
【+αの知識】
「フルトリ」を部首とする漢字は、
―――――――――――――――
◆雀
◆隼(はやぶさ)
◆雁(かり)
◆雛(ひな)
―――――――――――――――
などがあります。
また、「鳥」の成り立ちは、以下のとおりです。

4.左と右
【大人でも書き順を間違いやすい漢字】としてよく挙がるのが、『左』と『右』です。
形は似ているのですが、書き順が違うんですよね。
よかったら、続きを読む前に、メモ用紙などに『左』と『右』を書いていただけませんか。
そして、一画目に「★」をつけて、マーキングしておいてください。
(解答は、少しスクロールしたあとにありますよ)
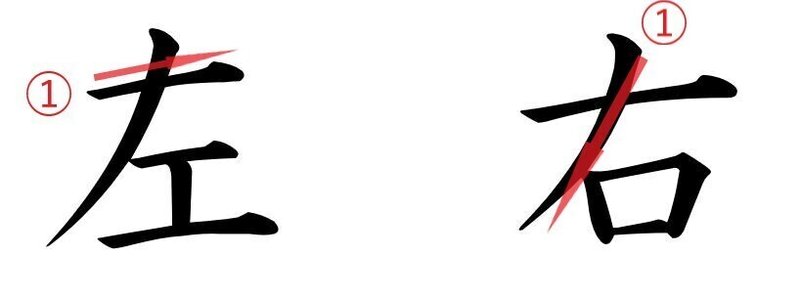
いかがでしょうか?
また、【左払い】【横線】の長さも違います。
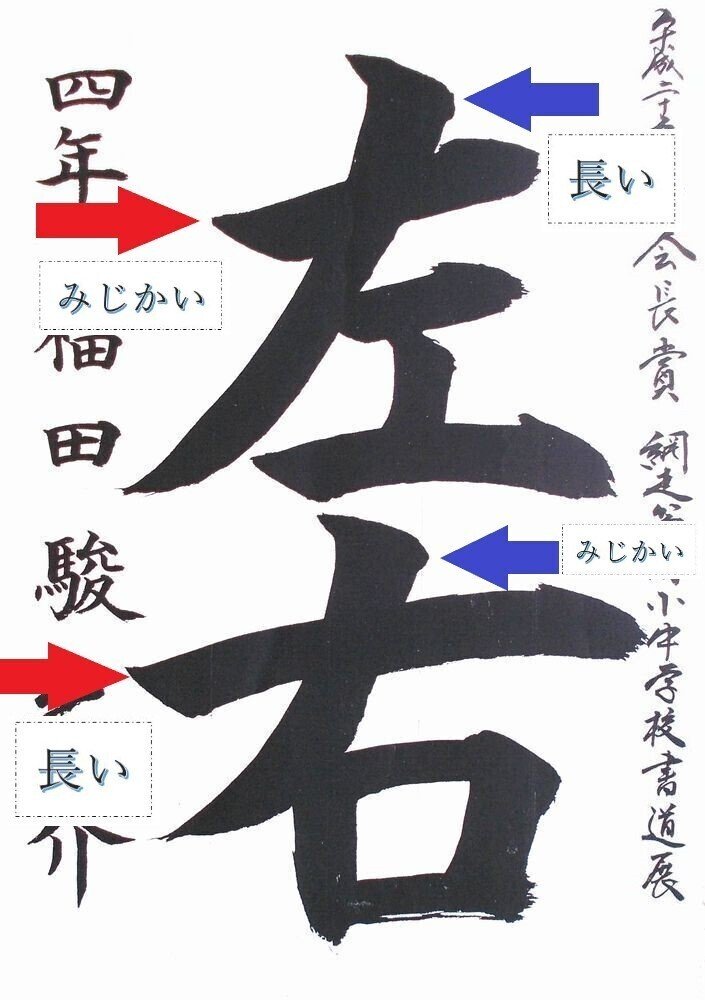
画像の出典元:https://maki9208.blogspot.com/2018/08/blog-post_16.html
(矢印などは、私が加えました)
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?
この違いも【成り立ち】を知れば理解できます。
―――――――――――――――
◆左
◆【成り立ち】左手の形と、祈りごとをするときの呪具
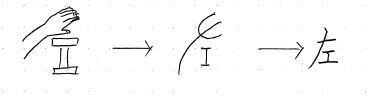
―――――――――――――――
―――――――――――――――
◆右
◆【成り立ち】右手の形と、神への祈りの言葉(祝詞)を入れる器
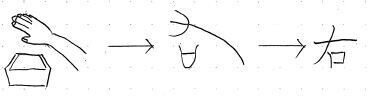
―――――――――――――――
成り立ちをみると、『左』も『右』も、長い部分は【腕】なのです。
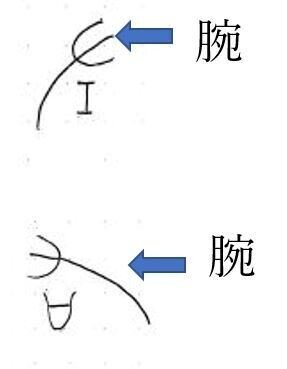
また、短い方は、【手のひら】を表しています。
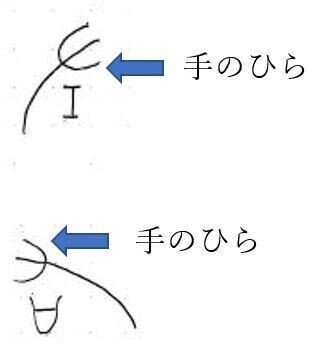
書き順が違うのは、『左』も『右』も【手のひら】を先に書いているからなのです。
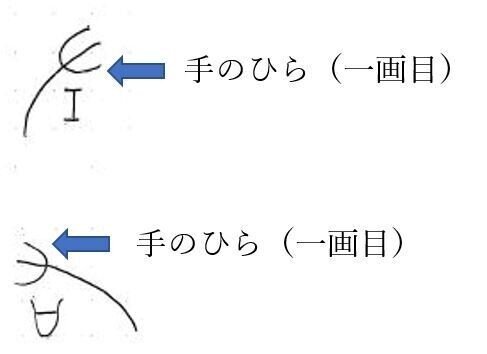
小学生~中学生のお子さんがいらっしゃる方は、ぜひ『左』と『右』の書き順をチェックしてあげてください。
もし違っていたら、この【成り立ち】も説明すると、書き順の間違いがグッと減りますよ。
漢字に興味を持つきっかけになるかもしれません😀
5.右手と右手を重ねると・・・・・・?
最後は、クイズです。
手と手を重ねた様子を成り立ちとした漢字あります。
それは、何でしょうか?

これだけでは、難しいですよね。
では、次に、絵画的にします。

これでも、まだまだ難しいでしょう。
さらに、線にすると・・・・・・
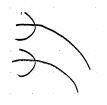
だいぶ近づいてきました。
形も変えて・・・・・・

鋭い人なら、この段階で気づくかもしれません。
【手と手を重ねた様子】というのも、ポイントです。
👇👇解答👇👇

そう、『友』です。
『友』という漢字の成り立ちは、【手を重ねた様子からできている】のですね。
6.まとめ
無機質な漢字が、何か温かみのある存在に変わったのではないでしょうか?
手書きする際、書けない漢字や意味が覚えにく漢字があれば、ぜひ【成り立ち】を調べてみてください。
漢字に対する理解が深まりますよ。
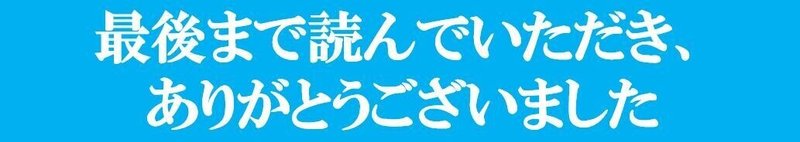
―――――――――――――――
👇👇この記事を書いた人👇👇
―――――――――――――――
【参考文献一覧】
◆新井重良『偏旁冠脚 図説 漢字がわかる字源事典』木耳社/2009年
◆白川静『新訂 字統』平凡社/2004年
◆セシリア・リンドクィスト『漢字物語』木耳社/2010年
◆小山鉄郎『白川静さんに学ぶ 漢字は楽しい』白川静監修/共同通信社/2006年
◆出口汪『本当は怖い漢字の本』水王舎/2017年
◆福井県教育委員会編『白川静博士の漢字の世界へ―小学校学習漢字解説本』平凡社/2011年
◆山田勝美『漢字の語源』角川書店/1976年
◆山元史也『神様がくれた漢字たち』白川静監修/理論社/2004年
出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆
