
◆読書日記.《秋元康隆『いまを生きるカント倫理学』》
※本稿は某SNSに2022年10月18日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
秋元康隆『いまを生きるカント倫理学』読了。
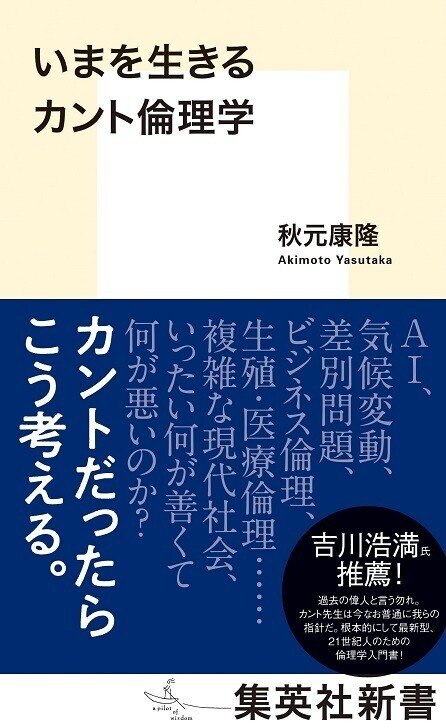
今年(2022年)の7月に出たばかりの集英社新書の新刊である。こちらも石川文康『カント入門』の時と同じようにカント思想のおさらいとして読もうと思ったわけである。
因みに、イマヌエル・カントは『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三批判書で有名な18世紀ドイツの哲学者であり、その後ドイツ観念論の流れを作るきっかけとなった西洋思想史の中でも重要な人物である。
本書の著者はドイツはトリア大学で倫理学の講師をしているカント倫理学の専門家。トリア大学付属カント研究所の研究員でもある。――という事で、日本のアカデミズムにおけるカント理解とはまた違った見方もあるかもしれないという期待もあった。
◆◆◆
本書の構成はシンプルで明快だ。
序章「カント倫理学の骨格」で分かり易くカントの倫理学の基礎について説明し、その規則に従って、その後の「ビジネス倫理」「道徳教育」「生殖・医療倫理」「環境倫理」「AI倫理」「差別に関わる倫理」といった各章の「現代的なテーマ」に当てはめて倫理問題を考えて行くという構成である。
いわば本書は現代的な問題をカント倫理学というスタンスで考え、18世紀のカント哲学の活性化をはかる目的もあるのだろう。果たしてカントは現代の問題にも適用できるだけの思想的な柔軟性を持っているのか。本書では、その辺が問われる事となる。
序章で説明されるカント倫理学の骨子を、自分のメモもかねて簡単にまとめておこう。
(1)自分の頭で考え、判断を下すこと。
(2)非利己的に純粋な動機から行為すること。
著者はこの2つの要件を何度も繰り返して「カントの倫理学」について説明をしている。
これは著者の述べる所によれば「この二つの要件が道徳的善に結びつくことを説いた倫理学者こそが、本書の水先案内人となる、イマヌエル・カントなのです」というのだそうだ。
つまりこれはカント倫理学の基本的な要件を著者なりに二つにまとめたものだと言えるのかもしれない。
そして、基本的には、この二つの要件に従って、後の各章にあげられる現代的な問題を分析していくというのが、本書の内容になっているのである。
この2つの要件に従って、著者はカントがその著作や講義などで示しているテーゼを紹介する。
まずは、カントの倫理学では必ずと言っていいほど挙げられるほど有名な、次の言葉である。
「汝が、それが普遍的法則となることを欲するような格率に従ってのみ行為せよ」(カント『人倫の形而上学の基礎づけ』より)
いくつか分かりにくいワードの補足説明をしよう。
これは所謂カントの「定言命法」と呼ばれるものである。
「定言命法」とは無条件に従うべき行為のルールを示したものだと思ってもらえれば良いだろう。
それに対して「仮言命法」は「もし汝が〇〇したいと思うならば××せよ」といったように、命法に「条件」が付く。
「格率」というのは「自らに設けた規則」だと言われている。平たく言えば「自分ルール」みたいなもので、自分で決めた、自分に適用させるルールだと思えばいい。
この自分ルールが「普遍的法則」――「みんなが従う規則」となる事が果たして妥当なのか、それを考える。
その自分ルールが普遍的にみんなのルールになった場合、それが望ましいか望ましくないのかを考え、望ましい規則だと思えば、それが道徳法則となる。そういった事を言っているのである。
例えば、本書における著者の挙げている具体例から説明すると――
「例えば、『私は車いすのおじいさんに手を貸す』という格率が普遍化された場合は、『誰もが車いすのおじいさんに手を貸す』ということになります。その世界が望ましいものであるかどうか想像してみるのです。もし、それが望ましいものであると思うのであれば、それは道徳法則なのです。当然、履行することが期待されるのです」(本書P.17より引用)
――といった感じになる。こう書かれると、少々「性善説」に寄りすぎな感じを受けなくもない。
だが、その上で(2)の「非利己的に純粋な動機から行為すること」という要件が関わってくる事が重要になってくる。
この「純粋な動機」が「道徳的善」に関わってくるのだが、それを例えばカントは次のようにいっている。
「あらゆる可能な行為について、それが正しいか、正しくないかを知ることは必ずしも絶対に必要なことではない。しかし、私がなそうとしている行為は、私はそれが不正ではないことを判断し、思念しなければならないだけでなく、それをまた確信もしなければならない」(カント『たんなる理性の限界内の宗教』より)
こういった記述からぼくが思うのは、おそらくカントは「正しい/正しくない」という道徳的基準は、客観的には決める事は不可能だと考えていたのではないかと思うのである。
客観的基準を設ける事ができないからこそ、先程から幾つも出てきているように「自分ルール」が出てきており、「私はそれが不正でないことを判断」し「確信もしなければならない」――つまりは、「自分の頭で考え、自分で判断する」という「主観的正しさ」のほうに注目しているのではないだろうか。
但し「主観的正しさ」というのは「利己的」という事を意味していない。だからこそ(2)の「非利己的に純粋な動機から行為すること」という但し書きがついているのである。
例えば、本書にも出てくる議論では、2016年に起こった「相模原障碍者施設殺傷事件」の被告の主張を検討するために「障碍者は無用な存在と考え排除する事」は、カント倫理学に照らし合わせて正しいのか正しくないのかという事を分析している。
この「障碍者は無用な存在と考え排除すべきだ」という主張は、いくら自分が正しいと思っていても他人に説明した所で受け入れられる事はないという事は分かり切っているので、その時点で既に普遍的妥当性は得られない主張だ。
それ以前に、こういった主張をする人間の動機を突き詰めて行けば、他人の事を考えない「自分勝手な動機」――つまりは「利己的な動機」が隠されているものだ……というのが、本書の結論の一つになっている。
つまり、カント倫理学は「動機主義」であって、「結果」については問わないのである。
完全に「非利己的に純粋な動機」であれば、結果が悪い事になってもそれは運が悪かった、やり方が上手くなかった……といった事であり、「道徳」的には悪いものではないと捉えるのである。
著者も本書の冒頭にカント倫理学の特徴を一言で表現して「人の内面に関心を寄せ、評価する思想」だと述べているように、カントの倫理学は「自らの内面」が重要なのである。
思えば、カントは物事を考える際、これまでの「神がそう言ったから」という宗教的根拠を排して考えた思想家だったと言える。
西洋の伝統的道徳は「神が言った」という不動の根拠が存在していた。
それが、教会の権威が揺らぎ、科学が発展していく事によって、「神が言ったから、それが正しい道徳なのだ」という根拠が通用しなくなってきていた時代だったと言えるだろう。
では、いったい何が「正しい」のだろう?
何をもってして「道徳的だ」と言えるのだろう?
今まで世間の道徳的行動を支えていた「神」という絶対的権威が揺らいだ時、では代わりに何を道徳の根拠としなければならないのか――それを「神」に代わって「理性」で考えようとしたのがカントだったのかもしれない。
だからこそ、カントの倫理学は「理性」が求められるのである。
「(1)自分の頭で考え、判断を下すこと」という考え方は、そういった背景がある。
これからの新しい時代の人間は、「神」の言っている事に頼り切るのではなく、自らの「理性」に働きかけて、自分の頭で考えて「正しさ」を見つけるべきなのだ――というのが、カントの倫理学の本質にあったのではないかと思う。
◆◆◆
これらカントの主張というのは非常に面白くて現代でも参考になる部分がありはするものの、しかし、それらを序章の後に続く各章に当てはめる「応用編」を読んでいくと、本書自体の主張はあまりに「弱い」という印象が否めなくなってくる。
カントの倫理学は、ぼくからしてみれば非常にシンプルで幅広く応用できるものだとは思いはするものの、「基礎的」な部分にしか触れられていないという印象が強い。
「あたりまえの事を、あたりまえに主張している」と感じてしまうのだ。だから弱い。
だから、本書を読んでいる間に幾度も「そんな簡単な話なのだろうか?」と疑問に思ってしまった。
カントの定言命法などは、あくまで「道徳を理性によって根拠づけした」という意味があったわけだが、それをもってして具体的な道徳的問題を"解決"する方法論になるかと言えば、そうはならないのではないかと思う。
つまり、カントの倫理学を現代に応用した所で、それを真剣に実践しようとする人については、確かに道徳的な考え方は涵養されるかと思うが、けっきょくそれで道徳的な社会になるわけでも、本書に挙げられている様々な現代的な問題に「正しい」判断ができるようになるわけでもない。
本書でも、各章の問題について確とした結論があるかと思えば、そうでもなく、完璧に答えられるような解答などはなく、結局は個々の問題については自分の頭で考えなければならない――それが「道徳的な態度」なのだ、という結論になってしまう。
個々の「道徳的なスタンス」を身につけるにはいいかもしれないが、直接「問題解決」には使えるわけではない。だから「基礎的」な部分にしか触れられていないという印象を持ってしまう。そこが弱いと感じてしまう理由の一つにもなっている。
カントは18世紀の哲学者で、その時代的な制約というものは当然あり、それは著者も本書で述べている所だ。
例えば本書にも、カントはルソーの『エミール』を読んで衝撃を受け考えを改めるまで、無知な臣民を軽視するような態度をとっていた等という事も書かれている。
だが、上に書いたようにカントの倫理学は非常にシンプルで応用が利く。それは現代にもじゅうぶん通用するだろう――という事を証明するために、著者は本書を書いたと言っても過言ではないだろう。
だが、現代的な問題というのは、あまりにカントの時代とはかけ離れて複雑化しているのである。そこでは自らの判断のみでは賄いきれないほどの様々な要素が絡んでくる。
著者も「重要なことは、さまざまな立場の人に直接・間接に触れ、少しでも事情を知ろうとすること、そして、共感感情が働くよう環境を整えることなのです。そうすることによって道徳的善への土壌もまた整えられていくのです(本書P136より)」とも言ってはいるものの、現代はあまりに状況が複雑化し、ひとつの問題にも様々な要素が入り込んでいて、その「少しでも事情を知る」事自体が非常に困難になっている時代になっているとは言えないだろうか。
例えば著者は「カントは、不遇な人のもとを訪れ、接することによって、人は共感感情を持ち、陶冶することができ、それによって、より相手に寄り添って考えることができるようになると考えているのです(本書P.120より)」というカントの言葉を引用して、臓器移植に感情的に反対する母親を批判するような記述をしている。その母親が臓器移植の現場に実際に足を運び、子供たちと話し合う事でカントのいうような「共感感情」を持つこと――これを主張するのである。
「道徳的なスタンス」を持つには、そういった事は必要なのかもしれないが、現代の事情というのはそんなシンプルにできていない。
上に挙げた臓器移植問題というものだけでも、単に道徳的な意識を持って現場の事情を知り「共感感情が働くよう環境を整える」だけで事足りる程のシンプルな問題ではない。
例えば、臓器移植をする場合に必ず関わってくる「脳死」の問題はどうすればいいのか? これがとても現場だけの問題にならないのは、例えば立花隆『脳死』や小松美彦『脳死・臓器移植の本当の話』を読めばよくわかるだろう。いま現在の現場の話だけではなく、未来の医療倫理にも関わってくる問題だ。
脳死に反対するのは感情的な問題や宗教的な問題からだけではなく、医療技術や医療倫理や社会問題や政治までも巻き込む問題になってくる。
それ以外にも「ヒューマン・ボディショップ」はどうすればいいのか?(アンドリュー・キンブレル『生命に部分はない』)貧乏人は労働させるよりも、切り刻んで臓器移植の具にすればもっと多くの儲けが得られる――といった『ドナービジネス』(一橋文哉、新潮社、2002)の問題は?
自分一人の道徳感情を涵養する事は重要なのかもしれないが、世の中はそれだけではない。
だからこそ、著者の述べている現代的な問題――「ビジネス倫理」「道徳教育」「生殖・医療倫理」「環境倫理」「AI倫理」「差別に関わる倫理」といったもの全てが喫緊な問題であるにもかかわらず、どこか本質のずれた穏やかで緩い議論になっているように思えてならないのである。
――このようにカントの倫理学は、ぼくからしてみれば非常にシンプルで幅広く応用できるものだとは思いはするものの、いかんせん現代の状況に合わせた実践に適したものとは思われず、「スタンス」上の問題以上に利用できるものではないのではないかと思うのである。
著者のカントの倫理学的な「基本的な道徳的スタンス」を再活性化させる議論としては面白いとは思うが、果たして著者のこのような試みは、例えばラカンがフロイトを再活性化したように、カントを現代的に蘇らせる事ができたのだろうか? ぼく的には、少々疑問だ。
ぼくとしては、けっきょく過去の思想・哲学はそのまま参照するべきではなく、それをヴァージョン2.0にアップグレードする根本的な考え方の変換が必要なのではないかと思うのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
