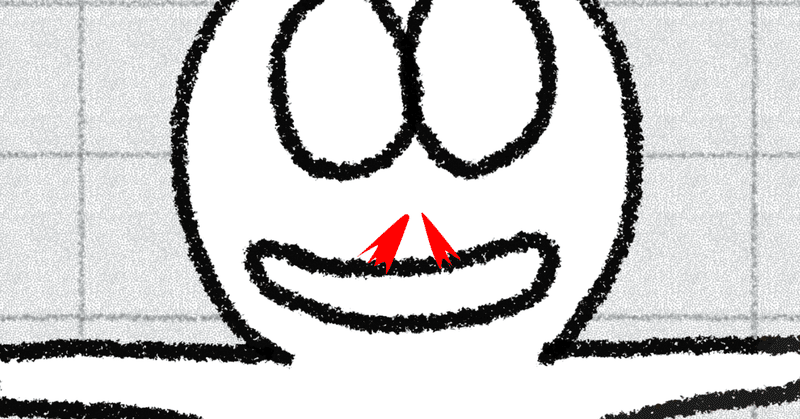
短編小説 天使のケア
「子供みたいなこと言ってんじゃないわよ!」
午後4時半すぎ、講師控室へと向かう渡り廊下にさしかかったら、くぐもった怒鳴り声が反響してきた。今どきコンプラがんじがらめの大学で、と若干引きぎみに不審がるや、
(あっ先生)
突き当たりの角に見慣れた顔が覗いた。二年生のHさんだ。
(こんにちは)
(おとといぶり~)
二人が続けてぽろぽろ顔を見せる。丁寧な会釈のMさん、ひらひら手を振るIさん、みんな実技科目の後らしく白衣姿である。なぜか小声なのでひとまず真似して、
(Aさんはお休みですか)
(せっ、きょう、ちゅう)
(バイ、アン、ドー)
(課題が間に合わなかったんです……)
HさんIさんは講師控室の壁をリズミカルに指さして、Mさんは心配そうに答えた。角を回り込んでみると在室時は原則開放のドアがぴったり閉まっている。
「なにが『おなか痛くて』よ、バカにしてッ!」
バァンと机を叩く音とともにガラスを掻きむしるような声が漏れてきた。確かにアンドウらしい、二年次の専門科目を担当する元看護師の、60手前の非常勤講師である。
「あなた先月もそれで遅刻してたわね。やる気あるの?」
「……あります」
渡り廊下のはじっこの壁に四人並んでへばりつき耳を澄ませる。五限も始まっているし、研究棟だし、だれか来る気配は一向にない。
「じゃあどうしてそんないいわけするの」
「……」
ひとくくりに女子大とはいえ中に咲くのは百花繚乱、H、I、M、Aはその縮図かと個性とりどりの、一年次からの仲良し四人組である。
──どうして看護師になりたいと思ったんですか?
──あの、タイトルは忘れちゃったんですけど、むかし伝記を読んで。
──白衣の天使系?
──それ系です、ふふふ。
前年の四月、初めての女子大また看護学部で右も左もわからなかったころ、新入生だった四人のクラスでまずMさんに話しかけた。背もたれを使わない上品な居住まいだった。
──Aさんは、どういうきっかけなんですか?
──背おっきいですね。
──なるほど背が大きいから看護師にね、把握。
──ちがいますよ先生が!
Aさんは「バレーボール中の怪我のリハビリで会った看護師に憧れて」、Hさんは「食いっぱぐれそうにないから」、Iさんは「祖母も母親も看護師で」とのことだった。
「それで社会に出て通用すると思うッ!?」
「……すみませんでした」
(先生あいつ黙らして、それか殺して)
(殺しでいいよ、まじ殺そ、殺す)
(……)
キイキイ怒鳴る一方ほそぼそ謝る他方、暴力的な構図に義憤の念がたぎる。白衣姿とは裏腹に物騒な二人も同じらしい。祈るように両手を胸の前で固く握りしめているMさんにも見上げられて、ハラを決めた。
──センセみたいなお方だと、気苦労も多いでしょうね。
──いえそんな、へえ。
──お相手はいらっしゃるのかしら。
──や、そういうものは。
──あらあら、あたしならすぐ食べちゃうのに。ちょんちょん、って。
──エヘヘ……
──やだかわいい、ホホホ!
大学教員の多分に漏れずアンドウもまた世間知らずの人格破綻者で、初対面で胸をつつかれてから会うたび胸や肩やペタペタ触られている。どこぞの大学病院のお偉いさんらしい夫ありきの似非アカデミシャン、一矢を報いてやれるなら願ったりだ。
(おれ行くから、ちょっと下がってな)
(おっけ!)
(かあっくい~!)
(すみません)
言い置いてから角を回り込み、ノックしてドアを開ける。
「はあい、あらセンセ、──ってやだもうこんな時間じゃない!」
こもった初夏の熱気と粉っぽい芳香を嗅ぐ。すぐそこに黒染めボブカットが座り、机をはさんで奥に、両手を下腹部で組んだAさんが立っていた。
「お疲れさまです、お邪魔ですかね」
「いいのいいの、お入りになって。お待たせしちゃったかしら」
「やっ今来たところで」
上背のある直立不動の愁眉がやわらぎ両肩からほっと力が脱けた。バレーボールをやめてから伸ばしているという髪をお団子に上げて、すらりと白衣が似合っている。
「ごゆっくりなさって。──とにかく来週までにやってきなさいよッ!」
「はい、ありがとうございました」
主従じみた角度で深々とお団子が下がった。いそいそ立ったアンドウは、ドアを背で支えている目前を通り過ぎかけて、やはり止まる。
「……センセ? ちょっと遅刻を甘く取りすぎじゃないかしら」
「え、そうですかね」
「月経痛なんて、女はなんとでも言えますよ」
「でも、顔がまっ白だったり、うずくまっているときもあって──」
「もう、だまされちゃだめッ」
夜伽のつもりかなれなれしいささめきで、磔のような格好の胸に右手を添えてくる。
「あんまりお優しいと図に乗っちゃいますよ、オンナは」
「は、すみませッ」
右手がさわさわ動く。そ、と離れて、す、と戻る。皺の指先が一本また一本と左の乳首を舐める。
「それじゃ、また──」
「お疲れさまでした」
足音なく出ていった。遠くの方でチーンと聞こえ、低頭から直った困憊の目が笑みかけてくる、ところへわっと三人が飛び込んできた。
「行った行った」
「がんばったね」
「先生ナイスう」
次々抱きつかれる口からはぶつぶつ呪詛が止まらない。
「まじ殴りたいしねヒスババアしねしねしねしね──」
「しねしねしねしね──」
「せんせえハモんないでえ」
「アハハハ!」
「言ったじゃん、アイツに生理は通じないって」
「だってほんとなんだもん」
「他にもやってない子いるのにね」
アンドウは贔屓がひどい。気に入った学生は自宅に招きまでしてかわいがるが、そうでない大多数はあからさまに悪しげに扱う。基準も日替わりか定かではない、と前年の二年生が泣きながら教えてくれた。彼女は中退した。
「先生ごめんなさい、ずっと遅刻ゆるしてくれてるの、言っちゃいました」
「なんも謝ることないです。これからもそのときは遅刻欠席気にしないでオッケー、メールだけください。みんなもよ」
「りょおかい!」
「ありがとうございます」
「先生だけだわほんと」
教員たちは九割が女性のくせ、十割が女性である学生たちに一切の配慮をしない。しないで、まるで若い心身を耗弱させるが目的かのごとく、休みも寝る間もないほど課題を出しつづけている。すでに四人も痛み止めの錠剤漬けだった。
「先生ほんとに胸さわられてた」
「えっ見たかったあ」
アラ還の色情おさわり癖については、その春に授業中"harassment"が出てきたとき解説に使っていた。だれとは明言しなかったが、みんなクスクスしていた。
「通報しないんですか? 完全にセクハラなのに」
「敵に回したら何されるかわからないですからね」
「エッつら~、てかキモッ」
「それで社会がどうこうって──」
「おまいう」
「もうそんなやつばっか」
アンドウは氷山の一角にすぎない。そこは全学年350人余りが裏アカに「ダマサレタ」と「オワッテル」とひっきりなくつぶやいているほど、理不尽、不条理、稚拙、暴言、えこひいき等々の異常が横行している、ケアの精神なき元看護師どもの巣窟なのだ。
「あーあ、つかれたあ……」
「やばッ精神看護のレポート」
「だ~思い出しちったあ」
「わたし心理療法は途中までやってるよ」
「マジなんじ神い」
過重と暴虐のまっただ中でもくじげず手を取りあう彼女たちは、愛でらるるべくして生まれた花のほか何でありえよう。
「みんな無理しないようにな」
「はあい」
「先生ばいばーい」
「ありがとうございました」
「──せーんせっ」
コーヒーサーバをいじくっていると、出ていく三人と離れてAさんが跳ねてきた。恥じらいを噛み含んだような呼びかけに向かい合うと、ぐいっと上体を突き出してくる。
「お、れ、い」
「お礼?」
「胸さわっていいですよ」
はにかみがあやしくささやく。
「きゃあ」
「えっなに、うそ」
「おおお……」
ドアぎわに群がる三者三様の反応に背を押されたように、さらに半歩ぴょんと跳ねて両肩を反らして、
「助けてくれたお礼です。はいッ」
どこかが弾けてしまいそうほど白衣の一部分が強調される。ふんわり目と鼻の先に花やぐ芳香に、ガァンと頭の中でなにか金属的なものがぶつかりあった。
「やっば! やァっば!」
「せんせえ見てるだけでいいのお?」
「よくないけど、いや見てないけど、ちょっと待って──」
「ふふふ!」
唯一止めてくれそうな人も満面むっつり笑顔を両手で覆っている。
「待ってな、これまじで、クビ飛ぶやつ」
「だれにも言わないですよ?」
とてつもない惹句と小首の連携技にコンプライアンスの盾も掲げたそばから木っ端みじん、ああ三千世界の教師を殺し主の団子をほぐしてみたい──
「──や、気持ちだけで十分ですよ、ありがとう」
「えー……」
かすかに上下するふくらみが、がっくりしょげる。
「先生つまんない! そこはいくでしょ!」
「なんか超かなしい……」
「どんまいどんまい」
「あーせんせえ泣かしたあ」
「ちがうって、そういう意味じゃなくてよ」
再び駆け込んできた三人に抱きとめられて、Aさんシクシクやりだした。みんな笑っている。
「強い立場で好き放題は、アンドウと一緒だしな」
「全然ちがいますよ先生は!」
Mさんがその日一番の、一年二ヶ月強で一番の、大きな声を出した。
「ありがとう。でもおれもああやって触られてるからさ」
「あッじゃあじゃあ──、せんせえちょっとあっち、ゴー!」
ひらめき顔のIさんに追い払われて、サーバのコーヒーを手に隅の方に下がる。四つの額がこそこそ明らかに悪だくみをしている──
「ちょっと左腕お借りしますねえ」
「右も~コーヒーは机に置いてくださあい」
「はあいゆっくり退がりましょお」
「アッタマ気をつけましょうねえ」
元気と陽気が大股で迫りきて、それぞれに両腕を取られ後退させられ背を壁に押し付けられた。慣れた手並みで右左とも肘と手首を各両手に縛されて、いよいよ磔である。
「これからヒスババアの上書きをします」
元バレーボール部キャプテンが粛然と言い放ち、一歩一歩と近づいてくる。きょろきょろ首だけ廊下に出してから静かにドアを閉めガチャリと鍵をおろした深窓の嬢が、パチパチ電気を消して、並ぶ。
「これは医療行為ですからね」
「先生なあんも悪くないよお」
「はいリラックスう、じっとしてえ──」
夕焼けの色濃い控室の隅の暗がりで、白衣をまとった四人の天使がケタケタと悪魔のように笑っていた。

この物語の続きを思い出して
あの日のように笑いたまえ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

