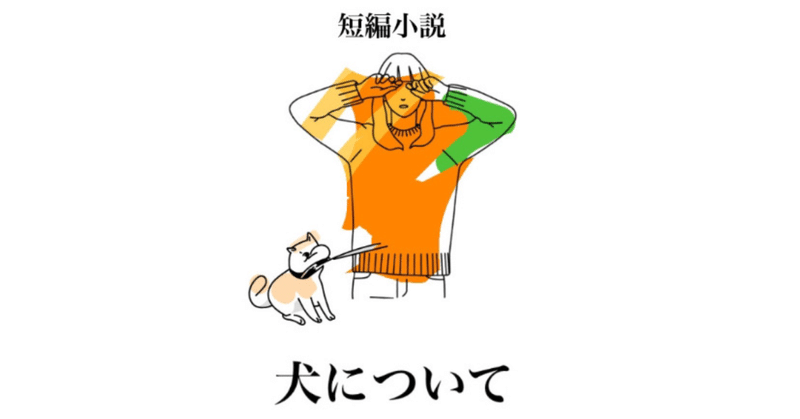
短編小説10「犬について」
Illustration&picture/text Shiratori Hiroki
へへ。肉球に踏まれた。足元にはヨダレを垂らした犬がこっちをみている。
初めて犬に足を踏まれた。そしてソファに顔を沈めてこちらをじっと見ていた。犬は奇妙な生き物のように思えてしまう。だって、ポチって呼んでもタロウって呼んでもワンと吠えるのだから、バカ丸出し。私はバカが嫌いだし、ずっと息切れしているんだもの。あれがとっても気が散るし、気に食わない。だからお兄ちゃんが捨て犬を飼うって言ったときは泣いて反対した。でも、お母さんがみんなと優しくしなさいって言うから頭を撫でてあげてる。
私が学校から帰ると犬はお散歩の時間をわかっていて、尻尾を振ってこちらをみている。あの顔がなぜか気に食わない。なんだか少し見透かされているよう気もするし、犬であるという可愛さを知っているようなあざとさを持ち合わせたような表情。
私も負けてはいられないと思って、犬の目の前にしゃがんで、じっと見た。まず犬の心理を知っておかないとこの子の可愛さに振り回されてしまう。言葉が通じないのなら、表情を見逃してはいけない。試しにニッコリ笑ってみせた。すると犬はこちらをみながらずっと息を切らしている。なんだか、わたしが馬鹿みたいに思えてしまって、首輪をつけて散歩に出かけた。
多摩川沿いの一本道を気が済むまで歩いて、橋を渡って反対側の一本道を歩いた分帰る。部活にも入っていなかった私が放課後することはいつもそうだった。この一本道を歩くのにはちょっとだけ理由がある。サッカー部のツカジくんがランニングしているから。ほんとその理由。ツカジくんは私とは対照的でクラスでも人気があって爽やかでみんなに優しい。たぶんこの犬にも優しくするくらい。そんなツカジくんを見ているとセンシティックな年ごろ女子の私の心を締め付ける熱さがある。憧れとかそうゆう雑な熱さ。そして虚しい切なさも一緒にやってくる。ベンチに座って一句読んで裏垢にそっと呟きたい薄っぺらい情熱と哀愁。たぶん数年後のわたしがそれを読んだら赤面してしまうだろうけど、今はこれでいい。そうゆう時期にそうゆう事するわけだ。そう思いながら犬の方を見た。犬は相変わらず息を切らしてる。
母に頼まれていたケーキを買って、駅から私は犬と一緒に家の方へ歩いていった。駅から近いわたしの学校から最終下校時刻のチャイムが鳴っているような気がして、ぞろぞろとこちらへ歩いてくる生徒を確認した時、少し嫌な予感がした。憧れのツカジくんと遭遇しちゃうかもしれない嫌な予感。こうゆう感じのときの予感は的中する。SF映画でこの結末だけは回避できないあれと同じような、不条理な確信的な予感。やはり彼は曲がり角から歩いてきた。正直なところ、わたしの心臓はバクバクした。恋とかそうゆうのではない身体的なバクバク。犬の手綱をギュッと握って「ねえどうしたらいい?」って聞くと、「ワン」と吠えてきてイライラした。犬の顔が少しニヤニヤしているようにも見えてきて、さらに心臓はバクバクした。ゆっくりと反対方向へ身体を向けて歩き出そうとしたが、犬は落ち着いた様子でそこを動かない。手綱を強引に引っ張ろうとした時、「B組のアヤセだよね?犬飼ってるの?」わたしの耳ではそう聞こえた。「え、あ、うん。そう」ツカジくんは「名前は?俺も犬飼ってるんだよね。」「ポチかタロウ。」不意に聞かれたので声がちょっとうわずってしまった。「え。何それ。変なの。」
彼はそう言うと信号を渡って走り去ってしまった。
耳の奥がぐっとなって唾を飲み込むとちゃんと音が聞こえるようになった。肩が緊張で強張っていたのか、深呼吸をすると周りの視界の色彩がふわっと戻るような感覚があった。一瞬の出来事のように思えたが夕日はもう沈みかけていた。
買ってきたケーキは正直溶けてた。たぶんあの犬のせい。フォークで苺を突き刺すとパウンドケーキとクリームが形状を保つのをやめてどろっと倒れ込んだ。ケーキを口の中に入れると生ぬるいクリームが一瞬で溶けて苺は甘酸っぱかった。随分前から何も食べてなかったから美味しい。今日はいろんなことが起きて少し眠くなってきた。ケーキを食べ終わって眠くなってきたのでソファーに横になるとあの犬と目が合った。ぼんやりとした視界の中で今日のことを思い出した。肉球の感触、ケーキ屋さんの甘い香り、犬の吠える声、ツカジくんの汗の匂い、夕焼けに浮かぶ太陽、生ぬるいケーキ、わたしの甘酸っぱい青春。そして犬に「あんたのおかげね」というと犬は「ワン」と吠えた。
INFORMATION
白鳥ヒロ
2001年生まれの巳年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
