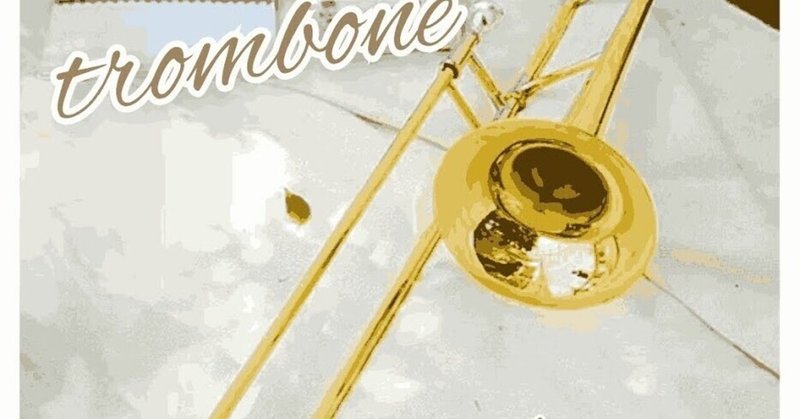
長女と吹奏楽のこと
娘の部屋から、トロンボーン四重奏団のCDが流れている。高校生の時に演奏会に行って、その会場で購入したものだ。
自らオタクと称し、ここ数年は推しの音楽ばかりを聴いていたのに珍しいな、そして懐かしいなと耳を澄ませる。
♪
小学校に入ってすぐに「アレやりたい!」と言ったもの。それがブラスバンドだった。4月の入学式、生徒が入場行進する傍らで演奏していた姿が強烈に印象に残ったようだ。5月の運動会の入場行進も娘はよそ見をしていて、傍らのブラスバンドの演奏に目が引きつけられているようだった。
入部できるのは3年生の後半から。
たまたま隣に住んでいた兄妹がやっていて、毎日毎日 朝練習のために早く登校しているのを目にしていた。早起きが苦手な娘に出来るだろうかと一瞬心配し、まあ3年後にはきっと忘れているだろう、気持ちも変わっているかもしれない、とその時は気にせずやり過ごした。
3年生になり、募集が開始された初日に迷わず音楽室へ行った娘。
ブラスバンドの入部をしてきた、と報告を受け、その想いの強さに驚いたものだ。
早起きの日々が始まる。
吹奏楽は、私には未知の世界。通った小中学校に吹奏楽はなく、音楽の授業で使用したリコーダー以外に、管楽器に関わったことも触れたこともなかった。
私が聞いたこともないユーフォニウムという楽器を希望した娘は、体が小さいという理由で希望が叶わずアルトホルンの担当になった。しかし彼女にとってそれは大きなことではなかったようだ。金管楽器を演奏できるならば何でもよかったのかもしれない。その日知ったこと、指の使い方や息の入れ方にいたるまでを興奮して教えてくれた。私に理解できることは少なかったけれど、楽しそうなことだけは、ひしひしと伝わってきた。ちゃんと早起きも出来るようになって。
ちょっと個性的な指導者ではあったが、的確なセンスで次々と大きな大会へと導いてくれた。それが自信へと繋がって子どもたちは更に実力をつけていった。小学校時代は親も演奏会や大会のたびに、楽器搬送や子どもたちを引率する役割があり、身近で手に取るように楽しそうな様子を目にすることができた。
東日本大会の直前に入院していた娘。出席は諦めていたところに、わざわざ先生が面会に来て「どうしても娘の音が必要だ」と言うものだから、医者に頼んで東京まで遠征に行かせたことがある。娘は音楽センスがいい、と私は親バカ度に拍車をかけたのだ。
同じブラスバンドに所属したものの中学からは他の部活を選んだ次女とは対照的に、長女は、中学に進んでも高校に進んでも微塵も迷うことなく吹奏楽を選び続けた。
中学からはトロンボーン一筋で、先輩はもちろん小学校時代にトロンボーンをしていた子にも早く追いつきたくて、負けず嫌いで練習も人一倍していた。実際先輩を差し置いて1年生で数少ないレギュラー入りを果たし、私を驚かせたものだ。こんなにも夢中になれるものがあって羨ましいなと見つめていた。
ただ、中学時代は悔しい思いが続くことになる。部員の多くは小学校からの仲間だった。金賞受賞ばかりだった彼らは中学時代には低迷することになる。我流で反面教師的な指導者とはうまくいかず、コミュニケーションもきちんととれていなかったようだ。まるで自分の中学時代のようだった。
中学生になると親はほとんど手伝う出番がなくなるので話で聞くだけしかできなかったが、小学時代に陽の目をみなかった隣の中学が頭角を現すにつれ、指導者との溝も深まっていった。
コンクールで銀賞だったときにパンフレットを破っていた姿を見て、あまりに驚いて声をかけられなかったことがある。のちに娘自身も、嬉しいことは少なかったと振り返っている。2年生でパートリーダーになったときも、生徒と先生との意見が合わずに辛そうなことだらけに見えた。それでも決して辞めたいとは言わなかった。(先生辞めて欲しいとは言っていたけれど)
高校は指導者も含めた吹奏楽部の評判についての情報も得て選んだ。ぶれることのない音楽への想いがあり、入学当初は音楽大学を目指すとも言っていた。私もそれが自然な流れなのだと思っていた。
高校では、評判通りの指導でコンクールでは安定した良い成績を残し、学祭や演奏会も楽しんでいる姿を目にすることが多くホッとしていた。
ただ思春期になり、遊ぶコトも要領のよさも覚えて、次第に始めたころのような、がむしゃらさはなくなっていく。中学で怒りにエネルギーを注ぎ過ぎたのかもしれない、と話していたことがある。あの3年の差は大きいとも。
それでも、ソロやアンサンブルコンクールに挑戦したり、プロの音楽講習を受けに行き、やるだけのことはやったのだと。そして、職業や将来を考えて2年生の後半に自分で決めた結論は、大学は英文科。ということだった。
大学に吹奏楽があれば続けるかも。でも、なかったら封印。将来的には、楽器はやめられないと思うけれど、それは時期を見て考える。
高校後半になってからは、そんな思いを抱えながら、楽器と向き合っていた。
音程を、スライド管をコントロールし奏でる、独特のスタイルのトロンボーン。人の声に近いといわれるトロンボーン。
娘が幾度もトロンボーンへの愛を語るなかで、私がわかったのはそのくらいで、あとはチンプンカンプンだったけれど。
そんな彼女の、もしかしたらしばらく見ることが出来ないかもしれない高校生活最後の演奏を見に行ったとき。いつもと同じ楽器に同じユニフォーム、同じ姿勢なのに、なんだか涙が幾度も溢れたのを覚えている。
頑張ってきたもんね。1ヶ月前の学校祭の時よりも演奏は格段によくなっていて、金賞を無事にとって終えることが出来て、自分のことのように、いやそれ以上に感慨深かった。
♪
結局大学も吹奏楽部員であり続けることになり、10代すべては音楽三昧の日々を過ごした。
卒業後は海外留学、就職と続き、どっぷりと英語漬けの毎日で楽器とは離れてしまっていた。ようやく仕事も一人前になり少し生活に余裕ができて、そろそろ楽器が恋しくなってきたのかな。
と流れてくるトロンボーンの音色に耳を傾けながら、感傷的になっているのは、意外と私のほうなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
