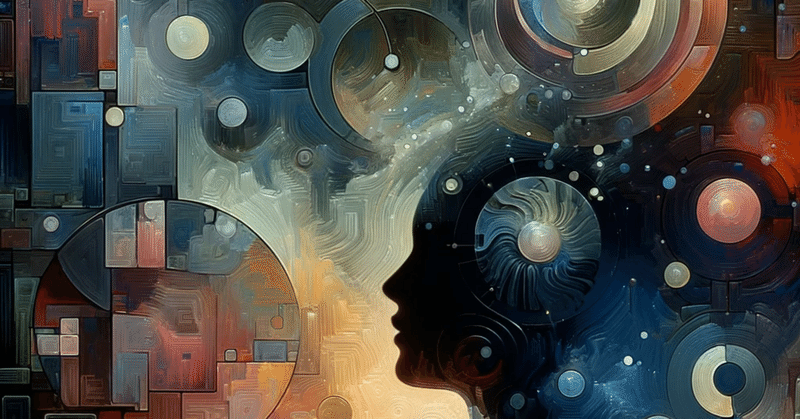
『痛みと悼み』 三十四
めぐむが考えた、完璧にこの世から自分の形跡を消す方法。
急な消え方は完璧じゃない。その方法に従って、義務教育の延長のレールに従って、最低限のことだけをして、目立たないようにそろそろと進む高校生活。ドロップアウトすることは、めぐむの望まないことだった。完全犯罪、それは、本当に人知れず自分の身を消すこと、そのためには、このレールの終点までは辿り着かないといけない。呪文のように、その思いが何度も頭を駆け巡る。そして、その後の方法を考えて6年目の高校卒業の春、めぐむは、熟した果実が落ちるように、母を残して家を出た。
母親の目の前で自分が事切れることが、復讐だと思った時期もあった。でも、父が出て行ってから、枯れて崩れるように細くなり、反比例して醜く膨れる下腹を抱えた、アルコールと睡眠薬でカサカサになった母。震える手で酩酊しながら床を這いつくばるそんな親を見ていて、その思いも消えた。この人は、自分と同じだ。この人も、人から望まれていないと思っている。絶望している。そして、そのことを痛いほど分かっている。耐えられずに、自分からゆっくりと身を殺そうとしている。自分に叩きつけるようにアルコールを浴びつづける母親に、めぐむは自分の死を見せることすら違うように感じた。母にすら気付かれずに、全てのものを消してしまう。消えたことすら誰にも思い出させないようにする。
めぐむは、卒業証書を渡された日、家に戻らなかった。密かに教科書に間に挟んだ、長い間にほんの少しずつ貯めたお金だけを持って家を飛び出した。生きている母を見たのは、それが最後になる。枯れ木のようになった虚な目の母が、自分がいなくなってもらえなくなる分の生活保護のお金を、市役所の人たちに食ってかかる姿が思い浮かんだ。ほんの少しの良心の呵責。でも、母について考えたことはそれだけだった。
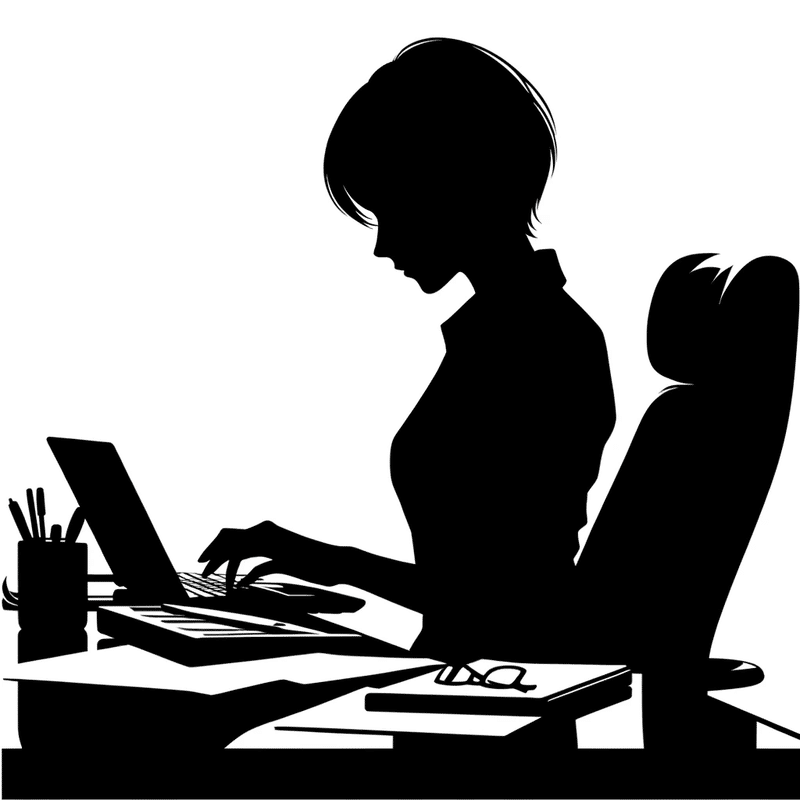
卒業して就職しためぐむの仕事は、小さな不動産仲介会社の経理のような仕事だった。商業高校で簿記の資格を取っためぐむは、不動産仲介をする小さな会社の経理として雇われた。やがて、そこの年配の社長に言われて、宅地建物取引士の資格を取った。年を取った社長が、自分の代わりにお客さんに物件を紹介する仕事をさせたいためだった。めぐむは、ここでも言われたことを冷静に最低限こなすという身に付いた習いで、宅地建物取引士の資格もすんなり合格した。社長は、驚いた表情も示さず、次の日から、会社に出て来ずにめぐむに代わりを頼むようになった。実際には、合格前から、お客さんとの取り次ぎはめぐむがやっていたので、お墨付きがついただけだった。
お客さんとは物件の契約までの短い付き合いで、相変わらず周囲と距離を置き、そんな生活が続いた。
そんな生活の3年目、どうやって身を消すかを手を止めて考える日が続いていたある日、警察から連絡があった。資格を取るため母に黙って市役所から自分の戸籍を取ったことが、連絡先の手がかりになったと、女性警察官の太田さんから言われた。
お母様がお亡くなりになったので、確認のために来てほしい。
最後に出ていくときに見た母の姿を思い出す。母は、めぐむが出ていくとは思わず、口を開けて、睡眠薬と酒の酩酊のまま、しきっぱなしの布団の上で丸くなって寝ていた。そのTシャツからはみ出るだらしなく広がるお腹の贅肉−なぜ人はこんなに痩せてまで内臓は脂肪がつくのだろうと、めぐむは人というものが恨めしくなった、それは本人すら意識しない生への執着なのだろうか−を冷ややかに見ながら。あの贅肉を抱えて、母は消えて亡くなった。
会わないと決めてからもずっと背負っていた荷物から解放されたような気がした。そして、少し浮かれた気持ちで、その心の色を表すような水色の半袖のワンピース姿で、警察の人に導かれるように、今にも倒れそうな古い文化住宅のかつての家に行ったときだった。
見慣れたはずの台所の横の部屋で横たわる黒い影を見たとき、めぐむは思った。これは、私だ、私が死んだんだ
