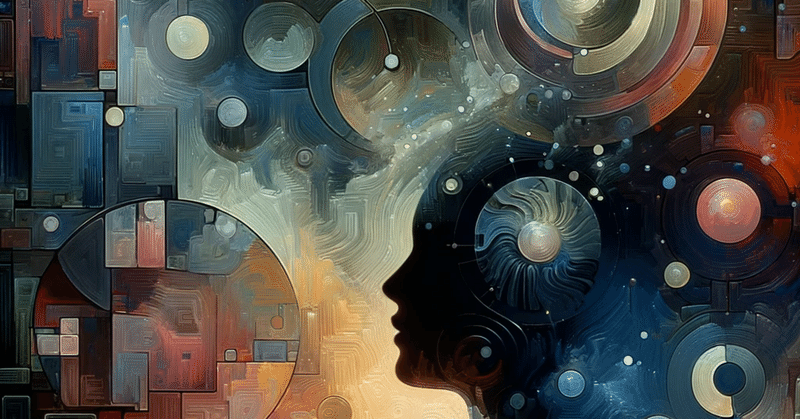
『痛みと悼み』 二十四
明るい日の下で一人腰に手を当てて微笑む、少しお腹の出たTシャツ姿の男性の古い写真を見て、お嬢さんは、先ほどの悲しみを吹っ切るように明るく言う。
「そうよ、だからお母さんのほうから猛アタックしたんだから。」
「うん、そう言ってたよね。」
母娘は見合って笑い、そして、またアルバムに目を落とす。
「あら、篤も写ってる。」
「あら、本当。」
男性とこの母の前に中腰になったこのお嬢さんとその左横に前を向いた神経質そうな小さな男の子が写っている。まだ小学生だろうか、黄色い帽子をかぶって眩しそうに目を細めて、サッカーの日本代表のTシャツから出た細い腕を後ろに回して父親に寄り添うように半身で立つ。一緒に依頼者のご家族の関係を聞いたときに、長女のお嬢さんのことは聞いたが、長男の方がいたことは聞いていなかった。めぐむの不思議そうな顔を見て、母が言う。
「長女の年子の弟で、サッカーが大好きだったんだけど中学生のときに頭の病気で亡くなったの。お父さん子だったんだ。あの人が一番ショックを受けて、お酒に逃げだしたのも、その頃からかも。」
母の目に、霞がかかったように見える。それぞれの家族には、それぞれの髑髏が入った引き出しがある、菰田社長の言っていたこと。それも、この仕事の、ある意味でのつきものだった。でも、その引き出しが開けられるときがある。それが、この仕事のある奇跡のような瞬間。
あの聡二さんの家が思い浮かぶ。富永家にも開けられなかった引き出しがあるような気がしたのに、あのメモ以外に、最後まで微塵もその気配が感じられなかった。なんなのだろう、あの本はその鍵なのだろうか。

ぼんやりしためぐむをみて、母娘は明るく言う。
「ごめんなさいね。寂しいことばかり言って。今日来るときは、もう暗い話はやめよう、明るく送ってあげようって言ってきたのにね。」
母娘は、二人で見合って、そして声を出さずに笑った。引き出しの開くとき、それを笑えるなら、家族の歴史にとってのある章のエンディングであり、それは次の章の書き出しにもなるような気がする。
めぐむも微笑むと、ダンボールを軽く手のひらで叩き、残ったものを大事に入れると、ガムテープで蓋をして、母娘に引き渡す。
遅い夏の終わりの部屋は、その時期にしては、不思議と涼しい、前日までと打って変わった日だった。一度きりの、その家族にとっての大事な夏が終わる。
2度目にめぐむが教会を訪れたのは、母娘の仕事の終わった週の日曜日だった。前と同じように、白いシャツワンピースとジーンズにデッキシューズで、聡二さんには連絡せずに会社の軽トラックを借りて出かける。同じように午前10時の礼拝前、同じ黒っぽいスーツ姿の聡二さんは、予めめぐむが来ることが分かっていたように、教会の中で年配の男性たちと談笑している輪の中から明るく右手を上げる。2時間ほどの礼拝が終わり、茶話会になったとき、若葉さんと啓介さんは、めぐむに笑って目で挨拶すると何か用事があるのか急いで出て行った。
お茶を用意する手が足りないと思い、めぐむは紙コップにお茶を入れて用意を手伝う。その様子を、聡二さんと聡二さんのパートナー−名前を早苗さんと紹介された−が、教会の信者の人たちを案内しながら微笑んでチラリと見る。
仕事のときと違って−仕事のときは、基本、一人で、人に見られることはない。そこにいるのは、菰田社長や何人かの清掃を手伝うアルバイトだけ−人に見られながら動いている自分に不思議な感じがして恥ずかしくなる。自分が、立ち働いているところを見られることへの深い戸惑いがめぐむにはあった。自分が人のためにこの仕事をしているのか、それは本当に人のためなのかという、自分自身への深い問いにも繋がっている。そして、その問いの答えを探そうとすると、それはいつもあるところで壁に当たって、めぐむはそこで怯えたように恐れて引き返す。まだ、自分が怯える理由ーそれは雨と河の記憶だーを見つめる勇気が、今のめぐむにはない。
