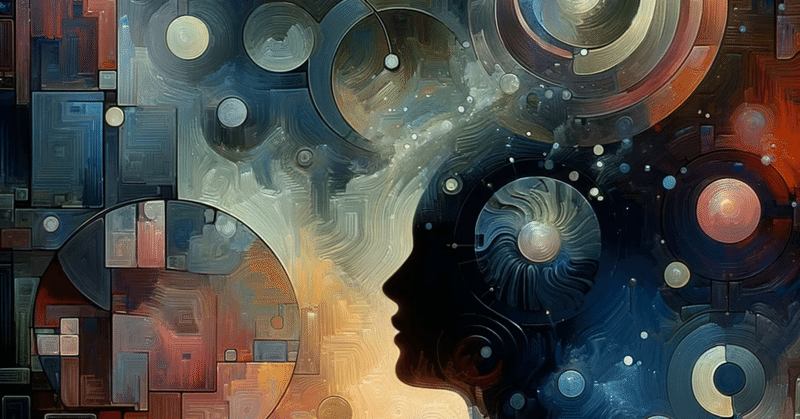
『痛みと悼み』 二十六
「その大事の意味を知りたいわけだ。」
めぐむの頭の中に、あの冨永多恵さんが残したメモが思い浮かぶ。
「すいません。立ち入ったことで。」
今度は、話を聞く聡二さんの方が、軽く頭をあげるとめぐむと同じ視線の車の先のさらに遠くを見やる。遠い思い出を確かめるようなその視線の先は、どんよりとした曇り空だった。めぐむも、黙ってじっと待っている。
「あの本の、檀一雄っていう人、聞いたことある。」
「すいません。私、あんまり小説とか読まなくて。」
「少し前の人でね。女優の壇ふみさんのお父さんって言えばわかるかなあ。」
「上品で落ちつたい女優さん。」
「あの人のお父さんで、壇ふみさんとは対照的って言ったら怒られるかもしれないけど、「無頼派」と言われていた作家さんなんだ。」
「無頼派。」
「そう、すごく勇ましく聞こえるね。」
「太宰治とかととても親しくて、そういう意味でも、世の中の形式的な常識には収まらない人で、そういう作品だった。でも、その内容は、とても人への愛情と自分への厳しさに裏打ちされた作品が多くてね。」
「そうお聞きすると、一度、読んでみたいです。」
「うちの母がいつも手にしていたのが、あの本だった。」
「あの本には、何が書かれていたのですか。」
「『火宅の人』っていう小説、知ってる。」
「すいません。」

「うん、とても簡単にいうと、不倫にまつわる家族と主人公−これは檀一雄本人に模しているんだけど−との話でね、特に最後の章は、檀一雄がガンを患って余命わずかの最後に妻のヨソ子さんという人に手伝ってもらって口述筆記で書いたものなんだ。」
「自分の人生を賭けて書いた本。」
「そうとも言えるかもしれないね。そして、内容は若干激しい。不倫とかの話だ。その本を何か時間のあるときに、いつも、母は手にとって読んでいた。夜遅くに暗い部屋で時間ができたときにね、ダイニングテーブルで手元だけ明るいなかで、じっとあの本のページを開いていた。その姿が目に焼き付いていてね。」
「女性からすると、そんな不倫の話って裏切られた感じがしないんでしょうか。奥さんのヨソ子さんは、そんな本の口述筆記をお手伝いされるなんて強い女性だったんですね。なぜ、お母様はそんな本を好まれたのでしょう。」
「そうね。母はどこに惹かれたんだろう。でも、僕も大きくなってその本を母に隠れて手にして、何だか気づいたことがあった。」
「気づいたこと。」
「冒頭、あの本は日本脳炎で障害を負って寝たきり息子への、優しい声掛けから始まるんだ。その声に、息子はうまく形にできないけど、言葉以上によろこんでいるように見える。そこには、言葉を超えた人間同志の尊い繋がりがある。そして、本の中には不倫もある。これは男の僕から見た感想だけど、主人公は、不倫するときでも誰に対しても卑怯な真似はしてないんだよね。形としては裏切っているのにね。そして、奥さんも不倫相手も周りの人もそれを理解し、悲しみ、でも何かその尊い繋がりを共有している。多分それが、ヨソ子さんが最後を迎える檀一雄の筆記を手伝われた理由じゃないかって、僕は思っている。」
「何かを共有している。」
人と分かち合うこと、その言葉にめぐむの心拍が少しはね上がる。その勢いがそのままのように口から疑問が飛び出す。
「そんな本と、あの裕福な家での幸せそうなお母様とがなんだか結びつかないのですが。」
「幸せそうか。」
聡二さんがつぶやくようにいう。人は、そう見えてそうでないことがある、それはこの仕事で目にしてきたことでもあった。今言った、共有する何か。あの寂しげなダイニングが思い浮かび、めぐむの中で意識がぼんやりとして鶴見警察署を出たときの雨に濡れる感覚が蘇る。遠いところで、聡二さんのつぶやきは続く。
「堅実な資産家の一人娘で、家産を守り続ける人間と、無頼派の作家。」
その声を聞きながら、めぐむはあのメモを思い出す。私の人生は失敗だった、あの激しいメモのとても悲しい文章のヒントは、檀一雄の本にあるのだろうか。
「あの。」
めぐむは、口籠もる。あのメモのことを言ってもいいのか、すでに聡二さんはメモのことを瑛一さんから聞いているのか、めぐむには分からなかった。
