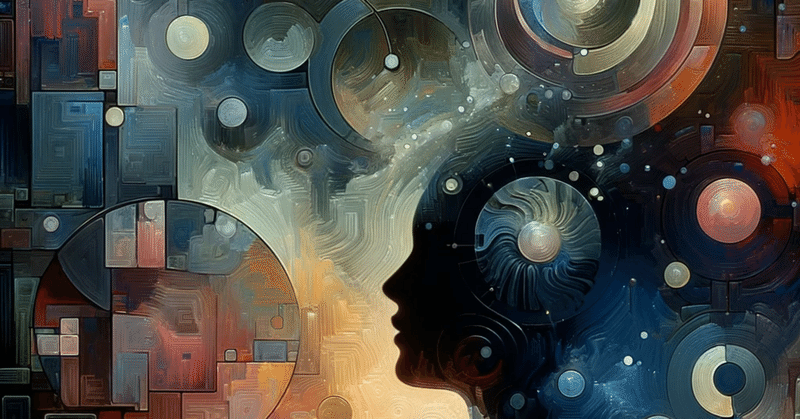
『痛みと悼み』 二十七
その思いを察したように、聡二さんがめぐむを見て、ニコリを笑う。
「こんな話、牧師の私がすることじゃあないんだけどね。」
打ち解けた仕草は、そう言われて聡二さんが牧師であったことをめぐむに思い出させる。
「母はね、本当は望む形で結ばれたい望む人がいた。でも、簡単にいうと、祖父にとても強く拒まれた。」
「好きな人と、結婚ができなかった。」
「簡単には言いがたいが、かなえられなかった望む形が、僕たちなんだ。」
めぐむの答えが詰まる。結婚を約束して、子供ができて、結婚できなかった。それを、私に言っていいのだろうか。
「君は、母の最後の整理をしてくれた。いろんなものを見ただろう。」
「私たちの仕事には、守秘義務があります。」
聡二さんは、めぐむの急に改まった言い方に、うなずいてニコリと笑う。
「祖父は家族に対し、穏やかだが求めるものが強く高い人だった。祖父は、母が一緒になりたかった人が許せなかったんだろうね。祖父は、同じように、そのままでは母と私たちを許さなかった、祖父の望む形でなければ。」
「でも、富永さんはいまいらっしゃる。兄弟ともに。」
「でも、父になる人はいない。」
「それって。」
「母は抵抗した。僕たちは産まれた。その人と望む形を作ろうとした。」
「でも、作れなかったのですか。」
「正確に言うと、僕たちが物心がつく前に、その人の方が、母のもとを去った。それが、結果として良いことだと思ったんだろう。母は、祖父の強い力で引き戻された。そのとき、母は何かに固く封印をして、戻ってきたのだろう。」
「それで、お二人を育てられた。」
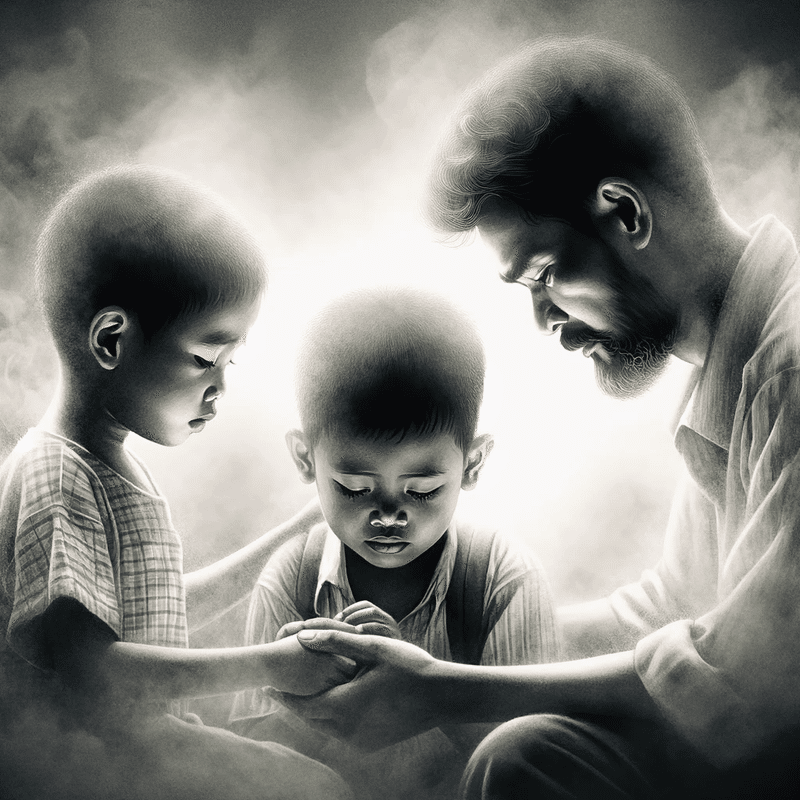
「そんなことがあった。僕と兄はまだ幼いころでね。父が会いたくても僕たちに会えないように、多少の工作はその人との間であったのかもしれない。そのくらいの力ー危険で大きな力だーは何でも無い祖父だ。それで他人になった。でも、その人を父と呼ぶことに僕たちは抵抗はないんだ。優しい人だった。でも、その優しさが、母の心の底に押し殺した何かを見ることに耐えられなかったのかもしれない。最後に僕たちの頭を撫でているときの、悲しそうな目はよく覚えている。それからは、その父にもあったことはない。後は、あの家で、祖父と母と僕たちの生活。」
「そうだったんですか。」
「あの本には、だからいろんな意味が込められている。」
「お母様の激しさを閉じ込めたもの。」
「勇気がなかった自分への想い。激しさとの折り合いの拙さ。人と何かを共有するということへの憧れ。」
「その何かがあれば、ご兄弟お二人もまた違った人生だった。」
「でも、それは僕たちにはどうしようもないことだ。幼い僕たちの埒外のこと。」
あのメモ、富永多恵さんは心に秘めていた。ずっと誰にも言わずに。
「お母様は、富永さんご兄弟に、厳しかったのですか。」
そう言われて、聡二さんはピクリと体を揺らし、その後少し姿勢を伸ばす。視線は、めぐむからまた後ろの曇った空に向かう。
「祖父は当然、僕たちに自分と同じことを望んだ。母はそれに従った。地味だがね、大体、そういう人たちって、なぜか、税務署とかそういう仕事につく人がいる。」
「税務署って、税金の税務署ですか。」
「資産を守るためにも、税の知識があった方がいいってことなのだろうね、税務大学校とかそういうところって、案外、資産家の子息と言われる人たちがいるんだ。ゲームをするには、ゲームのルールを知るのが一番ということなのかな。」
「でも、お二人とも全然それとは違う進路ですね。」
