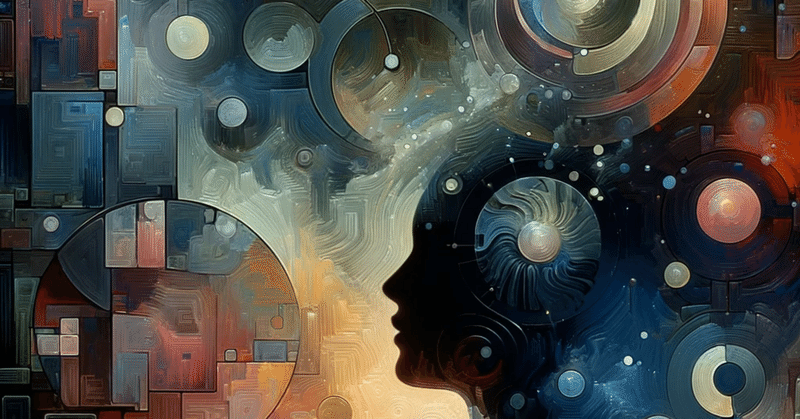
『痛みと悼み』 三十三
めぐむは、コンビニで買ってきた売れ残りの安いおにぎりを2つ、母に手渡す。母は、手を伸ばし、弱々しくそのおにぎりを掴む。しかし、小刻みに震える手がうまく三角形のおにぎりを掴めずに、滑り落ちて床に転がる。おにぎりは、弾むこともなく、空き缶に当たって、その間に隠れる。
消えたおにぎりを見ながら、いつからこんな生活になったんだろうと、めぐむは記憶を遡る。思い出せないほどのはるか昔。
そこにいたはずの父の思い出。いつからか苦い、思い出したくないものになっていた。めぐむは、家の中でもひとりぼっちだった。それが孤独というものだということすら、わからなかった。川の両岸に渡された橋の真ん中にいるように、どちらつかずの位置。橋の両岸にそれぞれいたはずの父と母の間には、見た目以上の距離と冷ややかな空気があった。その真ん中で、いつも泣いていたような気がする。悲しいから泣いていたのか、注意を引きたくて泣いていたのか。どちらだったのかも、もうわからない。考えることも、ある日、諦めた。父は、出て行った。母と激しい口論があったような気がする。それを見て、いつものように泣いていた気もする。この子ができなかったら、あんたとは一緒にならなかったわよ。私の美しさを間違った人に与えたのが、人生のそもそもの誤りよ。嘘をつけ、誰もお前なんかに見向きはしてなかったさ。うるさい。飛び交う手と足。その間に挟まれながら、そこに何かの望まれない原因があって、それがめぐむのことだと分かったのは、その繰り返しの言葉を聞いた何度目だったのだろう。父に投げつける母の言葉。返すような罵倒する父の言葉。
めぐむは、二人の後悔の源としてしか存在しなかった。めぐむは、無視され、邪魔扱いされる、いらない存在だと思った。「めぐむ」という名。何も恵まない、恵まれない子。

私って、いらない人間だったんだ。
めぐむが、自分のことを最初に定義したと言えるならばそのときなのかもしれない。自分はこの世の中に望まれていない、誰からも望まれていないのに、この世に転がりでた。 私がいることは、間違いだ。
そんな自分が、どうして生きているんだろう。
その理由が、分からなかった。リスカという言葉も頭をよぎった。でも、それすら、違うような気がした。リスカさえ、生きていることの確認のような気がする。自分には、そんなことさえ、まどろこしい。
やがて中学生になっても、めぐむは、学校から言われることだけを最低限こなして、誰とも接しなかった。
担任の女の先生は、何度もめぐむの心を開かせようと努力してくれていたような気がする。でも、めぐむは、望まれて人の期待に応えるような価値すら、自分にはないと思う。この世に望まれずに生まれたのなら、この世にいないはずの自分が、望まれることも答えることもないはず。
いつしか、この世に知られず、迷惑をかけずに、完全にこの世から、何の痕跡も残さずに消えることしか、考えなくなった。
中学校に行く登校の前後に考えることが、それだけになった。
めぐむの目に浮かぶ暗い光に、友達ができるはずもなかった。授業中は無表情に板書を書き取る。それは、周りから浮き出さないように最低限の防御の姿勢だった。頭を働かせず、単純作業のように繰り返されるノートに筆記をするそのときには、不思議に頭の中が空白になる。その空白のままの成績は中の下だが、その位置も、目立たないという防御のための最適な位置だった。
めぐむは、怒られるほど目立つこともない、目立たない手のかからない生徒として、誰の注意も引かない。
めぐむは、いつしか他の生徒から「影子」と呼ばれるようになった。存在感を消す名人だとからかわれた。しかし、そのからかう気すら相手に起こさせなくするほど、めぐむはその影を消した。
いつしか、誰の口にも、めぐむの話題は登らなくなった。
そのまま中の下の高校に進学して、やがて、クラスに、めぐむのことや家のことを知っている生徒もいなくなる。
