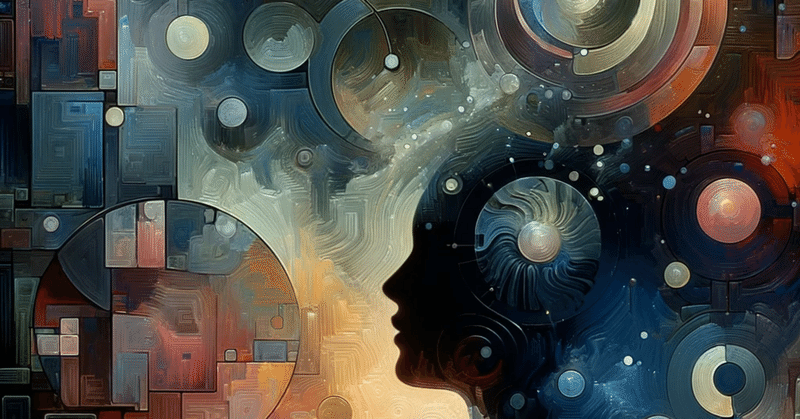
『痛みと悼み』 二十九
「周りにもともと教会とかそういう環境があったんですか。」
遺品の中に、聖書やそれに類するものを見た覚えはなかった。むしろ、魂抜きをして空っぽになった仏壇があった。
「いいや、うちの実家は、バリバリの浄土宗だよ。クリスチャンじゃない。地元の古い大きなお寺の総代のようなこともやっていたくらいだから。」
「なのに、神学部に入ろうと思われた。」
聡二さんの激しさのテコは、何だろう。
「そのときは、どういう気持ちだったんだろうねえ。」
困ったように、また空を見上げる。そこにはどんよりとした雲以外の答えはない。かつてあった青空のように、何かそこに希望を見出そうとした聡二少年が、そこにはいたんだろう。じっと見上げる聡二さんのアゴの線がめぐむから見える。エラの張った意思の強さを感じさせる顔は、母親譲りなのだろう。遺品整理のときに何枚か見た多恵さんの写真の、清楚で上品な老女のエラの張ったアゴの線を思い出す。その写真は、じっとカメラのレンズを見つめる穏やかで静かな目だった。感情を読み取るのに、慎重に近寄らないとわからないように見えた。あの写真と同じと思う。
顔を下げると、聡二さんは、目だけ笑ってめぐむに言う。
「僕たちが支援活動をしているホームレスになる人って、努力不足だと思うかい。」
聡二さんが、自分を例えるように言う。聡二さんは、見方によれば、おじいさまが望む道に求められる努力を怠ったことになるのだろう。そして、ある意味で我が家を捨てた。家を失う人は、どういう理由でそうなったのだろう。
「仕事をしない怠けものという意味ですか。」
「そう思うかい。」
めぐむは、何もできない、死を見つめながら部屋にじっとしていた自分のことを思う。フローリングの茶色い床板に張り付く自分には、重力が何倍にもなったように感じた。その重力は、体だけでなく心まで地面に這いつくばらせた。その重力から立ち上がり離れることは、自分の力ではどうしようもなかった。そして、自分の命すらどうでも良くなった。自ら命を絶つことすら億劫で、命をつなぐ僅かな動きすらしようとする意思も無くなり、じっとそんな自分を見つめていた。それを、自分の怠惰だと言われると、まるでハナから的を外れて飛んでいく矢を見つめているように、なんだか違う気がする。

「よくわかりませんが、違うような気がします。」
「人間って、そんな単純なものではない。そう思うんだよね。人はいつでもどこでも転んで倒れてしまう可能性がある。それは、やむをえずに転んだ人もいれば、僕みたいにわざと転んだ人もいる。」
聡二さんは、明るく笑う。そして、続ける。
「今は、たまたま立っているだけで、それって単なる偶然なんじゃないかって。僕は昔から、比較的恵まれた自分の環境が借り物のような気がしてね、それを兄に、どう思っているか聞いたことがあった。」
「お兄様の瑛一さんですね。どうおっしゃったんですか。」
自信に満ちた少し神経質そうな瑛一さんのハンカチが目に浮かぶ。
「兄はね、借り物でも今あるものは精一杯使うのが自分の役目だって。」
「お兄様は、強いんですね。」
あの口元に当てていたハンカチは、使い捨てされるのだろうか。
「ある意味では割り切っていて、そして、やはりそれも今考えれば復讐の考えられた筋道だったような気がする。復讐のため、借り物を目一杯利用する。今でもそうなんだろうね。」
「今のお兄様。」
「兄は、僕が放棄していらないといった相続財産を、びっくりするくらいドライに家も何もかも売却してしまった。まるで自分の生い立ちの匂いを消そうとするようにね。値段など気にもしなかったようだ。」
聡二さんは、少し悲しそうに笑う。自分の足跡を消そうとするように、あの家も何もかも売却する。めぐむは、あのリビングの大きな窓から見た、庭の桜の木−それは長かった夏の暑さで元気がなさそうな、背の低い古木だった。たぶん、春になるとこじんまりとした美しい花を咲かせていたんだろうーも伐採されたんだろう。
