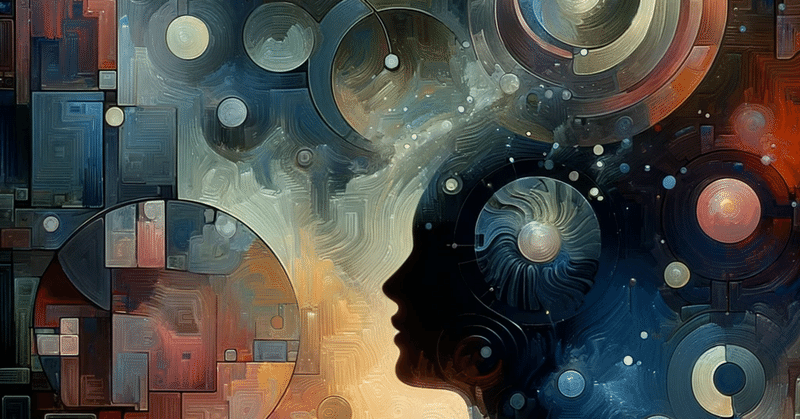
『痛みと悼み』 二十二
聡二さんの無念さの影が消えて、厳しい表情を敢えて緩めようと微笑む。でも微笑みに本当の心の影は消えていない、作り物の笑顔に見えて、この方らしくないと感じる。
「まあ、人はそれぞれどんな人も自分たちのことで精一杯なんだ。でも、僕たちは、できるなら、少しでも分け与えるものがあるなら、そうしたい。それがパンであるのか、パンのみに生きるにあらずの、心の問題なのか。」
「パンのみに生きるにあらず。」
どこかで聞いたことのある一文だと思いながら、めぐむは繰り返す。
「ふふ、だめだね。まだ、スイッチが入ったままだ、人に説教するのはここまでだ。」
笑って聡二さんは、そういった。そして、また来てねと言って、コロナ禍の握手の代わりに、肘を突き出しす。めぐむも、右肘を突き出して聡二さんの右肘に軽く当てる。
めぐむの車が走り出し、幌を開けて見えるバックミラーの、右手を軽く振る聡二さんの姿が小さくなっていく。
第5 夏の終わり
コロナによる感染者はこの夏に驚くほど増えていった。夏の終わり、1日の感染者が2万人を超えるようになった頃、お盆の頃に珍しい長雨が続き、2年振りに開かれた高校野球も雨による順延が記録的な日数になった。国の、断末魔の叫びのような緊急事態宣言が繰り返し延長されるたびに、人々は恐怖に慄き、日常生活はその速度を緩やかに止めていった。しかし、それに反比例して、そして、社会の歯車が回る速度が緩まるほどに、そこからこぼれ落ちるような人たちの、孤独な最後を見届けるこの仕事が減ることはない。
その仕事の最中、ふと、聡二さんからあのとき聞いた、存在しているのに敢えて存在しないことにされている人たちという言葉が思い浮かぶ。なぜ、こぼれ落ち、存在しないことにされてしまったのか。めぐむは、自分の仕事の中で、その遺品から伺うしか、遺族からお聞きするしか、その人のそこに至る道筋を思い描くことはできない。しかし、そこから推し量る事実でさえ、見ないようにしている人からは、原因から悲鳴をあげて目を逸らし逃げてきたような、決して心地よいとは言えないものだろうと思う。

その日の仕事も、たくさんあるかも知れない、そんな種類の悲鳴が聞こえるような仕事の一つだったのかも知れなかった。綺麗になった部屋の中で、依頼者のその母娘と、最後の確認をする。めぐむは、その男性が最後まで大事に持っていた、古びた子馬の小さなぬいぐるみを手にしていた。少なくなった立髪を指で解かしながら、それが男性の長女−離婚した母親が依頼者で、一緒に出ていったお嬢さんだった−が家を出るときに父に残していった物だとそのお嬢さんから聞いた。
部屋に残されていた少し中の綿がくたびれて萎んだチューリップのようなそのぬいぐるみのことを母親に伝えたとき、一緒にいたお嬢さんは、その瞬間に声も涙もなく泣きそうに顔を顰めた。時間がそこで止まったように、じっと動くことなく何か間違ったものを噛んでしまったように、下を向いてじっとすくんでいる。
「そのぬいぐるみ、この子がお父さんのお守りとして、置いていったものなんです。私たちが出て行くとき、お父さんが酒を飲みすぎないようにって、この子がお守り代りに置いて行ったのに。」
そう言った母親の横で、お嬢さんの肩上のショートボブの髪が小さく揺れて前に垂れる。
「お酒を止めること、お父さん、聞いてくれなかった。」
お嬢さんがぽつりとそう言う言葉を引き取って、母は慰めるように言う。
「優しい人なんだけどね、優し過ぎたのね。人に騙されて保証人になって裏切られたり、で、裏切られると酒に逃げちゃう。家の中で物が飛び交って、私も負けてないからあんたが酒を止められないなら私たちを殺してからあんたも死ねって泣いたりしてね。これ以上一緒にいると、みんな沈んじゃう。ギリギリまで頑張ったつもりだったんだけどね。最後は後悔してやり直してくれることを祈る気持ちで、逃げるようにしてこの子を抱えて出てしまったの。」
