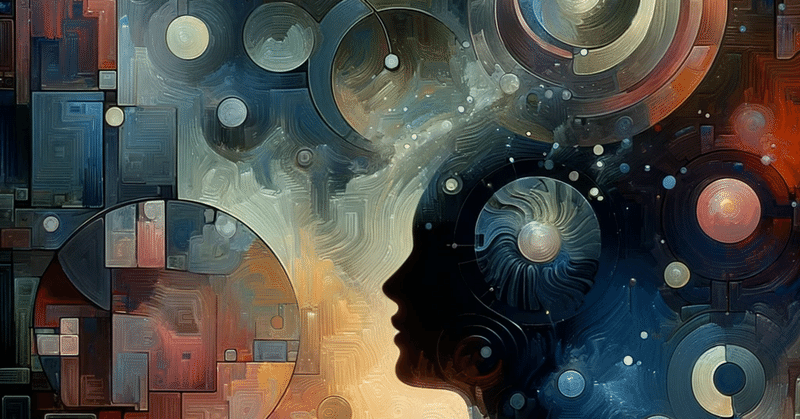
『痛みと痛み』 二十一
その日のミサと茶話会で、めぐむは、初めて会う種類の人たちばかりと出会った。自分にとって、人に見られてはいけない重い荷物のような母の気配を、周りの人たちに悟られないように隠して生きてきた過去に、友達と呼べるような存在はいなかった。今の仕事を始めて、人との距離も依頼者と請け負った会社という関係は、お互いに仕事の範囲内で必要なことにしか触れないという意味で、自分には重荷にならず適当だった。でも、この教会にきている人は、何か違う。めぐむが生きている仕事での関係の、その先から始まるもので繋がっているように思う。
それが何か分からない。
多分それぞれの人の仕事や住んでいるところや生きてきた道は違うはずなのに、皆が、何か同じ物を見ているように見える。そのことを、口に出さす言葉にせずにここでお互いに確かめているようにも見える。何か不思議な暗号をお互いに解読するような身振り手振りで、お互いの確かめたもので改めて繋がっていることに喜びを感じているように思う。
ここは、それを確かめる場なのかしら。
めぐむは、自分がその何かをまったく共有していないことに、温かいコミュニティーに一人だけ言葉の違う異邦人が紛れ込んだような孤独を感じる。しかし、孤独感は、めぐむにとって、ある意味の空気のような、常に自分の周りに意識せずにあるものになっている。慣れすぎていて感じられない空気の存在を、この場所は自分に改めて違和感として感じさせる。皆、めぐむからは見えない何かと向き合い、めぐむが持っていない何かを分け合おうと皆で持ち寄って、慎ましく明るく肩を寄せ合っている。
聡二さんが明るく笑いながら−マスクをしているのでその口元はわからないが聡二さんの声はマスクを通しても太く良く聞こえた−年配のニコニコ笑う小さな男性たちの輪の中で話している姿を改めて見る。
めぐむは、その違和感の原因への思いをやり残した宿題のように抱えながら、それがあまりにも個人的で壊れやす過ぎて、問いの言葉で形にできない。
教会から帰るときも、車を置いた駐車場まで送ってくれる聡二さんに聞けずにいた。
ただ、ヒントを尋ねるように、ひとこと尋ねる。
「ここに来られている人は、どんな方が多いのですか。」
「そうね、今日見て、どう思った。」
「年配の、しかも男の人が多かったような気がします。」

「このあたりはね、もう気がついていると思うけど、少し奥に入り込むと、昔からドヤ街と言われる場所なんだ。建設業など景気がいいときには都合良く日雇いで使われて、そうでなくなると見向きもされない。それで年を取る、体を悪くする、働けなくなる。仕事は安定せず、寧ろ仕事を失ってずっと長い間働けない人、体を悪くして仕事ができなくなってしまった人、中には家のない人もいたりする。しんどい思いをしている人たちが多い街なんだ。ましては、コロナで現場が動かない今はとても大変だ。そういう人の中で、ある思いを抱えながら決心してくれた人たちが来てくれる。僕は、そんな人の今の気持ちや悩みの話を聞いたりもしている。本人の意思があれば、小さいけれど住宅を紹介したりもしている。目の前のこととして、冬の厳しい時期なんかには、食事の世話をしたり、炊き出しをしたりもしてるんだ。」
「まだ、こんな夏の間はいいとしても、冬は辛いですよね。」
「そう、そんなときに、体力が弱って命を失ってしまう人もいるんだ。」
顔を上げた聡二さんは、誰を見るともなく中空に視線をそらす。その顔に、小さな無念さの滲む影が通り過ぎた気がして、空振り三振に終わったボールを見送る野球のバッターのように見えた。
「生きたくても寒さと飢えで命を落とす。今の日本ではないことになっているはずの人たち。」
めぐむが小さく唇を噛んだが、本人も気づかない。
「日本にあることで、ある人は、そのことを敢えて見ないようにする。存在しているのに存在しないことにする。それでも見てしまったときには、それを、その人の努力不足のせいにする。そう理解すると、その人は−ある意味、この社会における勝者とも言える人たちかもしれない−良心の呵責からは逃れられる。」
「良心の呵責。」
