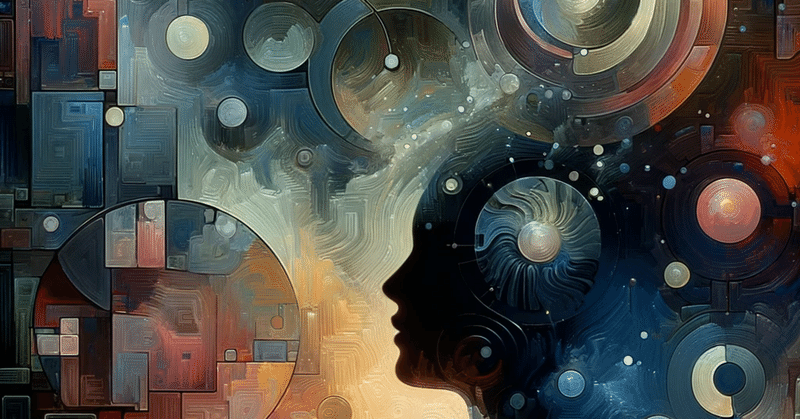
『痛みと悼み』 二十三
かつては、この家族の中でも修羅場のような出来事もあったんだろう、今は、静かに動かなくなった死者との思い出に、安心したようにくつろいで話す母娘が、かつて死者が生きていた部屋にいる。
この部屋も、めぐむたちが入ったときは、苦しみを壁や床に叩きつけたような状態だった。めぐむや菰田社長は、部屋に入った時に、久しぶりに、うーん、と声を上げる。それは、殴り書きのように、壁や床に撒かれた汚物と床に散乱するペットボトルや酒の紙パック、空き缶などに紛れて、一箇所だけ空いたスペースに、大きく黒い人型があった。それは、いつもの人型だが、散乱した部屋の中でそこだけが人の横になれるスペースで、そこの頭の、焼酎の紙パック−もう、コップを使うこともなかったんだろう、直飲みのような散乱の仕方だった−の上に、不思議なことにきちんと、頭の方に向かって顔を寄せるように、そのぬいぐるみは置かれていた。最後にこの人が見た景色、紙パックの上から心配そうに、あるいは微笑むように見ていた子馬のぬいぐるみが、その男性の最後を看取ったのかもしれない。そして、見とられる死者は、この子馬を見て、最後に何を思ったのだろう。めぐむは、散乱している紙パックを仕分けしながら大きなポリ袋に入れているとき、このぬいぐるみだけは綺麗に整えて絶対に捨ててはいけないと思い、母娘に渡した。
「このぬいぐるみも、役にはたたなかった。私って、お父さんのなんだったんだろう。」
ぬいぐるみを握りしめながら、お嬢さんの方がぽつりと言う。めぐむは、そうじゃないと言おうとして、言えなかった。お父さんは、最後も一人じゃなかったと思います、でも、そんなことをめぐむが言えるはずがなかった。
押し殺すように、めぐむは平静を装ってお嬢さんを見る。高校生なのだろう、半袖の白いシャツの胸元には赤いストライブのリボンタイが見える。ギンガムチェックの膝上スカートから健康そうな白い足と黒いハイソックスに、めぐむたちが用意した白いスリッパを履いている。俯いているその目は額にかかった前髪でよく見えなかったが、声が震えているのがわかる。
私って、なんだったんだろう。
その言葉を聞いて、めぐむは、抑えようもなく、感染したように動揺する。「私って、お母さんのなんだったんだろう」、めぐむがずっと心の中に抱えている言葉と共鳴している言葉。
引き取るように、母親が言う。
「あんたがいないと、お父さんはもっと早くだめになってたわよ。」
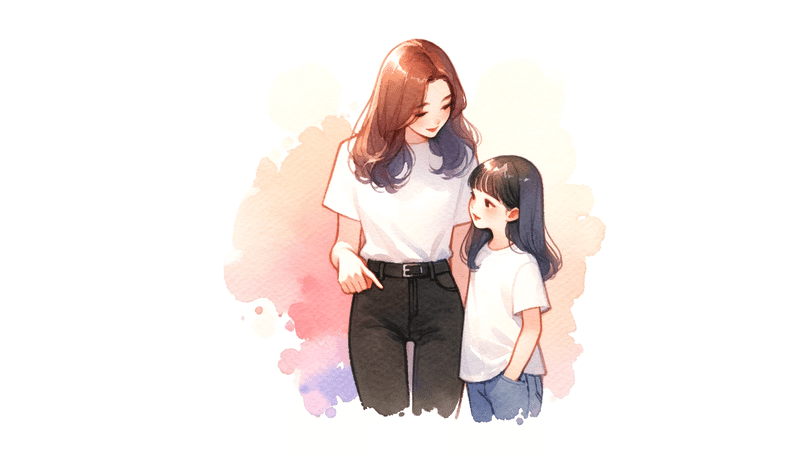
四十代に見える白いTシャツに黒いタイトなジーンズ姿の、お嬢さんの体の線をそのまま柔らかくしたような母親は、顎までのショートヘヤーを何度か揺らして頷き、背の高い娘の肩に手を当てながら言う。多分、母親も辛い決断で出ていったのかもしれない。でも、こうやって最後は、見送りをしてもらえている。それは、幸せなことなのではないのかと思う。
最後まで、この子馬ちゃんがお父さんを守っていたんだと思います、そんな言葉を言えないめぐむは、静かにその思いを仕事の言葉に紛れ込ませる。子馬を見つけたときの状況を、できるだけ陰惨にならないよう、色をモノクロにして、その陰影も付けずに母娘に話す。そんな説明の仕方は、この仕事の一部になっている。
それは嘘ではない優しさ。
世の中には、正確さだけが全てではないこともある。
そして、あとは、残された遺族が、自分自身の大事な務めとして、受け取る側で正確さの隙間を埋めていくのかもしれない。
母娘は、時々軽く頷いて、めぐむの話を黙って聞いている。見つけたものについて、確認するようにその置かれていた位置や場所を説明して、中身について確認してもらい、希望があればそれを目の前で広げる。必要でなければ、段ボールに梱包したまま会社の倉庫で保管して、あの廃棄を免れた本のような例外は別にして、やがて処分する。あの本のことを聡二さんに聞くことを忘れていた、とめぐむは思った。
今度会ったときには、あの本のことを聞いてみたい。
母娘は、めぐむに説明された段ボールを持って帰ると言った。部屋でペットボトルや紙パック以外のものといえば、少ない衣類と書類と写真の入ったアルバムだけが段ボール一箱ほどしか残らなかった。母娘は、ダンボールからそのアルバムを広げなから、小さな歓声を二人で上げる。逃げるように出ていった母娘は、アルバムさえ置いて出たらしい。
「ああ、お父さん、若い。このときは、結構いい男じゃない。」
