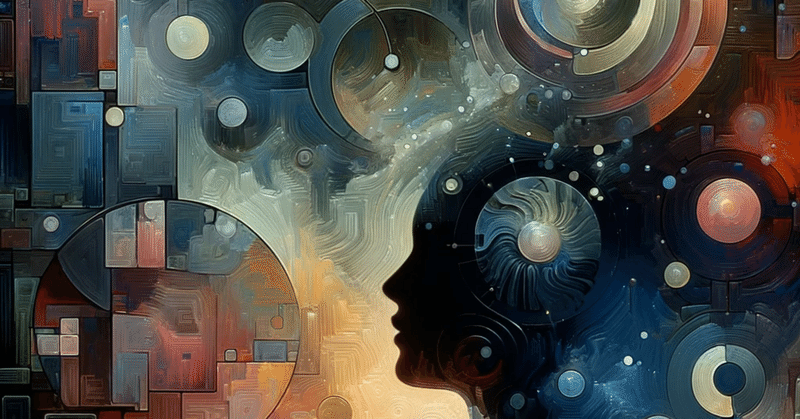
『痛みと悼み』 三十五
なぜだかわからなかった。見たとき、自分が、もう一人の自分を殺したような気がした。それを、さらにもう一人の自分が見ている。人に知られずに姿を消すことを考えていたこと、完璧に一人の中で完結すると思っていたことが失敗したと、そのとき、頭の中に衝撃のようなものが走った。完全犯罪を見破られ、先を越された。そして、自分の失敗を見せつけられた。
人間は、完全にいなくなることなんてできないんだ。
遺体は、痛みがひどくて、解剖の後、荼毘に付されました。死因は、おそらく栄養失調のようです。胃には何も見つかりませんでした。最後まで、アルコールは手放さなかったようですが。事件性はなしのようですね。
太田さんは、非難のこもっていない声で言ったが、めぐむには聞こえなかった。太田さんの音の記憶だけが残る。警察官も、幼いころから、めぐむに何があったのか、薄々感じているようだった。そんな境遇の人たちが少なからずいる社会。それを垣間見ているだろう太田さんは、ありきたりの慰めが無駄なことを知っているのかもしれないと思った。
条件反射のように、家の外に出て吐いた。
そして、そのあとのめぐむの中の押し殺した秘密。それは河の轟音と雨の記憶。あのとき聞こえたように思った声は、母の悲鳴だったのか、あざ笑う声だったのか。
それから、だった。この世の中に自分は触れてはいけないと、強迫観念にような思いに囚われた。会社にも出れなくなった。食べ物も、口に入れた瞬間、吐き気で喉を通らない。自分は誰からも望まれていない、この世の中にいてはいけない。望んでいた唯一の出口は、自分が思っていたものではなかった。その思いだけが、じっと息を潜めるめぐむの頭に、呪文のように巡る。
太田さんが家主さんと一緒に、合鍵を持ってめぐむのアパートの扉を開けたのは、めぐむと初めて警察で会ったひと月半ほど後だったらしい。暗い部屋の中で、片隅で痩せこけためぐむの目の光だけが、傷ついた動物のように光っていた。それが、後で見舞いに来てくれた太田さんが無理に笑って言ったことだった。
病院で健康を取り戻しためぐむが、この特殊清掃の仕事をしようと思ったのは、懺悔だったのか。
今でも答えが出ない。
めぐむは、考えないように、仕事を仕事として目の前の影とシミを見つめる。
あの冷たい汗の感覚を感じながら。
第7 2つの問い
あの突然の失礼な態度を聡二さんに許してもらえるだろうか。
週末に再び教会を訪れようと思ったとき、なによりもめぐむの思ったことはそれだった。その思いが頭を離れないのに、なぜめぐむはまた教会に行こうと思うのか。聡二さんの話が気になったのか。それとも、「富永さんだけだよ、自分を必要だと言ってくれた人は。」といったあの年老いた男性の言葉がそうさせるのか。
人から必要とされる、それは何だろうとずっとその言葉が頭から離れないまま、めぐむは軽トラを走らせる。しばらくは抑えていたはずの過呼吸とパニックが再び起こるんじゃないかと、運転しながらめまいがしているように思う。呼吸に意識を集中して、じっと前を見る。教会の白い建物が見えて車を駐車場に止めたとき、どっと疲れを感じる。
今日は、もうこのまま帰ろう。車から降りて教会に向かう足が何度も止まる。でも、今日行かないともう二度と聡二さんの教会には行くことはないような気がする。
ゆっくりとひきづるように足が教会の方に進む。
めぐむは、教会の大きな扉の前で立ち止まる。スマホの時計を見ると、まだ、朝の9時前だった。教会に集まる人はまだいない。大きく息を吸い、目を瞑る。ここまで来ても、まだ、決心がつかずにいる。思い詰めたように教会の前で佇む自分は、深刻な悩みを抱えた近寄り難い変な人と思われるかもしれない。いつもの白い大柄のシャツの下で、背骨の窪みを一筋の汗が落ちるのが分かる。
だめだ、帰ろう。
振り返ろうとしたときだった。
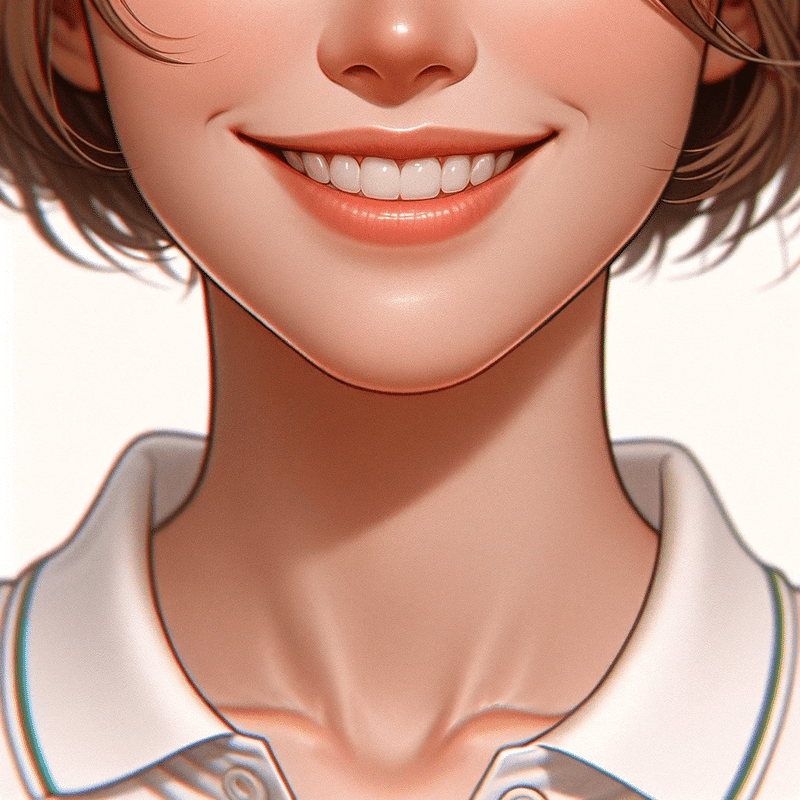
「あら、吉野さん」
誰かの手が背中にそっと触れた。
目を開けて、振り返る。白いポロシャツ姿の若葉さんがいた。微笑んでいる。初めて会ったときも、啓介さんと一緒に口数少なく教会にきた人たちのお世話をしていた。その印象のまま、めぐむの背中に軽く手を当てて微笑んでいる。
背中に手の平の温もりを感じる。
「いらっしゃい。」
