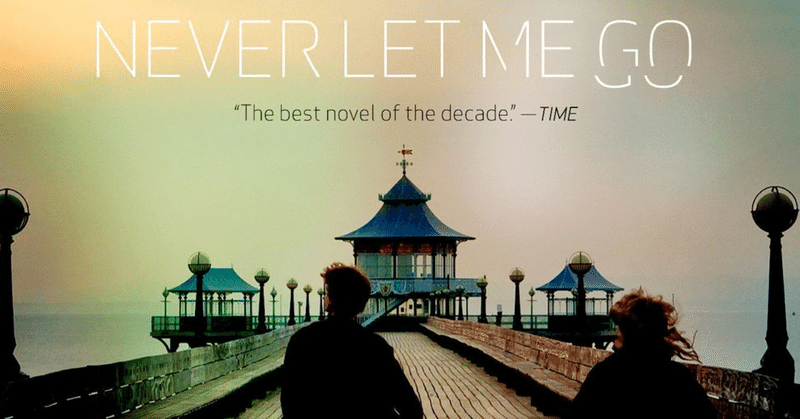
私的 "カズオ・イシグロ" の正しい読み方
Sir Kazuo Ishiguro
今回は、イギリスの小説家、サー ”カズオ・イシグロ" について ”note” していきたいと思います。

好きなんですよね~。
2017年にノーベル文学賞を受賞した現代作家さんなんですが(が?)、一部を除いて読みやすいし、面白いんです。
誤解を恐れずに言うと、SFやミステリーを好んできた自分にとっても ”合う” 感じがするんです。
まあ、世界的な作家さんだし、ノーベル文学賞の受賞後にブームがあったし、何を今さらって感じもするのですが、 ”カズオ・イシグロ" 氏の本をあまり読んだことのない方は、次に新作が出るまでの4~5年の間が、既刊を読破する機会だと思うんですよね。
ということで、私なりにサー ”カズオ・イシグロ" の作品を読む楽しさについてまとめていきたいと思います。
+ + + + + +
◎コンプリートできる作家さんであること
2022年1月現在、 ”カズオ・イシグロ" 作品は、長編が8作、短篇集が1冊しかありません。
寡作な作家さんなんですよね。
その全ての本が邦訳されてるんで、全著作をコンプリートすることが可能なのです。
1. 遠い山なみの光 1982年
2. 浮世の画家 1986年
3. 日の名残り 1989年
4. 充たされざる者 1995年
5. わたしたちが孤児だったころ 2000年
6. わたしを離さないで 2005年
*夜想曲集 2009年(短編集)
7. 忘れられた巨人 2015年
8. クララとお日さま 2021年
ノーベル文学賞作家の作品をコンプリートなんて、なんか誇らしげじゃないですか?
難関となる作品はありますが、決して手の届かないものじゃないんで、次作が出るまでの間、ゆっくりコンプリートしていくのは楽しい読書になると思うんですよね。
◎あらすじは読まない方がいい
さて、"カズオ・イシグロ" 作品を楽しむ上で最も大事なことの一つは
事前情報を入れないことだと思っています。
どの本でもそうかもしれませんが、"カズオ・イシグロ" 作品では、特に大事なことだと思うんです。
できれば、本の裏表紙等にある「あらすじ」とかも読まない方がいいんじゃないかと思います。
と、いうのも
"カズオ・イシグロ" 作品のほとんどは、主人公の1人称で語られる形でストーリーが進行するんで、読者は主人公が見たこと、聞いたこと、感じたことを通して、その作品世界を手探りで進んでいくことになります。
読み進めていくと、主人公と一緒に、少しずつ世界が広がっていくような感覚が得られるんですが、その感覚が "カズオ・イシグロ" 作品の楽しさなんです!
もちろん、作品世界や用語について、ほとんど説明がないため、最初の方は、限られた情報しかなく、ちょっとモヤモヤするのですが、焦らずに、ゆったりと読み進めていくと、上質な "カズオ・イシグロ" 感を体験することができるはずです。
そのためには、「あらすじ」や「感想」などの事前情報には出来るだけ目を通さず読み始めることがお薦めなのです。
よく "カズオ・イシグロ" 作品に登場する1人称の主人公(語り手)のことを「信頼できない語り手」 と評する記事を見かけます。
この言葉だけを見ると誤解が生じそうなのですが、例えば、ミステリーでは、嘘をつく語り手(または、本当のことを語らない語り手)が登場することがあります。でも、 "カズオ・イシグロ" 作品の語り手は、嘘をついて読者を騙そうとしているわけではないのです。
たしかに、読者に情報を伝えるべき語り手なんですが、その語り手自身が理解が足りなかったり、誤解していたり、見方が違っていたりすることがあるのです。 "カズオ・イシグロ" 作品では、その部分にこそ、作品テーマと直結する部分があったりするので、いわゆるミステリーにおける「信頼できない語り手」とは違いがあるように感じるのです。
◎最初に読むなら…
8作ある長編はすべて独立しているので、どの本から入っても問題ありません。なので、タイトルや装丁など、自分の好みやインスピレーションで選ぶのも良し!なのです。
が、はじめて "カズオ・イシグロ" 作品を読む人に、あえて、読みやすいと私が思う3冊を紹介すると
「クララとお日さま」2021

現段階で最新長編である本書は、物語性と"カズオ・イシグロ" 感のバランスのいい作品で、抜群に読みやすいので、海外文学とかを苦手にしてる方でも、入口としてはピッタリだと思います。
主人公となる語り手は『AFのクララ』なのですが、このAFが何なのかという明確な説明はありません。
もちろん、あらすじ等には、クララのことの補足があったりするんですが、そこも含めて想像していくのが正しい読み方だと思うのです。
「わたしを離さないで」2005

おそらく、一番、ポピュラーな "カズオ・イシグロ" 作品だと思います。
語り手の出身であるヘールシャムがどんな場所なのかは、ぜひ、読んで確かめてもらいたいところです。
"カズオ・イシグロ" 作品の中でも、特に人気の高い作品で、2010年に映画化され、日本でも2014年に舞台化、2016年には、綾瀬はるかさんの主演でテレビドラマ化されています。(実は私も最初に読んだ "カズオ・イシグロ" 作品はこれでした。)
といっても、映画やドラマは観ていないんですが、ドラマが話題になったことがきっかけで読んでみたいと思ったのは間違いないのです。
そういう意味では綾瀬はるかさんに感謝なんですよね。うんうん。

「日の名残り」1989
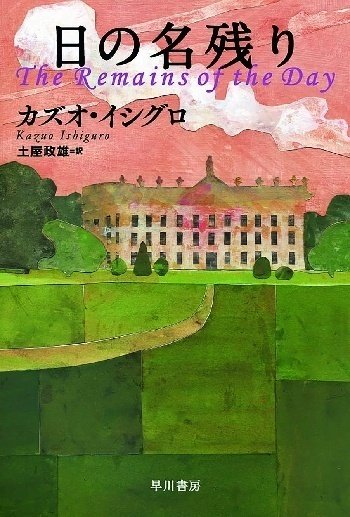
英国では「ブッカー賞」も受賞した作品ですが、淡々としてるのに惹きつけられる不思議な味わいのある作品なんです。
読み終わると、まさに『日の名残り』なんですよね~。
多分、自分的には1番好きな "カズオ・イシグロ" 作品で、40代で読んだのですが、50代でも、60代でも再読していきたい作品なのです。
◎逆に、最初に読むにはちょっと…
まあ、読みやすいものばかりではなくて、けっこう難物と思われる作品もあるんです。
「充たされざる者」1995
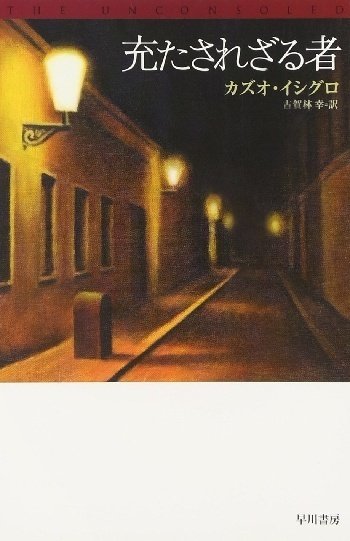
文庫で948ページもあるので、作家コンプリートする上で、けっこう歯ごたえのある1冊です。
長いだけならいいのですが、物語の構造も複雑で迷路のような感じなんですよね。
"カズオ・イシグロ" 作品は「あらすじ」を読まない方が… と言いましたが、この作品は例外かもしれません… でも、安心してください。「あらすじ」を読んでみても、よくわからない状況は変わりません!w
まあ、この作品は、物語が進まないことにイライラせずに、たくさんのエピソードそれぞれを味わいながら、迷宮をさ迷い歩くことを楽しむ小説なのです。
「わたしたちが孤児だったころ」2000

刊行順でいえば「充たされざる者」の次の作品になります。
全編ではないものの、「充たされざる者」と同じく迷宮を歩かされるような部分があって、読みにくさを感じた作品です。
多分、この時期は、そういう方向性だったのでしょうね。
この2冊は、最初に読む作品としてはお薦めしないのですが、じっくりと読んでいくにはいい作品なので、慣れてきた頃に手に取るといいと思います。
◎その他の長編
「遠い山なみの光」1982
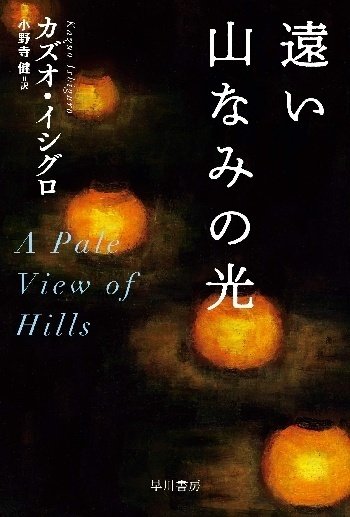
記念すべき、デビュー長編です。
まず、なんといっても、文庫本で275ページなんで、すいすいっと読めてしまいます。
長崎が舞台となってるので、それも読みやすくしてる要素なんですが、最後の方になると、あれ?っと思わせる部分もあって、デビュー作でも、ちゃんと "カズオ・イシグロ" 感を味わうことができるのです。
「浮世の画家」1986
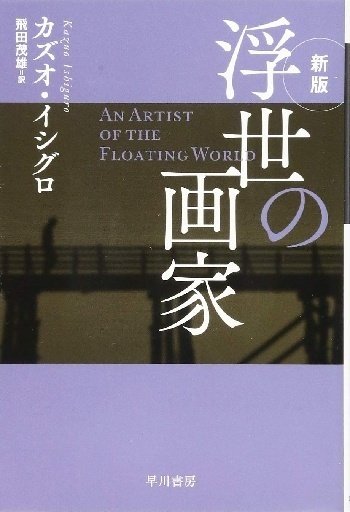
第2長編です。
これも、文庫319ページなんで、読みやすい長さなのです。
余談ですが、画像は新版で、私が読んだ旧版では表紙に”浮世絵”が描かれてたりしたんです。
このタイトルにその表紙なんで、すっかり「浮世絵師」の話かと思ったら、浮世絵なんてひとつもでてこないので、ご注意を!
多分、だからこその表紙カバー変更だったのだと思います。
「忘れられた巨人」2015
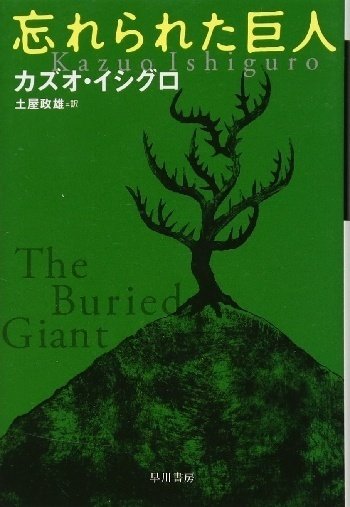
珍しく3人称で語られる作品なんですが、旅する老夫婦について回るドローンカメラのようなもんで、限られた情報しか与えられないことは同じです。
アーサー王の時代を舞台としたファンタジー的な色合いのある作品です。
曖昧で不明確なことこの上ない小説なのですが、その不確かさこそが、この本の主題なのです。
好き嫌いは分かれるかもしれませんが、よくわからないことを楽しむことが大事な作品なのです。
+ + + + + +
サー ”カズオ・イシグロ" の長編8作品を紹介しました。
同じ時代を生きてる作家さんなんで、新作待ちができるのが嬉しい事なんですよね。
それが日本にルーツを持つ作家さんだとなおさらなんです。
現在67歳の ”カズオ・イシグロ" 氏の新作が、あと何冊読ませてもらえるのか、ほんと楽しみなのです。
できれば2026年頃に読めるといいなぁ…
📖
