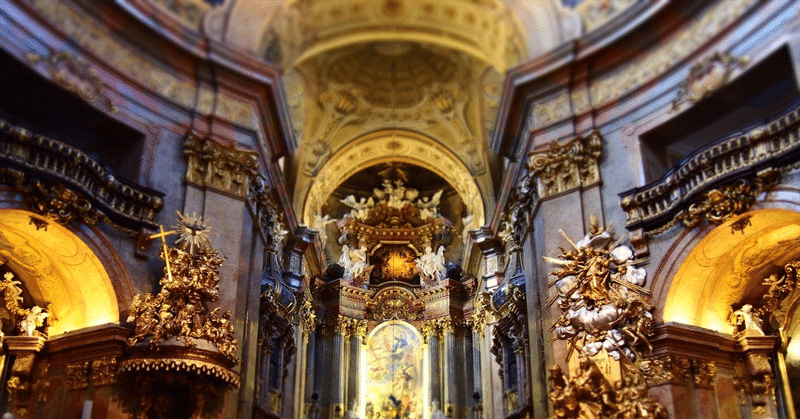
読後感想 「フリードリヒ・ハイエク」Ebenstein,Lanny(著) 田総 恵子 (翻訳)
私は伝記マニアで子供の時から図書館で色んな偉人の伝記を読んできました。伝記は人生という物語が凝縮されていて、ヘタなフィクションより何倍も面白いんですよね。今回紹介する本の主人公はタイトルの通りフリードリヒ・ハイエクです。
日本において有名な彼の業績は「隷属への道」という本でしょう。この本ではソ連がバリバリ元気な時代にハイエクは社会主義は崩壊する事を予見しており、しかもファシズムと社会主義は個人より国家を優先する点において本質的には同じものであると述べ、その2つの思想を喝破した。この本が出版された年は1944年という第二次世界大戦真っ最中という事もあり、この本は瞬く間にアメリカ、イギリスなどの連合国側に広まっていった。
ハイエクの思想は、チャーチルやマーガレットサッチャーなどによって世界中に広められ「新自由主義」の理論的支柱になった。彼は1974年にノーベル経済学賞を受賞し、1991年にはソ連崩壊という自身が思い描いたビジョンが現実になる所を見届けて93歳で亡くなります。
こんな風に紹介するとまるで最初から最後まで、彼の人生は上手くいった様に思われますが決してそんな事は無かったのです。
実は戦前、彼の経済学の学説はそこまで影響力を持っていた訳ではありません。なんといってもその頃の経済学界の中心にはケインズが君臨しており、彼はケインズに論争を挑んでいますが経済学の思想における両者の溝は深く(友人としては交流を続けていました)対立していきます。これまで仲間だった学者仲間もだんだんとケインズの学説の方に引っ張られていきハイエクはアカデミアの世界で孤立していきます。
その後彼自身も経済学の研究に愛想を尽かし、立法についての研究に没頭していきます。私生活の面でも離婚を経験したり、資金面が苦しくなってきたりします。そんな中でファシズムや共産主義の台頭に脅威を感じて書いた「隷属への道」が大ヒットしました。しかし、この本の印税は出版社との契約上、印税がハイエクにあまり入って来ずまたもや生活が苦しくなってきます。その後は祖国のオーストリアにあるザルツブルク大学で教鞭を取りますが、その大学の経済学部門は法学部の中の一つの学科に過ぎず、ハイエクの満足のいく研究環境では無かったのです。
そんな中突然、ノーベル経済学賞を受賞する事になり75歳で彼の人生は一転します。同じく経済学者のミルトンフリードマンが「1974年のノーベル経済学賞受賞がハイエクの命を救った」と述べる程にこの出来事のインパクトとは大きく
ハイエクはこの受賞によりローマ法王に謁見したり、イギリス女王と会食したりと一気に表舞台に出てくる事となります。そして先述の様に晩年にはソ連崩壊を見届け永遠の眠りにつく事になります。享年93歳の大往生です。
この本の素晴らしさはなんといっても引用の多さです。本人の著作からの引用は勿論、同時代にハイエクと共に生きた経済学者の著作からも引用も多くて著者の力量に驚かされます。また翻訳がめちゃくちゃ読みやすく、感動しました。原書が海外の本の場合、翻訳者の腕は本当に重要になってきます。ただ海外の言葉に詳しいだけでなく日本語力と専門知識の幅も問われてくるので、翻訳という仕事は大変だなといつも思っています。
分厚い本で面喰らいますが翻訳が自然だし、内容が面白いのでスイスイ読めると思います。二度の大戦を経験し、波乱の時代を生きた学者の人生を皆さんもこの本で追体験してみませんか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
