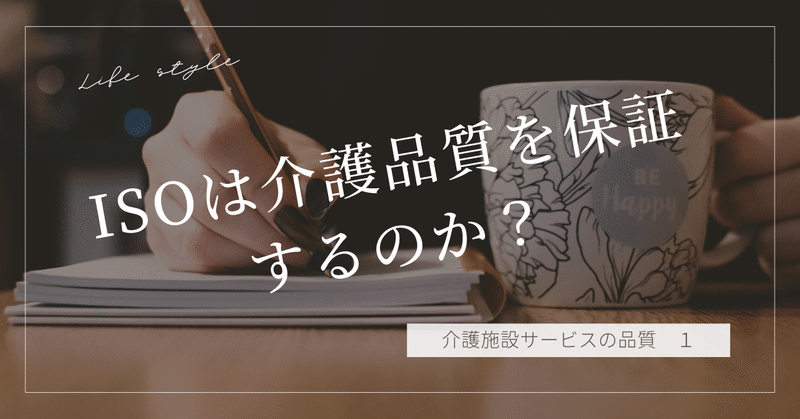
ISOは介護品質を保証するのか?-介護施設サービスの品質 1
よく、「介護サービスの品質向上」という掛け声を聞きますが、この介護サービスの品質について、じっくりと考えてみる必要があると思います。
じっくりと考えるといことは、何かの外部指標等に囚われたり、軽々に飛びついたりせずに、介護サービス利用者の視点を踏まえながら考えるということだと思います。
1.ISOとは
先ほど、外部指標に囚われずに、と記しましたが、外部指標、外部機関の評価ということで言えば、真っ先に頭に浮かぶのはISOではないでしょうか?
ISOとはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称ですが、このISOが定めているISO規格にISO 9001(品質マネジメントシステム)というのがあります。このISO 9001は顧客に品質のよいモノやサービスを提供すること、つまり『顧客満足』を目的としています。
自らのサービス品質の高さを示すために、このISO 9001を取得している介護施設がありますが、ISOの認証を取得するには、次の①から④までをしっかり行う必要があるとのことです。
① 日々の活動のルールを明確化にする(現在の活動を明確にする)
② ルールに従って活動する(普段通りの活動を確実に行う)
③ 日々の活動において、間違いや問題がないかを確認する
④ 課題や問題を改善する
ようするに、ISO9001の認証取得のためには、品質改善のためのPDCAサイクル[1]ができているかがポイントとなっているようです。
また、このISO9001の認証取得は「日頃から適切にケアがおこなわれているか」に対して承認されるものとされています。
ISOが前提とするPDCAは計画が前提にあり、安定的な状況が想定されています。そして、PDCAは計画に従って実行することに執着してしまうことから、想定外の事態への対応が不得意です。
介護の特性は当事者(被介護者・入居者等)の、不安定(Volatile)、不確実(Uncertain)、複雑(Complex)、曖昧(Ambiguous)な状況への迅速かつ適切な対応が求めらられるところにあります。VUCAへの対応が介護の基本にあることだと思います。
私はVUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)な状況・事態への対応である介護にPDCAは不向きではないかと思っています。
2.介護の国際規格
今までは、介護事業者がISOを取得するとすれば、サービス業のISO9001を取得することが多いのですが、介護事業専門のISOができるというニュースが流れています。
「169カ国で構成する国際標準化機構(ISO)は2025年にも介護サービスの質や安全性に関する基準をつくる。経済産業省など政府は高齢者向けの食事提供や事業者の経営情報公開といった日本基準の反映をめざす。」
国際標準化機構(ISO)が介護領域の国際基準を作ろうとしているらしいのです。
経済産業省は、日本の大手介護事業会社の海外進出を後押しするために、この国際規格に要介護高齢者の摂食量や嚥下機能を考慮した食事の提供、適切な栄養を摂取できる献立の作成、身体機能の維持や改善につなげる科学的介護の考え方などの日本基準を創設される国際基準に取り入れるよう働きかけているようです。
この国際基準ができると、介護の世界にも、またまたISOブームが押し寄せてくるかもしれません。
しかし、このようなISO・標準化が、VUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)的状況下での相互行為である介護の品質向上につながるとは思えません。
介護が分かっていないから、そんなことを考えるのではないでしょうか?
3.ISOは介護の核心に触れない
介護とは本来的には、介護される者と介護者との相互行為ですが、ISOで評価するのは、介護する者たちの活動・業務と組織です。
ということは、ISOは被介護者と介護者との相互行為としての介護ではなく、介護を介護者の一方的な行為とすることを前提としています。
つまり、ISOは介護の核心に触れることがないのです。
ISOの評価と相互行為としての介護の評価は別物なのです。
介護は介護される者のニーズがその起点であり、そのニーズが満たされたか否かを判断する権利を有しているのは原理的には介護される当事者(入居者)です。
入居者のニーズが満たされているか否かを介護の相互行為の外部にいる第三者に委ねることができるニーズというのは客観化・数量化されたものでしかなく、入居者と介護者の相互行為から生ずる主観的満足、感情交流、信頼関係とかは全く考慮する余地はありません。
よって、ISO認証を取得しても、決して良い介護、適切な介護を原理的に保証できないと私は思っています。
4.介護は定型業務だけではない
また、相互行為としての介護はISO、PDCAが前提とする定型的業務だけで成り立っているのではありません。
介護は当事者一人ひとりのその時々の心身の状態に応じて、コミュニケーションを図りながら細やかな配慮とそれを実現する技術で成り立っています。
介護はVUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)的状況下での相互行為ですので、介護の中核は最もマニュアルにしづらいものなのです。
私は、近内悠太(哲学者)さんの次の言葉がとてもアイロニカル(ironical)で、かつ介護とマニュアルの関係についての的確な表現だと思っていて好きな言葉です。
「硬直したケアはたしかにマニュアル化できる。」
ISOは相互行為である介護を介護者の一方通行の活動・業務と見做すところにその限界があります。
ISO認証取得を目指すプロセスにおいて、介護が相互行為だという最も肝心なことを忘却してしまうとしたら本末転倒となってしまいます。
5.介護のシステム化
ISOは品質マネジメントシステムだといいます。ですから、介護のISOとは介護の品質マネジメントシステムということになり、介護のシステム化を推進するものとるのでしょう。
ここで、システムという概念について検討することも必要だと思います。
近内悠太(哲学者)さんは、システムについて次のように指摘しています。
『「システム」は個別の出来事を考慮できません。
個別の出来事に配慮するシステムというものは存在しません。それは端的な形容矛盾です。そして、システムに従順な者は思考する必要がありません。なぜなら、全てはシステムが決定してくれるからです。そこでは、「決まりですので」というまさに決め台詞がきちんと用意されています。』
「システムは個に対するケアを行えません。なぜなら、人間という存在は不合理だからです。」
介護は原理的に個別性の高い相互行為です。一人ひとりの違う人間の相互関係だからです。この個別性の非常に高い介護をシステム化するということについてもっと深く考えていく必要がありそうです。
介護は、あらかじめすべて決めてかかったり、コントロールし過ぎたりするのではなく、その日の条件の中で、偶然に任せて決めていくクロード・レヴィ=ストロース[2]の言うブリコラージュ[3]なのだと私は思います。
6.サービスは味わうもの
そもそも、私たちは、一般的にレストランなどを選ぶときに食べログの点数やミシュランガイドを参考にする人はいるかも知れませんが、ISO認証を受けているか否かを気にすることは、まずありません。
やはり、実際に自分が食べてみなければ評価はできないでしょう。食するのは自分なのですから。
介護はレストランのサービスよりもはるかに複雑で個別なものです。ISOの認証を取得するより、当事者(入居者)の傍らにいて、入居者の言葉に耳を傾け、入居者の表情を注意深く観察し、入居者とコミュニケーションをしっかりとりながら、入居者の潜在的、顕在的な訴えに応答しているか否かが、適切な介護か否かを判断するポイントでしょう。
ISO認証取得に頼り切るのは、味がわからないレストランオーナーのようなものです。
経営者は実際に介護現場に出て自社の介護の味を賞味すべきでしょう。自分が食べたいと思えるような味なのか否か(将来、自分が受けたい介護なのか否か)、慎重かつ正直に見定めるべきだと思います。
7.ホモ・サピエンスだから「味わう」
私は何かを評価する場合には、「味わう」ということがとても大切だと思っています。眺めるのでもなく、「味わう」とは、その「もの」・「こと」に直接触れて、消化する、そんなニュアンスがあると思います。
哲学者の國分功一郎さんは、人類、ホモ・サピエンスは「味わうこと」に由来すると指摘しています。
國分:『人類を指す「ホモ・サピエンス/homo sapiens」の「sapiens」というのは、ラテン語の「sapor(味わうこと)」という言葉に由来するのだそうです。
ギリシャ語のソフォス「sophos」も、「知」や「賢さ」など、技術的に熟練していることを意味するのですが、これも語源的には「sapio(味わう)」の仲間だそうです。
人類の語源である「味わう」ことを、介護サービスの評価の基本にできないものかと考えています。
問題はこの主観的な「味わい」を相互主観化できるのかということではないでしょうか?
人それぞれ好みは違いますが、誰にとっても毒は毒です。
このような観点からすれば、介護サービス評価の大原則はabuse/虐待の有無、頻度、程度については相互主観的な判断の可能性ガあるのかもしれません
[1] PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念。
[2] フランスの社会人類学者、民族学者
[3] ありあわせのものを寄せ集めて、必要な道具などを自分で作ることを表す概念
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
