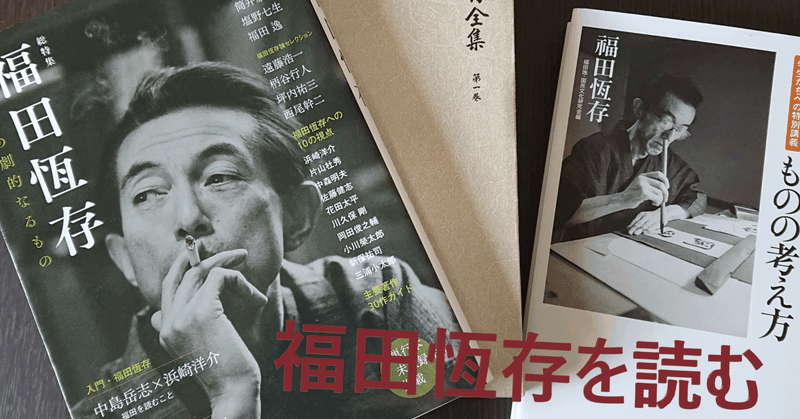
『小説の運命 Ⅱ』すなわち批評の運命
『小説の運命 Ⅱ』は昭和二十三年に発表された。まず冒頭の引用から始めたい。
「「小説の運命」といふ課題は、すでにそれ自体において、ぼく自身の精神が明確にみづからの存在を確証しうる様式の探求を意味するものにほかならない。「小説の運命」のそとにぼくの精神の運命は考へられぬ。」
明治以来、近代日本の作家たちがそれぞれの方法でもって一途に探求してきたのもこの「精神が明確にみづからの存在を確証しうる様式」であったといえよう。
二葉亭四迷をはじめ、近代日本文学の発想と系譜は、大方、十九世紀ヨーロッパ文学の文学概念にその様式の模範を求めてきた。
しかしその後に誕生した日本的私小説という文学形式はついにかれらの精神のための「鞏固な形式」の役割を果たせず、結果としてかれらの「文学にたいする猜疑は増大して、つひにこれに固執する情熱を危殆に瀕せしめ」ることとなった。
既存の小説様式では現代の精神の危機は救えないのではないか。それほどまでに精神の危機は深刻なのではあるまいか。
日本において最初にそのような疑惑を明確に意識した批評家こそ、小林秀雄である。小林の登場によって「小説の運命」と「批評の運命」とは軌を一にするものとなった。
「小説の危機に最初に気づいた批評家は、日本では小林秀雄であるが、このときから批評は「小説の運命」に拘泥せずしてものがいへなくなつたのだ。作品の解説や評価が低級なしごとだなどといふのではない。小説の危機に気づいたものの眼には、解説や評価にたへる作品などといふものは近代日本の文学史のうへに存在しなくなつたのであり、また解説や評価どころのさわぎではなくなつたのである。」
「そこで、小林秀雄のしごとは小説の否定抹殺にむけられた」と福田は述べる。「小林秀雄は現代精神を危機にあると感じたればこそ、小説を捨てて批評をおのがしごととして選んだといふわけである。にもかかはらず、いまだ小説を捨てぬ人間があるとすれば —— かれらにかれは軽蔑と攻撃とをもつてたいするよりしかたなかつたであらう。おれは小説を書かないのに、なぜ諸君は書くか —— といへば、ぼくらしく嫉妬めくが。」(『小説の運命 Ⅱ』福田恆存全集第一巻)
小林の慧眼は、自己の精神のクリティック(危機的)な状態を見逃しはしなかった。精神がクリティックな状態にあるということは、自己のうちに無限の対立を含むということである。要するにそれは、造型と均衡が不可能なほどに旺盛な批評精神の躍動ともいえる。その点にまた「批評の自恃」も生ず。
「ただ造型的安定といふこと、その点においてのみ批評はおのれのインフェリオリティを感じてゐるのにほかならない。が、そこにまた批評の自恃がある—— たとへ造型性を犠牲にしても、すくなくとも現代の精神的危機だけは、おのれがまつかうから耐へてゐるといふわけである。批評の立場からみれば、この宿命に耐へてゐるかぎり、いかにして造型が可能であるか、どうしても現代小説家の心事が理解できぬのであり、結局のところ、かれらは真に危機を感じてはゐないのだ、と決めてしまふよりほかにしかたなかつたのである。」
小林によって行われた「小説の否定抹殺」という仕事を目にして、若き福田は批評家として己れの歩む道を直観したのではないだろうか。いやむしろ正確に言うなら、福田をして小林の批評精神に共鳴させたものこそ、福田自身の批評精神に他ならない。だが批評家の真に成すべき仕事はさらにその先にある。
福田は言う。
「批評家にして小説の限界と危機とに気づかぬものはすでに論外である。とはいへ、大切なのは危機の状態にあること、ないしはそれを自覚することではなく、そのうちにあつてしかもなにをするかといふことだ。小説家にたいする軽蔑と嫉妬 —— それもいい、が、批評はそれを超えて、いつたいなにを意思するのか、いかなる世界を自分のものとしようとしてゐるのか。つねにクリティックであるといふことは、自分自身のクリティックな状態にたいしてすら、なほ対立的に立ちむかはうとする精神形態を意味する。」
批評精神とは「自分自身のクリティックな状態にたいしてすら、なほ対立的に立ちむかはうとする精神形態」である。だとすれば、無限の対立の中から如何にして自己の真実の保証を得るか。まさしくそれが批評家の直面する課題であろう。
福田の言葉で言えば、「安定を嫌ふ精神の安定、造型性をのがれようとする精神の造型、真実をつねに懐疑する精神の真実 —— その保証と定着とは、はたして可能であらうか」、そういう問いかけとなる。
これこそ批評家が本当に対峙せねばならぬ問いである。そこで福田はまたしても、ひとつの解答を小林秀雄の仕事に見出す。
「かれは賢明にも日本の近代を放棄した。かれの関心はヨーロッパと日本の古典とに向ふ。ドストエフスキーとモーツァルト、実朝と西行である。批評はそれ自身のうちに造型力をもたない。いや、造型性そのものを破壊するのが批評精神である。とすれば、批評はその対象として、ゆたかな造型性をめぐまれた作品を採つたときにはじめてその幸福を実感するのである。そのときはじめて批評は造型的安定をもちうるのであり、批評家は真に批評のたのしみを味ふのである。真の批評文学の成立は、近代日本の作家と作品とを対象としてゐるかぎり、ほとんど絶望であるとしかおもはれぬ。」
その後、批評家として福田が辿った道は小林の道と如何に共通し、如何に相違したか。それは私の大きな関心事である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
