
中世以降のヨーロッパ軍事史を概観した『ヨーロッパ史における戦争』の紹介
歴史学者ブラウンは『近代ヨーロッパの起源(The Origins of Modern Europe)』(1972)という著作の中で「ヨーロッパの起源は戦争という鉄床の上でたたきだされたのだ」と書いたことがあります。
実際、ヨーロッパの歴史は相当の期間が戦争の歴史で占められており、特にローマ帝国の支配が崩壊した5世紀以降は、ヨーロッパ各地で武力による争いが繰り返される時代が続き、長期にわたって単独の勢力により統一されたことがありません。
したがって、ヨーロッパの歴史を学ぶためには、その地域で起きた戦争の歴史についても知ることが必須になります。イギリスの歴史学者マイケル・ハワードの著作『ヨーロッパ史における戦争(War in European History)』(1976)は中世から第二次世界大戦までのヨーロッパの戦争史の流れをコンパクトにまとめた概説書であり、この分野の基本文献として位置づけられている一冊です。
この記事では、ヨーロッパの戦争史でも特に重要な転換期である中世から近世までの議論を紹介しようと思います。
マイケル・ハワード『改訂版 ヨーロッパ史における戦争』奥村大作、奥村房夫訳、中央公論新社、2010年
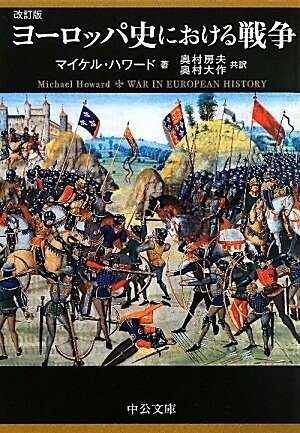
目次
1 封建騎士の戦争
2 傭兵の戦争
3 商人の戦争
4 専門家の戦争
5 革命の戦争
6 民族の戦争
7 技術者の戦争
封建制の下で遂行されていた戦争
中世のヨーロッパに成立した封建制は、もともと軍事的に必要な兵力を確保するように設計された制度であり、特に騎兵部隊の編成が重要視されていました。このことは中世ヨーロッパの戦争の歴史を理解する上で重要なポイントであると著者は述べています。
866年、カロリング朝の西フランク王シャルル二世(在位843~877)は、土地を与えて生活を保障した見返りに、臣下の騎士に軍馬を伴って軍役に就くことを厳しく命じました。軍馬の維持に多額の費用を支払わなければならなかったものの、当時の農業生産が中心の経済構造において自分の領地と領民を支配できることは、それを上回る経済的な報酬でした。
そのため、騎士階級にあった人々は長い時間をかけてでも騎兵戦の技術を身に着け、武装を改善し、それを子孫に継承するように努力しました。ただ、封建制は国王の権力をさまざまな側面から制約していました。封建制の下で国王は臣下と軍役に就かせる契約を個人的に締結していたにすぎず、臣下の行動を国王が無制限、無条件に統制する手段や権利を持っていませんでした。
フランスではフランドル、ブルターニュ、プロヴァンスなどに定住した貴族の権力が強大化し、国王に従わない地方政権と化した歴史があります。このためにフランス王は徴税の機能を強化し、独自に傭兵を雇用し、常備軍を編成する必要に迫られました。その結果として、カペー朝のフランス王フィリップ二世(在位1180~1223)の治世では徴税の拡大と王領の整備、そして軍制改革が進み、フランスの勢力は大きく拡大することになりました。
もちろん、歴史学者が何度も論争してきたように、ヨーロッパにおける封建制の形態は時代や地域によって多種多様でした。例えばイングランドでは当初から国王の権限が弱く、また国土地理上の特性から騎兵よりも歩兵が必要とされる場面が少なくありませんでした。このために、軍事制度の発達も独特な経路をたどったことを著者は説明しています。
イングランド王のエドワード一世(在位1272~1307)はウェールズとの戦争を通じて長弓(ロングボウ)を歩兵の新しい武器として取り入れたのですが、長弓は訓練にかなりの時間を要する武器でしたが、射程が大きいだけでなく、矢を射る速さで非常に優れていました。
百年戦争でイングランド軍とフランス軍が激突したクレシーの戦い(1346年8月26日)で長弓隊は大きな戦果を出しました。これは封建的騎士階級の軍事的意義が急激に低下したことを示す象徴的な出来事であり、イングランドに軍事的優位をもたらしました。
しかし、フランスに対するイングランドの軍事的優位は長くは続きませんでした。フランスが火砲を調達し、砲兵隊を編成するようになったことで、戦争の様相が大きく変化したためです。火砲がヨーロッパの戦場で使用されるようになったことで、戦争の様相に大きな変化が生じてきました。
国王の権力拡大と近代的な軍隊の発達
著者が述べているように、ヴァロワ朝のフランス王シャルル八世(1483~1498)はヨーロッパで初めて近代的な軍隊を編成した君主と見なすことができます。彼が指揮した軍隊は、歩兵、騎兵、砲兵という3種類の戦闘職種の部隊から編成されており、その給与は国庫から支出されていました。
ヨーロッパの歴史学者の間では、近世史の原点をシャルル八世がイタリアに侵攻して始まったイタリア戦争(1494~1559)に求めることが通例となっていますが、これは戦争史の立場から見ても妥当性があります。
シャルル八世の砲兵隊は封建領主が拠り所としてきた城壁をたちまち破壊する能力で恐れられ、多くのイタリアの都市が戦わずして降伏してしまいました。しかし、イタリア戦争を通じて、分厚い堡塁を築くことによって、敵の砲兵の火力に対する防護ができることが分かってきました。
攻囲する側も砲兵の威力だけに頼ることができなくなったので、多数の兵士が地面に塹壕を掘りながら敵の要塞へ接近していく攻城戦の手法が編み出されました。この作業には多数の人手が必要となったために、国王は多数の傭兵を雇用し続けるための賃金の支払いに明け暮れました。
この戦費の支出を維持する上で国王にとって欠かせない収入になったのが植民地貿易でした。著者はヨーロッパの戦争史において植民地貿易がもたらした富の重要性を次のように論じています。
「ヨーロッパ企業の海外膨張と、ヨーロッパ人同士の内紛との間の、たえざる相互作用が事実存在していた。膨張は、それらの内紛に対してより一層の資源を供することになったし、またかなりの程度その内紛によって引き起こされもした」(74頁)
16世紀に新航路を切り開く探検が次々と実施され、入植者や企業家がラテンアメリカの植民地事業に乗り出したことは、ヨーロッパ各国の君主が大規模な軍隊を維持することを可能にしたために、戦争の形態にもさまざまな影響を及ぼしました。
その影響はヨーロッパで海軍が陸軍から独立した軍種として発達を遂げたことからもうかがわれます。16世紀のヨーロッパ諸国は海外植民地との交易路を行き来する商船を護衛するために海軍を必要とするようになりました。特にスペインは大西洋、インド洋、太平洋を渡る航路を発見し、その貿易で得た富を守るために、巨大な火砲を搭載した軍艦で艦隊を編成しています。
まとめ
全体を通してハワードの議論が持つ利点は、非軍事的な要因である政治的、経済的、社会的な要因を積極的に取り入れて議論することによって、軍隊の制度や戦略・戦術に注目するだけでは読み取ることができない戦争史の大きな流れを明らかにしているところです。
封建制の制約からいち早く脱却したフランス王が常備軍を発達させたことは先に述べた通りですが、17世紀から18世紀にかけて繰り返された戦争で財政の収支は悪化し、1789年のフランス革命が起こる原因となりました。しかし、その後のフランスで国民に対して兵役義務を課す一般徴兵制が導入されたことによって、ヨーロッパの軍拡競争は新しい段階に移行しました。このような大きな流れを捉える上でハワードの著作は優れた文献だと思います。
ただし、戦争形態の長期変動を捉えることを第一にしているので、個別の戦争に関する記述は簡潔であり、第一次世界大戦、第二次世界大戦といった20世紀の世界情勢を決定づけた戦争の歴史はごく簡単にしか触れていません。ハワードの著作を手掛かりとした上で、他の文献を利用しながら理解を深める必要があるでしょう。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
