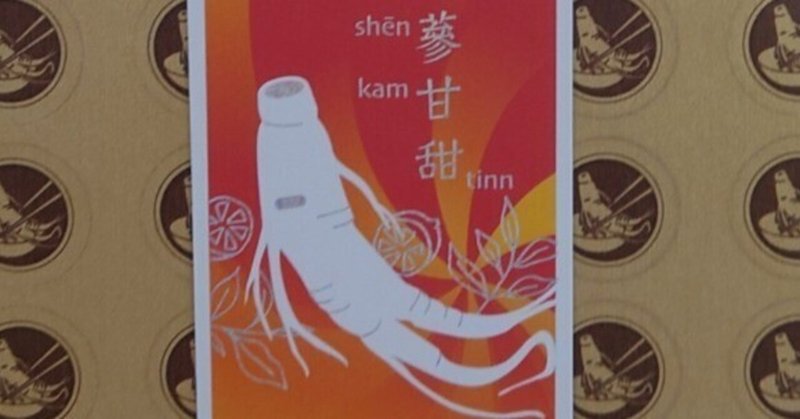
白昼夢の青写真2次創作を経験して、改めて習作したこと。
種を植えてみなければ、芽はでません。どんなことでも、上手くなるまでが大変です。自分の小説が上手くなるかどうかはわかりませんが、今日は久しぶりにオリジナルの小説を書いてみました。日本橋ヨヲコ先生へのオマージュです。
9月10日に、noteに初めてのオリジナル小説を書きました。自分自身、あれは小説なのかと懐疑的でしたし、twitterの友達にも「むしろ随筆だね。」と言われました。おっしゃるとおりだと思います。
今日の話は、「白昼夢の青写真」という作品の二次創作をしているとき、とある話を書いた後に感じた、自分の心中を題材にしています(フィクションですよ。)。超短編です。これもまた、やはり小説なのかと言われれば、甚だ疑問です。
「妄想中毒」
「どうしておれはこうなのか。」
ディスプレイに表示される多くの否定的なコメントを前に、堺はまず、そう思った。そして形容しがたい寂しさと悲しみが、彼の胸に去来した。
堺龍之介の趣味は、二次創作小説を書くことだった。書いた小説は、「noots」という、主にテキストコンテンツで表現を行う者を対象としたウェブサイトに掲載している。作品を投稿し、タグを打ち、また違うSNSで投稿の告知を行い、作品の鑑賞者を募る。
堺自身、普段はクリエイティブな世界とは無縁な場所におり、元々は人に読ませるための話を書いたことなど一度もなかったが、1作目を書きあげて以降、2年3年と作品を書き続けるうちに、それが習慣となっていった。
作品の質はともかく、どんなことでもこつこつ長く続けていれば、それなりにファンというか、継続的に、彼の作品に目を通す読者も増えていくようだ。この界隈でいうフォロワーの数も、1000名を超えた。
彼の最近の二次創作小説のモチーフは、とあるビジュアルノベルだ。16世紀頃のイギリスを舞台に、主人公たちの成長、覚悟、情熱、恋愛、表現、演劇、信仰、階級格差等々といったテーマに盛り込んだ、意欲作だ。
その完成度は、近年のビジュアルノベルでは出色で、PCゲームから出発したこの作品は、評判が評判を呼び、昨年には国民的ハードへの移植がなされ、着実にファンの数を増やしていった。
3日前に堺が書いた、この作品の二次創作小説の、とある表現内容を理由に、原作のファンの一部で炎上が起こった。モチーフとなる原作では、人間の良心や寛容さ、やすらぎの象徴として描かれていたキャラに、堺は、惨忍な手口で人をなぶり、そして殺人を行わせた。
これが原作のファンの大変な不興を買ったようで、勝手にキャラクターを改ざんするな、キャラクターへの愛を感じない、世界観をまったく理解できていない、猟奇趣味をこの作品に持ち込むな、サイコパスもどきめ、中二病野郎、といった意見が多数寄せられ、原作のファンが募る場においても拡散された。
堺のなかでは、テーマを持たせ、面白いとは何か、を計算して作り出した作品だった。面白いと感じてほしい、と願いながら書いた作品だった。それが、この結果だった。
もっとも、大物有名作家がパクリを行っていたというような話であればともかく、素人が書いた二次創作小説をわざわざ読みに来て、炎上という祭に参加して楽しむというほど暇な人間は、さすがに多くなかった。
住所や氏名が特定されるというような流れにまではならず、時間が経てば、そのうち鎮火するだろう。
ただ、堺自身がわりと繊細な性格なので、彼自身の感性が、世間の感覚との間に隔たりがあるということを改めて実感したという点に加えて、もうひとつ、気に病んでいる点があった。
「人の作品のキャラを貶めることは、原作者に対する冒涜なのではないか。」
堺が強く悔いていたのは、そんなことだった。
*
どうにも子供の頃からそうだ。意図せず、ズレる。仲良くなりたい相手との距離感を、関係性を、見誤る。みんなが喜んでくれると思ってした悪ふざけが、自分では面白いと思っている悪戯が、周りをドン引きさせた。
元来、いくらかお調子者だったおれは、何度も何度も人間関係における失敗を繰り返すうちに、内向的な性格になっていった。
そして、そうした傾向には拍車が掛かり、人と話していても、
「おれから話し掛けられて、嬉しいはずがない。」
「おれなんかと会話をさせられることになって、気の毒に。」
という思いに支配されるようになった。
買い物や仕事など、「日常生活を営む上で、仕事をする上で、やむを得ず」という場合を除けば、自ら他人とコミュニケーションをとることは、一切なくなった。
おれはそんな自分の姿勢を、他人への心遣い、配慮だとすら考えていた。気がつけば、他人は、水平線上の遥か彼方の存在になった。また、他人との間に生じた溝は、そこにはまれば、二度と這い上がれぬほどの深さになった。
おれの何が悪かったのか、未だにわからない。それがわからないこと、つまり自分自身の存在が、周りから、世間からズレてしまっていることが、最近はたまらなく悲しかった。
人と違った視点を持っているだとか、発想が個性的だとかと言われても、少しも嬉しくなかった。おれが高校生くらいになる頃から、世の中では個性の時代と言われるようになった。しかし、周囲と足並みを揃えられない個性は弾かれる。おれの中の普通は、常におれを悪目立ちさせてきた。
ずっと、「ふつう」がよかった。「ふつう」になりたかった。でも、「ふつう」が分からなかった。
*
堺にとって創作は、自分と世間の感覚の隔たりを確認して、自分のズレている部分を修正する作業でもある。書いて、読んでもらって、自分を「ふつう」にしてもらう。匂いのしない自分を作る訓練でもある。
作品のキャラクターは、作家にとっては「我が子」でもあるという者もいる。愛情を込めて作り込む。作り込みの確度と情熱が、そのキャラクターに命を宿す。やがて自分の足で歩き出し、時に作家の想像を超える動きをし、物語を終える頃に、作家のもとを巣立ってゆく。確かに、子になぞられるのも分かる。
「俺は、他人の子供の、尊厳を穢してしまったか。」
そこまでのことをしたという意識は、書いているときには露ほども無かった。作中では、背景が現代とは異なるし、個人の命や権利の重みが足りない時代だから、目的を果たすためなら、拷問や殺人くらいはするだろう、と、そのキャラの違う一面を描けた、と、満足すらしていた。だが、猟奇描写に不快感を覚える者は多い。少なくとも、堺が考えているよりはずっと。
堺自身、いわゆる「薄い本」を嗜まないわけではない。しかしながら、ハードな凌辱が行われる作品には、むしろ嫌悪感を覚えた。多くの人に愛されるキャラクターを壊して、そのキャラクターのファンの心を蹂躙するような真似をして、そんなことが楽しいのか、と怒りに似た感情を持っていた。
今回、堺がしたことは、堺の中ではそれに等しかった。原作者に対する耐えきれないほどの申し訳なさが、堺を襲った。
書いたもので他人を傷つけて、何が「ふつう」だ。これは、罰だ。物語を、自分の矯正の手段に用いたことに対する、物語の神様からの罰だ。物語は、人を楽しませたり、幸せにするものだ。
どうしておれにはそれができないのだ。自分が自分であることが許せない。
*
悲観的な方向への堺の妄想は、いつも留まるところを知らないが、そもそもこの話が、原作者の耳に入っているかどうかはわからない。耳に入ったところで、特に何も思わないかもしれない。起こってもいない事態を、自分の心の中に大きな問題として創出し、勝手に悔い、悩み、悶えるという行為は、この上なく無意味だ。
堺はこれからも、何の意味もないことに、そのエネルギーと時間を消費し続けていくのだろう。わざわざ自分から悩み事を探しに行き、ひとり苦しむというばかばかしい所業を続けていくのだろう。それに気付く日が来ることも、おそらくはない。
堺という人間は、「そういうふうに出来ている」のだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
