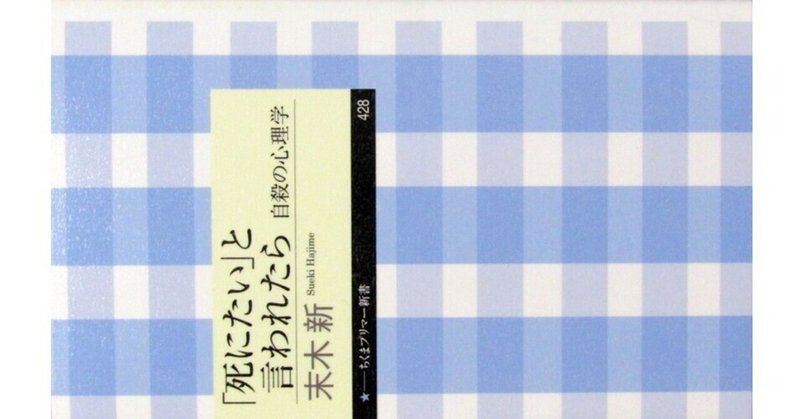
『「死にたい」と言われたら』(末木新・ちくまプリマー新書)
これは、テーマが重い。サブタイトルが「自殺の心理学」である。いまは「自死」という言い方が広まっており、すでに「自殺」という語が刺激の強すぎる語だと認定されつつある。だが、中高生にこの言葉を突きつけることになる。ちくまプリマー新書は、本来そこをターゲットに据えているからである。恐らく出版社側でも議論があったことだろう。だが、出した。その気概と向き合いたい。
著者はもちろん心理学畑の人である。まだ40歳になる年に書いている。だが著書を見ると自殺を中心に据えているようであり、特にネット絡みの自殺防止の団体への協力をしているようである。
そのため、言葉を選びながら、また対象となる読者の顔をとても気にしながら、執筆している様子が分かる。本書を手に取った人がかくかくしかじかである場合には、といったふうに、一人ひとり異なる立場や感情を非常に配慮しながら、場面を描いていくことになる。しかしまた、それでもなお、どのように受け取られることになるのか、分からないのも事実である。
それでいて、本書のタイトルは、自殺を仄めかす人に実際に遭遇した人をターゲットにしている。だから、そのニーズには応えなければならない。いったい、どう応えればよいのか。そのために、自殺をしようと考える人の心理について解説もするし、対応の方法を、一義的には決まらないにしても、アドバイスしなければならない。
ジレンマは、そうしたこの本の叙述を、「死にたい」と思う当人が読む可能性が十分にある、ということだ。そうか、自分はそういう心理でこう思っているのだな、などと冷静に受け止めることができるだろうか。否、そういう人もいるかもしれない。とにかく千差万別なのだ。こうすればよい、という万人のための特効薬があるわけではない。それでいて、逆にまた、こうすれば死ねるのか、という認識を与える危険性もないとは言えないのだ。実に書きにくい話題である。しかも、誰かが書いて、事の次第を伝え、共に考えてもらわなければならない。また、相談された対処しなければならない。
そういうわけで、これは実に苦しい本である。事実は書くべきだ。「死にたい」と漏らす人が皆自殺を図るわけではなく、そのうちのこれこれの割合くらいが実行している、という事実は伝える必要があるのだろう。だが、これを当事者が見たときに、俺はそんな意気地なしじゃない、という気持ちが生まれないとも限らない。なんとも辛い状況がそこに起こり得るわけである。
こういった苦しい事情を踏まえつつ、本書が描いているアウトラインだけはご紹介しよう。まず、以上の懸念にまつわるような、著者の「注意事項」から始まる。必要なことだろう。最初の章は「自殺はなぜ起こるのか」というテーマ。世間は、あるいは報道は、自分が納得したいために、何々を苦にしての自殺、というような言い方をするが、そんなに一意的に原因が決まるわけではないだろう。但し、本書で頻繁に触れられるが、著名人の自殺の報道については慎重にならないことが強調される。
次は「「死にたい」と言われたら」というから、本書の中心軸に入る。ある程度具体的に、当事者の心理を、「死にたい」と思わない人に対して開示する。相談されて切羽詰まった状態にある人は、まずここを開いてよいかもしれない。
さらに「「死にたい」と思ったら」では、当事者が見ることを配慮した形で、多少踏み込んだ形で告げる言葉が並んでいる。しかし、本当にそれへの傾向性をもつ人がここを読むだろうか、という心配もあるし、実際に読んだとしたらこれをどう受け止めるだろうか、というのも心配である。ここは、予備軍の人が予防的に読むのがベストなのだろう、という気がする。特に、家族や身内の人を自死で失った場合、「自分もそうするようになるのだろうか」という、暗示にも似た束縛を覚えることがあるという。その辺りへのブレーキ、というふうに捉えるのもよいかもしれない、と私は思った。
それから「自殺は悪いことか」と題して、善悪の観点から、少し距離を置いて論じている。自殺は悪い、という前提で、私たちは考えているのが通例である。だがそうすると、当事者は悪い人だ、というレッテルを貼られていることになる。それで当事者を理解することにはならないのではないか。もちろん、社会的に、あるいは法的には、自殺はよくないこととされている。社会通念としてはそうである。だが、倫理的に根柢を探れば、自殺を悪だと決める定かな理由はないかもしれない。
たとえば、キリスト教で自殺は罪だ、という言い方をすることがあるが、それはキリスト教の歴史の最初からではない。いろいろな解釈からそういう教義がつくられたのであって、聖書にそのように書かれているわけではない。しかし一旦これが教義になってしまうと、自殺者を裁くようなことさえ西欧では行われている。その墓を暴き、死体を罰したのである。
この問題は、ぜひ私もまた考えてみたい。調べてもみたい。哲学的に自殺を悪とすることは、カントも言っているが、それはもちろん道徳の原則から導くカントなりの規定である。生まれなかったほうがよかった、という近年の思想とも併せて、考察する意義があるだろうと思う。
最後に「幸福で死にたくなりづらい世界の作り方」がある。個人的事情に対しては完全に挑むことはできないだろう。だが、社会的に、制度的に取り組む最大限の方法はあるかもしれない、と考える。社会的意義である。自殺防止キャンペーンが、おもに年に2回ある。しかし、それがどの程度効果を上げているのか、という検証は見たことがない。実際なされていないのである。しかし、それをしなければ、キャンペーンを行う意義が分からないはずである。現実には、対費用効果も問題視されて然るべきである。人の命を経済で、という声もあるだろうが、政治の役割からすれば、これは必要な営みであるわけだ。
その政策にしても、現実にどのようなことをしていけばよいか、私たち全員の関心を伴いつつ考えていきたいものである。そんな方策が、と思われるかもしれないが、たとえば、自殺へ導くウェブサイトというものが現実にある。これへアクセスできないような仕組みを実現できれば、それを知ったばかりに死んだという人を少しでも減らすことができる。「死にたい」とSNSに書きこんだ人へ警告が出る、というだけのシステムなら、簡単にできるのだ。
しかしなお、日本では年間2万人は統計上自殺のために亡くなっていることが分かっている。その周辺に、大きなショックを受ける人が5人ずついるとすると、年間10万人の人が傷つく、という計算を著者はしている。もちろん数字は定かなものではないが、これは決して見逃してよい数字ではない。
では、何ができるか。実はいろいろ可能性があるのだ、と著者は言う。著者自身、血筋の人を自殺で失っているのである。傷ついた一人なのである。それで、何かできないか、と考えていたが、心理学という方面は、当初考えていたものではないのだという。それでも、そういう仕事が見つかり、続けている。このような、証しとも言えるところから、本書は、複雑な事情を絡めながら、世に問われた。苦しんでいる人の目に触れ、生きるほうへ働く力がそこから生まれたらよいのに、と願っている。
また、このような悩みは、キリスト教の牧師や神父の許へも打ち明けられることがよくある。そこでただ神の愛を説いたり、まして自殺は罪です、などと言ったりしたら、どうだろう。私から見ても、それは最悪である。牧会心理学なるものもあるそうだが、あまり力を入れて学んでいないのではないだろうか。神学校や神学部で、カウンセリングの実習など、するのだろうか。本書は、キリスト教会の人にも、ぜひお薦めしたい。宗教抜きで、大切なものに出会えるに違いないのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
