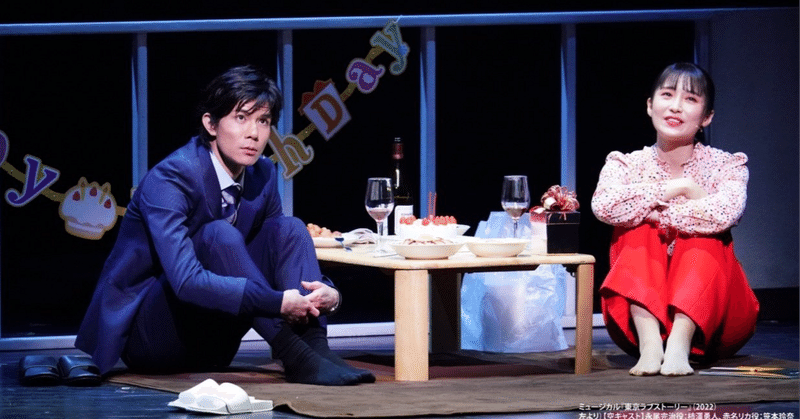
【短編小説】「人生劇場」第3話(全5話)
6月20日。午前11時。
昨日の夜9時から深夜の1時過ぎまで、景子は1時間おきに、夫正則のスマートフォンに電話を掛け続けていたが、正則が出る気配は全くなかった。
LINEに何度メッセージを送っても既読が付かず、今朝になってから会社に電話を入れ、上司の坂本さんに「夫は出社してますか」と聞いてみたが、「え? 景子さんも知らないんですか? 私の方も何度も掛けては見ているんですが、まったくのなしのつぶてですね。どうしたんでしょう。彼らしくもない」。
坂本が言うように、正則はイベントの企画運営に携わる今の会社に勤めて早15年になるが、無断での欠勤は初めてのことだった。景子は事件や事故の線も疑い、警察にも相談してみようかと思ったが、まだ昨日の今日と言うこともあり、連絡するにはためらいがあった。それに電話をすることで、本当に夫が事件や事故に巻き込まれたことになってしまうのではないかと、そんな嫌な予感も働き、とにかく無事に家に帰ってきてくれることだけを考えていた。
正午を過ぎ、朝からトーストを一口かじった以外、何も食べていなかった景子は、腹の虫が鳴ったことに気付き、もう少し胃の中に何かを入れておこうと、リビングのテーブルの椅子から立ち上がり、キッチンの冷蔵庫を開けてみた。本来であれば今日の朝、正則の胃の中に収まっていたであろう、朝のおかずの卵焼きやきんぴら炒めがそのままそこにあることに、景子は改めてショックを受けた。子育て時代以来の寝不足もあってか、思考がネガティブな方向に傾いていた景子は、まるで昨日と今日で、二人の人生がまっぷたつに分かれ、自分は今、あの人がいない世界で生きているのではと、そんなことさえ考えてしまった。10代の頃に舞台の役者を目指していた景子は、自身の元々の気質に加え、人一倍想像力が豊かな人間だった。そして正則とは、大学の演劇サークルで出会ったのだった。
景子より数カ月遅れて入ってきた正則は、高校時代も演劇部で、舞台に立つ人間と言うより、裏方でもっぱら脚本を書く人間だった。約半年の交際を経て、アパートでの同棲を始めた時、正則が自分の部屋から運んできた段ボールの中に、箱の外側に「演劇ノート」とマジックペンで書かれたものがあった。気になった景子が「見てもいい?」と聞くと、正則は頭の後ろを掻きながら、「うん、いいけど」と言って、照れくさそうに笑うのだった。
段ボールの中には、B5サイズの罫線入りのノートが30冊近く入っていた。パラパラとページをめくってみると、走り書きで、大小さまざまな文字が色濃く刻み付けられていた。中には読めない文字もあったが、とにかく正則がノートを書き記した時の熱意が、からだの底から伝ってくるような、そんなノートだった。
正則によると、ノートは自分が高校3年間で、考えられる限り考え尽くし、脚本の種としたアイデアノートとのことだった。1年生の頃は、学校内での友達関係や部活、親との葛藤など、思春期特有のアイデアが目立ったが、2年生になると、喫茶店、工事現場、球場、地下道、電車内、宇宙空間、森の中、サバンナなどの舞台設定のほか、医師や刑事、弁護士、俳優、探偵、小説家、プロ野球選手、宇宙飛行士、科学者など、まるで仕事図鑑か何かのように、各職業について調べた内容の記載が増え始め、舞台や登場人物が高校生活を離れ、フィクションの世界に飛び出し、とてもにぎやかになっていた。3年生を迎えると、再び学校内に戻り、恋愛や受験、将来のことなど、自分たちにとって身近で切実な問題に立ち戻っていた。それはもしかしたら、自分で作り上げた登場人物たちに、自分の当時の考えや想いを代わりに語らせ、また、その行く末を占ってみたかったという気持ちもあったのかもしれないと、景子は思った。
就寝前の時間を使い、1カ月を掛け、正則のノートを一通り読み通した景子は、こういったノートを書き溜める彼のような人が将来、プロの脚本家になるのだろうなと思っていた。
――が、正則は脚本家にはなれなかった。いや正確には、ならなかったと言った方がいいかもしれない。高校大学と、演劇に人生を費やした正則は、大学三年時の学園祭で、脚本と演出を一手に引き受け、手塚治虫の『火の鳥』に材を取った舞台で、内外からそれなりの反響を受けた。地元の新聞でもその様子は取り上げられ、景子は正則はこのまま、演劇の世界に進むのだろうと何となく思っていた。しかし、それからしばらくすると、正則は演劇にまつわる話を一切しなくなり、みんなと同じように就職活動を始めた。景子はまるで、別人のようになってしまった正則に、ある日の夜、たまらず、「演劇はいいの?」と、半ば涙ぐみながら尋ねたことがあった。すると正則は、景子に背中を向け、「あの舞台で俺の役目は終わったんだ。もう火の鳥のように、演劇に対する情熱が蘇ることはないと思う。高校大学と、本当に頑張ったと思うよ。自分で自分のことをほめてやりたいくらいだ。だからもう、後悔はない。俺は普通に就職して、君と結婚して、子どもをもうけて、幸せに暮らしていきたい。ただ、それだけなんだ」。
景子はその瞬間もその直後も、その時の正則の言葉を、何度も何度も思い返し、本心からそう言っているのか、わたしのためにそう言っているのか見極めようとしてきたが、結局のところは分からなかった。
2人は正則が27歳、景子が28歳のときに結婚した。すぐに景子のおなかは大きくなり、娘の菜々子が生まれた。3人の生活の中には、ほかの家族と何ら変わらず、フジテレビの月9に代表されるようなテレビドラマがそばにあったが、正則は決して熱心に見ることはなかった。一度、チケットが手に入った宮本亜門の舞台に誘ったこともあったが、正則は仕事を理由に断り、景子は友人の瀬名園子と2人で観に行くことになっただけだった。
小学3年生になった菜々子が、学習発表会でサン=テグジュペリの『星の王子さま』の主人公の「ぼく」を演じることになった時、景子はあの頃の正則がひょっこり顔を出して、娘に対して色々とアドバイスをしてくれるだろうと、密かに期待した。しかし正則は、菜々子が台本の読み合わせに付き合ってと頼んでも、ただ淡々と菜々子の声出しに付き合っていただけで、脚色された話の展開や娘の演技に、一言も口を出さなかった。
景子は、「菜々子に何か言ってあげたら」と正則に言ったこともあったが、「――いや、子どもたちに指導することはないよ。子どもたちは自分たちの思うように演じればいい。下手に大人が口を出すと、それは大人の劇になってしまう」。なんだか、うまく言いくるめられるようにそう言われ、それ以上、正則に何かを期待する気持ちもなくなってしまった。景子は、一番好きだと思っていた頃の正則の姿が、遠い彼方に行ってしまったように思えた。「演劇に対する情熱が、もう蘇ることはない」。ことあるごとに、あの時の正則の言葉が、頭の中に浮かんでは消えていった。
昨日の夜、帰ってこなかった正則のことを菜々子には、急に出張が入ったみたいで、ということで何とか納得させ、朝学校に送り出したが、この後、何日間も帰ってこなかった場合、どう説明すればいいのか、景子には分からなかった。本当にあの人は、どこで何をやっているのか。景子は心配で胸が押しつぶされそうだった。
刻一刻と時間が過ぎていった。景子は今まで生きてきた中で、一分一秒と言うものが文字通り、これほどまでに重たいものだとは思いもしなかった。
やがて、家の中でただ待っているということに耐えられなくなり、椅子から立ち上がっては、リビングの短い距離を行ったり来たりした。景子は、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』のエストラゴンとヴラジーミルの2人は、もしかしてこんな気持ちだったのかと、初めて実感として理解できたような気がした。さすがにしびれを切らした景子は、これが居ても立っても居られないということかと、これまた既存の言葉を我が事として実感し、直後、決意を固めた。リビングのテーブルに「帰ってきたら電話して下さい。お願いします」と、正則に宛てた書き置きを残し、夫を捜すためにショルダーバッグ一つで家を飛び出した。景子は、ゴドーを待つことは出来なかった。待つのではなく、迎えに行くべきだと思った。
タイムリミットは午後5時。菜々子が下校して、その後、いつも立ち寄る友達の紬ちゃんの家で遊び、帰ってくるのがちょうどその時間だった。菜々子には、紬ちゃんの家から帰る前には、必ず電話を寄こすようにと伝えていたので、もし帰りが早くなりそうな場合は多少無理を言って、紬ちゃんのところでもう少しだけ、遊んでいてもらえばいいと思った。景子にはその時、それ以上に複雑なことを考える余裕は残されていなかった。
自宅のマンションを出て景子がまず向かったのは、正則が通勤に使う最寄りのO手町駅だった。同棲していたアパートからマンションに居を移して約7年間、毎日通勤に使っていたところなので、正則の顔写真を見せれば、駅員の誰か1人くらいは覚えている人もいるのではないかと思った。
だが、景子の読みは甘かった。当然と言えば当然だが、毎日約20万人の人間が乗り降りする駅で、元々顔見知りでもない特定の人物のことを覚えている人などいるはずもなかった。落とし物をしたり、急病人を看護したり、痴漢を捕まえたり、乗降以外のイレギュラーなことをした人物であれば、まだ誰かの記憶に残っていた可能性はあったが、正則はどうやら7年間、本当に何事もなく、流れるように改札を抜け、決められたように電車を乗り降りしていただけだったようだった。どこまでも真面目だった。
構内で駅員に話を聞いて回るだけで約1時間を消費した景子は、体力的にも精神的にも、普段とは異なる疲れを感じ始めていた。手掛かりが得られず、スマートフォンの時計を見るたびに過ぎていく時間が、うらめしくて仕方なかった。――いっそのこと、時間が止まればいいのに。そんな子どもじみたことすら思い始めていた。早くも正則を捜す当てを無くしてしまった景子は、しばし途方に暮れた。景子の事情などまったく知らず、当たり前のように日常を送り続ける構内を行き来する人たちが、自分とは無関係の世界の人たちのように思えた。
景子は深いため息をついた後、自分のことを落ち着かせるために、構内から出て外の空気を吸いたくなった。少し移動して、構内の案内板の前で立ち止まると、すぐ近くの出口を捜した。今の自分の頭の中のような複雑に入り組んだ案内版の中でふと、「屋上庭園」という文字を見つけた。景子はそんなところがあるんだと、急に窓が開いたかのように、ふさぎこんでいた気持ちがふっと軽くなるような感覚を覚え、気分転換にそこへ足を運んでみようと思った。
そこは、T京駅の煉瓦造りの駅舎を見下ろすことのできる場所だった。目に鮮やかな青い芝生が一面に広がり、芝生の先はウッドデッキになっていた。空はあいにく曇っていたが、時々頬を撫でる心地よい風が吹き、景子の心をほんの少しだけ和ませた。きれいに長さが整えられた芝生の上では、カップルや親子連れ、老夫婦などがゆったりとくつろいでいた。景子はウッドデッキの手すりに両腕をかけ、横目で何となく人々の様子を眺めていた。
ちょうど1歳を過ぎたくらいの、ようやく1人で歩くことを覚え始めた女の子が、芝生の上を1歩、2歩と、進んでは手をついて転び、その場で顔を上げて、うあ、あ、と言葉にならない声を上げるたび、周りの人たちから笑い声がこぼれた。女の子はしばらくすると、しりもちをついた姿勢から、前に手を突き、前屈みになって自力で立ち上がり、また1歩、2歩と歩き始めた。さらに、3歩、4歩と進むと、今度は歓声が上がった。景子もまた、女の子の姿を見て、微笑ましくなった。娘の菜々子が自分で歩き出し、5メートルくらい離れた場所で待つ自分のもとへ、なんとかたどり着くことが出来たのも、確かどこかの芝生の上だった。
景子は記憶の糸を手繰り寄せ、それが正則の友人の高梨勇樹、知世夫妻と、ダブルデートの形でピクニックに行ったS宿御苑だったことを思い出した。
知世と互いに弁当を作り、芝生の上にレジャーシートを敷き、1歳になったばかりの菜々子を加えた5人で、弁当を食べながら他愛のないおしゃべりをしていた。
「勇樹さんって、お休みの日は何かされたりしないんですか」
ほぼ初対面だった正則の友人に、景子は当たり障りのない話題を投げかけた。
「まあ、趣味と言うほどではないけれど、ジョン・コルトレーンっていう、ノースカロライナ生まれのジャズのサックスプレーヤーがいるんだけど、柄にもなく、彼のサックスにはまってしまって。検索して見つけたんだけど、A草にさ、サックス奏者が経営してるジャズバーがあって、一目で気に入ってしまって。今は時間があれば、そこに入り浸ったりしてるかな」
急に饒舌になった勇樹の話を聞きながら、景子がちらりと知世の方を見ると、知世は我関せずといった風に、遠くで芝生の上に寝転がり、右に左にごろごろと転がって遊ぶ子どもたちの様子を、目を細めながら眺めていた。景子にも、子どもたちの笑い声が聞こえていた。
「で、こいつもさ(勇樹はそう言って正則を見た)、1回誘ってみたら、思いのほか気に入ったみたいで。お互い月に2、3回は、休日や仕事帰りに立ち寄ったりし――」
勇樹が急に口ごもったので何かと思い、景子が勇樹の視線の先に目を向けると、正則がそれ以上は言うなとでも言うように勇樹を睨みつけ、唇をかみしめていた。景子は正則がジャズが好きだという話は、一度も聞いたことがなかった。家の中でもBGM代わりに流すのは、せいぜいショパンやリストなどのクラシックで、時々は菜々子が好きなアニメの主題歌を一緒に歌ったりしていた。景子の視線を感じた正則は、何か申し訳なさそうに顔を伏せ、弁当のからあげを箸でつまみ、口の中に放り込んだ。
――ジャズバー。まるでひらめきのように、その言葉が景子の頭の中で光り始めた。景子はすぐに頭を働かせ、もしかしたら昨日の夜、そこに立ち寄った可能性もあるのではないかと、途端に正則とのつながりが見つかったような気がした。善は急げと、それこそ藁にも縋る思いで、景子はそのジャズバーを訪ねてみることにした。時刻は、午後2時25分を過ぎていた。
つづく
#小説 #短編 #手塚治虫 #火の鳥 #サン =テグジュペリ #星の王子さま #学習発表会 #サミュエル・ベケット #ゴドーを待ちながら #エストラゴン #ヴラジーミル #ジョン・コルトレーン #ジャズ #バー #探偵 #演劇 #創作大賞2024 #オールカテゴリ部門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

