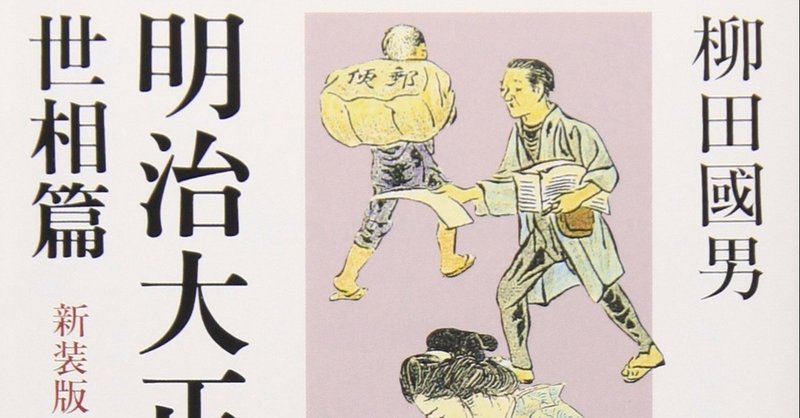
『明治大正史世相篇』柳田国男で言及されているトンデモ学説は誰のもの?
柳田国男の『明治大正史世相篇』は現在民俗学とよばれている研究の方法を用いて明治・大正時代の歴史を人々の感覚や社会状況の移り変わりから分析しようとした本(注1)であるが、この本の「自序」はいろいろな視点から読むことができて非常におもしろい。その「自序」に以下のような文章がある。
いま一つは正反両用の証拠の共に示しがたく、たとえば日本人はギリシアより来るという説までも、成り立ったり闊歩したりするような区域において、この無敵の剣(筆者注:Folklore(注2)、現在の民俗学)を舞わすことは、何か巧妙なる一種の逃避術のごとき感がある。(後略)(筆者が重要であると考えた部分を太字にした。)
上に引用した部分は現在で言うところの「トンデモ学説」であるが、柳田は当時誰を意識していたのだろうか?
先日、神保町のオタ様のプログ「神保町系オタオタ日記」のこの記事を読んでいて、上記に一部を引用した「自序」を書いた時に、柳田は木村鷹太郎を意識していたのではないだろうかと思い始めた。木村鷹太郎は『プラトーン全集』を英語からの重訳ではあるが、日本語にはじめて翻訳した哲学研究者である一方で、「日本人はギリシャ方面から来た」という説を唱え『世界的研究に基づける日本太古史』などを出版しており、現在からみると「トンデモ研究者」と考えられるような一面もあった。柳田はいくつかの文章で木村のことに言及しているため、木村や彼の説を知っていたことが分かる。『定本柳田国男集』から柳田が木村のことに言及した箇所を一部以下のように引用してみたい。
(前略)仮に木村鷹太郎君の日本希臘同族説が、出鱈目の極であったとしても、スエズ以東の広漠たる海の上にも、やはり海豚が此神様の三叉の鉾を、かついであるいて居たことはたしかだ。(『定本柳田国男集』第3巻の「海豚文明」より引用。筆者が一部現代仮名遣いにあらためた。)
「日本の言葉」の著者もよう御存じの如く、語源論ほど水掛論になりやすいものは無い。今まではとにかくえらい人の説が、はあさうですかと謂われて居た。しかし木村鷹太郎のやうな人は別として、我々の間にならば一通りの申し合わせ、誰でも認める出発点はある筈である。(後略)(『定本柳田国男集』第7巻の「馬鹿考異説―「日本の言葉」を読みて―」より引用。筆者が一部現代仮名遣いにあらためた。)
直接的には書かれていないものの、柳田が自分と木村の研究は異なるものだと考えていたことが分かる。「仮に」とは断っているものの、木村の「日本希臘同族説」を「出鱈目の極」であると言っており、柳田も木村のことを「トンデモ研究者」として考えていたのではないだろうか。1つ目に引用した文章は1924年に書かれたものだが、「木村鷹太郎君」と言ったり慎重な表現をしたりしているのは、木村が存命であったからだと思われる。木村は1931年に亡くなっている。2つ目の文章は木村没後の1941年に書かれたため、君付けでなくなったのだろう。
余談だが、柳田と心霊主義(現在で言うところのオカルト)との関係性は、神保町のオタ様のブログや大塚英志の本などで指摘されている。私もこの部分はまだまだ分からないことが多いため、引き続き関心を持っていきたい。
(注1)以下の記事も非常に参考になる。
http://www.webchikuma.jp/articles/-/856
(注2)柳田は民俗学の創始者として語られることが多いが、柳田は当初「民俗学」ということばを使用することに慎重であった。『明治大正史世相篇』の「自序」でも「民俗学」ということばを使用するのに慎重になっている。背景には、折口信夫らとの民俗学という学問の方向性をめぐる対立があった。柳田は民俗学を現在の問題を解決するための学問、折口は古代を復元するための学問と考えていた。この対立は『明治大正史世相篇』の自序にもあらわれている。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。
