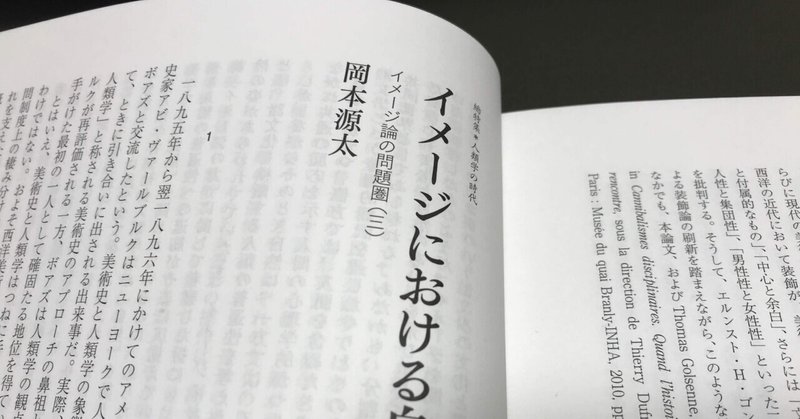
イメージにおける自然と自然の「大分割」を超えて──イメージ論の問題圏(三)
1 一八九五年から翌一八九六年にかけてのアメリカ旅行中、美術史家アビ・ヴァールブルクはニューヨークで人類学者フランツ・ボアズと交流したという。美術史と人類学の象徴的な出会いとして、ときに引き合いに出される出来事だ。実際、今日「イメージ人類学」と称される美術史のアプローチの鼻祖としてヴァールブルクが再評価される一方、ボアズは人類学の観点から芸術研究を手がけた最初の一人として確固たる地位を得ている。
とはいえ、美術史と人類学はつねに手をたずさえて歩んできたわけではない。およそ西洋美術史と民族芸術学として、長らく学問制度上の棲み分けをおこなってきたというのが実情だろう。それを支えたのが、一つには、十九世紀的な「芸術」と「装飾」の概念にほかならない(1)。十九世紀末葉から二十世紀初葉にかけてのヨーロッパでは、衣裳にも室内にも市街にもアール・ヌーヴォー様式の装飾が氾濫していながら、しかし言説上は、そのような装飾は「応用美術」「工芸」であるとして、芸術の副次的な所産にすぎないものと語られていた。アロイス・リーグルなどの稀有な例外を除き、美術史家が装飾を主題に研究することはほとんどなかった。対照的に人類学者・民族学者は、ボアズを筆頭に、かえって装飾や工芸をこそ研究したのだった。特別な才能のある人間が一人でつくりあげる芸術作品よりも、名もなき人々が日々生産し活用する装飾や工芸のほうが、一個の社会、一個の文化をよりよく説明してくれる──逆にいえば、装飾や工芸は無個性な集団の反映にすぎず、芸術作品のごとく一人の人間のたぐいまれな才知の達成を見せてはくれない。そのようにして、十九世紀的な「芸術」と「装飾」の概念は西洋美術史と民族芸術学の棲み分けを促し、さらには西洋と非西洋への分割を支えてきたのである。
もちろん、現在では時代遅れの概念だろう。昨今のイメージ人類学は、そのような旧弊の概念と手を切るためにこそ、「イメージ」という語を選択している(2)。とはいえ、「芸術」と「装飾」の語を避けて、ただ「イメージ」などの別の語に置き換えるだけでは、実のところ問題は隠蔽されるばかりであって、解決されはしない。問題は、十九世紀的な「芸術」と「装飾」の概念が支えてきた西洋と非西洋への分割を克服して、人類の普遍性を「イメージ」において問えるのかどうかである(3)。いっそ普遍性はないとしてしまう多文化主義は、一つの答えではありうる。けれども、人類の分割をさらに細分化するのみにおわってしまいかねない。近年、文化人類学者や社会人類学者が「自然」を論じはじめ、美術史や美学でも「自然」が問われているのは、あらためて見いだされるべき人類の普遍性への道筋がそこに仄見えているからだろう。以前「イメージの力」に関して考察した折にも、すでにそうした自然の姿があらわれでていた(4)。イメージにおいて自然を問うことは、諸文化を横断する人類の普遍性を考えさせてくれる。
しかしながらそのとき自然は、一方では、イメージに多かれ少なかれ共通の反応を示す人間の心理学的かつ生物学的な自然本性と見なされつつ、他方では、人間を含めたさまざまな存在者がイメージという普遍的翻訳を通したやりとりのなかで構成していく共同世界としてあらわれる。あたかも、分割が文化と文化のあいだから──文化と自然のあいだを飛び越えて──自然と自然のあいだに転移したかのようだ。イメージを問いながら、人類学者フィリップ・デスコラのいうところの文化と自然の「大分割」を超えようとするのであれば、その先には自然と自然の「大分割」が控えているのだろうか。
2 フィリップ・デスコラは、自身の「自然の人類学〔anthropologie de la nature〕」のプログラムの一環として、近年、「造形人類学〔anthropologie de la figuration〕」を展開している。これまでに「造形の諸様態」(二〇〇五—二〇〇六年度/二〇〇六−二〇〇七年度)および「イメージの存在論」(二〇〇八—二〇〇九年度/二〇〇九—二〇一〇年度/二〇一〇−二〇一一年度)と題した講義をコレージュ・ド・フランスにておこない(5)、パリのケ・ブランリー美術館での「イメージの製造所」展(二〇一〇年二月一六日〜二〇一一年七月一一日)を監修している(6)。もっとも、その成果はいまだ総合的には公表されておらず、なおも進行中の仕事である(7)。だが、デイヴィッド・フリードバーグ、ハンス・ベルティンク、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンといった美術史の側からのイメージ人類学の試みに対して、デスコラの造形人類学は──アルフレッド・ジェルの芸術人類学やカルロ・セヴェーリの記憶人類学などとともに──人類学の側からの包括的なイメージ論の展開として興味深いものだ。
デスコラは意図的に「造形〔figuration〕」あるいは「イメージ・メーキング〔mise en image〕」の語を選び、「芸術〔art〕」の語を避ける。デスコラによれば、これまでの芸術人類学は、「芸術」という西洋的な概念──ゆえに普遍的な人類経験とはいえない分析概念──に足を掬われ、諸文化ごとの「芸術」(の対応物)に関する民族学になってしまっている。それはもちろん民族誌としての貴重な研究価値を有するものの、「人類学」の名に値するような人類の普遍性には関わっていないという。そこからデスコラは、諸文化ごとに分断された民族芸術学ではない、イメージを生み出すという人類の普遍的な造形実践の人類学を企てる。
デスコラの狙いは、一言でいえば、人類が世界各地で造形してきた多種多様なイメージをそれぞれの文化の反映にしてしまうのを避けて、人類の普遍性を示すような造形の操作をそこから剔抉することである。このとき造形の操作は、諸文化それぞれの社会制度・価値観・象徴系などを表象するものとは見なされない。多種多様なイメージをまえにして造形人類学が明らかにすべきなのは、その形態のレパートリーでもなければ、イコノロジーの元型でもなく、手続きのシステムでもない。そうではなく、諸文化への分割以前、さらには文化と自然への「大分割」以前に、世界の諸存在者を組織化する図式──デスコラが「存在論〔ontologie〕」と呼ぶもの──を、いかに造形の操作が可視化しているのかだ。
周知のごとくデスコラは、人間が世界の諸存在者の「物理性〔physicalité〕」と「内面性〔intériorité〕」のそれぞれに連続性を見いだすか、それとも不連続性を見いだすかにもとづいて、ありうる存在論を「アニミズム」(物理性の不連続・内面性の連続)、「ナチュラリズム」(物理性の連続・内面性の不連続)、「トーテミズム」(物理性・内面性とも連続)、「アナロジズム」(物理性・内面性とも不連続)の四つの変形の型にまとめた(8)。この四つの存在論、四通りの諸存在者の関係づけが、人類の社会編成と思考体系のさまざまなヴァリエーションを世界各地に生み出しているというのである。存在論がそのように諸存在者の関係づけの図式であるとすれば、その図式が可視化される諸様態の解明、存在者同士の「関係の形態論〔morphologie des relations〕」こそが、造形人類学の目指すところである。したがって造形人類学は、〈アニミズム/ナチュラリズム/トーテミズム/アナロジズム〉という四つの存在論の変形の型を定式化したデスコラの主著『自然と文化を超えて』(二〇〇五)の延長線上で、彼の「自然の人類学」を──社会論と認識論に加えて──イメージ論にまで敷衍する試みにほかならない。
具体的に見てみよう。アニミズムの存在論では、たとえば、動物の体に人間の顔が浮かび上がるアラスカの仮面や、外側の動物的な顔が割れて内側に人間的な顔があらわれるカナダの仮面にうかがえるように、諸存在者のたえざる変身と、そのあいだでのパースペクティヴの「交替commutation」を示す造形がなされるという。アニミズムとは、人間と非人間とのあいだに、外観上の差異(物理性の不連続)を超えて、同一の魂(内面性の連続)を見いだすものだからだ。
アニミズムの正反対に位置づけられるナチュラリズムの存在論では、十五世紀北方ヨーロッパ(なかでもフランドル)の肖像画から顕著になるごとく、人物の個性の徹底的な描写をおこない、写実的な「類似ressemblance」を造形する。自然を均質な連続的空間として描く同じ十五世紀北方ヨーロッパ以後の風景画もまた、ナチュラリズムに典型的な造形だという。なぜならナチュラリズムは、自然も人間もすべて同質の物質で構成されていると見なしつつ(物理性の連続)、人間だけに精神とそれゆえの個性を認める(内面性の不連続)からである。
トーテミズムの存在論では、オーストラリアのいわゆるX線絵画が動物の解剖学的構造によって世界生成の秩序を可視化しているように、区分と相同性にもとづく安定した「配列〔ordonnancement〕」が造形される。トーテミズムは、たとえば動植物界の秩序を人間社会の秩序に重ね合わせて(物理性・内面性とも連続)、世界に安定した構造を見るのである。
最後のアナロジズムの存在論では、山・川・雲・人などのあいだでの気の循環にもとづく中国の山水画をはじめ、分散し流動する雑多な諸要素のはてしない「結合〔connexité〕」が造形される。アナロジズムは、トーテミズムとは逆に、世界に諸存在者の分散を見いだし(物理性・内面性とも不連続)、それらをたえず繰り返し構造化しなおすものなのである。
これら「交替」「類似」「配列」「結合」という四つの存在論的関係の造形は、実際に眼に見えるイメージの形態としては多彩なヴァリエーションを示す。また地理的にも、前述の地域に限定されて見いだされるわけではない。さらにはハイブリッドな造形もありうる──アンデスでのアニミズムとアナロジズムのハイブリッド、カナダでのトーテミズムとアニミズムのハイブリッド、キュビスム以降の現代美術におけるナチュラリズムからの逸脱、などのごとく。
このようにしてデスコラの造形人類学は、諸存在者の関係づけ、人間がその自然的かつ文化的な環境と取り結ぶさまざまな存在論的関係の可視化を、イメージに見いだす。とすれば、デスコラがみずからの試みを、芸術人類学のみならず、セヴェーリの記憶人類学からも区別するのは当然だろう。セヴェーリは、イメージの残存現象を「社会的記憶」の受容と変容であるとして研究したヴァールブルクの美術史を、人類学に接ぎ木し、記憶人類学へと発展させた(9)。イメージは言語に比べて容易に文化を跨いで伝播し継承されるが、その歴史的プロセスのなかで、図像の混淆、意味の分極化、イメージの強化、といった現象が生じる。それは文化を跨いだ社会的記憶の生成変化のプロセスそのものだ。ゆえに、セヴェーリにとってイメージとは、単一の文化を透明に表象するものではなく、諸文化間の歴史的な接触と葛藤の痕跡たる合成物、いわば「キマイラ」である。だが、デスコラからすれば記憶人類学は、民族芸術学のように単一の文化の反映としてイメージを見ているわけではないものの、あくまで記憶の社会的使用の人類学であって、文化のレヴェルのみを扱っている。それに対してデスコラの造形人類学は、文化だけでなく自然をも含めた世界の全体を、イメージにおいて見いだそうとしている。だからこそ造形人類学は、文化と自然の「大分割」を超えていく「自然の人類学」の一環といえるのである。
3 イメージに対する昨今の人類学的アプローチのなにが新しいのか、あらためて確認しておけば、それはイメージの形態や様式、あるいは意味や内容よりも、その機能や効果──フリードバーグのいう「イメージの力」──にはっきりと問いの焦点を移したことだった(10)。デスコラもまた、とりわけアルフレッド・ジェルの『アートとエージェンシー』(一九九八)に依拠しながら(11)、「力」たる社会的な「エージェンシー」(行為主体性)をイメージに付与するものとして、造形の操作を捉える。造形されたイメージは、一個の「エージェント」(行為主体)となって、人間やそのほかの存在者と同様に、社会のなかで影響力を行使する。先に確認した「交替」「類似」「配列」「結合」という存在論的関係が可視化されるのは、イメージのエージェンシーが作用するそのありようにおいてである。いうなれば、デスコラの造形人類学が描き出す関係の形態論は、「イメージの力」の形態論なのである。
この形態論という点で、デスコラはジェルから離れていく。人工物が「アート・ネクサス」として作用連関を構成していく動的な場面を捉えたジェルを、デスコラは評価しつつも、そこに造形上の特性を体系的に捉える形態論が欠けているとするのである。しかしながら逆にデスコラの分析では、ジェルのものと比べて明らかに、イメージのエージェンシーが実際にはたらく場面が後景に退いている。デスコラは、ジェルのように次々と連鎖していく行為と作用をつぶさに辿ることはなく、その全体がどのタイプの存在論的関係を可視化しているのかを、俯瞰的に描く。したがって、イメージのことを社会的エージェントと捉えながらも、実際にその力によって関係が連鎖的に構成される点にはさほど着目せず、もっぱら造形以前から存在している全体的な関係の可視化ばかりをイメージのなかに見ているとの印象が強い。
率直にいえば、現時点でのデスコラの造形人類学は、関係の形態論を目指してはいても、イメージが可視化する諸関係のあいだの変形の規則を確立していないために、実際には形態論になっておらず、あれもあればこれもあるという類型論にとどまっている。加えて、イメージを具体的に構成する規則が明示されていないために、存在論の図式がそのまま造形によって可視化されるかのごとき、反映論になってしまっている。結果、造形されるイメージを諸文化ごとの自然観の反映と見なすことと、さほど違わない見解に落ち着いているように思えてしまう。もちろん、いまだ進行中のデスコラの研究を現時点で批判するのは、時期尚早にちがいない。とはいえ、デスコラが今後、かつてクロード・レヴィ=ストロースがブリコラージュ論(12)として打ち立てたような変形と構成の規則を造形人類学において確立できるのかどうか、それがデスコラのイメージ論を文化類型論的な反映論から区別する決め手になるだろう。
デスコラの造形人類学には二つの前提がある。第一に、造形はまったくの無からの創造などではなく、人間の認知構造にもとづく存在論の図式にしたがい、その図式を可視化する、というもの。したがって認識から制作まで、眼から手へと、同一の図式が反復されるというのである。第二に、「イメージの力」、つまり造形がイメージに付与するエージェンシーは、イメージがなにかしらの「原型」(プロトタイプ)を示すイコン記号かつインデックス記号であることにもとづいている、ということ。つまり、造形されるイメージは、表象であることによってこそ力を行使するというのである。第一の前提は、心理学的かつ生物学的な認知構造として、諸文化への分割を免れた人類共通の自然本性を想定するものだ。そして制作は認識の反映にほかならず、眼に見えるイメージは眼に見えない図式の表象でしかありえないことになる。対する第二の前提は、イメージが、人間であれ非人間であれ、人工物だろうと自然物だろうと、実在物からも想像物からも、その力を委託され代理=表象してはたらくことを想定している。その意味でイメージは、文化と自然への「大分割」を免れて、人間に自然との共同世界を構成できるようにしている。
デスコラの造形人類学は、この二つの前提、認知構造と共同世界の二つの自然を暗黙のうちに重ね合わせる。その根拠はいずれにおいてもイメージを表象と見なしていることである。実際、デスコラは自身の研究からイコン的な表象でないイメージを周到に排除する。かならずしも西洋絵画に見られるような写実主義的な類似性を必要とはせず、極端な場合には幾何学的なモチーフでもかまわないが、しかし人間であれ動物であれ神格であれなにかしらの原型を示すイメージのみが、デスコラによって存在論的関係の可視化として探究される。そうでないイメージは、ただ固有の文化を語るだけの絵文字や紋章であるか、もしくは、ただ注意と情動を惹起するだけの装飾にすぎないというのである。
装飾──かつて芸術から排除されたものが、ここでまた造形から排除される。それは表象ではなく、意味がないからだ。装飾には作用と効果しかない。そのように研究対象からたんなる装飾なるものを排除するデスコラの発想に、十九世紀的な西洋の「芸術」概念の残存を看て取るべきだろうか。翻って、装飾こそ、表象でも意味でもなく作用と効果そのもの、まさしく「イメージの力」そのものとしてのイメージではないだろうか。それは注意と情動を惹起する力をもち、すぐれて社会的エージェンシーを発揮するイメージにほかならない。
美術史家トマ・ゴルセンヌは、そのような「イメージの力」そのものとしての装飾のイメージを基礎づけうる存在論を、デスコラのアニミズムに──実のところデスコラ自身の造形人類学に反して──見いだしている(13)。万物に同一の魂を見いだすアニミズムの存在論においては、外観のイメージによってこそ差異が生まれる。イメージはなにかの表象としてよりもまず万物の差異化と特異化の効果として作用するのである。このとき装飾は、とりわけ身体装飾は、まさにそうした差異化と特異化の効果を発揮する最たるものだ。実際、デスコラはアマゾンの先住民の羽根飾りや牙の首輪などを、アニミズムの存在論にもとづいて動物の身体をイメージとして借用し、人間同士の差異化に使用するものである、と論じていた(14)。ゴルセンヌによれば、このような装飾のイメージのアニミズム的な使用は、ヨーロッパにも無縁のものではない。中世には騎士階級が、紋章のイメージによっておたがいの差異化を発達させた。また、なによりルネサンスのイタリア文化の全体が、外観のイメージによる特異化をすぐれて洗練させたのだった。その典型はルネサンスの万能人レオン・バッティスタ・アルベルティ、ありとあらゆる仮面を付け替える隠蔽と誇示の天才にうかがえると、ゴルセンヌは示唆する。あるいは、かつてアンドレ・シャステルが論じたルネサンスのグロテスク装飾のことを思い起こしてもよいだろう(15)。人間の形が動植物や鉱物の姿と結びつき混ざり合い、奇怪で幻惑的な紋様となって衣服や室内を覆い尽くすという、ただ想像力を強く刺激する以外の意味をもたない装飾的イメージである。
ゴルセンヌによれば、「イメージの力」を問うイメージ人類学でも、あるいは視覚文化論でも、おおむね装飾のイメージはなにかしらの表象と見なされてはじめて論じられている。効果と作用しか示さないイメージはたんなる「装飾的なもの」として排除される。排除されずにかろうじて表象へと還元された「装飾」は、文化や社会や時代などを示すものとして、西洋と非西洋──さらには文明と未開、男性性と女性性など──への概念的な分割を支えてきた。しかしながら、イメージを表象としてのみ捉えることから離れるならば、非表象的な「装飾的なもの」として排除され、また表象的な「装飾」として還元されてきたイメージの効果は、まさしく差異化と特異化の作用として理解できる。抽象的であったり幾何学的であったり非具象的なものがすべて装飾的と呼ばれるわけではない。表象や意味に対して過剰なものこそが装飾的とされる。装飾性とは、意味の同一性を確立するような定義をたえず超過する過剰性であり、そうして差異化と特異化をもたらすものなのである。
そこからゴルセンヌは、イメージを「表象〔représentation〕」ではなく「表現〔expression〕」──ドゥルーズ的な意味での「表現」──と捉えなおす(16)。ゴルセンヌと同様、ドゥルーズ哲学から多くのインスピレーションを引き出している美術史家にして哲学者のベルトラン・プレヴォーにとっても、装飾はイメージの理解を「表象」モデルから「表現」モデルへと移行させるための蝶番だった(17)。もしイメージにおいて人類の普遍性を問うのであれば、かつて西洋と非西洋への分割を支えてきた「芸術」からの「装飾」の概念的な排除を、イメージ論において反復すべきではないだろう。むしろ意味に対する過剰性であり、表象ではなく表現であり、「イメージの力」そのものたる装飾のイメージこそ、普遍性への足がかりになりうると、ゴルセンヌとプレヴォーは示唆している。
ゴルセンヌは、デスコラのいうアニミズムの存在論に装飾のイメージの普遍的な基礎を見いだしたあと、翻って、デスコラによるナチュラリズムの存在論にもあらためてその普遍的な基礎を見いだす(18)。動物行動学が示すように、動物もまた人間と同様に「表現」としてのイメージによって注意を惹き、社会的な作用連関を構成しているというのである。さらにゴルセンヌは、動物行動学が想定しがちな表現行動の目的論を斥けるべく、ベルクソン的な創造的進化の視座を示唆しながら、無機物の生成から生物の進化をへて人間の歴史にいたるまでを貫く、差異化と特異化の運動が万物における装飾的イメージとしてはたらいているとの見通しを語りさえする(19)。
もっとも、このようなゴルセンヌの議論には、ともすれば旧弊のゼンパー主義のようなイメージの造形に関する唯物論的な決定論へと逆行しかねない危うさがある(20)。とはいえ、デスコラの造形人類学が排除してしまう装飾をこそ「イメージの力」の中心に位置づけなおし、それをアニミズムとナチュラリズムという対立しあうはずの存在論の変形の型の双方から基礎づける点には、二つの自然、イメージにおける自然の自然への「大分割」を超えていく道筋が示唆されてはいないだろうか。デスコラは、イメージを表象と捉えることで二つの自然を暗黙に重ね合わせようとしていたが、そこからは装飾のイメージが過剰なものとして排除されていた。だが、装飾からイメージを表現と捉えなおすなら、造形は人間だけの普遍的な活動ではなくなり、万物がみずからをイメージとして表現し、差異化と特異化をおこなっていることになる。デスコラの「自然の人類学」が提起する四つの存在論を、認知構造という人類共通の自然本性にもとづかせる必要はなくなる。装飾のイメージを介してアニミズムとナチュラリズムが反転し、人間と動物に共通の普遍性を考えさせてくれたように、表現のイメージこそが中核になって四つの存在論の循環的な変形が起こるとき、おそらくは自然という普遍的な造形を考えさせてくれるように思う。*
*岡本源太「イメージにおける自然と自然の「大分割」を超えて──イメージ論の問題圏(三)」、『現代思想』第45巻第4号(2017年3月臨時増刊号「人類学の時代」総特集)、2017年2月、317-325頁
(1) Cf. Thomas Golsenne, « L’ornement est-il animiste ? », in Thierry Dufrêne et Anne-Christine Taylor (dir.), Cannibalismes disciplinaires. Quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontre, Paris, Musée du quai Branly-INHA, 2010, pp. 255-268; Thomas Golsenne, « L’ornemental. Esthétique de la différence », Perspective, no 1/2010-2011, 2011, pp. 11-15.
(2) Cf. ハンス・ベルティンク『イメージ人類学』仲間裕子訳、平凡社、二〇一四年、六頁; ジャン=クロード・シュミット『中世の聖なるイメージと身体──キリスト教における信仰と実践』小池寿子訳、刀水書房、二〇一五年、三三〜三六頁; Thomas Golsenne, « L’image contre l’œuvre d’art, tout contre », L’Atelier du Centre de recherches historiques, no 6, 2010. [http://acrh.revues.org/2059]
(3) このような普遍性への問いは、「芸術」を「イメージ」に置き換えれば前進するというものではなく、実のところ、これまで「芸術」概念の普遍性をめぐって芸術人類学が積み重ねてきた議論を引き継いで考察されるべきものだろう。芸術人類学の学説史については、以下を参照のこと。渡辺文『オセアニア芸術──レッド・ウェーブの個と集合』、京都大学学術出版会、二〇一四年、三〜二五頁。日本における「芸術」「美術」概念の成立についても、北澤憲昭『眼の神殿──「美術」受容史ノート』(美術出版社、一九八九年)の問題提起以来、重厚な議論の蓄積がある。それに照らすなら、こののちに見るフィリップ・デスコラによる芸術人類学批判は、大枠では正当であっても、やや皮相なものと映る。ある概念の普遍性は、包括的な定義によって確立されるのではなく、その概念の前史(比喩)と後史(翻訳)の具体的な手続きにおいてこそ構成されるのだから。
(4) 岡本源太「イメージの人類学から自然の美学へ──『イメージの力』展に寄せて」、『REAR』第三三号、二〇一四年、一一八〜一二一頁; 岡本源太「眼差しなき自然の美学に向けて──イメージ論の問題圏(二)」、『現代思想』第四三巻第一号、二〇一五年一月、一四三〜一五一頁。
(5)Philippe Descola, « Anthropologie de la nature [Modalités de la figuration] », in Annuaire du Collège de France 2005-2006. Résumé des cours et travaux, 106e année, Paris, Collège de France, 2006, pp. 447-461; Philippe Descola, « Anthropologie de la nature [Modalités de la figuration (suite et fin)] », in Annuaire du Collège de France 2006-2007. Résumé des cours et travaux, 107e année, Paris, Collège de France, 2007, pp. 451-466; Philippe Descola, « Anthropologie de la nature [Ontologie des images] », in Annuaire du Collège de France 2008-2009. Résumé des cours et travaux, 109e année, Paris, Collège de France, 2009, pp. 521-535; Philippe Descola, « Anthropologie de la nature [Ontologie des images (suite)] », in Annuaire du Collège de France 2009-2010. Résumé des cours et travaux, 110e année, Paris, Collège de France, 2010, pp. 799-816; Philippe Descola, « Anthropologie de la nature [Ontologie des images (suite et fin)] », in Annuaire du Collège de France 2010-2011. Résumé des cours et travaux, 111e année, Paris, Collège de France, 2011, pp. 681-697.
(6) Philippe Descola (dir.), La fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris, Somogy-Musée du quai Branly, 2010.
(7) 上記の講義録と展覧会図録のほかは、おもに以下の論考・インタヴューに、現時点での研究の構想と成果がうかがわれる。Philippe Descola, « Une anthropologie de la figuration » (Entretien avec Nikola Jankovic), Art press, no 336, 2007, pp. 56-61; Philippe Descola, « L’envers du visible. Ontologie et iconologie » in Dufrêne et Taylor (dir.), Cannibalismes disciplinaires, cit., 2010, pp. 25-36.
(8) Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
(9) Carlo Severi, Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Torino, Einaudi, 2004.
(10) 岡本、前掲「眼差しなき自然の美学に向けて──イメージ論の問題圏(二)」。Cf. 松原知生「美術史学からイメージ人類学へ」、ヴィクトル・I・ストイキツァ『ピュグマリオン効果』(松原知生訳)解題、ありな書房、二〇〇六年、三九三〜四〇八頁; 水野千依『キリストの顔』、筑摩選書、二〇一四年、三四三〜三五二頁。
(11) Alfred Gell, Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998.
(12) Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage [1962], in Œuvres, Paris, Gallimard, 2008, pp. 553-872.〔クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』大橋保夫訳、みすず書房、一九七六年〕
(13) Golsenne, « L’ornement est-il animiste ? », cit.
(14) Philippe Descola, « Un monde animé », in Descola (dir.), La fabrique des images, cit., p. 36.
(15) Cf. アンドレ・シャステル『グロテスクの系譜』永澤峻訳、ちくま学芸文庫、二〇〇四年
(16) Golsenne, « L’image contre l’œuvre d’art, tout contre », cit.
(17) Bertrand Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », Images Re-vues, no 10, 2012. [http://imagesrevues.revues.org/2181]〔ベルトラン・プレヴォー「コスミック・コスメティック──装いのコスモロジーのために」筧菜奈子、島村幸忠訳、『現代思想』第四三巻第一号、二〇一五年一月、一五二〜一七六頁〕
(18) Thomas Golsenne, « Généalogie de la parure. Du blason comme modèle sémiotique au tissu comme modèle organique », Civilisations, vol. 59, no 2, 2011, pp. 41-58.〔トマ・ゴルセンヌ「装いの系譜学──記号学的モデルとしての紋章から有機的モデルとしての織物まで」筧菜奈子訳、『現代思想』本号掲載〕
(19) Golsenne, « L’ornemental. Esthétique de la différence », cit.
(20) この点についての批判は、すでにプレヴォーがおこなっている。Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », cit.〔ベルトラン・プレヴォー、前掲「コスミック・コスメティック──装いのコスモロジーのために」〕
