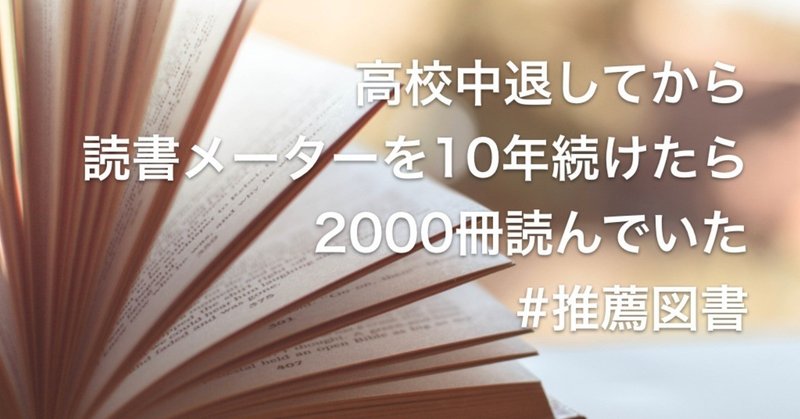
読書メーターを10年続けて2000冊読んできた中で薦めたい10冊(後半)
というわけで、続きです。1ヶ月近くかかってしまった上に、前半では押さえ気味に書いて、書籍毎の文量を揃えるようにしていたのがここに来て崩壊。
気持ち切り替えて、少し熱っぽく推薦させてくださいね。
6. 『難しいことはわかりません』で終わっていた世界線
投資って難しくてわからないし、仕事をしながら学ぶなんて到底無理。その気持ちはとってもよくわかります。でも、お金は増やしたい、それもなるべくリスク(損)を減らした上で。それが世間一般の下っ端リーマンの気持ちだと思う。だって、時間なんて全然ないんだもの。
おそらく、そのたった一つの冴えたやり方がインデックス投資。分散して積み立てるだけのいたって真面目な方法で、アーリーリタイアができるわけではなく、むしろよく働きましょうというのが前提。そうして得られる収入だけが、投資に回せる唯一のお金だからです。
この本の何がすごいのかって、始めるためのハードルを一般の人の目線まで下げて解説してくれる本当に稀有な本であるということ。インデックス投信はマネーリテラシーの低い我々にも扱える方法で、その機会を失うのはとても残念なことなので、少しでも知ってもらいたいと思い一冊に取り上げました。
ちなみに、実際に実践している人の話として、こちらがオススメです。山崎元さんの推薦文もありお墨付き。
7. 『ミニマリスト』の本質は自己コントロール感
発達障害ではなく定型の範疇なのでしょうが、僕はモノが多かったり、作業が複雑化してくると混乱してきます。部屋はいつも散らかっていて、いつも自分の人生をコントロールできていないように感じて暮らしてきました。
断捨離もこんまりメソッドもうまくいきませんでしたが、ミニマリズムはある程度うまく行っています。実は、卒業アルバムも名簿だけスマホで写真に収めて捨ててしまいました。こんまりメソッドでは捨てきれなかったんです。そうした自分の生活に必要としないモノを手放していくと、少しづつ余計なことに時間を奪われることがなくなり余裕がでてきます。
モノの価値に縛られず、コトである時間と経験に重きを置くのがミニマリスト。でも、その本質は自己コントロール感だと思うのです。その感覚はじわぁっと僕らの幸福感を高めてくれます。
8. 食に関する情報に騙されないために『データ栄養学』
栄養士・管理栄養士なら必ず読んでおかなければいけない書籍の一冊(というか二冊)だと思います。
凡庸だからこそ間違えるわけだけれど、そんな我々にも人生を攻略するための武器があります。それがデータです。学問としては統計学であり、栄養学の分野としては栄養疫学です。
先に上げたインデックス投資はその恩恵と言えて、特別な才能がなくても長期的な利益が期待できるのはこの武器のおかげです。そしてこれは健康に対しても言えます。人に寿命があり、老化が避けられない以上に、身体的に衰えたり、病気のリスクが増すのも必然です。ただ、そのリスクを下げて病気の予防をすることは可能で、それを食事の面から科学的に伝えられるのがデータ栄養学といえます。
なぜデータ栄養学が重要なのか
たとえば、ビタミンCはその抗酸化作用から風邪に効くという説があります。これはその栄養素の機能面からそのような働きが期待できると考えていて、いわゆるビタミンC点滴療法などもその理屈を進めたものです。では、実際にビタミンCをサプリで取るとして予防はできるのでしょうか。現在あるデータから導かれる結論としては一般の健康な人には効果がないと考えるのが妥当と言えます。
他にも魚油などに含まれるn-3系脂肪酸には様々な効果が期待されてたくさん研究されていますが、実際の結果は効果がみられない場合が多かったりします。でも、魚の摂取自体には健康に寄与する効果があるとする研究があって、成分と食品の効果が一致しないのです。だから、単純に栄養素ひとつとって良し悪しを語るというのはとても難しく、こうしたところは栄養学の難しい部分だと僕も思います。
一概にざっくりと言ってしまいましたが、そのアウトカムが妥当なのかどうかなど判断するには、やっぱり論文を正しく読めるようになるしかありません。それを、一般にわかりやすく解説、啓蒙してくれるのが本書というわけです。
9. 被害者目線になんてなれない『聲の形』
『聲の形』はいじめる側といじめられた側の話です。それは複雑にからみあって、ねじれています。描かれる感情はあまりにも生々しくて重く、追体験をしているかのように錯覚するほど繊細な揺れ動き方をします。
いじめのニュースが流れてくると、僕らはたいてい自分は関係していないからと、被害者の側に立って加害者を糾弾します。でも『聲の形』では、被害者目線でなんてきっといられない物語です。
「しにたい」
ただ、生きるのがつらいというだけではなく、人に迷惑をかけていると感じると、僕らはどんどん自罰的な感情に支配されていきます。その感情にどう向きあうのか。
色々読んできましたが、間違いなく傑作です。
10. 「太っちょのおばさん」に救われる話
賛否あるだろうけど、個人的に爆笑問題のススメ最終回 ゲスト:太田光「死ぬまでに読め!のススメ」の解説が本当に素晴らしくて、その捉え方に全面的に同意したい。本書に関して言えば、僕の感じたことを本当にそのまま言葉にしてくれたような気がしているくらい。
ニコニコ動画でしか、その内容を知ることができないのが残念。
言葉や外見で着飾るなんて無意味だ、そんなやつはいやらしい。そう憤りを感じる一方で、自分もまたかっこよくなりたい、好きな子に振り向いてほしいと思う人間の一人だったり。あるいは、どうして貧困を解決せずにそんなに裕福な暮らしができるんだと憤りながら、自分もまたその一人であったり。死にたいと考えながら死なずにただ世話になって、親の生活を疲弊させたり。つねに自己嫌悪に苛まれて、なんのために生きるのかがわかりませんでした。中学校生活も疲れ果てて、挙げ句には不登校になってしまったくらい。
同じとは言わなけれど、フラニーも自己嫌悪に苦しんでいた一人でした。そんな彼女の救いが、兄ゾーイの伝える「太っちょのおばさん」の存在です。いろいろな方の解説で「おばさん」とは誰かが解釈されていますが、太田さんのようにそれは読者の自由なのです。僕が感動した時に目の前にいたのも、本当にただの「太っちょのおばさん」でした。
ちなみにこの太田さんのススメの中で『タイタンの妖女』という小説が出てきます。この動画を見てから読んだのですが、これが本当によかった。人生が舞台なのだとしたら、その幕引きはきっと本当に愉快で、みんながみんなのために拍手喝采しているんだろうなってそう思えました。
僕の中では『フラニーとゾーイ』『タイタンの幼女』、今回紹介できなかったけれど『世界のすべての七月』の3冊は切り離すことができません。作風なんてぜんぜん違うんですよ。でも、根底にあるのはすべて救いでした、少なくとも僕にとっては。
最後に
これが「高校中退してから、読書メーターを10年続けたら2000冊読んでいた、そんな僕が薦めたい10冊」です。
勢い余って、後半は構成めちゃくちゃになってしまいました。日数もかかってしまったし、まだまだ紹介したい本はたくさんありますが、今回はこれでおしまい。
本が読めるって本当に幸せなことだと思います。
読メさん、これからもどうぞよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。これからも役に立つnoteにしていきます。
