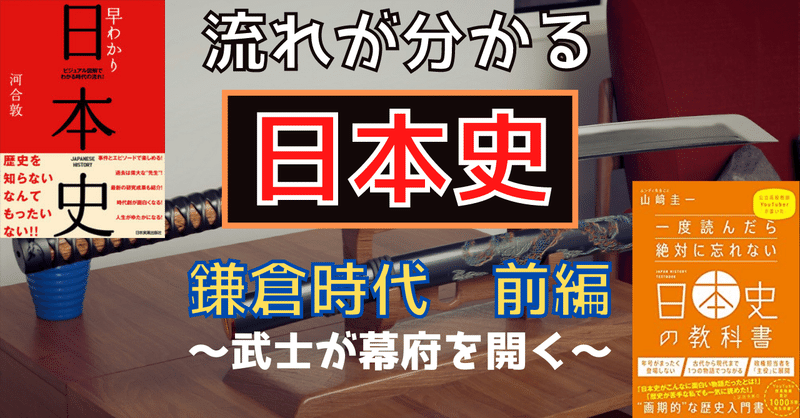
流れをつかむ日本史「鎌倉時代 前編」
トモーロです。
今回から流れが分かる日本史は、鎌倉時代に入っていきます。
前回、義経の指揮のもと平氏を滅ぼした源氏。しかし、活躍した義経は、頼朝の恨みをかい奥州藤原氏に殺されてしまう。
そこから、鎌倉でどんどん勢力を伸ばす源頼朝はその後どうなったのか。
それではいきましょう!
<鎌倉幕府の成立>
義経が平氏を滅ぼしてある間、頼朝は鎌倉を中心に政権づくりをしていました。
奥州藤原氏を滅ぼした後、頼朝は征夷大将軍に任命され、鎌倉に幕府を開きます。これが鎌倉幕府の成立。
幕府とは、一般的に征夷大将軍が作った政権のことを指す。
鎌倉幕府の役割は、基本的に治安維持であった。その要員として、守護や地頭が置かれた。
この守護、地頭は将軍の家臣である御家人の仕事であり、将軍と御家人は、御恩と奉公のもと契約が結ばれていた。
簡単に説明すると、将軍が新しい土地を支給(御恩)、幕府のために鎌倉の治安を守る(奉公)という主従関係であった。
しかし頼朝の死後、源頼家、源実朝を将軍に立てるが長く続かず、源氏はわずか3代で途絶えてしまった。
ここで、実権を握るのが。北条氏であった。中でも頼朝の妻、北条政子(ほうじょうまさこ)は「尼将軍」と呼ばれ、大きな影響力を幕府に及ぼしていた。
<力でねじ伏せる後鳥羽上皇>
どんどん勢力を伸ばす幕府に対して、衰えた朝廷の権力の復活を図っていた人物がいた。
それが後鳥羽(ごとば)上皇である。この男は、超筋肉野郎でした。
勝ち気な性格で、武芸を好んだと言われる後鳥羽上皇。
盗賊逮捕の現場にも自ら赴き、自ら族をねじ伏せるという伝説を持つ男であった。
後鳥羽上皇は、西の武士や御家人を集め、西面の武士という武士団を設置して軍事力を強化します。
東の武士たちは、北条氏と主従関係を結んだわけではなく源氏と主従関係を結んだ。
だから、北条氏のことは裏切るはずだと読んだ後鳥羽上皇は、大軍を送り込みます。
それに動揺した東の武士たち。しかし、これを静め奮起を沸かせたのが北条政子の演説であった。
「朝廷から差別され続けた武士たちを現在の地位に引きあげたのは誰だ。それは頼朝ではなかったのか。その恩に報いるのはまさに今であろう。もし朝廷に従うと言うのであれば止めはしない。私を斬り捨てて行きなさい。」
この演説に目を覚ました東の武士たちは、朝廷軍を打ち破りました。
これが承久の乱である。
戦後、当時執権であった北条義時は子供の北条泰時(ほうじょうやすとき)を朝廷を監視し西日本を統括する六波羅探題に任命する。
<絶体絶命モンゴル帝国襲来>
北条泰時は、とても優秀であった。義時の死後執権となった泰時は、武士たちの基本法「御成敗式目」を作った。
これがよくできた法律であると評価され、室町時代以降もこの法律に追加する「式目追加」という手法が取られた。
こうして、全国政権がついに成立し、もう敵はいないなと思った北条氏。
そんな時、大事件が起こります。それはモンゴル帝国(元)のであった。
中でもフビライ・ハンは、当時の執権、北条時宗(ほうじょうときむね)にうちの属国になれと使者を送ります。
しかし、これをフルシカトする北条時宗。それに怒った、元のフビライ・ハンは3万人の兵を日本に送り込みます。
もう日本は絶対絶命。当時日本は騎馬戦での戦い方が主流の中、元軍は集団戦法で戦ってきました。
さらに、陶製の球の中に火薬を詰めた「てつはう」という武器を使って日本を攻めます。
夕方になり、夜襲を警戒した元軍は自船へと引き上げて行きました。
しかし、夜中に暴風雨が元軍の船を襲いなんと船が沈んでしましました。まさかの日本勝利。
しかし、こんなもんのでは諦めないフビライさん。翌年、今度は14万人の兵で日本に乗り込んできました。
前回、3万人でも苦戦したのに今回は14万人とか日本からしたらもう意味が分かりません。
もはや日本に勝ち目なし。そして、「フビライさんあんまりじゃない。」と言いながら頑張って戦う日本。
そして、「まあ、去年は失敗したけどよ。一旦船戻るぞ。」と自船に戻る元軍でした。
そして翌朝、海を見るとなんと2度目の暴風雨で元軍の船が沈んでいました。またも日本勝利。
これ以来、日本には不敗信仰が流れました。
これに対し、戦闘を行なった武士や御家人に対して恩賞を受けようとしました。
しかし、防衛戦のため恩賞を与えることが出来なかった幕府。徐々に不満が溜まっていきました。
<まとめ>
いかがだったでしょうか。今回は鎌倉時代の前編を見て行きました。
源頼朝の話がいつのまにか妻が実家を握り、妻が主役になるという鎌倉時代。
女性の言葉が武士を動かすというまさに尼将軍でしたね。
また、二度のモンゴル帝国襲来はまさに日本の大ピンチ。奇跡の連続で免れた日本でした。
さて、鎌倉時代は文化が栄えた時代でもありました。次回紹介したいと思うのでお楽しみに!
もし読んで面白いと思っていただけたらサポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金につきましては、質の高いアウトプットのために本の購入や費用に使い、よりよい情報発信をしたいと思います。
