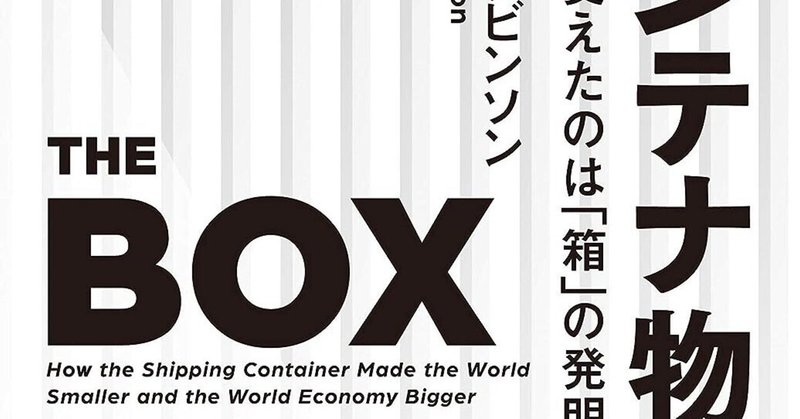
読書感想 コンテナ物語/マイク・レビンソン
物流革命を起こしたのは、ただの「箱」だった。
今回紹介の本は『コンテナ物語』。世界的に話題になった本なので、名前だけでも聞いた人は多いでしょう(でもあんまりにも分厚い本なので諦めちゃった人も多いでしょう)。コンテナが物流の世界に登場したのは1950年代の話。このコンテナが登場したことによって、物流の世界だけではなく、社会の形そのものも変わってしまった。それも世界規模の変動だった。コンテナは文字通りの「革命」を起こした発明だったのだけど、現代、その偉業は完全に忘れ去られていた。著者も研究を始めた頃、まわりに「なんであのただの鉄の箱に過ぎないものなんか研究しているんだ?」とずいぶん言われたそうだ。それに、研究しようとも、まとまった資料がどこかに保管されているわけでもない。本書の主人公に相当するマルコム・マクリーンにしても、別に“銅像が建っているような偉人”というわけでもなく、忘れられた人物だった。まるで遺跡発掘のように、色んなところを駆けずり回り、資料や人々の発言を探して回って、ようやく完成させたのがこの1冊だったというわけだ。
(Wikipediaを見るとマルコム・マクリーンのページがあるが……もしやと思って履歴を見ると、ページが作られたのは2021年……この『コンテナ物語』が出版された後だった。内容もほぼ『コンテナ物語』を元ネタにしたものだった。『コンテナ物語』の出版によってやっと再発見された人物だった)
この本に巡り会った私も、正直なところ「コンテナが? 革命?」と言われてピンと来なかった。でも読んで納得。確かにコンテナは世界を変えた発明だった。読んでいるうちに考え方が変わるくらいのインパクトのある一冊だった。

では簡単に、コンテナが発明される以前、1950年代以前の物流がどんな様子だったかを触れておこう。
コンテナが登場する以前、物流は「金」のかかる世界だった。国内輸送はまだなんとかなるけど、海外輸送なんて考えられなかった。当時はさすがに「樽」を転がしていたわけではなく、「パレット」があり、フォークリフトもあったが、そのフォークリフトで積み荷を一つ一つ運び、クレーンでつり上げて船に積み込んでいた。波止場には一杯の大小の荷物があって、「沖仲仕(おきなかし)」と呼ばれる力自慢の港湾労働者が働いていた。荷物の積み込み・積み下ろしには時間がかかり、当時の船にはそこまでの積載量もなかったし、船から降ろしても次に待っているのは一杯のトラックの列。とにかくも効率が悪かった。
それに沖仲仕たちによる窃盗も横行していた。沖仲仕はいわゆるな“海の荒くれ”たちで、自分たちでそういうキャラクターを演じていたところがあり、荷物を積んだ箱をいかに傷つけず、中の物を手品のように抜き取るのか……を自慢しあっていたくらいだった。
物流は時間も金もかかるし、荷物が破損することも多かったし、盗難も当たり前だったから到着しないことも多かった。それが1950年代、ある「箱」の出現によって劇的に変わっていくことになる。今回のお話しはそのはじまり物語。
第2次世界大戦が終わった後、アメリカは好景気に沸いていた。が、海運業はそうではなかった。というのもアメリカの船は戦時中政府に徴発されていて、終戦から2年間民間に戻ってこなかった。それに、戦時中、ずいぶん船が沈められていた。その間にトラックがシェアを拡大。船は数が減っていただけではなく、働き方が昔のまま、一つ一つ積み込んで運んでいただけなので、効率が悪かった。いわゆるな衰退産業だったが、船会社はその体質を変えようとも思っていなかった。
そこに現れたのは本書の主人公、マルコム・マクリーンである。

まずマルコム・マクリーンの来歴を確かめておこう。
マルコム・マクリーンはノースカロライナ州マックストンで生まれた。人口3500人程度の、小さくて沼地の多い田舎だった。かつてはシューヒールと呼ばれて、18世紀末にスコットランド人が入植してできた街だった。それで地元の新聞は今でも「スコティッシュ・チーフ」と呼ばれている。1901年になってやっとロブソン群に電気が通り、マクストンの街には電話がやってきたけれど、周辺の町や村にはまだなかったので、その周辺の町や村の人々が電話をするために列車に乗ってわざわざマクストンにまでやってきた、というエピソードがある。
そんな田舎で生まれたのがマルコム・マクリーンだった。
マクリーンの父親もマルコムといって、地元ではなかなかの農場主だった。シューヒール周辺にマクリーン農場が5、6箇所あり、ランバートンにもマクリーン農場が1つ、さらに法律事務所も経営していた。父マクリーンは親戚の伝手(つて)があって、1904年に地元の郵便配達の仕事を得て、農場収入を補っていた。息子マクリーンもやはり親戚の伝手で食品店に勤め口を見つけていた。こういう時代だから、「親戚の伝手」の力が強かった。
次の話もやはり親戚の伝手だった。ガソリンスタンドの経営者募集があったので、伝手でその仕事をもらい、青年マクリーンは借金をしてガソリンを仕入れていた。
マクリーンの最初の転機は1934年3月のことだった。地元から45キロ離れたファイヤットビルまでいけばガソリンが安く仕入れられる、と聞いたマクリーンが行ってみたところ、そこのガソリンスタンドのオーナーが中庭に放置してあったおんぼろトレーラーを使ってもいいと言ってくれた。これでマクリーンはダンプカーの所有者となった。
わらしべ長者はまだ終わらない。ダンプカーを手に入れたマクリーンは州の大型公共事業の土を運搬する仕事を手に入れ、これで運転手を雇って仕事ができるようになった。さらに新しいトラックを1台購入。地元の農産物を運ぶ仕事を始める。
翌1935年になるとマクリーンはトラック2台、トレーラー1台、運転手9人を雇う運送会社の社長になっていた。1940年になると好景気で勢いがのり、トラック30台、年商23万ドルのそれなりの会社に発展した。1946年にはトラック保有台数162台、売上高220万ドル。右肩上がりで急成長していた。
マクリーンはコスト削減の鬼だった。仕事を獲得するために営業マンを派遣するのだが、その時に徹底的に「ルート」の研究をさせる。運転手にはどのルートを通って、どこのガソリンスタンドで給油するかも指導した。マクリーン社のトラックは側面がギザギザになっていたが、これは空気抵抗を減らすための工夫だった。とことんコスト削減に努め、その上で他社よりも低賃金で交渉し、それでもきっちり収入を出す。そのことに全精力を注いでいた。
新人研修も徹底していて、新人はベテランと半年間組んで、その後ようやく仕事を任される。その時に寄り道なんか絶対にさせない。言われたとおりのルートをきっちり走るよう指導させる。そうしたほうが早く、安く仕事が済む、ということを理解させるためだった。もしも1年間無事故でルートを守ればボーナスが出る、という仕組みだったから、このおかげで運転手達はみんなルールを守るようになっていた。
そんな徹底したコスト削減と契約獲得で事業を拡大していき、1954年には全米最大級のトラック輸送会社になっていた。総資産額は1140万ドル。トラック保有数は617台だった。
そんなマクリーンに新しい閃きが降りてきたのが1953年。当時、車社会が進行していてハイウェイの渋滞が問題になっていた。そこでマクリーンは、「そうだ! 混雑した道路を走らせるより、トレーラーごと船に乗せてしまえばいいんだ」と思いつく。
当時のアイデアは、船に渡り板をかけてトラックがトレーラーをひいて甲板まで運転する。その甲板上でトレーラーを切り離す……という方法だった。
さあわらしべ長者の続きだ。1953年末、マクリーン運送はターミナル用地を探すが、ニューアーク港がちょうど港湾事業の見直しを図ろうという時だった。そこはトラックを何十台も入れるのに充分なスペースがある。マクリーンが港湾局に相談を持ちかけると、あちらにとっても濡れ手に粟。マクリーンは資金調達することなく自分のアイデアを実現できるチャンスを得ることができた。
さて船はどうするか? ちょうどパンアトランティック海運という船会社がストライキの影響で仕事ができない状況に陥っていた。よし、買収だ。マクリーンはパンアトランティック海運を4200万ドルで買収し、港湾事業を開始。当時、政府が戦争時に徴発していた船をタダ同然で払い下げていたわけだが、マクリーンはこれも所有することができた。その時に法律上のいろいろややこしい問題は起きたが、そこはスルーしよう。
船会社と船を手に入れ、港の改良が進行している1955年頃、マクリーンのアイデアは進化する。はじめはトレーラーに車輪を付けて船に積み込むつもりだったが、いや、車輪も外して「ボディ」だけにすればいいんじゃないか。「箱」の状態にしてしまえば、2段3段に積むことができる。だから港にはでかいクレーンを作って、トラックから箱だけ外して船に載せる。これができるなら、船だけではなく、箱を列車に、飛行機にも乗せられる!
しかしその肝心の「箱」がその時代、世の中に存在していなかった。そこでマクリーンはコンテナ製造専門会社であるブラウン・インダストリーに連絡する。マクリーンは自分のアイデアを技師に伝え、取り外し可能、積み重ね可能の画期的な新型コンテナを特注で作ってもらった。当時の新型コンテナは業界で注目はされたものの、「みんな興味は持ってくれるが、買ってくれなかった」という証言があるように、それを作って買っていたのはマクリーンだけだったようだ。
いよいよ準備が整い、新事業開始……といきたいところだが、政府が横槍を入れてきた。トラック業界、港湾会社もいろいろ文句を言ってくる。どこの国のどこの業界も派閥やら慣例やらしきたりやらでうるさかった。マクリーンが始めようとしている新しい仕組みをなかなか受け入れようとしなかった。
そんなゴタゴタを抱えながら1956年4月26日、パンアトランティック海運所有のアイデアルX号が初出港する。その現場には沿岸警備隊も集まってきて監視していた。アイデアルX号は8時間あまりで長さ33フィートのコンテナを60個ほど積んで出航した。
マクリーンは直ちにコスト計算をした。当時の中型貨物船に積み込む場合、トン当たり5.73ドルかかっていた。アイデアルX号はトン当たり15.8セントしかかかっていなかった。およそ37分の1である。このコスト計算を出したとき、マクリーンは勝利宣言をする。輸送革命の始まりだった。

本の感想
はい、本の紹介はここまで。ここから先のお話しは、本を読んでくださいね。
この後のお話しをダイジェスト的にまとめると、間もなくマルコム・マクリーンにライバルが出現する。というのも、マクリーンとほぼ同じ時期、同じようにトラックの荷台を「箱」にして外し、船に乗せて運んでしまえばいい……と気付いた人がいた。それがマトソン海運に勤める地球物理学者のフォスター・ウェルダンである。もちろん、ウェルダンはマクリーンのアイデアをパクったわけでもなく、コンテナが世に現れる前から同じ閃きに至り、計画を進行し、結果的にマクリーンよりも後発になったものの、1958年にコンテナ船の運用をスタートさせた。
「素晴らしい閃き」というのは、一人の天才の頭に脈絡もなく与えられるものではなく、諸条件が整ったときに起きるものである。これには時代的な要因というものがあり、その時代に必要な材料が整ったからこそ閃きは訪れる。だから「同じ閃き」に至る人が同じ時代に何人もいても不思議ではない。同じ時代に似たような物語作品がやたらと作られたり、一つの大ヒット映画が作られると「あれは俺が作ったやつのパクリだ!」と言う人が何人も現れるのはこういう理由である。
とにかくもマルコム・マクリーンとフォスター・ウェルダンは同じ発想に至り、ほぼ同じタイミングで港に巨大クレーンを設置し、コンテナを船に積み込む仕組みを作った。二人はお互いに面識がなく、お互いのアイデアを見ることなく、ほぼ同じものを作ったわけだ。二人の間にどんな違いがあるのかというと、マクリーンは直感を頼りに行動する人だから、コンテナを船に積み込んでから、コストがどれだけかかったか……という計算をしていた。一方のウェルダンは学者気質だったので、なにかを始める前に綿密に綿密に計算を重ねて、「コンテナで運送した方がお得」という確信を得てからやっと動き始める……というやり方だった。ほぼ同じ時期に閃いたのに、ウェルダンのアイデアが世に出るのがやや遅かったのはこういう理由だった。
ナワバリも違った。パンアトラティック海運は大西洋側を。マトソン海運は太平洋側を拠点とした。お互いのアイデアを確かめ合ったわけではなかったから、コンテナのサイズも違っていた。とにかく拠点も違ったので、パンアトランティック海運とマトソン海運はお互いをライバル視しながらも、別々の地域でコンテナ革命の開拓を進めていったのだった。

西海岸をパンアトランティックが、東海岸をマトソン海運が、それぞれで巨大なコンテナを運ぶようになって、運送の業界はいきなりコンテナ一色になったのか……そうはならなかった。確かに話題にはなったけれども、「じゃあうちでもコンテナを」とは誰もやろうとはしなかった。むしろ「あんなのは一時だけだよ」「儲かりはしないよ」という意見の方が大勢だった。1960年頃になるといろんな大学が「コンテナの有用性」について研究し、論文が発表していたが、その中で「コンテナは有用である」と書いたものは少数だった。学者もコンテナの有用性を過小評価していた。港で働く人々も、学者達も数十年後、港湾の風景がコンテナ一色になるとは思っていなかった。
コンテナの有用性は誰も気がつかなかったが、その後何年もかけて、少しずつ港に巨大クレーンがある風景が当たり前のものになり、それを使うことが当たり前になっていき……。コンテナ革命は非常にゆっくり、ゆるやかに移り変わっていったので、コンテナの時代がやってきたとき、それが「革命だった」とは誰も考えなかった。
違う例えでいうと、私たちは「産業革命以後」の社会にいる。私たちの社会制度や習慣、ものの考え方の多くは、実は産業革命以後を起点にして生まれたものだ。しかし私たちの大半は、私たちを取り巻く社会そのものが「産業革命以後だから」なんて意識しない。それが当たり前だと思っている。確かに移り変わりが始まる頃はゴタゴタがあったものの、その時代を過ぎて10年、20年が経ってしまうと、人間は忘れてしまうものである。
そんな具合だったので、1950年代、コンテナの運用が始まった最初の頃というのは、パンアトランティック海運とマトソン海運以外はどこもコンテナを使おうとはしなかったし、使ったとしても使い方をよく理解していなかった。それで荷物を送った先で空のコンテナを山積みにしたり、その空のコンテナをそのまま送り返したりしていた。コンテナに荷物を積んでも満杯にせず、そこそこの量だけで送り返したりしていたから、かえって運賃が高く付き、それで「コンテナはかえって予算がかかるダメだね」みたいな話にもなっていた。送られてきたコンテナを満載にして送り返せばこっちもお得……という発想に至るまで、やはり10年とか20年とかかかったのだった。
それでも世の中はゆるやかにコンテナの活用法に気付き、少しずつコンテナを使うのが当たり前の社会になっていった。1950年頃、マルコム・マクリーンがコンテナなるものを思いつき、それを船だけではなく列車や飛行機にも乗せちゃえばいいんだ! というその通りのものが実現したのは、1980年代に入ってやっとだった。コンテナ革命はそれくらいの時間をかけてようやく完了したものだった。
ではコンテナ革命によって世の中はどう変わったのか? 最初に「世界の形そのものを変えた」と書いたが、どういうことだったのか?
かつての社会では、国内で製造した物を海外に送るのは輸送費が高すぎて割に合う商売ではなかった。ところがコンテナで輸送するとコストは数十分の1で済んでしまう。輸送費がそれだけ安くなってしまうと、製造の現場を国内に置いておく必要はなくなり、より人件費の安い国で商品を作り、輸送すればいい……という発想が生まれた。今ではコンテナの中に入っているのは「部品」だけである。ある部品はマレーシアで作り、ある部品はインドネシアで作り、ある部品は……という感じに色んな国でいろんな部品を作り、最終的に寄せ集めて商品にする。そういうやり方のほうが安い、という状態になった。
例えばバービー人形だ。バービー人形はアメリカ生まれのおもちゃだが、実は一度もアメリカで作られたことはない。ナイロンの髪は日本製、ボディは台湾製、染料はアメリカ製、服は中国製……と世界中でいろんなところで作られて組み立てられているのがバービー人形だった。
ジャストタイム方式というものがあって、これはトヨタやホンダが採用しているのだが、顧客が必要なときに、必要な数だけ生産して送り出す方式である。かつては一杯作って、一杯ストックする……というやり方だったが、ジャストタイム方式が可能になったので、余計な在庫を抱える必要もなくなった。
そうすると問題なのはもともと工場のあった国だ。アメリカや日本は、コンテナリゼーションが始まる以前、国内にたくさんの工場があったが、これらが一気に姿を消すことになる。インドネシアやマレーシアやベトナムといった人件費の安い国には工場が一杯作られ、潤う反面、逆に先進国から工場が撤退したため多くの失業者を作ることになった。
2000年代はじめ頃まで、「メードインアメリカ」の家電というものも存在しなかった。経営者は利益追求のために、アメリカ以外のところで家電を作って送る……というやり方を取っていたためだ。しかしそれではアメリカ国内が失業者だらけになり、作っても買う人がいない……という状況に陥っていた。
別に国内の失業者を救済しようという理由とかではなく、いよいよアメリカ人労働者の人件費も安くなったから、という経営者的な理由ではあるが、2000年代以降、ようやくアメリカ国内で工場が復活し、メードインアメリカの家電も今では存在している。
似たようなお話しは日本でも起きていて、最近の日本は円安だ。今まではインドネシアやマレーシアといった国に工場を持っていたが、とうとう「日本国内に工場を作った方が、製造費が安くつく」という状態に陥った。それは日本がそこまで落ちぶれた……という意味ではあるが、こういう事情で日本は2020年代に入って急に工業化を始めている。
このように人件費の高い/低いで拠点をコロコロと変えるようになったのも、コンテナ革命以後の話だ。
前回の読書感想文で『実力も運のうち』を紹介したのだが、そちらの内容を踏まえて考えると、「世界における労働の総数」には限りがある……ということがだんだんわかってくる。流通革命により、より賃金の安い国に工場が移る。するともともとあった国に失業者で溢れる。最近は工場が戻ってきてそこで雇用される人が増えてきたが、すると賃金が安かったために工場が作られていた国では、失業者で溢れていることだろう。
人間は世界規模の流れを俯瞰して見ることができないから、そうした変化を頭に置かず、「仕事がない奴らは自己責任だ」と言ったりする。
脳天気な人は「仕事がないんだったら起業すればいいじゃない」とか言ったりする。しかしそれは誰にでもできるものではない。工場に勤めているだけの人にそんなことを言ってもうまくいくわけがない。
こういうときに、「自己責任だ」と切り捨てることが果たして道徳的か? 仕事をなくした人に「働かないのは甘え」という余裕があるくらいなら、自分が新しい産業を興してその人を雇うほうが人道的ではないか。……という話は『実力も運のうち』で書いたので読んでもらいたい。
話をコンテナに戻そう。
港湾労働者の環境も激変した。かつての港では「沖仲仕」と呼ばれる屈強な男達が何人も働いていた。これからは荷物をコンテナに積み込んで、クレーンで運べば良いだけだよ……となったら問題になるのが沖仲仕たちの仕事だった。「港の仕事はクレーン1つあればいいんだ」となれば、沖仲仕のほとんどは必要でなくなってしまう。
沖仲仕たちはコンテナの導入に激しく反抗し、各地で大規模ストライキを起こした。コンテナ導入が何十年もかかったのは、これが原因だったといってもいい。沖仲仕たちはコンテナに反抗するため、荷物を港に下ろしたとき、いったん梱包をほどき、荷物を港にずらりと並べ、再び梱包し、積み込む……というまったく意味もなく、無駄に時間がかかる作業をやっていた。そうやって意味もない作業を入れないと、港で働く人々に仕事が行き渡らない状態になりつつあった。
沖仲仕と経営者との間に起きた十数年という長い対立と葛藤の末、ようやくコンテナの時代がやってきて、いま港には大量のコンテナが山積みにされているが、実際に働いているのは数十人のブルーカラー達でしかない。もともと数百人が働いていた現場が数十人程度になったので、いま港で働くブルーカラーは超高級取りとなっている。
では港を去った沖仲仕達はどうなったのだろうか? アメリカでは沖仲仕たちは20人ほど班を作り、この班のことを「ギャング」と呼んでいた。ギャングという名前を聞いてピンときた人も多かろうと思うが、失業した沖仲仕達はいわゆる犯罪者の「ギャング」となっていった。日本ではヤクザというものがいて、そのヤクザの代名詞的存在である山口組も、実はかつて港湾労働者達であった。一度に大量の失業者が生まれると、そのうちの何割かは犯罪組織化するという法則があるが、今回もそうなってしまった。コンテナ革命は世の中に混沌をもたらす犯罪集団も生んでしまったのだった。
日本にも関係のある話なので、この話も載せておこう。
1965年の冬、アメリカはベトナムへの軍事介入をはじめた。そこで問題になったのは物資の供給だった。アメリカ政府は昔ながらのやり方でベトナムに荷物を運び込もうとしたが、とにかくも効率が悪い、荷物が届かない、紛失する、港周辺に船の大渋滞が発生する……などの問題が起きた。
そこに飛び込んでいったのが我らがマルコム・マクリーンだった。マクリーンはコンテナ船で送れば輸送の問題はたちどころに解決する、と提案し、納得させ、ベトナムの港を改良してコンテナ船の運航を開始させた。ベトナム港での問題はマクリーンの言ったとおりに解決し、以降、政府は輸送の問題は民間に任せることにした。
政府公認でコンテナ船をベトナムまで送り込めるようになったら、次は帰るときだ。コンテナを空にしたまま本国まで戻るのはもったいない……。そこでマクリーンが目を付けたのが日本だった。
日本はこの当時、まだコンテナ船を入れていなかったのだが、マクリーンが営業に飛び込み、コンテナ船の有用性を説得。それで行きはベトナムへの物資、帰りは日本の家電を満載にしてアメリカに帰還する……という運航が始まった。
日本の家電神話が始まったのは、実はこれが切っ掛けである。この時マクリーンがコンテナ船を持ち込んだおかげで、世界中で日本の家電の良さが知られるようになり、現在に至るまでの地位を作った。コンテナ革命は日本人の地位向上に大きな影響を与えていた。マルコム・マクリーンがこの時に日本に来なければ、「日本の家電神話」は生まれなかった。もしもこれが別の国だったら? その国に「家電神話」が生まれていたかも知れない。日本の家電神話は、日本人自身の自尊心にもなっているが、これを作ったのは他ならぬマルコム・マクリーンであった。
日本人の大半は、日本の家電神話が始まったのは、日本の家電がもっとも優れていたから……と思い込んでいるが、実際はそうではない。まずベトナム戦争があり、そこでマルコム・マクリーンがやってきて、ベトナムからの帰りにコンテナにモノを詰め込みたい、そこに日本がちょうどいい位置にあったから、日本の家電が世界に広まった。すべては地理的な要因だったので、もしもそのちょうどいい位置に別の工業国があったら、その国の製品が「世界に名だたる家電」の地位を得ていただろう。
さっき「2000年代初めまでメードインアメリカの家電はなかった」と書いたが、これを滅ぼしたのが日本の家電で、その切っ掛けを作ったのがマルコム・マクリーンによるコンテナ輸送だ。お話しは全部繋がっているのだ。
その後、日本の工場は中国に奪われ、仕事も技術も奪われていった。犯人は誰だったのか……というと日本自身。輸送費が安くなれば、「より人件費の安い国へ」行くのは当然の摂理で、中国は世界の工場を自国に集めようと国を挙げて誘致していたため、日本はこの計画に乗り、国内の雇用も技術も奪われることになる。日本国内に大量の失業者を生み、不況を作り、家電の地位は中国に奪われていくことになる。私が使っているモニターも中華製だ。なぜなら今や中国製品の方が品質が良く、安いからだ。誰が犯人か……といえば日本人自身。日本の大企業と政府が利益追求した結果、この状況を作った。
こういう経緯はなかなか俯瞰して見ることができず、単純に失業した人々に対し「自己責任だ」と軽々しく言うが、実際には個人の責任以上に大企業や政府のやらかしがあった。「より安く、効率よくモノを作ろう!」という合い言葉の上に、気付けば国内の不況を自ら作っていたのだった。大企業の偉い幹部連中すらも、このことに今も気付いてないかも知れない。
大企業や政府は「より安く、効率よくモノを作ろう」相変わらず変えていないが、日本国内が30年にわたる不況で賃金も物価も下がり、2020年代、とうとう日本国内に工場が戻ってきた。どうしてこうなったか……というのはご存じの通り、“いわゆる後進国”よりも日本国内で工場を作って日本人を雇った方が安くなったからだ。
なんとも情けない話ではあるが……ようやく世界に誇る「メイドインジャパン」を取り戻す切っ掛けを私たちは掴んだ。今、熊本にTSMCの半導体工場が作られ、すると工場への雇用だけではなく、その周辺の商店も賑わう……という現象が起きている。これが工場一つ作られることのメリットである。大企業や政府は相変わらず「安ければどこでもいい」というスタンスだが、私たちはこのチャンスを逃してはならない。
話を1970年代に戻そう。
コンテナにすると、輸送費が格安で済む! これがわかってくると、いよいよ競争の時代に入っていく。あちこちでコンテナ船建造ラッシュが始まる。日本もこの時にコンテナ船を作った。過当競争の時代になると、自ずと価格競争が始まる。輸送費は安くなり続ける一方で、コストとの兼ね合いが難しいものになっていく。コンテナ船の運用は当たり前だがガソリン代がかかる。そのガソリン代を上回らないよう、ぎりぎりの値段設定にしなければならない状態になっていく。
そんな最中、1973年第四次中東戦争が始まり、オイルショックが起きる。コンテナ船は動かすだけで赤字を吐き出しまくる、厄介なものになってしまう。
それだけではない。コンテナ船はより多くのコンテナを積み込むために、どんどん大型化した。大型化すると港も大型化しなければならない。港の改築費も高く付いた。船会社が統合され巨大化し、運用する船の数も減り、港の数も減り、そこで働く人も減っていった。例えば台湾にはもともと数カ所港があったが、高雄の港が大成功したが残りは衰退した。コンテナがやってくるかはどうかは、港運営に大きく関わるし、さらに国家運営の問題にも関わってくるから、どこもコンテナ船誘致に必死だった。
例えば2012年、ドイツのヴェルヘルムスハーフェン港は、大水深を確保するために4億3400万ドルも投資した。しかし港が完成する頃にはコンテナ船のほうがもっと大きくなってしまい、コンテナ船がこの港にやってくることはなかった。
逆に大成功だったのがシンガポールだ。シンガポールはもともとマレーシア連邦の一州だったが、65年に分離独立。この時に外貨獲得の手段として提唱したのが港だった。シンガポールは独立したばかりで産業もほとんどない。ならばハブ港にしよう、というビジョンを立てて、そのための港建設を始めた。これが大成功を収め、日本、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンの船が集まるターミナル港として繁栄した。
大失敗するところがあれば、大成功するところもある。コンテナは始めれば儲かるものではなく、常に未来の状況を見通して投資しないと逆に大損してしまう、難しいものになっていた。
コンテナは負の側面も一杯作り出した。すでに書いたように、現代のギャングやヤクザはコンテナ革命によって生まれたものだった。輸送費がやたらと安くなってしまったために、工場が賃金の安い国へ移ってしまい、逆に先進国に大量の失業者を作ってしまった。
コンテナの負の側面はまだまだある。コンテナは基本的に到着するまで開封されないものだから、中に何が入っているのかわからない。そのため武器の密輸、麻薬、密入国者、核汚染物質といったものも輸送する隙を与えてしまった。こういう危険なものが入っている可能性があるから、そのための設備や人員が必要になった。

海賊の問題も起きた。コンテナ船は大量の荷物を積むから、速度が20ノットから速くても30ノット程度でしかない。高速船を飛ばせば、あっという間に追いつけてしまう。一攫千金を狙うならず者から見ると、船の上を宝船がゆっくり動いているようにしか見えない。2000年以降から海賊の問題が頻発するようになり、ほぼ毎月というくらいにどこかのコンテナ船が海賊の襲撃に遭い、荷物を奪われたり、船員が誘拐されて身代金を要求されるようになった。最近ではようやく船に武装警備員を置くようになり、海賊の被害は減少するようになった。
他にも、ある国の前を通過しようとすると「ジハードだ!」と叫びながら船ごと突進してくる輩もいた。それでコンテナ船は高速船が突っ込んでも穴が開かないくらいに作らねばならなくなった。
こんなふうに、「コンテナ」という革命は間違いなく世界を変えた。社会の仕組みも変えたし、風景も変えた。世界を変える革命だった。私たちは今、Amazonで海外の商品を輸送費など気にすることなく気軽に買えるのもコンテナのおかげだ。それだけの恩恵があったのに、なのに現代に至り、「コンテナは革命だった」ということは忘れられてしまった。
理由はいくつもある。
まずコンテナ導入の変化は非常に緩やかだったこと。始まったのは1956年だが、最初にマクリーンが提唱した理想通りの状態になるまで1980年までかかった。仕事の現場では世代が1つ2つ移り変わるくらいの時間だったから、後からやってきた世代にとって、クレーンでコンテナを積み込むのは当たり前。その以前の運送がどういう状況だったのか、は記憶の彼方になっていた。
それにコンテナ船は金食い虫だった。コンテナ船自体の建造にお金がかかるし、港の改築にもやたらとお金がかかる。せっかく大金をかけて港改築したのに、コンテナ船の誘致に失敗……そんな話は一杯あった。コンテナ船の運用にも金がかかり、石油ショック以降は輸送費とガソリン代のせめぎ合いだった。コンテナ事業に乗り出したものの、大赤字を出して撤退……そんな話も多かった。
当事者からすると、「コンテナ船ってそんなに儲かるかな?」みたいに感じになる。現状の損得感だけを見てしまうと、コンテナ船によって大幅に輸送費が下がって社会観が変わった……と言われても、なかなかピンとこない感じだった。
最後に「コンテナの父」であるマルコム・マクリーンの撤退だった。
1977年2月、マルコム・マクリーンが自分の作った会社から去って行った。理由は、会社があまりにも巨大化し、社員が官僚的な人間ばかりになって、直感的なタイプだったマクリーンと折り合いが合わなくなったからだった。
その後、田舎で農場経営をやっていたのだが、同じ年の10月、あっさりと海運会社に復帰する。1977年10月、マクリーンはユナイテッドステーツ海運を買収し、現役復帰した。
そこでマクリーンは超大型コンテナ船の建造を構想する。70年代の造船ラッシュが終わって、ちょうど建造費が安くなっていたタイミングだ。
この時、マクリーンは船の速度をあえてゆっくりめに作った。というのも当時はまだ石油ショックの影響下にあったから、石油の値段は今後も上がると踏んでいた。だから船の速度はゆっくりめで、燃費効率に優れ、そのぶん積載量がとことん大きな船を作る……という構想だった。
これが大失敗だった。1985年、原油価格は1バレル28ドルから14ドルまで下落。石油の値段は下がったのだった。すると「燃費効率のいい遅い船」は勝負にならない。そんな速度の遅い船に誰も荷物を預けない。この時作った船は数回運航したようだが、それだけだった。
マクリーンは読みを誤ったのだった。この失敗により、2億3700万ドルの損失を計上。ユナイテッドステーツ海運倒産、船売却、数千人の従業員が失業……。マクリーンはこの時、表舞台から去り、その後ほとんど姿を現すことはなかった。
2001年5月30日、マクリーンがこの世を去る。マクリーン死去の朝、世界中のコンテナ船が汽笛を鳴らして弔意を表した。「コンテナの父」の存在はこの一瞬思い出されたが、その後、忘れられていく。とうとう銅像が建てられることもなかった。
こうしてコンテナ革命の一時代は完結し、コンテナが当たり前の世界となり、その功績は誰のものだったのか、忘れられたのだった。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
