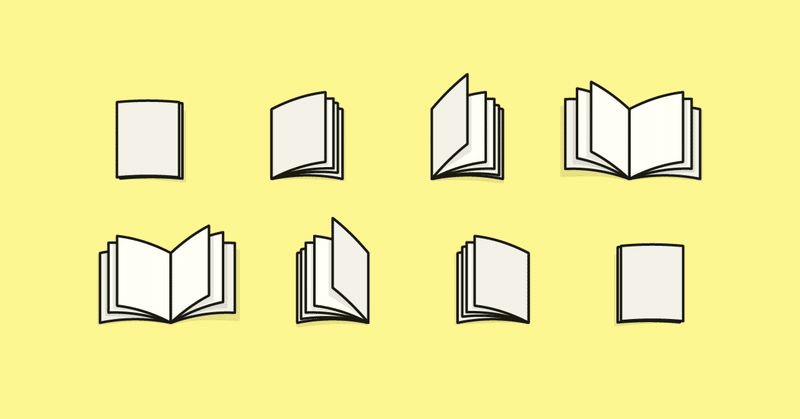
恋と学問 第28夜、聖典から他者の心に達した人。
今夜お話するのは、紫文要領の目次を作った時に一括して「補説」と名づけた、本論と結論の中間にある部分です。(岩波文庫版、151~162頁)
本居宣長はここで、源氏物語について言い残したことがないように、思いつくかぎりの論点を列挙しています。
補説1.栄華と物の哀れ
補説2.仏教・再論
補説3.人の情の本当の姿
補説4.物語中の迷信について
補説5.過去を想像する力
以上の5項目を、質疑応答の形式を用いて論じているのですが、議論の本筋からは離れているという事情もあってか、宣長の書きぶりも幾らかリラックスしているようなので、私たちも少しくらい砕けた物の言い方をしても許されるでしょう。宣長の議論をQ&Aにして、整理してみようと思います。
補説1.栄華と物の哀れ
Q1.物の哀れを知る人が善き人だとあなたは言いますが、一方では光源氏が栄華をきわめたことも善きことだと言っていますね。矛盾していませんか?栄華をきわめることと物の哀れを知ることは、全然関係ないことではないですか?
A1.関係ないことはありません。他人の外見や地位や品格などを見て、善いものだと感じることもまた、物の哀れを知ることです。いかに地位が高くて名誉もある人であっても人生は難儀なものだと知れば、何の取り柄もない人間の難儀な人生を知るよりも、いっそう深く物の哀れが知られるでしょう。作者は物の哀れを知らすために書いているのですから、主人公が栄華をきわめた容姿端麗の男であっても、なんら不思議ではありません。
補説2.仏教・再論
Q2.登場人物たちは皆、この世を厭う心が強く、ともすれば出家の志があることを口にしています。これはやはり、仏の道に読者を引き入れようとする、作者の意図があってのことではないですか?
A2.違います。この物語は当時の風俗習慣や世間一般の通念を、余さずありのままに書いたものです。当時、世の中を憂う人が仏門に入るのは普通のことでした。登場人物がしばしば出家しているのは、当時の人々がしばしば出家したことの反映にすぎません。仏の道に引き入れるため、と見るのは深読みのしすぎです。
補説3.人の情の本当の姿
Q3.光源氏をはじめとして、善き人とされる登場人物は誰も彼も、みな女子供のような心をしていて、何事につけても優柔不断で未練がましく、男らしくキッパリとしたところがなく、ひたすら儚くだらしなく、愚かなところが多いように思います。どうしてこんな人たちが善き人とされるのかが分かりません。
A3.人の情の本当の姿は、未練がましくて愚かなものです。男らしくキッパリとしていて賢いのは、うわべを繕って己を飾り立てているだけのことです。心の底を探ってみれば、どんなに賢い人も女子供と変わるところはありません。それを包むか包まないかの違いがあるだけです。善き人は物の哀れを知っているために、ますます情が深く、忍びがたいことが多いのですから、心がなよなよとして愚かに見えることが多いのも当然です。たとえば戦争を考えてみたら良い。主君のため、国家のために、命を捨てる勇気を称えるのが、中国文学の流儀です。しかし、いざ戦地に赴こうとする兵士の情の本当の姿は、決してそんなものではない。ふるさとの父母も恋しかろう、妻子にも今いちど逢いたかろう、そう考えると己の命も少しは惜しくなりもしよう。なるほど、こういう心は正しくはないかもしれません。しかし、情の中の善き部分を育て、悪い部分を押さえることで、人を正しい方向に導くのは、儒学や仏教などがする仕事です。文学の仕事じゃない。文学は情の本当の姿を知らせて、そこから読者に何かを感じ取らせるものです。それを私は「物の哀れを知らす」と言うのです。
補説4.物語中の迷信について
Q4.この物語では、神仏のご利益、星占い、人相見、夢判断など、数多くの迷信を信じているかのように言っています。愚かしく幼稚なことではないですか?また、人が病に臥せると加持祈祷ばかりして、あげくの果てに臨終の時まで僧法師ばかりを頼り、医療を施さず薬を与えないのも、愚かなことではないですか?
A4.それが当時の風俗習慣だった、というだけの話です。あなたは迷信を信じることを愚かなことだと言うが、そういうあなたも自覚せず迷信の中にいる。彼等のことを笑えた立場ではない。あなたはこの物語に医薬の記述がないことをもって、当時は病気の治療に薬を用いなかったのだと思い込んでいますが、それこそ歴史に無知な証拠で、愚かしいことです。平安時代にも医学があったことは多くの文献に明らかで、それを紫式部が記さなかったのは、医療行為を描写するよりも、神仏の加護を祈り修験者の念力にすがる人間の姿を表現した方が、より深く哀れが感じられるからに他なりません。
補説5.過去を想像する力
Q5.この物語に記されている恋は、ずいぶんと乱れたものに思えます。昔の男女関係は、これほどまでに乱れたものだったのでしょうか?また、この物語は世のあらゆることを書いたものだと、あなたは言いますが、ならば庶民の身の上も詳しく書くべきであるのに、上流階級のことばかり書いて、庶民の描写がそれほど多くないのは、どうしたわけなのですか?
A5.そのように現代の価値観で過去を断罪するのは不当です。中国には中国の、日本には日本の、古代には古代の、現代には現代の風俗習慣があるのですから、特定の風俗習慣を普遍的な尺度とすることは出来ません。文学を正しく観賞するには、作品が書かれた時代の風俗習慣をよく心得て、当時の人間の心になってみる必要があります。この物語が書かれた当時、男女が対面する時は御簾を隔て、さらに几帳を隔てたものでした。兄妹であっても、多くは几帳を隔てて会話し、顔をあらわに見せませんでした。女は声を聞かせるのさえ、親しくない人の前では慎みました。これらの風俗習慣は、今よりも厳格なところがあります。であるからには、当時の男女関係が乱れていたと一概には言えません。また、庶民のことも書くべきだったとあなたは言いますが、紫式部が書かなかった理由は単純に、彼女が宮廷に仕える女房の身で、庶民の生態をよく知らなかったからです。作者にとって身近なことを書くのは、創作上、自然なことでありますし、この物語の読者が宮廷の貴族たちであったことも関係しています。つまり、「誰が誰に向けて書いた作品か」という、執筆当時の具体的な状況に思いを馳せれば、庶民を描かなかったことは別に非難に値しないと分かるのです。むしろ問題は、過去を想像する力がなく、何でも現代の価値観で過去を測ろうとする、われわれ読者の側にこそあります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
さて、足早にはなりましたが、宣長の議論をQ&Aの形で振り返りました。それぞれ独立した事柄について論じているにも関わらず、宣長が伝えたかったことは基本的にひとつで、かんたんに言ってしまえば、「その時その人の心持ちになってみよ」ということに尽きます。
それは正しく文学を観賞するための絶対条件であるだけでなく、広く言えば、他者を理解する唯一の方法でもあります。このことを宣長は当の源氏物語から教わりました。宣長は紫文要領の執筆によって、源氏物語から受け取った教えを、主題解釈という形で源氏物語に戻したのです。
小林秀雄は「宣長は、「源氏」を研究したというより、「源氏」によって開眼したと言った方がいい」(小林秀雄「本居宣長」新潮文庫、2007年改版、140頁)と言います。たしかにそうです。宣長は紫文要領という本で、源氏物語を解釈したかったのではなく、「俺は源氏によって悟ったのだ」と告白したのです。有名な「もののあはれ」は、この悟りの感動を意味する標語に過ぎません。概念の内包する範囲を気にするだけでは不充分です。
宣長という、歴史上の特定の時点に実在した人間が、源氏物語の読解によって、自己理解と他者理解を深め、人生の味わいを強めて、己の経験に「もののあはれを知る」という名前を与えた。源氏物語の解釈論として「もののあはれ」をこねくりまわす前に、もっともっと注目されて良いのは、宣長がそういう読み方をしたという「事実そのもの」ではないでしょうか?
これは読書ですが、私たちの月並みな読書とはまるで違います。愛読と言ったって足りない。それを読むことによって人が開眼する本のことを、普通「聖典」と呼びます。紫文要領は、人が聖典と出会った時にどれだけ多大な精神上の影響を受けるか、聖典はどれだけ深く人を成熟させるかについての、克明な記録でもあるのです。
今夜はいつもより短めですが、このへんで。
それではまた。おやすみなさい。
【以下、蛇足】
今回は、紫文要領の結論部分の前に置かれた文章、いくつかの想定される疑問点に答えることで、源氏物語の正しい読み方を明らかにした、「補説部分」を扱いました。
源氏物語を愛読する人は、今も昔も珍しくありませんが、読むことによって思想家になった人は本居宣長ただ一人でしょう。思想家が読むことはよくあります。読むことで思想家になった人は、本当に珍しい。
さて、次回は結論部分に入ります。これまでの私たちの歩みを振り返ると、宣長の議論は文学論であり、道徳論であり、人生論であり、認識論でもあるような色調のものでした。意味を広く取れば、「哲学」と名付けてもかまわないような種類の議論でした。
結論では、こうした前提がいったん崩れ去ります。・・・冒頭の謎めいた言葉によって。
本書(紫文要領)で述べてきたことは「歌道論」であったと言っていい。
結論部分の読解は、この「謎解き」から始まります。
次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
