
【エッセイ】「お前がヒトラーだ」と言ったプーチンがヒトラーによく似ている話
私は以前、移動体通信の某巨大企業のコールセンターで故障受付の仕事をしていたことがある。仕事の内容はといえば、携帯電話のエンドユーザーが掛けてくる「携帯が壊れたみたいだ、繋がらない」という電話に対応し、適切なアドバイスをしたり、ショップの窓口を案内したり、クレームにもひたすら謝罪する、というものであった。基本的にユーザーが電話を切るまで、オペレーターから電話を切ることは許されなかった。するとどうなるか? あそこのコールセンターに電話をすればずっと話を聞いてくれるぞ、ということがとある界隈に知れ渡り、その手の人からの電話にも対応しなくてはならなくなったのである。どんな界隈かといえば「心を病んだ人たち」の界隈だ。もちろんまともなユーザーとのやり取りがほとんどであり、ありがとうおかげで助かった、と感謝されることもあったが、大抵一日に一人か二人、その手の人と当たり携帯電話とまったく関係のない話を延々と聞かされることになった。まったく病んでいるとしかいいようがない妄想であり、政府が頭の中を覗いているとか、そんな話をずっと……。24時間対応なので、深夜に何時間もそんな話を聞かされ続けたこともある。なので私はついにギブアップした。入って半年も経たずにその職を辞めた。同期で入った友人に「まったくやってられない。◯◯◯◯と電話で話したくなんかないよ」と言ったのを覚えている。私はその職場でとても大切なことを学んだ。それは「世の中には狂気が溢れている」ということである。
さて、2022年4月現在、世界は狂気に包まれている。言わずもがな、ロシアによるウクライナ侵攻という狂気だ。仕掛けたのはロシア側であり、一方的な侵略にほかならない。しかし当事者であるロシアのプーチン大統領は直後に行ったテレビ演説で「ウクライナ国内でロシア系住民が虐殺されている。それを救うために特別軍事作戦を行わざるをえなかった」とありもしない身勝手な理屈を述べて自らを正当化した。いや、プーチン大統領がテレビカメラを見据える目を見て私はハッとなった。「これは狂人の目だ」とすぐに思った。もしかしたら彼は自分の口から出た言葉を真実だと思い込んでいるのかもしれない。本当にウクライナ国内で、ロシア系の人々が虐殺されていると、本気で信じているのかもしれない、と。
プーチン大統領のその有無を言わせない独裁者ぶりから、彼とナチスドイツのヒトラーをなぞらえる声は当然ながら世界各国から噴出した。プーチンとヒトラーを合わせた「プトラー」という言葉もさかんに使われ出したようである。21世紀である現在も、世界各国がすべて国民の意思が尊重された民主的な国ではない。選挙など一度も行われていない全体主義的な独裁国家も存在する。独裁者が国のトップに君臨しているのはロシアだけの専売特許ではない。しかしプーチン大統領の経歴がテレビの情報番組でも紹介されるにつけ、ただ「残虐な独裁者である」という共通項があるというだけに留まらない、似たような匂いがプーチンとヒトラーの間に漂っているのではないか、そんな思いが強く私の心をとらえた。実は私も以前からヒトラーの伝記やナチス関係の本を何冊か読んでいたからである。
ヒトラーやナチスに興味があった、といっても私自身はネオナチでもないし、ユダヤ陰謀論を振りかざすようなオカルト論者でもない。(去年にはそれとはまったく逆の「ユダヤの陰謀などないという話」というコラムをこのnoteに書いているし)。ただヒトラーに興味があった、彼がどんな人間だったのか正確に知りたいと思った、そんな単純な考えがあっただけのことである。ヒトラーの名前はそれだけ特別である。20世紀のドイツに君臨した独裁者という範疇を超えて人々の記憶に刻まれている一方で、有名であるがゆえに誤解され、歪曲され、いいように弄ばれ、使い捨ての常套句のように安売りされている。例えば今年の1月、日本の政界でもひと悶着があった。元首相の管直人氏が野党の維新の会と以前の党首であった橋下徹氏について「弁舌の巧みさでは第1次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒトラーを思い起こす」とツイッターに投稿し、物議を醸した。これはほんの一例だ。自分と対立する相手に対して「あいつはヒトラーだ」といえば「とんでもない残虐な奴だ」と言うのと同義であり、当然言われた方は怒り出す。私がまだ若い頃から、テレビの討論番組でも政敵を攻撃する常套句として簡単にヒトラーの名前を取り沙汰すこのような状況はあったし、21世紀の現在もそれは同じである。そんなわけで私は「ならヒトラーという男は具体的には何をしたのだろうか?」という疑問を抱くようになった。ヒトラーはどれだけのことをした男なのか? 現代人はヒトラーのことをよく知らないまま軽々しいレッテル貼りの道具として彼の名前を利用しているだけなんじゃないか、と。
去年書いたコラム「ユダヤの陰謀などないという話」でも触れたが、私は高校生ぐらいの頃に手塚治虫の長編漫画『アドルフに告ぐ』を読んでヒトラーのことを詳しく知った。この漫画はあくまでもフィクションであり、ユダヤ人絶滅を命じたヒトラーその人にユダヤ人の血が流れているのではないか、という謎を軸にして三人のアドルフの名を持つ男たちの運命が交錯する、手塚漫画の中でも後期の代表作に上げてもいい傑作である。ちなみに実際にヒトラーの父は私生児として生まれており、ヒトラーの父方の祖父は誰なのか本当に分からないそうである。そんな歴史の隙間につけ込んで、ヒトラーの祖母はユダヤ人と間にヒトラーの父をもうけたのであり、ヒトラー本人には4分の1ユダヤ人の血が流れている、という噂は戦前から囁かれていたようだ。手塚治虫はどこかでそんな記事を読んだのだろう、そこから更に話を膨らませて本書を描いたとのことだ。『アドルフに告ぐ』では主人公の一人であるアドルフ・カウフマンが神戸生まれで、なおかつ日本人との混血ドイツ人にも関わらず、ドイツ本国に戻りやがてヒトラーの親衛隊の一人になる。そんな彼の目を通して描かれるヒトラーの姿はフィクションだとは分かっていつつも「ああ、本当にこんな人だったんだろうな」と思わせるリアリティがあった。どんな人かといえば、ニコニコ動画のニセ字幕シリーズでも知られる映画『ヒトラー 〜最期の12日間〜』に描かれていたヒトラーにも近い、そう、カリスマ性がありながらもどこか狂気をまとった近寄りがたい人物、そんな造形だ。それはそうである。ひとつの国を支配して世界大戦を引き起こし、さらには大勢のユダヤ人を民族ごと根絶やしにしようとした独裁者、そんな人物が明朗快活で誰からも愛されるような男ではない、そんな刷り込みが事前にあるからなのか、とにかくヒトラーは狂気と表裏一体である。大衆を熱狂させたカリスマであると同時に、ヨーロッパを絶望の淵にまで追いやった狂人、尋常ではない残虐な独裁者、それが21世紀にも通じるヒトラーの姿である。
もしあなたが「ではヒトラーの実像に迫る伝記などでお勧めがあったら教えてくれ」というのであれば、私もいくつか用意がある。『アドルフに告ぐ』はフィクション作品だが、おなじ漫画作品では水木しげるの『劇画ヒットラー』がある。これはまだ若き日の画家か建築家になることを目指していた怠惰な青年ヒトラーが、時代の波に翻弄され、独裁者の道を進んでいく過程を描いている伝記漫画である。水木漫画そのままタッチで、日本の妖怪のようなヒトラーがヨーロッパに厄災をもたらしていく様子は、漫画的な誇張が含まれているにしてもほぼ史実のとおりであり、ヒトラーの生涯をなぞる本の入門編としてお勧めしたい。
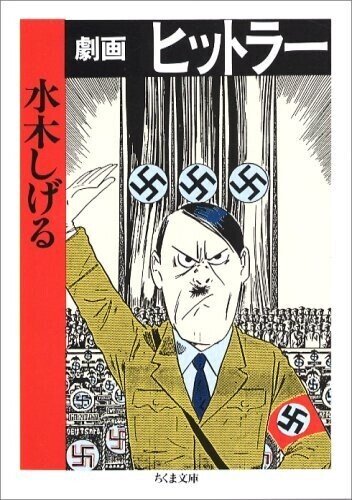
最近読んだ中でおすすめは、芝健介著『ヒトラー 虚像の独裁者』(岩波新書)が面白かった。若い頃のボヘミア生活から第一次世界大戦の一兵士を経て、ナチス党に入り、総統となり、ドイツの首相となって独裁者の地位を確立し、第二次世界大戦をおっぱじめてドイツとナチスとともに破滅する生涯が、時系列で紹介されている。この本でわかりやすかったのは、「どのようにして独裁者は生まれたのか?」ということだ。現在でもヒトラーの代名詞は独裁者であるが、彼は軍事力に物を言わせて無理やりその地位に上り詰めたわけではない。ナチス党の初期はカルト的右翼の泡沫政党であり、国民のほとんどからは鼻で笑われるような存在でしかなかったが、選挙によって国民の支持を集め、ついに政権を奪取する過程がわかりやすく描かれている。そしてなぜ国民が彼を支持したかも「三〇年代には、ドイツの危機も相俟って、政治に関心を持つ市民の間では偉大な政治指導者の出現を待望する声が強まっていた。」(同書95ページより)という一文に凝縮されているだろう。そう、ヒトラーは混乱の時代だからこそ出てきた男なのである。第一次大戦の敗戦により膨大な賠償金を命じられ、社会が混乱し、ナチスの台頭と同時に共産主義勢力も力を持っていてドイツも共産化する一歩手前まで行きかけた、そんな混迷の時代の申し子であるからこそ、ヒトラーは国民の支持を集めてカリスマを発揮できたのである。そしてこの本の特徴は、死後のヒトラーがドイツや世界でどのように消費されてきたか、という戦後史の一端も描いている。すでに触れた映画『ヒトラー 〜最期の12日間〜』であったり、2012年にドイツ国内でベストセラーになった『帰ってきたヒトラー』(現代に蘇ったヒトラーがコメディアンとして大人気になるという、ユーモア小説)などが紹介され、もうすでにヒトラーは同時代の恐ろしい独裁者というより歴史の彼方の亡霊なのだからおちょくりの対象にもなる、というドイツ内での現状が紹介される。そう、現代の日本で信長や秀吉や家康が女体化したり、現代に転生したり、高校生になって学校に通っている、そんなノリで描かれているものの同種だ。そしてこの『ヒトラー 虚像の独裁者』は長らく発禁状態にあったヒトラーの著書である『わが闘争』の再販を巡る騒動を描いて終わる。
ヒトラーやナチスを研究する本は書店や図書館の棚にたくさん並んでいる。『ヒトラー 虚像の独裁者』は良書だが、残念ながらすべての疑問に答えてくれるわけではない。ナチスが政権を取る歴史の流れや、第二次大戦のよって滅びていくさまは頭に入るとしても、もっと根本のところ「結局、ヒトラーという怪物は何なのだ?」という謎はますます深まるばかりである。なぜなら、ヒトラーはもともと貧しい階層の出身であり、政治家になるまでも何か傑出したことを成し遂げた人物ではない。貴族や有力政治家の家系の出でもないし、ビジネスやスポーツの分野で名を挙げたわけでもない。軍人としても第一次大戦では伝令兵として塹壕の間を駆け回っていただけであるし(一応、勇敢な働きをしたとのことで勲章は貰っているが)、行政の中でも有能な面を見せて地方の議員や首長になったわけでもない。彼は第一次大戦から帰還後の30歳の時に機械工のドレクスラーが党首を務めていたドイツ民族至上主義を掲げる総勢七人のドイツ労働者党(ナチス党の前身)に入り、そこで頭角を現して国民的な政治家へ突き進んでいくのである。まったく「なろう小説」顔負けのありえない展開だ。たとえば、同時代のリーダーであるイギリスのチャーチルと比較してみよう。チャーチルは貴族の家系の出であり、父親はイギリスの財務大臣まで務めた有力な一族である。学校の成績こそ振るわなかったが、パブリックスクールから士官学校を経て陸軍に入隊するという、典型的なイギリス貴族の出世コースをたどる。そう、まったく上流階級のエリートなのである。血筋がよく、能力があればいずれ国王の臣下として国の中枢で働くことは約束されたような男なのだ。もちろん、その途上で能力がないことが判明すれば切り捨てられるだろうが、彼は陸軍除隊後に26歳で選挙に出て、見事当選し国民の信託も得る。海軍大臣だった第一次対戦時にトルコとのガリポリ上陸作戦での惨敗で失脚し、政治の第一線からは遠ざかるが、第二次大戦が勃発すると再浮上、リーダーシップを発揮してイギリスと連合国を勝利へと導く。チャーチルは没後半世紀が経過した現代でもイギリス国内では人気のある政治家だが、毀誉褒貶はあるにしても、そこに至るのが当然のルートをたどって出世して政治の世界で活躍した。それがイギリスという国のシステムなんだから当然だ、と言われればそれまでだが、ヒトラーとは正反対の道筋をたどって山の頂上に達している。ではヒトラーをその山の頂上まで押し上げたものは何かといえば、それは演説である。ナチス党の政治集会に集まった人々に向けて彼は演説をぶち、それが評判となって集会に集まる人数はウナギ登りとなり、カリスマを発揮して独裁者の地位にまで登りつめる。いわば舌先三寸だけで成り上がったのだ。混乱の時代、ドイツ国民の間に偉大な人物が出てきてくれるのを待ち望む願望が高まっていた、そこにヒトラーがぴたりと嵌った、ともいえるが、なぜ30歳まで不遇をかこっていた上等兵上がりの男がそこまでのことが出来たのか、謎といえば謎であるし、怪物の正体はまだ見えてこない。
そんな中で、怪物の実像に迫る本を三冊ほど紹介したい。『ヒトラー 虚像の独裁者』が正統な研究書であるとすれば、いわば異端の本である。正直、オカルトと紙一重の怪しい内容なのだが、もしあなたがヒトラーに興味があるならぜひとも読んでほしい三冊である。
『ヒトラーとドラッグ 第三帝国における薬物依存』ノーマン・オーラー著(白水社)
ドイツといえば優れた工業の国、というイメージがあるが、一方で医学の国でもある。そして当然、薬学も発達していた。そんなドイツ軍やドイツ社会には第二次大戦前から薬物が氾濫し、そして今までほとんど語られることがなかったがヒトラーその人も薬物に汚染されていた、というのがこの本の内容である。本書が発売されたのは2015年と最近であり、なぜ今までヒトラーが重度のドラッグ依存症であったことが解らなかったのか、という謎が出てくる。ドイツ敗戦後、アメリカなどがナチス党の幹部を尋問し、取り調べているはずだが、どうして今まで判明していなかったのか、その謎も本書では紐解かれていく。著者は研究者というよりジャーナリストであり作家だが、当時の公文書を丹念に調べ上げることで、このような結論に達したとのことである。ヒトラーを薬物漬けにしたのはヒトラーの主治医を務めたモレル医師で、初めのうちこそビタミン注射程度だったものが次第にエスカレートし、ヘロインやコカインと同程度の作用を持つ薬剤を注射するに至った、というのである。そもそも当時、日本でもヒロポンが合法だったように、ドイツ国内の薬局では覚醒剤やコカインなどの薬物を医師の処方箋なしに合法的に買えた。モレル医師の診療記録は残っているのだが、その筆跡が悪筆だったので、オイコダール(ヘロインに似た薬物の商品名)をエンカドールと読み間違えたため、ヒトラーの診療記録を押収したアメリカの調査団では問題視されなかった、とのことだ。さらには1944年のヒトラー暗殺未遂事件の後からは、痛みを癒やすのにコカインも使われるようになり、ますます独裁者は薬漬けになっていく。ナチスの高官でさえも総統がどんな薬をキメているのか知ることはない。主治医と本人だけの秘密であった。もともとヒトラーは酒も飲まず、タバコも吸わないどころか肉も食べないベジタリアンの禁欲主義者というイメージを国内に広めていたが、実情はまったく違ったのである。『アドルフに告ぐ』でも『ヒトラー 〜最期の12日間〜』でも狂乱のヒトラー像は描かれていた。しかしそこに薬物の姿は描かれなかった。微塵も描写されていなかった。彼の狂気は理解しづらい孤独な独裁者であるがゆえのもの、そう解釈するしかなかったのだが、この本を読んだ後だとその背景には薬物があったのかと納得できる面もある。しかし、私は全面的には受け入れがたい。モレル医師がヒトラーの主治医になるのは1936年からだが、ヒトラーの狂気はそれよりももっと前から始まっていたからである。1933年に政権を奪取する以前から、ナチスが泡沫政党だった頃からヒトラーはユダヤ人排斥を唱え、ドイツ人が世界の頂点に立つべきだとかいう妄想を垂れ流していたのだ。彼の狂気はもっと根深いものであるはずだ。

『ヒトラーの秘密の生活』ロータル・マハタン著(文藝春秋社)
そういうわけで、そんなヒトラー個人の内面に迫ったのが本書である。早い話が「ヒトラーは同性愛者だった」と告発する内容である。私が最初にこの本を読んだ時、そういうこともあるかな、と考えた。しかしそれは最近のLGBTについての盛り上がりや心と身体の性が一致しないという流れではなく、戦国時代の武将が若い男の侍と衆道の関係にあった、というようなものの一種ではないか、そう思えたのである。しかし、本書によればヒトラーの同性愛的な嗜好はもっと根深いものであり、ヒトラーの人生には女性の影がほとんど見えてこないのである。「いや、エヴァ・ブラウンがいただろう」と指摘する声があるかもしれない。これまでの通常のヒトラー伝の中で彼の愛人であり、ベルリン陥落の間際に結婚し共に死を選んだ情婦であるエヴァ・ブラウンの存在は決して小さいものではない。しかし本書によれば「エヴァの少女時代のある知人は、「彼女は男の子みたいな子だった」と語っている。その知人によれば、少女時代の彼女には浮いた噂は一つもなかった。また、扮装することが大好きで、特に「男役」がお気に入りだっとという。」(本書412ページより)とのことだ。つまり、ヒトラーはあまり女性っぽくない彼女を自らの同性愛をカモフラージュするための道具としてそばに置いていたことになる。そして彼女自身もそんな自分の役割を理解していたとのことだ。ヒトラーの若い頃、まだウィーンにいて美術大学の入学を目指していた頃から彼には仲の良い男性がいたことがわかっている。一緒に部屋を借りて暮らしていたとのことだ。芸術家になることを目標としていたヒトラーと芸術談義をしたり、オペラを見に行った仲だという。果たしてそれは同性愛なのか、それとも貧乏なのでルームシェアをしていただけなのか、はっきりとは分からない。その彼と別れた後、ヒトラーは独身男性のための寮のようなところで暮らしていたが、そんな場所は同性愛者が相手を見つけるための施設だと当時から認識されていた。しかしだからといって全員が同性愛者とも限らないだろう。また、ヒトラーはオーストリアからドイツのミュンヘンに移り、ドイツ軍に入って第一次大戦に従軍する。そしてそこでの生活を楽しでいる。戦争に赴くのが楽しいのかと疑問に思えるが、彼は伝令兵として本部と前線の塹壕を往復するのが任務だったようで、決して最前線で敵と対峙していたわけではない。そんな男しかいない、男の友情だけがすべてのような軍隊の生活が気に入っていたし、昇進の話もすべて断っていたとのことだ。つまりこの本で書かれているのはすべて状況証拠なのである。当たり前かもしれないが、物理的な証拠やカミングアウトする当事者の証言などはない。当時のドイツで同性愛の男性がよくしていた行動様式に、若き日のヒトラーがあてはまる、それだけなのだ。いや、もっと直截的な証言記録も紹介されているが、その頃のヒトラーには政敵も多かったことも加味して考えなければならない。民主的な選挙で独裁者にまでなったとはいえ、敵がいなかったわけではないし、追い落とそうと付け狙う勢力も存在していたのだから誹謗中傷や不当な非難はあたりまえにあった、そのあたりを無視するわけにはいかないだろう。
正統的なヒトラー伝やナチスの記録でも唯一「同性愛者だった」とはっきり紹介されている男がいる。エルンスト・レームという男である。ナチス党の私設軍事組織である突撃隊の隊長を任されていた軍人であり、はじめてヒトラーと出会ったときナチスはまだ泡沫政党だった。彼は生粋の軍人であり、軍人としての男らしさを追求すればするほど、女性の存在は排除しなければならなくなった、そんな戦国武将のような思考の持ち主であった。そして彼はそんな自分を偽ることはなく、同性愛者であることを公然と周囲に見せつけていた。ナチスが政権を奪取した後、あまりにも巨大になりすぎた突撃隊とドイツ国防軍が対立するようになり、ついには粛清されてしまうのだが、若き頃のヒトラーとレームはかなり親密だったという。二人が同性愛の関係だったのか判別できないが、すでに軍人として名を成していたレームがヒトラーを政界の大物たちに引き合わせ、ヒトラーの成長に一役買っていたことは確かである。一方でレームはヒトラーの思想に共鳴したし、彼の突撃隊がナチスの対抗組織に暴力的に圧力をかけたりと、互いに利用し合う持ちつ持たれつの関係だった。
私が最初にこの本を読んだ時、状況証拠だけをみれば確かにヒトラーが同性愛者だったのに疑いを持てないな、とそう思った。しかし「ゲイと一言で言っても、人それぞれ色々とあるのよ」とはマツコ・デラックスがテレビで語っていた言葉(うろ覚えです。違ってるかも)であるが、例えヒトラーが女性にまったく興味がなかったとしても、奔放に男漁りをしているような同性愛者像を当てはめるのも早計だろう。例え人生のほとんどを独身で過ごし、軍隊的な男同士の強い絆しか信じることが出来なかったとしても、ただそれだけの男だった可能性もある。そうした一歩引いた視線で本書を眺めると、著者のカップリングは最近の腐女子のようでもある。さらにヒトラーの同性愛的な相手として名を挙げているのが、ルドルフ・ヘスなのだ。ヘスは初期のナチス党に入り、ビアホール一揆(いわゆるクーデター)にヒトラーと共に参加し、クーデター失敗後はヒトラーと同じ監獄に収監される。ヒトラーの著書である『わが闘争』はこの監獄に入っていた時に書かれたものであるが、実際にはヘスが口述筆記したものであるという。ナチスが政権を奪取した後には副総統の地位にまで登りつめるが、次第にヒトラーに疎んじられるようになる。第二次大戦が勃発すると、単身戦闘機を操縦してドイツを脱出し、イギリスに緊急着陸するという謎の行動をおこして世間をあっと言わせた。イギリスとの和平のための行動と解釈されているが、ナチスからは精神異常者と切り捨てられる。結局彼はイギリス国内に収監されたまま、戦後のニュルンベルク裁判では終身刑を言い渡され、1987年の死の時までイギリスの刑務所から出ることはなかった。私がまだ十代の頃「最後まで生き残っていたナチスの幹部がついに死んだ」とかなりセンセーショナルなニュースになっていたのを覚えている。そんなヘスも一時期、かなりヒトラーと親密な関係だった。師匠と弟子のような間柄だったそうである。果たしてそれは同性愛の繫がりなのか、本当に師匠と弟子なのか、当然ながらわからない。ヘスは女性と結婚しているが、同性愛の男性が世間体を考えて所帯を持つのはどこの国でもよくあることである。現代の腐女子の視線で見れば、確かにヒトラーとヘスはボーイズラブの範疇に収まってしまう。いや、実際に二人がそういう関係だったとしても、織田信長と森蘭丸が衆道の間柄であっても日本史になにか修正が入ることがないのと同じように、ナチスとヒトラーが世界に惨禍をもたらした二十世紀の歴史に新しい視点が加わるとも思えない。私が数年前に初めてこの本を読んだときは、かなりの部分で納得させられてしまったが、今回このエッセイを書くにあたって読み返してみたら、著者の腐女子的カップリングが鼻について仕方がなかった。ちなみに訳者のあとがきによれば、本書が出版された2001年、ドイツを始め世界的にセンセーショナルな受け止められ方をした一方で、批判もいくつか寄せられた。ひとつは「ヒトラーが同性愛者だったなんて戦前から囁かれていた。目新しくない」というものであり、また「ヒトラーの悪行が同性愛であることが原因のように受け止められかねない」という声もあったという。現代に生きるゲイの人からすれば「ゲイは異常者だからヒトラーもあんな虐殺が出来たのだ」と言われたようなものなので、怒り出す人も多かったという。そりゃあそうだろう。
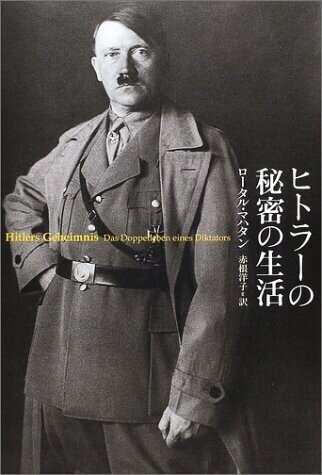
『野戦病院でヒトラーに何があったのか 闇の二十八日間、催眠治療とその結果』ベルンハルト・ホルストマン著(草思社)
さて、三冊目、これはかなり問題の本である。私が初めてこの本を図書館で借りて読み進めていた時「ええと、この本はたま出版から出ているのかな?」と奥付を眺めてしまったくらいである。どういう内容なのか、これから掻い摘んで要約してみるが、長いタイトルがすでに半分、説明しているだろう。こんな内容である。
第一次大戦に従軍した若きヒトラーは大戦末期、西部戦線でイギリスによる毒ガス攻撃を受けて一時的に失明する。彼は前線から退き、ベルギーからドイツを横断するような形でベルリンの東、ポーランド国境近くのパーゼヴァルク野戦病院に収容される。そこでヒトラーを診察した医師は失明は毒ガスによるものではなく、ヒステリーが原因だと見抜く。そして医師はヒトラーに催眠治療を施す。一種の暗示をかけたのである。それはどんなものか?「あなたは奇跡を起こす、ドイツを救う英雄になるでしょう」と暗示を医師からかけられたことでヒトラーは視力を取り戻した。本来であればそんな暗示をかけられた患者は、数日後には暗示を解かれるのだが、戦争の状況が悪化して、医師は暗示を解かないまま去ってしまった。そうして戦争も終わり、催眠治療による暗示をかけられたままのヒトラーが社会に復帰して、独裁者への道を歩み始めた。
ううん、えーと、たま出版かな、民明書房かな、それともなろう小説かな、通常で考えればありえない話である。そしてもちろんこの本はフィクションでもない。いや、ノンフィクションを装ったフィクションなのかなとも思えたが、日本語版を出している草思社は小説などよりも学術書などを多く出している真面目な出版社である。少なくとも体裁としてはノンフィクションで間違いはない。では著者はどんな人なのか? 巻末の著者略歴を引き写してみる。
ベルンハルト・ホルストマン 1919〜2008。ミュンヘンに中産階級の子弟として生まれる。第二次大戦では国防軍の将校として従軍、大戦末期に反ヒトラー運動に連座して逮捕、釈放ののち最後のベルリン攻防戦に参加、ソ連に抑留後、1946年9月に解放。戦後は法律家、ミステリー作家として活躍。80歳を過ぎてから本書の執筆にとりかかった。
そう、この人は戦後生まれの研究者やジャーナリストではない。ヒトラーとは歳が離れているにしても、同時代の人であり、ドイツが戦争に突き進んでいく時代の空気を吸っていたのである。これまでの正統的なヒトラー伝では、野戦病院で何があったかなどほとんど問題視されてこなかった。『ヒトラー 虚像の独裁者』でも「ヒトラーはイープル近郊で英軍の毒ガスを浴び、失明状態でシュテッティン近郊パーゼヴァルクの病院まで搬送された。幸運にも徐々に視力を回復していったが、一一月九日にドイツ革命、一一日には休戦のニュースに接し、数日間は激しく心乱れ、体調さえ崩したようだ。」とサラッと流しているだけである。しかし本書ではこの野戦病院で起きたことにスポットライトを当てている。ここで狂人ヒトラーが生まれた、いや作られたというのである。これまでこの野戦病院での出来事がクローズアップされなかったのは、記録がほとんど残っていなかったからだ。ヒトラーが1933年に政権を得てから過去の自分の都合の悪い公的な記録は残らずかき集め処分したらしいのだ。『わが闘争』では当然、脚色されたストーリーが語られているだけだ。では著者はどのようにして資料を探し出し、こんな結論を導き出したのだろうか?
著者は2000年の夏の終わり、アメリカの諜報機関が1943年頃に亡命ドイツ人の医者に聞き取り調査を行った報告書を手に入れる。そこで野戦病院でヒトラーを治療した医師を突き止める。名はエドムント・フォルスター。彼は優秀な精神科医であり第一次大戦では軍医として戦争により心の内面に傷を負った兵士たちの治療にあたっていた。ただ少し強引な性格だったようである。ナチスが政権を掌握した後、ナチスから何らかの脅迫を受けていたようで1933年に自ら命を断っていた。しかし彼はあらかじめヒトラーを診察したときの様子を手記に残し、ナチスに迫害されてパリに亡命していたユダヤ人のグループに手記を託していた。
その中にユダヤ人作家のエルンスト・ヴァイスという人がいた。彼はすでに何冊もの小説と戯曲を世に送り出していた元医師の職業作家であった。トーマス・マンやカフカとも知遇があったようである。彼はフォルスター医師から受け取った手記を元に『目撃者』というタイトルの小説を書き上げるのだが、出版社の反応は芳しいものではなく出版には至らなかった。その後、ナチスの復讐を恐れるあまり、ナチスがパリを陥落させた1940年に自殺してしまい、ただ原稿だけが残される。小説はなかなか出版社に受け入れられなかったが、若き出版人の苦労により戦後の1963年になってやっと世に出る。しかし反響はなく、商業的にも失敗する。そんなわけで、ヒトラーが野戦病院でどのような治療を受けたのかずっと対外的には知られぬままになっていた、というのである。
なんだか、この話自体が良く出来たミステリー小説のようでもある。ヒトラーが野戦病院で治療を受けている様子も、小説の一場面としてしか知ることが出来ない。それならこの話自体が作り物のでっち上げなのか? 正直、それはよくわからない。ただヒトラーが戦争末期にパーゼヴァルクの野戦病院に収容されていたこと、同時期にそこにフォルスター医師が勤務していたことは他の資料からも確認できる事実である。そしてフォルスター医師がマッドサイエンティスト気質な、強引な治療も辞さない過激な医師だったことも他の医師が残した評判からも間違いないようだ。そして彼はヒトラーに「ヒステリーの 精神病質者」と診断を下していた。十数年後、独裁者にまでのし上がったヒトラーがフォルスター医師を迫害したものそれが原因のようなのだ。
医師による治療は通常は密室で行われ、患者のプライバシーから言っても診療記録などは軽々しく誰もが見れるものでもない。なので著者はこのように推測する。ヒトラーが毒ガス攻撃を受けたのは事実としてもその影響は軽微で、深刻なものではなかった。しかしドイツが敗戦したとの報を聞き絶望のあまりヒステリーによる失明状態となったのでは、と。私のような素人考えだと、ヒステリーで失明? そんなことあるのか? と疑ってしまうが「ヒステリー 失明」でググってみたところ、強い心的外傷から視力を失うこともあるとのことだ。当然そのあたりは『わが闘争』ではぼやかされ、毒ガスによる失明は徐々に回復したかのように書いてある。これから国民的な政治家になる男がヒステリーを起こして失明するわけなどいかなくなったのだ。さらには第一次大戦のドイツの敗戦と革命により下級兵士が上官に反乱を起こす気配が充満し、上官であったフォルスター医師は身の危険を感じていた。 精神病質者にかけた暗示を解くような余裕はすでに失われ、急いで野戦病院を後にしてベルリンに旅立った。そのため催眠状態に置かれたままのヒトラーが一人残されたのである。それまで芸術家気取りで、周囲に溶け込まない根暗な男だったヒトラーが戦後、気迫に満ちた演説家として人々の前に現れる。ほとんどの人が映像の中で見たことのあるあのヒトラーである。熱に侵され陶酔するような演説を人々の前で行い、カリスマの権化と化して多くのドイツ人を熱狂の渦へと引きずり込む怪物が誕生したのである。精神科医が「ドイツを救え」と暗示をかけた、ただそれだけのことで……

結局のところ、どれを信じればいいのだろう。ヒトラーは薬物中毒だった? 同性愛者だった? 催眠状態から醒めないままの男だった? どれも本当のようであるし、よく出来た作り話のようでもある。しかしヒトラーがサイコパスだとの解釈はかなり納得できるものである。ナチスがドイツを支配してから戦争に突き進み、ヒトラーが死ぬまで戦いを止めなかった、止めることが出来なかったのは絶大な権力を持つヒトラーが軍事のすべてを指揮しようとし、将軍たちがまともな戦略が立てられなかったからである。国民の支持が絶大であるために、誰も反対できなかったのだ。一方で21世紀にもサイコパスな政治家がいきなりに出現した。第45代アメリカ大統領のドナルド・トランプである。病的にまで政敵を攻撃し、嘘を平気でつき傲慢、他人への共感を示さない点などから少なくともサイコパス的ではある。そして退任間近には自分への支持に集まった群衆をけしかけ、連邦議会に乱入させて警官五人が死亡するという前代未聞の事件を起こした。とはいえ、トランプはインターネットとSNSという21世紀のツールを使いながらフーリガンの暴動程度のことを起こしただけだ。しかしヒトラーは違う。人を集めての演説会や新聞雑誌、映画などの20世紀のメディアしか使っていないのに、ドイツ一国を熱狂させてユダヤ人迫害や、世界大戦を引き起こしているのだ。トランプなど比べ物にならない、20世紀の傑物であると言ってもいいだろう。そしてプーチンである。彼も2022年現在、ひとつの国を支配し、熱狂させている。彼はヒトラーに肩を並べるほどの怪物なのだろうか?
ウラジミール・プーチン現ロシア大統領は1952年にサンクトペテルブルグ(当時はレニングラード)で生まれている。『プーチン、自らを語る』(扶桑社)という本によれば、父方の祖父はレーニンとスターリンの別荘で長くコックとして働いていたそうである。父親は第二次大戦でドイツとの戦いで死にかけたが、なんとか生還を果たす。「父は沼に飛びこみ頭まで沈んで、追手の犬が通り過ぎるまで先端を水面に出したアシで呼吸していた。父はそうやって生きのびた。部隊の二十八人のうち、帰還したのは四人だけだった。」(上記の本より)とのことだ。プーチン本人の経歴として有名なのは、KGBのスパイだった、という点だろう。しかし彼が優秀な、花形のスパイだったかというと疑問符がつく。彼が諜報員として派遣されたのは東ドイツのドレスデンという地方都市なのだ。当時はまだベルリンの壁が健在なのでスパイが活躍するのならベルリンになるだろう。いや一流のスパイならアメリカやイギリスに派遣されているはずだが、そういうわけでもない。当時のプーチンは新聞のスクラップ程度のことをしていただけだ、なんて声もあるが具体的な仕事はよくわからない。ただ、ドレスデンにいた当時、ベルリンの壁崩壊に伴う騒乱を経験している。彼が務めるKGBのオフィスは東ドイツ保安省のすぐ隣りにあったのでデモの群衆がビルを取り囲み、身の危険を感じるほどの思いをしたという。その後、東ドイツどころかソビエト連邦そのものが崩壊することになるのだが、ロシアに戻ったプーチンはKGBを退職してサンクトペテルブルグでの役人生活を始める。大学時代の恩師が選挙で選ばれて市長になったので、その補佐をすることになったのだ。その恩師が落選すると、一時は無職になるが今度はモスクワの連邦政府から声がかかって政府の職員として働くことになる。あとはトントン拍子で出世していく。スパイとしては二流だったかもしれないが、官僚としては一流だったのだろう、あるいはとてつもなく強い引きがあったというべきなのか、彼は大統領府のスタッフに入ってわずか三年で当時のエリツィン大統領に首相に任命される。さらにはエリツィンが健康上の理由により大統領を去ると、プーチンは大統領代行になり、その後正式に選挙で選ばれて大統領になるのである。
もう引退してすっかり姿を消してしまったタレントの上岡龍太郎が昔テレビで言っていたのだが、ある日、占い師が彼を占い、上司に認められて出世しますよ、と言われたそうなのである。上岡龍太郎はふざけるな、と一喝する。「上司に認められずに出世するやつなどいるか!」と。まったくその通りで、出世した人とは上司に認められた人であり、出世しなかった人とは上司に認められなかった人である。どんなに実力のある人でも上司に嫉妬されて潰されることもあるわけで、上司に認められ、可愛がられ、引き上げられなければ出世などありえないのである。と考えると、プーチンのこの猛スピードでの出世は異常に思えてくる。もちろん彼が優秀な働きをしたからかもしれないが、一方で強力に引き上げた存在もいたはずである。エリツィンかと思いきや、後年彼はプーチンを後継者に指名したことを後悔するようなことを述べているので、違うかもしれない。他に考えられるのは、KGBの大物の誰か、あるいはKGBの組織全体がプーチンを支持して押し上げたのではないか、ということだ。スパイ組織であるKGBが自分たちの誰かをリーダーに仕立て上げ、国のトップに据えなければロシアはなくなってしまう、そんな切羽詰まったところまで追い詰められていたのだ。それはソ連崩壊後、大統領になったエリツィンの体制がまったく機能せず、 新興財閥たちによって国が乗っ取られてしまい、ロシアがズタボロにされてしまっていたからに他ならない。テレビのワイドショーではプーチンが、 新興財閥の面々を迫害したかのような言い方をしているが、いやいや、オリガルヒたちがソ連崩壊の混乱に乗じて国営企業を乗っ取り、税金を収めず、財力に物を言わせて好き勝手にロシアを食い物にしていたやり方もまったくえげつない。大統領になった直後のプーチンがしたことといえばオリガルヒたちの追い落としであり、それはうまく行く。彼の政党である統一ロシアが国会の過半数を占めたことで安定した政権運営が出来たこともあるし、KGBが裏で暗躍したこともあるのだろう。さらには原油高騰の追い風もあり、ロシアは息を吹き返す。そしてプーチンは国民の英雄になっていくのである。
この流れ、どこかで見たものに似ていないだろうか? そう、ヒトラーが政権を握り彼とナチスが台頭していく1930年代のドイツの状況とよく似ているのだ。もともとドイツは第一次大戦の敗戦により、国が混乱する。つまり元凶は第一次大戦にあるのだが、実のところ、私もこの最初の世界大戦のことはよく分かっていない。日本があまり関わっていないこともあるし、遠く離れた欧州で事態が進んでいたから馴染みがないのだ。youtubeの動画を見て、流れがやっと頭に入ったくらいである。
第二次大戦の戦端を開いたのは1939年のナチスドイツによるポーランド侵攻であるが、第一次大戦においてドイツは巻き込まれた、と言ったほうがいいくらいである。大戦の末期にはドイツで革命が起きる。末端の兵士が上官に対し反乱を起こしたのだが、主に共産主義勢力が蜂起している。そのせいでドイツが力を失い、戦争に負けたとヒトラーは恨みを募らせる。ヒトラーといえばユダヤ人虐殺で有名だが、それと同じくらいに憎んだのが共産主義だ。ドイツ国内にもソ連の影響を受けた共産主義は広まっていたので、政権を奪ったあとのヒトラーは祖国の裏切り者であるとして彼らも厳しく弾圧する。さらにはその大本であるソビエトがどうしても許せなかったために、バルバロッサ作戦を発動させてソビエトとの泥沼の戦いに突き進むことになる。それはともかく、第一次大戦の敗戦によって疲弊したドイツの状況はソビエトの崩壊によるロシアの混乱になぞらえていいだろう。1918年のドイツ敗戦からヒトラーが政権を奪取するのが1933年、1991年のソビエトの崩壊からプーチンがロシアの大統領に就任するのが2000年である。その間の両国は動乱期と言っていいくらいの安定が失われた混迷の時代であった。そしてヒトラーもプーチンも混乱の祖国を一時的には立て直すことに成功し、国民から絶大な支持を得るのである。
ヒトラーが憎んだユダヤ人と共産主義には共通点がある。それはどちらも国境を超えた存在である、ということだ。ユダヤ人は国民というよりユダヤ教によりまとまった民族なので、どこの国にも住んでいた。そして共産主義も究極の目的として世界同時革命を掲げているので、その思想を広げようと画策していた。地主に虐げられている小作農民や、資本家に搾取されている労働者など世界中どこにでもいるので、共産主義が広まる素地も世界各国にあったのである。しかしヒトラーのような民族主義者からすればどちらも倒さなければならない敵になる。実際、武装していなかったユダヤ人は狩りつくされ収容所に送られてしまったが、軍隊を組織していた共産主義ソビエトとは泥沼の世界大戦で凄惨な殺し合いになり、双方が数百万単位の命を落とすことになる。そして2022年、プーチンが向き合っているのも同じく国境を越えた存在であるEUでありNATOであり、そして「西側」ということになるだろう。プーチンについて書かれた本の多くには、彼は祖国ソビエトを崩壊させた西側を憎んでいる、とあった。ソビエト崩壊に際して西側は一発の銃弾も撃っていないので逆恨みもいいところだが、長い冷戦の末に崩壊したわけであるから、アメリカを始めとした西側が無関係だというのも無理がある。ヒトラーは第一次大戦の敗戦による屈辱をそそごうと奮闘し、国民もそんな彼を支持する。戦勝国から押し付けられたベルサイユ条約を無視し、再軍備を果たし、さらにはポーランドに攻め入って第二次大戦の火蓋を切る。ポーランド侵攻は第一次大戦によって割譲された東側の領土を取り戻すための行動であると解釈されている。ソビエトの崩壊を認めたくないプーチンも現在、同じようにウクライナに侵攻した。もともとウクライナはソビエト連邦の一地方に過ぎなかった。第二次大戦でナチスは穀倉地帯であるウクライナに侵攻するが、ソビエトは多大な犠牲を払ってナチスからウクライナを取り戻す。そんなウクライナに現在、ロシアの息のかからない政権が生まれている。ソビエト崩壊の混乱に乗じて西側がそそのかし、ウクライナを独立をさせたというのがプーチンの解釈なのだから、ロシアに背を向けるゼレンスキーのことは「ネオナチだ」と言うしかないだろう。つまりヒトラーとプーチンの一番の共通点とは、奪われたものを取り返そうとしている、とそれのただ一点に尽きる。しかし一番、異なっているのはヒトラーは核兵器を持っていなかったが、プーチンは持っている、ということになる。あまりに大きな違いだ。
我々は第二次世界大戦がどんな結末を迎えたのか知っている。ドイツは二回の世界大戦を経てやっとまともな民主主義国となり、安定した発展をすることになった。つまり今、我々が目にしているのはソビエト連邦が完全に崩壊を迎える最終段階なのかもしれない。例えプーチンの軍事作戦が成功し、ドンバス地方を占領しても、いやウクライナ全土を手中に収めたとしても、世界的な経済制裁は収まるはずがないのだから、ロシアが衰退し、崩壊へ向かっていくのは間違いない。崩壊はしなくても、よく言われているのように大きな北朝鮮になっていく未来しか見えてこない。プーチンはおそらく薬物中毒でもないし、同性愛者でもないし、催眠がかけられたままでもないだろう。しかし間違いなくサイコパスである。ウクライナを取り返さなければならない、という妄想に凝り固まったプーチンはロシア兵が何人死のうとウクライナから手を引くつもりはないようである。この軍事侵攻の結末には何が待っているのか? おそらくそれは誰にもわからない。なので最後に、途中で紹介した『プーチン、自らを語る』の中から私がとても印象に残った一節を紹介したい。そもそもこの本は2000年に大統領になったばかりのプーチンにジャーナリストがインタビューした内容であるため、まだ初々しい素のプーチンの姿が垣間見えるのである。この本の最後の質問、今までに愚かな行為をしたことがあるか? という問いに答えるプーチンの回答が面白いので、その部分をまるまる写してみる。
プーチン そうだな、あるとき、私はトルード・アスレチック・クラブの上級コーチを助手席に乗せて、レニングラード郊外の合宿所まで車を走らせていた。当時、私は大学生だった。干し草を積んだトラックが反対方向から走ってきた。車の窓を開けていたので、干し草のいい匂いが流れこんできた。そこで、カーブでトラックとすれちがうときに、私は干し草をつかみ取ろうとして窓から手を伸ばしたのだ。そのために私の車は道を飛び出した。しまった、と思ったね。ハンドルをきると、車はトラックの後輪に向かっていた。あわててハンドルを反対方向にきると、今度は片側のタイヤが浮きあがり、私のおんぼろザポロージェツは二本のタイヤで走った。もう少しで制御不能になるところだった。溝に落ちてもおかしくなかったが、幸運なことに、浮いていたタイヤはまた道路に戻ってくれた。
コーチは何も言わずにしばらく固まっていた。合宿所について、車から降りたとき、彼は私をにらみつけた。「危ないことしやがって」そう言い捨てて、歩いていった。このような愚かな話ならばほかにもある。どうしてそのトラックに引きよせられたかって。それは干し草のいい匂いのせいだろうな。
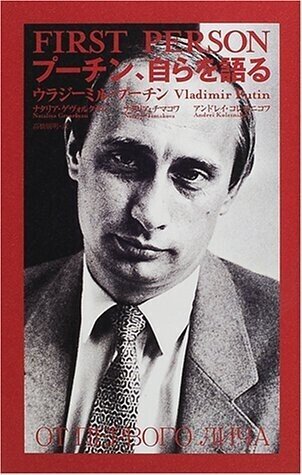
このエピソードから何を読み取ればいいだろう。人は時に馬鹿なことをしてしまう、ということだろうか。どんなに慎重で思慮深い人でも、魔が差したとしかいいようがない、ほんのいっときの気の迷いによって、身の破滅にしかならない事態を招いてしまうことがある。若くて向こう見ずな性分だろうと、経験を積んだ熟練の老人であろうと、不完全な生き物である人間は、どういうわけだかそのような理解不能な行動に走ってしまうのである。このエピソードは今から半世紀前のプーチンの思い出話だが、現在の彼は柔道に打ち込んでいた若い大学生ではない。ロシアの独裁者であり、ウクライナ侵攻のすべては彼の胸先三寸にある。彼の手がほんの気の迷いによって、核ミサイルの発射ボタンに伸びることはないのか、それは誰にもわからない。考えても仕方がないし、悩んでも無駄である。ただロシアが崩壊に向かって突っ走っているのは間違いない。敗北を認めようとしなかったヒトラーのようにプーチンもロシア国民を破滅の淵にまで道連れにするのか、しないのか、それも今現時点では、まったくわからないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
