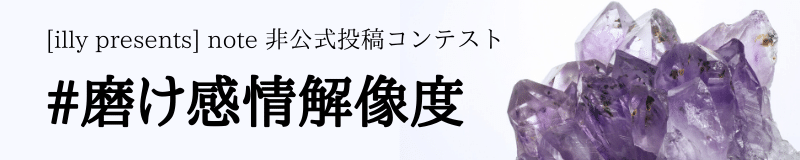摘花の恋【てきかのこい/掌編小説】
手持ちの服をすべて試してやっと選んだすみれ色のワンピースも、二日分のバイト代をつぎ込んで買った桜色の下着もぜんぶ剥ぎ取ってから、佐伯さんは私に「可愛い」と囁く。
佐伯さんの手で投げ捨てられた私の服が、ホテルの床に散らばる。力なく人型を保つそれは、さっきまで嬉々として身支度をしていた自分の亡骸みたいだ。
私は今週もこの男に会えたことが、嬉しくて虚しい。
肌色一色になった私の体に、佐伯さんの薄い唇がおりてくる。長くしなかやかな手足が、私の体を弄ぶ。
「窓のない部屋なんて、息苦しくて好きじゃない」
ラブではなくビジネスと名のつくホテルを使う理由を、佐伯さんは尤もらしくそう言う。関係がはじまって半年も経てば、嫌でもわかる。
「ビジネスホテルなら。万が一、同棲する彼女にバレても誤魔化しがきく」そんなみみっちい理由で、私はここに呼び出されている。
まどろみと快楽をだらしなく繰り返しているうちに、やがてカーテンから朝陽が漏れてくる。私たちは「眠いね」と言い合って、朝食を食べに行くため部屋を出る。
エレベーターが一階についた瞬間に、佐伯さんは絡ませていた指を優しくほどくから、私はぽつんと胸に広がっていく寂しさを、閑散としたホテルの風景のせいにしてみる。
寝癖をつけたままトーストを齧る佐伯さんは可愛くて、彼をひとりじめする幸せに笑みが溢れると、佐伯さんも「ユイちゃんと一緒にいると楽しい」と、微笑んでくれる。
ホテルの部屋からぞろぞろと出てくる暗い色のスーツを着込んだ大人たちに囲まれて、私たちは秘密を共有する子供のように、小声でくすくすと笑いあう。
部屋に持ち帰ったコーヒーを佐伯さんが飲み終えたら、それが私たちの情事が終わる合図だ。「じゃあ」とだけ言って、そそくさと立ち去る佐伯さんの背中を、バタンと閉まる重いドアを、一人残される冷えきった部屋から眺める。
来週も、ここに呼んでもらえるだろうか。私から彼を呼び出したことは一度もない。「会いたい」と、言葉にしたら余計な感情まで堰を切って溢れ出てしまいそうで。
ベッドに倒れこんで寝乱れたシーツにくるまると、ふたりの汗がまじりあった匂いがした。
ホテルを出ると、朝陽が私の目を灼いた。さっきまで感じていた佐伯さんの肌の感触を思い出そうとするけれど、それは陽炎のようにとらえどころなく、私の肌をゆらゆらと漂う。
これを確かなものにしたいから、私は佐伯さんに呼び出されるたびに尻尾を振って、このホテルに来てしまうんだろう。
私は大学の一限に間に合うように、走って地下鉄の駅へ向かった。
❇︎
『おっさんと、まだ会ってる?』
隣に座る健太がノートの端にそう書いて、コツコツとシャープペンで机を叩き、私に合図した。単位のためだけにとった現代農学概論の授業。教授のくぐもった声が子守唄になりかけていたから、ちょうどよかった。
『昨日も会ってたよ』
『何回やった?』
『3』
『元気だな 笑』
『眠すぎる』
筆跡の違う、ふたりの文字が並んでいく。声を出さずにククッと笑ってから、健太は黒板に向き直った。肌が若いと、健太のつるりとした横顔を見て思う。コマーシャルでよく見る「ハリ・きめ」という言葉の意味を、佐伯さんと寝るようになってから理解した。佐伯さんは他の三十代よりも若く見えるけれど、その肌は、私とも、私と同年代の男の子とも違って乾いた感触をしている。
私も、前に向きなおりノートをとる。
「◉摘花…生育のよくない花を剪定する。美しい花を残し、余分な実がつくことを防ぐ」
そんな真面目なメモの横に、健太との会話が並んでいる。私の秘密が夜から漏れだしてきたようで、なんとなくその文字をペンケースで隠した。
「ユイは、おっさんのことが好きなの?」
席がほぼ埋まった騒がしい食堂で、目の前でカツ丼を頬張る健太が言った。
「好き、だと思うけど」
「思うけどって、なんで疑問形」
「向こうはちゃんと彼女がいるからね。愛人の分際で、好きだなんて言っちゃいけない気がして」
「ふうん。どんくらい会ってんの」
「週一。彼女さんが毎週出張で、水曜だけいないの」
佐伯さんとはじめて会ったのも、水曜日だった。バイト先のバーが、一週間で一番暇な日。佐伯さんはひとりでカウンターに座っていた。
今思えば、いくらでも引き返すタイミングはあった。
ドリンクを奢るから、ちょっと話し相手になってと笑いかけられたとき。
何時に仕事終わるのという質問。
じゃあ危ないからタクシーで送るよという提案。
一瞬だけ見えた「さなえ」という着信に、バスルームから漏れる優しい話し声。
逃げ道は、塞がれていなかった。
私は正しい選択肢からあえて目を逸らして、佐伯さんの手で仕掛けられた罠に、まっすぐに足を踏み入れたのだった。
「いいな。彼女と同棲して、週一で若い女とセックスか。俺もそんなおっさんになりたい」
アホみたいな顔で、健太が言った。
「健太には無理でしょ」
「なんでだよ」
「女に振り回されて、痛い目みる想像しかできないもん」
「まぁ、そうか。好きな女の子が悲しむのも、見たくないし」
健太は不服そうに言って、ぐいっと麦茶を飲み干した。
「よっし、三限行くぞ。寝るなよ」
二人分の皿を持って立ち上がる健太の背中に、ゆっくりとついて行った。
❇︎
佐伯さんの手が、つま先から徐々に上へと伸びてくる。私はもう一度「可愛い」を聞きたいと思うけれど、佐伯さんは黙って私のいい場所にふれる。
「好き」という言葉を口にできないセックスは虚しくて、どれだけ虚しくてもきちんと反応する体はとても便利だ。
毎週、すこしも変わらないシナリオ。陳腐なその喜劇を、いつまでも二人きりで再演していたかった。だからだろう。聞いたことのないセリフが佐伯さんの口から出てきて、私は想像していた以上の打撃をくらった。
「彼女の福岡出張、来週から無くなるみたい」
佐伯さんは私に背を向けていたから、どんな表情をしているのか分からなかった。
「現地担当者を採用したみたいでさ。彼女はこれから本社の仕事に専念できるらしい」
午前一時。いつもなら、まどろみながら二回目をする時間だ。佐伯さんはベッドの端に腰掛けて、煙草を吸っている。どうしてだろう。早くさわってほしい。
「で、ユイちゃんにはちゃんと言っておこうと思って」
言わなくていい。誠実さのふりをした言い訳なんて聞きたくもない。
「これを機に結婚しないかって向こうから言われてさ」
佐伯さん。ねぇ、こっちに来てよ。もう一回、最初からはじめよう?
「向こうも俺も、もう三十二だからさ。いい加減ちゃんとしなきゃとも思うんだよね。もう五年も一緒にいるし」
『さなえ』という名前を頼りに、SNSのアカウントを見つけたよ。あんな地味な女。どうせこんな場所に呼び出したことなんて、ないんでしょう。
「彼女がね。子供が欲しいから、はっきりして欲しいって。なんか甥っ子とか見てると、それもいいかなって」
彼女彼女彼女彼女のことばっかり。佐伯さんは。結婚なんて興味ないって、ユイちゃんと一緒にいると楽しいって、笑ってくれたよね。嘘でもいいから、信じていたかった。
「ユイちゃんといる時間は、本当に楽しかったんだ」
いつから過去形にしてしまったの。
「でも、もう会うのはやめた方がいいんじゃないかな」
疑問系で終わらせるなんて、ずるい。ちゃんとその手でトドメを刺して。
「どうかな」
佐伯さん、好きなの。
「好き」
出会ってから一度も口にしなかった言葉が、溢れた。
「佐伯さん、好き。好きだった、ずっと」
言葉にするたびに涙が出て、悲しいはずなのに、なぜか私は安堵していた。涙と一緒に、今まで溜めこんできた胸の痛みが溶けていく。私はずっとこうやって、佐伯さんにすがって泣きたかったのかもしれない。
「ユイちゃんのそれは、恋じゃない。今は感情に流されているだけで、すぐに忘れる日がくるよ。俺なんかより、よっぽど素敵な恋人ができるから」
佐伯さんが私を抱き寄せ、赤ん坊を寝かしつけるような手つきで私の髪を撫でる。
涙と佐伯さんの体温で、うまく呼吸ができない。
私ね。きっとちゃんと覚えてるよ。ふたりで過ごしたいくつかの夜を。あなたの背中を何度も見送ったことを。
私たちの間にあるものが恋じゃないなら。あなたが今日までしてきたすべての恋を、記憶から抹消してほしい。最後まで口にできなかった願いを、きっとずっと、覚えてるよ。
感触を、体温を覚えておくために。私はもう一度、佐伯さんをベッドに押し倒す。「好き」と言葉にできるセックスも、その感情が相手に届かないなら、それはそれで悲しいものだと知った。
❇︎
思い切り泣いた後のご飯は、いつだって美味しい。
朝食を食べながらそう呟くと、佐伯さんは「若いっていいな」と笑った。
この笑顔をもう見ることができないのかと思うと、また涙が溢れてくる。
若さなんて捨ててもいいから、あなたに選んでもらいたかった。
こんな場所で泣いたら、嫌われる。でも、もう会わないから嫌われてもいいのか。頭の中は堂々巡りで、涙だけが波のように寄せてはかえす。ぼやける視界の中心で、佐伯さんが気まずそうに微笑んでいるのが見えた。
秘密を共有する子供だった私たちは、現実の大人に戻ったら、話すことさえないみたいだ。
今日は一緒にホテルを出たい。部屋に戻りコーヒーを飲み干した佐伯さんに最後のわがままをぶつけると、佐伯さんは一瞬だけ逡巡してから、引き攣った笑みをこちらに向けた。
『頼むから、困らせないでくれ』
言葉にされなくても、答えは明白だった。守りたいものがある人間は、どこまでも残酷になれるらしい。
部屋のドアが閉まり、ウィンと小さな音を立ててオートロックが掛かる。
最後は抱きしめてもくれなかった。今頃はホテルの外で、うまく別れられたと胸を撫でおろしているんだろう。
一ミリでもいいから、惜しい関係だったと思ってくれるだろうか。
あんな男。あんな男のことが、大好きだった。
ブレーキをかけていた涙に「もういいよ」と伝えると、溢れてくる水分がシーツを濡らした。チェックアウトの時間がくるまで、私は一人、吐くように泣いた。
往来の人々が、嗚咽しながら歩く私をちらりと見ては目を逸らす。
私は今後、泣きながら路上を歩いたことのある大人以外は信じない。そんなことを考えながら、あてもなく歩く。
しばらくしてたどり着いた公園で、ベンチに座って息を整えた。ぽっかりと抜けるような青空に、夏が終わりかけていることを知る。
ベンチの目の前には、美しく整えられた花壇があった。
シルバー人材センターと書かれた蛍光色のジャンパーを着たお婆さんが、ちいさな花を首からもぎり取り、地面に落としていく。
灰色のコンクリートが、色とりどりの死んだ花で彩られていった。
摘花。生育のよくない花を剪定する。美しい花を残し、余分な実がつくことを防ぐ。
授業で目にした単語が、頭をよぎる。
他の美しい花のために、咲ききる前に摘みとられてしまうなんて。まるで私の恋みたいだ。
風で足元に飛ばされてきた白い花を拾いあげる。その花弁は、「まだ生きていたい」と訴えるかのように瑞々しかった。
携帯が振動する。佐伯さんから連絡がきたんじゃないかと胸が高鳴ったけれど、表示されていたのは二限に出ているはずの健太の名前だった。
「もしもし、ユイ? どした。寝坊したの」
「ううん。でも、今日はこのままさぼっちゃおうかな」
「めずらしいね。一晩に三回やっても授業にでる女が」
「ちょっとね。おっさんに振られちゃった」
乾いていた涙が、また喉からせり上がってくる。
「あらら。大丈夫かい。今、どこ」
「どっかの公園」
「なんて公園? 近くになにがある?」
「花壇とベンチ」
「いや、それじゃなんもわからん」
電話の向こうで、健太が笑った。私もつられて、泣きながら笑った。
こんな時間を重ねていれば、佐伯さんが言ったように、いつか胸の痛みも忘れてしまうんだろうか。
健太が自転車で公園にやってくる頃には、摘み取られた花たちは、ゴミ袋に詰められどこかへ行ってしまった。
健太はなぜかはしゃいでいて、うるさい。
気晴らしに二人でどこかへ行こう。バイト代が入ったから一泊でもいいし。海とか。山とか。そんな言葉に、そうだね、いいかもね、と適当に相槌を打つ。
花壇では、美しい花が人を誘うように揺れている。隣にいる男の子は優しくて、いま私がいる場所は、きっととても正しい。
それでも私は、握りしめて粉々に砕けてしまった花弁を、どうしても手放すことができなかった。
お読み頂き、ありがとうございました。 読んでくれる方がいるだけで、めっちゃ嬉しいです!