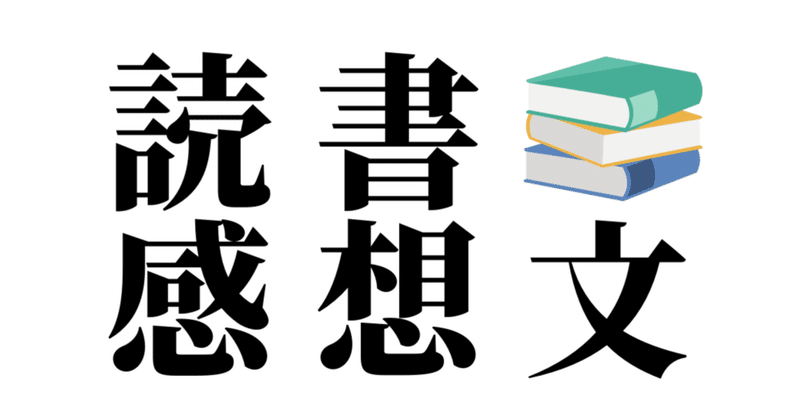
読書感想文『ストーリーでわかるファシリテーター入門』森時彦著
『ストーリーでわかるファシリテーター入門』森時彦とは
2018年発売。
サブタイトルは「輝く現場をつくろう!」
本書は、2004年と2007年に上梓した『ザ・ファシリテーター』シリーズの第3弾になるものです。お陰様で前作はいずれも好評を博し、発表から10年以上にわたって増刷を重ねてきました。この間に、ファシリテーターという言葉も広く浸透し、いまでは会議やワークショップなどで当たり前のように使われるようになってきました。
しかし、一方でファシリテーター=司会者という誤解も多いと感じます。それ以上に、ファシリテーションの本来の姿が、まだまだ広く認知されていないのは残念なことです。
こうした状況を踏まえ、ファシリテーションの力とその応用範囲の広さを、もっと多くの方々にわかりやすく伝えようと、入門編として改めて書き下ろしたのが本書です。
――『ストーリーでわかるファシリテーター入門』
勝手に会議のファシリテーターの話かなと思ったのだが、ワークショップのファシリテーターの話がメインだった。
そこに若干だが、会社経営の話も割り込んできて、物語としてはメリハリがあっておもしろかったかなと。
この本を読んだ理由
図書館で何気なく見つけて、そのまま借りてきた。
ココに刺さった
インプットの時間は短くとどめて考える空間を残す。長くインプットすると、もっと考えてくれとなって「正解」を教えてもらおうとする依存体質を助長する。
――『ストーリーでわかるファシリテーター入門』
説明が長いと、聞いてる人間は「考える」行為を止めてしまうということ。
それどころか、「正解」を教えてもらえるものと勘違いしてしまうようになるのだとか。
確かにその通りだなと思った。
だって学校の授業って、50分間先生が喋りっぱなしで、先生が言うことがすべて正解で、中には「ここテストにでますよ!」とまで教えてくれるケースもあるからね。
真面目に話を聞いていたら正解がやってくるって、僕らは教育されているのだからしょうがない。
黙って聞いていることが勝利の方程式。
でも会社の場合はそれじゃダメで、そもそも上司って「先生」でもない。
相手に「考える空間を残す」ってのは大事な考え方だなと思った。
ちょっと物足りないくらいが良いのかもしれない。
重要なのは、「もっと知りたい」と思わせるだけの説得力のある説明と、隙のないロジックだろう。
この本を読み終えて
付箋を使ってのブレストって、そこかしこで見たり聞いたりするけど、なんとなくこの話を読んで、やってみようかなと思った。
おそらく単なる「ブレスト」という切り口だと、まあやってみたらいいかもねくらいの温度感だが、この本だと、ファシリテーターとして、その場の仕切り方メインで描かれているので、「同じことやったら効果ありそう」「こうやって仕切ればいいのか」って思えた。
「何をやるか?」よりも「どのようにやるか?」を示すほうが、第三者のアクションに結びつきやすいのかなと感じた。
* 各自付箋にアイデアを書いて、席を立って、壁(ホワイトボード)に貼る
* タイプの違うアイデアは横に、同じようなアイデアは縦に並べることで、カテゴライズしてみる
* その後、縦軸に効果の大小、横軸に実現可能性の大小のマトリックスをつくってカテゴライズされたアイデアがどの位置に属するか貼り直す
▼他のユーザーさんのレビューも要チェック!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
