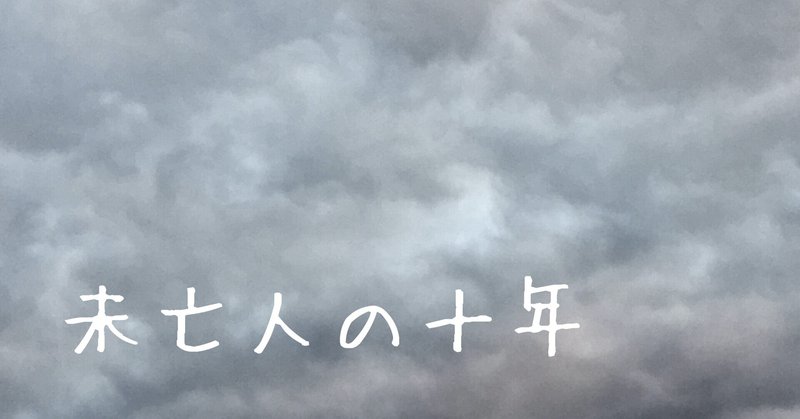
[未亡人の十年]_003 虫の知らせってあるのだろうか。
ごきげんよう、ある未亡人です。
記事を見ていただき、ありがとうございます☆
前回の投稿は自分にとって記念すべき出来事となりました。
といいますのも、夫を亡くしてからのわたしは、自分のことが書けなくなっていたからです。
仕事ではかろうじてフィクションを書きつづけてきました。
が、自分にかんすることとなると、ごく親しいひとたちとのやりとりに限られていました。
それさえも、かるく社交辞令できかれただけの質問を真に受けたり、過剰反応してみたり、出来事をひとにどう伝えるかの距離感がわからなくなってしまったり。
一進一退の低空飛行といった十年間でした。
結果として、大勢のひとを遠ざけました。
誰かに自分のことを語りたいという気持ちも無くなっていました。
もののみかたが冷笑的になり、自分を見捨て、生活は荒れ果てました。
家にひきこもるようになり、最終的に専門家からつけられた診断は
<複雑性悲嘆>というものでした。
そんなわたしが、こちらnoteにて、自分に起きたことを綴っていくとっかかりを得たのです。
ようやく、<その時がきた>ということでしょうか。
とにかく、うれしかったのです。
コメントやスキをくださったみなさん、
見てくださったみなさま、
ほんとうにありがとうございます☆
この先の勇気へと繋いでいただきました。
・・・すっかり前置きが長くなりましたが、ここから本題に入ります!
前回からのつづきです。
化けて出る約束をしたのに・・・
" 夫逝去 " の連絡をメールで受け取り、急ぎメールの送り主である夫の同期に連絡を入れた。
が、からだがふるえてしまって、ナンバーボタンがうまく押せない。
何度も押し違えては、かけ直すということを繰り返した。
わたしはこのとき、まるでピンときていなかった。
涙も出てこない。
夫が死んだということがまるで腑に落ちていない。
茫然自失。
アタマがフリーズ状態で、こころと繋がっていなかった。
いまおもうに、電話をかけ直したのは、ほんの数回だったような気がする。
からだでかんじる時間は、記憶のなかで、永遠と隣り合わせなのだろうか。
そんなみじかい時間のなかで、思いがこまぎれに押し寄せた。
最初に、「嘘つき」という言葉がうかんだ。
化けて出ようねって約束したのに。
わたしたちは約束していた。
先に死んだほうが化けて出る、ということを。
霊魂の存在があるってことを<生きてる側>に知らせようね、と。
その約束は毎年の正月ごとに確認し、更新していた。
それはそれは、しつこいな・・と思うくらいに確認し合っていた。
だから、死んだなんて、なにかの間違いじゃないのかな。
それとも、ちょうど地獄の入り口で釈由美子みたいなキャラにつかまっているところなのかな。
そもそも、まだ死んだって自分で気づいてないのかも・・・
夫の同期の話
電話がつながった。
「ひさしぶり」からはじまり、数年ぶりにきく夫の同期の声は、思いのほか明るかった。
「まさかきみに、こんな話をしなきゃならないなんてね・・」
彼は言った。
「部署でも、○○君が結婚していることすら知らない人がいて・・」
たしかに、彼はわたしたち夫婦が<別居婚>というスタイルをとっていることを知る、数すくない関係者ではあった。
まるで世間話でもするみたいに。
彼は前日に知ったという<夫の死>について話しはじめた。
部署が離れているから、○○君が亡くなったらしいということだけが第一報で入ってきて、詳しいことはまだわかってないんだよ。
いまわかってるのは、○○君が会議があるのに出社してこなかったってこと。仕切る人が来なくて、会議はお開きになったらしい。
で、モーニングコールをしていた女性がそれを知って
(・・・あ、念のために言っとくけど、そのひとはきみが気にするような女性じゃないからね・・・)
その彼女が、朝電話で話したばかりなのに会社に来ないのはおかしいと社内で騒ぎはじめたらしい。
で、人事部がマンションに駆けつけて、鍵を開けて入ってみたら、亡くなっていたと・・。
愛人だろうな、とおもった。
夫の性格から、ビジネス以外で女性にモーニングコールを頼めるとはおもえなかったからだ。
しかし、それよりも・・
「死因は?」
その単語を口にしたとたん、嗚咽がこみあげ、わたしは
わあっと声をあげて泣いていた。
相手はひどく冷静だった。
その冷静さにハッとして、秒で我に返った。
そうか・・・。
彼にとっては、すでにひと晩が経過している。
衝撃からのタイムラグがあるのだ。
冷静なひとをまえにして、わたしは自分の立っているところがわからなくなった。
「・・自殺・・じゃないよね・・・?」
おそるおそる尋ねた。
涙は引き、会話によってアタマがまわりはじめていたが、またからだがふるえてきた。
部屋のなかが冷え切っている。
真冬だということを失念し、エアコンをつけていなかった。
こんなときにも生体としてのからだのふるえはやってくるのだとおもった。
「違うと思うよ。詳しいことはまだきいてないけど」
彼は苦笑しながらこたえた。
なんでそんな質問しちゃったんだろう。
自分で繰り出した質問に驚いて、近くの椅子に手をつき、座り込んだのをおぼえている。
腰を落ち着け、目の前にある固定電話の本体を見た。
留守電のマークが点滅している。
夫からのメッセージがのこっているはずだった。
「だって・・・二日前に食事したし・・・」
夫はその日、めずらしく引かなかった。
どうしても、新刊の感想を直接伝えたいのだという。
いま電話で聞くよ、と言ったが、会って直接伝えたいのだと食い下がった。
それで、近くの小料理店でかるく食事をすることになった。
そういえば、そのとき・・
夫は生ビールをひとくち飲んだとたん、「痛い!」と声をあげ、背中を押さえた。
「なんだろう・・ほんとに痛いんだけど」
夫が言うので、わたしは何度も背中をさすった。
「ありがとう。なんか楽になった」
さすっているうちに背中の痛みが引いたのか、なにもなかったかのようにそれからいろいろな酒を飲み、話をした。
それらはすべて未来の話だった。
夫とは20年間の付き合いになる。
そのうち、結婚してから13年が経っていた。
結婚生活の半分の期間を、夫の病気に苦しみ、ともに闘った。
当時はパニック障害という診断がつけられなかった。
結果として、別居というスタイルをわたしたちは選択した。
その夜は出会った頃のような活力に満ちた対話をたくさんした。
新刊の文章をとても褒めてくれた。
欠点をなおすのではなく、むしろ逆に、推し進めていったらどうだろうかと夫は言うのだった。
これからは仕事量を抑えて、ゆっくり旅行にでも行きたいね、という話もした。
海外もいいけど、国内でも。
それには体調もととのえないとね。
公園のランニングコースでウォーキングからはじめようか、などなど。
なかなか話し足りなくて、カフェに場所をうつすことになった。
国立の大きな病院のまえを通ったとき、
救急搬送の入り口にWELCOMEという文字の電飾がみえた。
クリスマスの飾り付けだろうか。
「ほら、病院がいらっしゃいませしてるよ」
わたしは冗談めかして言った。
出典は相米慎二監督の映画である。
わざわざ牧瀬里穂の真似までして言ってみた。
「ほんとに病院、行かなくていいの?」
もう一度、真摯に、電飾を指して言い直したのを覚えている。
あの文字が気になる。
確かにそうおもった。
その直観にしたがって、無理にでも連れこんでいたら助かったのだろうか。
その晩、夫はなかなか帰りたがらなくて、コーヒーを何度もおかわりした。
「あーあ。帰りたくないなあ。帰ったら仕事しなきゃなんないしなあ」
何度も言い、いつものように上司の愚痴をこぼしていた。
お茶を飲み終わったらとっとと家に帰る。
そんなルールがなんとなくあったものだから、めずらしいなとおもった。
そうおもいつつ、わたしはのこしてきた自分の仕事のほうも気になっていた。
この日も徹夜になりそうだった。
あれは、虫の知らせ・・だったのだろうか。
病院の、救急搬送の入り口のネオン管。
あれはピンクだったか、ブルーだったかーーー。
「とにかく、一刻もはやく会社の上司に連絡したほうがいいよ」
夫の同期に言われて、電話を置いた。
そのとき、正午前だったのをおぼえている。
そこから、生き地獄がスタートしたのだった。
いただきましたサポートはグリーフケアの学びと研究に充当したく存じます。
