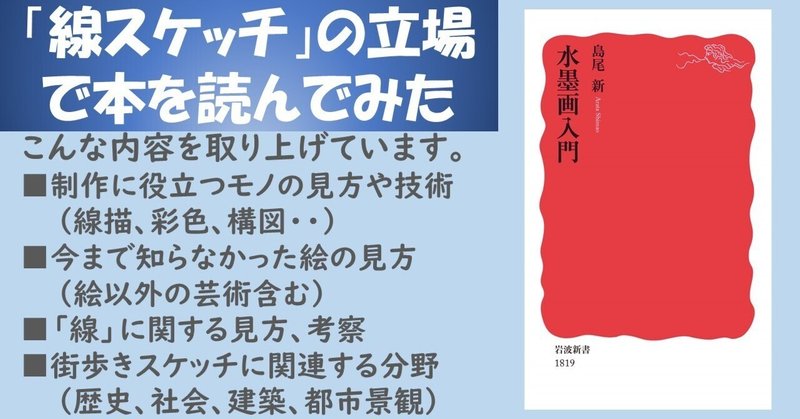
島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。その1
はじめに
現在私は「線スケッチ」による作品を描いています。
「線スケッチ」は「ペン画」のジャンルの一つで、フェルトの筆先のペンを用いるので、描き手の気持ちが、線の表情に現れるのが大きな特徴です。
ですから、あえていえば東洋の筆で描かれた「水墨画」の延長にあるとも言えます。
その「線スケッチ」の特徴をスケッチ教室で折に触れ生徒さんに語っているのですが、それでは私はどれほど「水墨画」のことを分かっているのか、実は大変心もとない状況です。
その心もとない状況を、以前投稿した下記の記事の中で述べました。
水墨画といえば、私がぼんやり思い出すのは高校の「日本の歴史」教科書の中で、まず中国、南宋の画家牧谿の水墨画が出て、そのあと鎌倉、室町時代の日本人の水墨画が並んでいた様子です。例えば如拙作の瓢鮎図が思い出されます。
あくまで私の当時の感想ですが、日本の水墨画のどこに魅力があるのかわからず、どれをみても中国絵画の模倣としか見えませんでした。
丁度それは欧米人が日本の美術全般が中国の模倣ではないかとみなすのとよく似ています。中々日本独自の部分が見えてこないのです。
おまけに、一見正統派に見える雪舟等楊も、実はアヴァンギャルドな画家であると、赤瀬川原平氏や、明治学院大学の山下裕二氏、山口晃氏はいろんな場所で強調しています(私は昔の教育を受けていて雪舟は正統水墨画の巨匠であると刷り込まれています。急にアヴァンギャルドと云われても当惑します)。
もしそうだとすると、水墨画のページ(注)は、アヴァンギャルドの作家で占められたことになります。
(注)美術教科書の中の日本の水墨画のページ
正直に言えば、今に至るまで、名品と云われる水墨画を前にして、「どこをどのように鑑賞したらよいのか」分からないのです。さらに、一番フラストレーションを感じるのは、多くの水墨画の専門家が「日本の水墨画は独自性がある」と云うのですが、一体どこに独自性があるのかまったく理解できないことにあります。
例えば、教科書に出てくる南宋の牧谿の絵と雪舟の絵がどのように違うのかです。「筆」、「墨」、「紙」の画材は共通ですし、描き方は一見同じようにしか見えません。

出典:共にwikimedia commons, public domain
とは云え、これまで手をこまねいたわけではありません。一般読者向けの入門書を読んだりしたのですが、続きませんでした。
その理由は、著者が大概の場合研究者や学者など専門家である場合が多く、中国における「水墨山水画」の理念や本質部分の正確かつ詳細な説明を優先していて、初心者でしかも日本人にはなじみがない「気」の概念の記述を読むだけで、絵を味わう前に疲れてしまうからです。
ところが、今回ご紹介する本書の著者、島尾新氏は、学者ではありますが、まるで私の不満を事前に知ったかのように水墨山水の理念ではなく、まず「筆墨の文化」の中の筆、墨、紙の画材、磨墨、紙の繊維での墨の動きなど具体的、実証的な話と線の描き方の技法から始めており、これまで読んだ本とはかなり毛色が異なります。
現実に絵を描いている人間にとっては、とても分かりやすい導入法なのです。
さらに特筆したいのは、水墨画の代表事例として出てくるのは、郭煕の「早春図」や范寛の「谿山行旅図」など山水画の例示に欠かせない名作は別として、例示作品の大半が日本の水墨画であり、中国の作品は日本の水墨画との違いを示すために出す程度であることです。

出典:共にwikimedia commons, public domain
このことも、水墨画の入門書としてはかなり変わっています。
著者は明確には云っていないのですが、日本の水墨画が中国の水墨画と何が違うのかを示すことも、この本の目的の一つだと見てよいでしょう。
以下、私の二つの疑問について、「線スケッチ」に絡めながら、回答に繋がる著者の考えを紹介します。
■水墨画はどこをどのように見て鑑賞したらよいのか?
■日本の水墨画は独自性はあるのか?
「線のよろこび」
著者は、第1章「水墨画とはなにか?」の中で、水墨画の定義からではなく、「筆墨の文化」における「墨」「木筆」「紙」の画材の使用感から話をはじめます。
そして筆には欧米の鉛筆やペンなどの筆記具には見られない「自由に線を引くよろこび」があるのだと言います。
このように「筆墨」が洗練されてゆくなかで極めて重要なのは、人々が「自由に線を引くよろこび」に気づいてゆくことだ。線の幅を変えて抑揚をつけ、穂先を返しながら自在に腕を動かしてゆく。筆をすべらせるのは心地よく、そのあとに残る線は美しい。
これにはまったく同感です。「線スケッチ」では毛筆ではなくフェルトの筆先を持つサインペンですが、線を引く時に筆先が紙の抵抗を受け、指先から腕を通して絶えずその抵抗感を脳で感じます。そして不思議なことにそれが確かによろこび(快感)に転ずるのです。
私が「線スケッチ」を続けてこれたのも、線を引く時の「よろこび」のおかげです。
実はこれに関連して、現代書家の石川九楊氏はその著書「書とはどういう芸術か 筆蝕の美学」(中公新書 1994)の中で、通常使う「筆触」ではなく、「筆蝕」を提案しています。
私はなぜペンで線を引いて絵を描くことが心地よいのか、この本を読んでまさに腑に落ちたのです。この辺の事情を以前下記のブログで書きました。
島尾氏が云う「線のよろこび」と重なる部分を以下に引用します。
中でも、第一章「書とは筆蝕の芸術である」の「筆蝕とは何か」の節において、以下に示すフレーズの中に著者の主張が簡潔に述べられています。
「「肉筆」の「書きぶり」の中に書の美を云々する何かが書き込まれている」
「「書きぶり」とは作者の書字する姿ではない。また、定着された書字の姿=造形でもない。それは作者が手にした筆記具の尖端と紙との関係に生じる劇(ドラマ)である。その劇をここでは、「筆蝕」と名づけることにする。」
そして、「筆蝕」は、1)筆が加える力と紙の反発から生じる摩擦、筆触、2)墨跡を調整、制御するための視認、二つの要素からなるとします。
私はこの時、「書の美をこれまでは頭のみで見ようとしていたが、実は筆(線スケッチの場合はペン)を動かす実動作を通じて、すなわち身体感覚を通じて見て感じるものなのだ」と気が付きました。
島尾氏は、以上述べた石川氏の「筆蝕」という言葉は使っていませんが、「線の幅を変えて抑揚をつけ、穂先を返しながら自在に腕を動かしてゆく。筆をすべらせるのは心地よい」と身体感覚を強調し、それが「線の芸術」としての書画が生まれるきっかけになったとします。(下記)
「線のよろこび」の発見は、中国の芸術史における大事件だった。その欲求がさらなる道具の高みを求め、筆もすみも改良されて「線の芸術」としての書画が立ち上がってくる。」
さらに歴史的には「書」における「草書」の出現があり、「画」では均一の幅の線で描く「白画」がそのあとに続きます。
そして、いよいよ「水墨」の発見となります。
「墨は色(五彩)を兼ねる」「筆の(新機能)の発見」
第二章「水墨の発見」では、水墨が現れる前、岩絵の具による著色画が一般的だったのが、墨と筆の新しい機能が発見されて「水墨」が生まれていく過程が述べられます。
一つは「墨」の機能で、墨は濃淡を自由に調節でき、グラデーションを表現できることに気が付きます。
濃淡は自在に調整ができ、暗いところから明るいところまで、連続したきれいなグラデーション(諧調)を表現できる。殷仲容(注)が気づいたのはここだった。濃淡のある墨の面を活かせば、対象の質感と立体感を表現することが出来る。
(注)唐の則天武后の時代に活躍した画家
二つ目は「筆」の新たな可能性の発見です。
ここで重要なのは「墨の線」によって「風が表現されていること。これも「コロンブスの卵」で対象の「かたち」をえがくものと思い込んでいた墨線が、それ以外のものも表現できることに気づかれたのである。「この一人で何役もする線」によって「えがける世界」の可能性は大きく広がった。
これが前代の「白画」と「水墨」と分かつところとなり、「筆墨」の線は、単なる線ではなくなったと著者は云います。
具体的に、日本の南北朝時代の禅僧、可翁の「竹雀図」を取り上げて、特に、左上の風で動く竹の葉を例題にして説明します。

出典:wikipedia, public domain
竹の葉は、ひと筆で引かれた濃墨の線である。このように、墨線をそのまま「なにか」の化けさせるのが水墨の基本技。もっともシンプルなのが、このような植物の葉で、直線的にさっと引けば竹になり、柔らかな曲線にすれば蘭になる。(中略)
ここには「竹の葉」と「墨の線」が同時に見えている。それで「気持ちのいい線だね」などというえがかれたものとは関係のない、線自体の評語がでてくるわけだ。
上の方の竹の葉は、左上を向いている。右からの風になびいているのだ。これが呉道元が見つけたもの。墨の線が「風」も表現しているのである。これには「筆の動き」も関係していて、左上へ勢いよく引かれることで、風の動きを感じさせる。「さっと引かれた」線が、そのまま「さっと吹く」という感覚を生んでいるのである。墨の線はいって見ればベクトルで、方向と長さそして速度ももっている。
私たちはこれは水墨画だよと小さい頃から見慣れているために、墨で竹の葉を表すことに何の不思議も感じませんが、確かに言われてみれば、単なる墨の線にすぎないのです。しかも、その墨の線が左上に向いているだけで、空気(風)すらも感じてしまう。
著者は、これについて、水墨を見る人の「身体感覚」に言及します。
もっともここは東アジアに独特の感覚だろう。「筆墨」に馴れた私たちは、線がどちらからどちらへ引かれたか、どのくらいの力が加わり、どんな速さで引かれたかが感覚的に分かってしまう。水墨をえがいたことがなくても、書に少々親しんでいればーテニスや卓球と同じようにー「腕の感覚」が甦る。これも水墨の特徴で、「目で見る」だけでなく「からだ」でも感じられるのである。
前章の「線のよろこび」に続いて、この章における「腕の感覚」が甦るにも本当に同感です。
なぜなら「線スケッチ」の教室で私が初心者の方に力説しているのは、まさにこの身体感覚を身に付けてほしいということであり、その内容と呼応しているからです。
「大人」は絵を習う前に「すらすら」と描いている自分をはじめから思い描きます。ところが実際に大きな紙に線を引こうとすると思うようにできず、愕然としてしまうのです。
すると誰からも怒られことがない大人は、出来ない自分がいやになり、そのまま諦めて止めてしまいがちです。これが長続きしない原因なのです。
しかし最初から「すらすら」と描くのは難しいのは、ちょっと考えれば分かるはずです。大人は手首から先の手と指に力を入れて文字を書くのに慣れ過ぎて、肩から腕、手首までを動かして大きく線を引く動作に慣れていないからです。
ここで思い出してほしいと生徒の皆さんにお願いしているのは、小学生の時に習った「書道」の運筆です。書道では、筆を持つ手を肩から腕全体を使って動かしたはずです。
島尾氏がいうように、水墨を見る立場だけならばテニスや卓球の時の腕の振りの感覚を思い出して、墨で描かれた「竹の葉」の作者の動きを身体感覚的に理解することはできるでしょう。しかし、思い出すだけでは、絵は描けません。改めて、肩から腕、手首までを自在に動かす練習を繰り返し、脳の中に新たな神経回路を作り出す必要があります。
いわば、「リハビリテーション」と同じなのです。
私は練習による神経回路の創り方の例として、子供の頃の「自転車」と「水泳」、そして大人の例としては「ゴルフ」を挙げています。
すべて、自分だけが頼りの運動です。けれど、一度神経回路が出来てしまうと、失敗しようにも失敗できない脳の神経回路ができてしまうのです。
一旦神経回路が出来ると、例えば自転車であれば、どのように転ぼうと思っても、転ぶことが出来ない、水泳であれば、溺れようと思ってもどうしても溺れることが出来ない、ゴルフであれば、あれだけ地上に止まったボールを空振りしたのに、空振りしなくなるのです。
話が随分横道にそれてしまいました。「竹雀図」に戻ることにします。
著者は「風」の表現に続き、右端の笹の葉が擦れていることに注目します。この笹の葉のとぎれは偶然ではなく、わざと筆を浮かせて描いたのだとみます。それは、左の枝も途中で消えていることから、竹の手前を「さっと霧が横切っている」表現とみなせるからです。
ここで、水墨を観るものの立場について島尾氏は述べます。
「水墨」は半ば想像力の世界である。画との対話によって、観る者もイメージの形成に参加することができるのだ。もちろん画の性格にもよるけれど、いま風にいえば、インタラクティヴな面も持っている。(中略)
そして「線」の表情そのものも楽しめる。
西洋絵画のように作品を客観的な対象として観るのではなく、作品の中の筆の動きに観る人も感応し、必然的に参加することになるというわけです。
この後興味深いことに、西洋の油絵との比較にも著者は言い及んでいることです。
このような雰囲気(注)は、丁寧に絵具を重ねてゆく油画にはなかった。筆のタッチは見せないのが基本で、ゴッホのようにそれを露わにし、そこに観る者が「画家」を感じるようになるのはーある意味で「筆墨」に近づくのはーずいぶん後のことである。これに限らず、欧米の絵画では十九世紀から二〇世紀に始まるものが、東アジアでは遥か昔からあることが多い。その中でも水墨もけっこういろいろのものを先取りしている。
この文章に続き、「天才画家・呉道元」のエピソードを借りて水墨山水のポイント「胸中の丘壑(きゅうがく)」、「舞うように描く」そして水墨画の解説では必ず出てくる「画の六法」、すなわち有名な「気韻生動」「骨法用筆」「応物象形」「随類賦彩」「経営位置」「伝模移写(伝移模写)」の紹介が続き、「潑墨」と「アクションペインティング」についての説明がなされます。
「胸中の丘壑(きゅうがく)」、「画の六法」は中国絵画の紹介には欠かせない言葉ですが、「舞うように描く」、「潑墨」と「アクションペインティング」の項目では、またしても西洋美術との対比がなされます。
アクションペインティングといえば、ジャクソン・ポロック(図3-11)で、二〇世紀の産物のように見られているが、これに類するものは遥か昔の中国にあった。そして、従来の絵画を逸脱したポロックが「抽象表現主義」として認められたように、「潑墨」も「逸品」として新たな価値を与えられたのである。ここも「水墨」の懐の深いところ。「筆墨」の歴史からみれば「前衛書道」や「パフォーマンス書道」も決して新しいものではない。
上の引用の中で参照する図3-11、ジャクソン・ポロックの作品No29は、下記をご覧ください。
「潑墨」とは、「墨を潑(そそ)ぐ」ということで、偶然出来た墨の模様に手足を使って墨を加え山水画に仕立てあげることから呼ばれる手法です。
従来の中国絵画の紹介書籍の中では、このようなパフォーマンス的な手法をきちんと紹介した例はないように思います。少なくとも私は初めて知りました。
著者も、この辺を意識したのか、次のような補足の説明をわざわざ加えています。
画家は「作品」で勝負すべきで、この種のことは邪道、という向きもあるが、すでに唐代からあるのは見ての通り。そしていかにえがかれるかをみておくと、画に対したときの面白さが違ってくる。ここもダイレクトに筆の迹や墨の滲みが見える水墨ならではで、「ショー」は観者の水墨への理解を深めることになるのである。私もときどき水墨画家の先生を招いて、学生に見せるようにしている。
著者は、さらに水墨の本質部分、「偶然性・抽象性・創造性」と、節「王維と文人画」において後代に中国絵画で重要な潮流となる「文人画」の発生について述べたあと、第2章の最後の節「筆墨論」では、まだ本の序盤にすぎないのに、まるで「あとがき」かのように「筆」と「墨」について熱く語っています。
そのもとにあるのは「筆」と「墨」それ自体の美しさ。「すばらしい線」や「深みのある墨色」は水墨画の大きな要素で、書が視覚芸術として成り立つのもそれによる。どのようにして独特の線を引き、きれいな墨色を出し、滲みをコントロールするか、などは画家にとっての重要な課題であり、表現の上でも「潑墨」で見たような「山水画という名の抽象画」が成り立ってしまう。これらは、「水墨のテーマ」で「絵画のテーマ」ではないから、ときとして水墨の自己目的化を招き、画としてのテーマを弱くすることもあるけれど、水墨マニアにとってはたまらないものだ。
「水墨マニア」はおそらく著者自身も含まれていると思いますが、あえて自虐的な表現を使うことで、水墨への思いと同時に、著者が「水墨の発見」の章を設けたこと、すなわち、いかにこれまでの水墨画の入門書とは異なるアプローチなのか、その思いが伝わってきます。
著者は、このあと第三章「水墨画の存在様式」において「筆」と「墨」と「紙」の物質・材料科学をベースに「水墨」について話を展開していきます。
今回は、ここで一旦終わりにして、「その2」で紹介することにします。
(その2)に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
