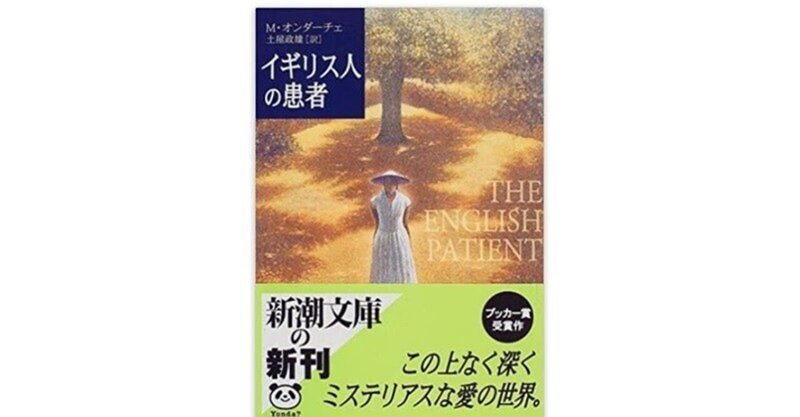
『イギリス人の患者』 マイケル オンダーチェ (著) 土屋 政雄 (訳) 四人の主人公の、過酷な、凄絶な、しかし美しくもある個人的体験を通じて、戦争が世界にもたらした変化を描き切った大傑作でした。
『イギリス人の患者』 (新潮文庫) 文庫 – 1999/3/1
マイケル オンダーチェ (著), Michael Ondaatje (原著), 土屋 政雄 (翻訳)
Amazon内容紹介
「痛いほどの美しさ。救いようのない悲劇。『The English Patient』(邦題『イギリス人の患者』)は、第二次世界大戦末期のイタリアのある修道院を舞台に語られる、4つの破壊された人生の物語である。疲れ果てた看護婦ハナ、障害のある盗人カラヴァッジョ、用心深い土木工兵キップ。そして彼らの心を捕らえる、ひとりの謎に満ちたイギリス人の患者。修道院刈り込まれたの2階に横たわる、やけどを負った名前もわからないその男の熱情と裏切りと救出の記憶が、稲妻のように物語を照らし出す。マイケル・オンダーチェは詩的叙情にあふれた文体で、それらの登場人物たちを互いに絡み合わせ、固く結びつけたかと思うと、真実をえぐる鋭い感性で、織り上げた糸をほどいていく。
偉大な文学の要素をさまざまに備えた『The English Patient』は、ブッカー賞を受賞。」
ここから僕の感想。
幸いにして僕は映画「イングリッシュ・ペイシェント」(アカデミー賞作品賞監督賞という主要賞含め9部門を受賞した名作)をまともには観ていなかったので、(WOWOWかなんかで、ちらっと、見たけれど、なんか砂漠が、出てきた?くらいの記憶しかない。)ので、なんの予備知識もなく小説を読むことができた。
映画は、おそらく「イギリス人の患者」の恋を中心に、かなり刈り込まれた別物になっているのではないか。と読んでいる途中から思っていた。この複雑な四人の物語を2時間~3時間の映画にまとめるのは不可能だと思う。訳者解説にもそのようなことがちらと書いてあった。
以前に、オンダーチェの『戦下の淡き光』の感想にも書いたが、(note『戦下の淡き光 』 マイケル・オンダーチェ (著), 田栗美奈子 (訳) 母親が戦争に絡んで突然、謎の失踪しちゃう小説としては、イシグロの『わたしたちが孤児だったころ』があるが、イギリスって、そういうことが結構あったのかしら。日本にはない戦争小説の形である。) イギリスと言う国の、先の大戦における関わり方と言うのは極めて複雑で、そのことがイギリス人の戦争体験をややこしいものにしている。
のだが、オンダーチェ自身が、スリランカ生まれ(1943年生まれだから、戦争は知らない世代だ)であり、11歳の時に母とともにイギリスに移住し、その後カナダのトロント大に進学し、カナダ国籍を取得するという複雑な生い立ち経歴であることが、この小説の複雑に深く反映している。
この小説には、主人公が四人いる。「イギリス人の患者」は、全身大やけど黒焦げ状態で、話はできるが、外見はもう、ただ黒焦げである。明晰に様々な話はする、砂漠の調査をしていたイギリス人のようであるが、正体は不明である。、イタリアのフィレンツェ郊外の、元・尼僧院だった屋敷、野戦病院で、その患者を看病している20歳の看護師ハナは、カナダ人である。そこに現れる、ハナの父の友人、ハナを幼い頃から知るカラヴァッジョは、イタリア人だが、ハナを幼い頃から知っているということは、カナダ暮らしが長い。もう一人の主人公、爆弾・地雷処理の達人である、若い工兵キップは、インドのシーク教徒であり、イギリスに渡り工兵としての訓練を受け、優秀さから昇進し、連合軍のイタリア侵攻に参加、ドイツ軍が敗走撤退しつつ大量に仕掛けた爆弾や地雷の撤去を行いつつイタリア各地をめぐり、この尼僧院の屋敷にたどり着く。
イタリアを舞台としながら、地元在住のイタリア人は出てこないし、「イギリス人の患者」といいつつ、患者は黒焦げで身元不明である。この主人公四人の、それぞれの複雑な過去と、凄惨というか、それぞれに心に深い傷を負わせる戦争の体験が次第に明らかになっていく。この屋敷で、戦争がほぼ終わった時期に不思議な共同生活を送る四人の関係が、小説の進行と共に、複雑に変化していく。
小説は、そこにいる主人公四人と、そこにはいない、それぞれの家族や恋人との過去の物語を、お互いが少しずつ共有していくことで進んでいく。
また、それぞれが負った複雑な戦争体験が、すこしずつまじりあう物語でもある。
いやいや、それだけではない。イギリスとインドの関係の、いや、西洋と東洋の根深い文明の対立の物語でもある。物語の最終盤に、思いもかけず、日本も深く関係してくるのである。
話はちょっと戻るが、そもそも、時代背景と舞台が、日本人には少し分かりにくい。その解説。
そもそもの話、イタリアの、第二次大戦の経緯と言うのを、ちゃんと勉強したことが無かったので(世界史で大学受験しているのだが、近代史の、しかもイタリアの歴史なんかまで、手が回るわけはないのである。本当に今回まで、全然知らなかった)、なぜ、イタリアを舞台に、連合軍とドイツ軍が戦っているのだ?というところから、恥ずかしながら、分からなかったので、例によって、Wikipediaで学習しつつ、また、グーグルアースで、付近の風景を見て観つつ、また、多くのイタリアの寺院と、そこにある絵画、壁画、彫刻が出てくるので、そしたものもGoogle先生で検索鑑賞しつつ、読書を進めたのである。
イタリアは、枢軸国では、いちばん初めに1943年7月末には敗色濃厚になり、ムッソリーニは失脚監禁され、後を継いだバドリオ政権は連合国と秘密休戦協定を9月3日には結び、ローマを無防備領域とすることになった。ところが「秘密」なのに、アメリカのアイゼンハワー連合軍司令官が9月8日にイタリアの無条件降伏を発表しちゃったものだから、「そんなことじゃあないか」と疑って準備をしていたヒトラーは、速攻でローマに侵攻、9月10にはローマを占領しちゃうのだ、ナチス・ドイツ軍が。で、監禁されていたムッソリーニをドイツ軍が解放して、イタリア北中部に、ドイツの傀儡政権「イタリア社会共和国」っていうのをナチスドイツは作っちゃうのだな。
で、それに対して、連合国はイタリア半島の南はじっこ、長靴のさきっぽの隣にあるシチリア島から半島に上陸して、北上しながらドイツ軍を追い出す作戦や、フランス側から攻めて行ったり、ユーゴのチトーの協力で東北部から攻めて行ったりと、ドイツ傀儡政権が占領したイタリアの、ドイツ軍をじわじわと攻めて行った、というわけだ。この小説は、そうやって、ほぼドイツ軍を追い出し切ったころの、1944年8月(11日にフィレンツェからドイツ軍を追い出した)から、1945年の8月、日本が敗戦を迎えるまでの一年間くらいを中心に描いているのだな。
という、基礎知識、ヨーロッパの人には常識なんだと思うが、それが分からないと、イタリアを舞台に、フィレンツェで、ドイツ軍に占領されていた屋敷を、野戦病院にして、とか、イタリアにドイツ人将校がいて、そのイタリア人愛人宅に忍び込んで、とか、どういうことだ、というのが全然わからないわけなんだな。
欧米の人が、戦前戦中の日本や中国や朝鮮半島や満州国を舞台にした小説を読んだとしたら、「ん、日本と韓国の関係はどうなっているんだ」とか「満州国っていうのは、何語が話されていたんだ」とか、「現地の満州国人、というんか中国人は日本人のことをどう思っていたんだ」とか、いろいろ分からないことだらけで、それは、Wikipediaで、そのあたりの歴史と経緯をざらっと調べないと、何がなんだかわからないだろうなと思う。海外の小説を読むときには、たいていの小説は、関係各国の読者なら当然知っていることを前提に書かれているので、それは調べながら読まないと、何が何やら、になってしまうのである。
それにしても、第二次大戦の、フランスのヴィシー政権時代のこととか、イタリアの、この「ドイツに占領されて、ドイツ軍と連合国軍の戦争で国中ぐちゃぐちゃにされた体験」とかいうのは、フランス人、イタリア人、それぞれ、ドイツには「えらい迷惑かけてくれたよな」という気持ちは強いだろうなあ。今、よく、EUで、とりあえず仲良くやっているよな。日本も韓国北朝鮮中国台湾、フィリピンインドネシア、インドシナ半島ビルマまで、そしてオーストラリアまで、そして南太平洋の島々のみなさんまで、いろいろ迷惑かけまくったわけだから、これはまだまだいつまでだって「あのときはすみまんでした」っていう謝罪の気持ちは忘れたらいかんと思うよな。
では、小説の感想に戻るが。
主人公四人の、人物造形が、ほんとうに素晴らしいんだよな。それぞれが、もともと、あるかなり強い個性を持っていて。それが戦争の過酷な体験を経て、どのように変化していき、そして、今、その四人が不思議な共同生活をする中で、どのように相互に作用していくか。そこのところが、それぞれの人物が、いきいきと、全く作り物のようではなく、存在感と魅力とをもって描かれていく。
人物だけでなく、自然の描写も、絵画や教会や彫刻や壁画といった芸術作品の描写も、繊細で美しい。自然といったって、フィレンツェ郊外の山腹の僧院を取り巻く自然から、砂漠の過酷な、壮大で厳しい美しさまで。この作家、人を描いても、風景を描いても、人の作り出した芸術を文章で描写しても、どれも素晴らしく上手い。
恋愛描写も、心理も肉体的な行為についても、あるいはその両者の混ざり合った、そうとしかいいようのない恋愛と性愛の描写も、これまた、まったくもって、切実な美しさがあるんだよな。すごいよ。ほんとに。
ミステリー、謎解き的な要素もあるから、これ以上は書くのをよそうかと思うけれど、最後の大きな事件を読んだとき、僕は東京裁判で、ただ一人A級戦犯全員無罪を主張したインド人のパール判事のことを思い出したんだよね。オンダーチェがスリランカ出身であること。シーク教徒のインド人、パックの、戦争の受け止め方。イギリス軍の、連合軍の兵士として戦争を戦ってきたことと、自分がアジア人であることの関係。そうか、この小説の射程は、そんなところにまで届いているのか。ちょっとびっくりするのだな、最後のところで。
同じようなことは、砂漠探検家であった「イギリス人の患者」の回想にも、色濃く表れる。戦前、イギリス人、ドイツ人、アフリカ人がチームを組んで、砂漠を探検してまわる。現地のベドウィンたちとの関係。国境がない「砂漠」という世界に、戦争が持ち込まれたときに起きる、様々な変化。
四人の、個人の体験の重なりの中に、戦争の、いや、戦争がない時代からのヨーロッパの国と、アフリカの砂漠やインドとの関り、戦争を通じて世界全体に起きたこと、変化の意味。
映画は、おそらくは「イギリス人の患者の、過去の恋愛」に、どうしてもそれは重心がいっていたんじゃあなかろうか、それはそれだけで、究極の美しさとドラマチックで壮絶で、びっくりするような展開なのだが。しかし、それすらも、この小説の中では「一部分」でしかないのだよなあ。それくらいスケールの大きな、美しい小説でした。
そういえば。
2018年7月10日の東亜日報
「「イギリス人の患者」と呼ばれた男性の悲劇的な愛の物語が、去る半世紀の英米圏の最高の小説に選ばれた。スリランカ出身のカナダの作家、マイケル・オンダーチェ氏の『イギリス人の患者』が8日(現地時間)、英ロンドンで開かれたブッカー賞50年記念式で歴代受賞作の中で最高を意味する「ゴールデン・ブッカー賞」に選ばれた。主催側は、ゴールデン・ブッカー賞を選定するために、審査委員団が1969年からの50年間のブッカー賞受賞作の中から10年ごとに5作品を最終候補に選んだ。9千人が参加したオンライン投票の結果、1992年の受賞作の『イギリス人の患者』がライバル候補を退けて1位になった。」
ということで、過去50年のブッカー賞の中でも評価の高い一作なのだな。
しかしまた、「ブッカー賞の中のブッカー賞」というのもあってもこれは1993年にブッカー賞中のブッカー賞 (Booker of Bookers Prize) として、サルマン・ラシュディの『真夜中の子供たち』(Midnight's Children、1981年受賞)が選ばれたのだそうだ。つぎは、これを読んでみようと思うのである。
追記 作品タイトルについて。
原題 The English Patient 映画では、日本ではそのまま「イングリッシュ・ぺイシェント」で、小説翻訳では「イギリス人の患者」なんだけど、ぼくは英語が得意ではないので、自信は全然ないけれど、思ったことを書きます。というか、読書師匠のしむちょんとFacebookでやりとりしていて書いた、そのときのコメントを引用しちゃいます。自信はないけれど。
patientって、名詞だと患者だけれど、形容詞だと「忍耐強い」じゃん。「苦しみにずっと耐えている」から患者なわけで。「受苦」みたいな語源からの派生で患者でしょ。なんか、この、タイトルっていうのは、そういう全員が苦しみに耐え続けているということと、Englishも、イギリス人じゃなくて、イギリスという国の振る舞いが世界にもたらした苦しみっていう感じとか。「イギリス人の患者」という、四人のうちの一人のあの人物を指している、というのよりもうひとつ大きいいろんな連想を、呼び起こすように付けられたタイトルなのかなあ、と思ったのだが。何せ英語が出きないもんだから、「いや、ネイティブが読んだり聞いたりしても「イギリス人の患者」としか思わないよ」って否定されたら恥ずかしいから、しむちょんコメント返信にだけ、ひっそりこっそり、思いつきとして書いておく。
文法的にはこのpatientは名詞だから患者でしかありえず、それを形容しているからイギリス人の、というEnglishに間違いはないのだけれど、読み終わった時に感じられるこの小説のテーマとしての「イギリスの行為により(戦争だけでなくいろいろいと)傷ついた、『イギリス周辺人』たちの受苦の物語である」というイメージが浮かび上がってくると思うわけ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
