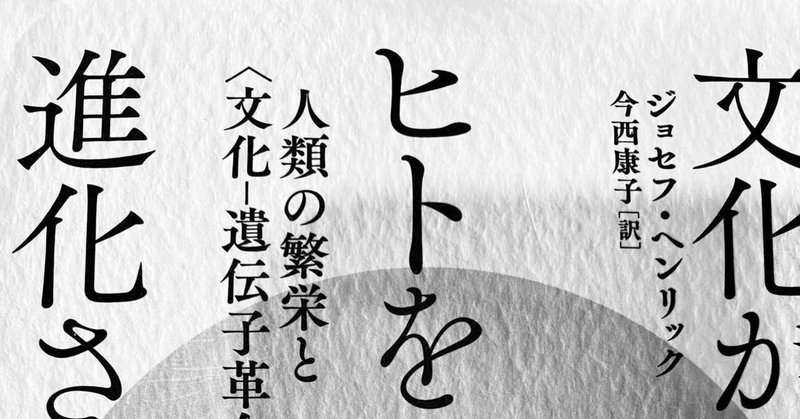
あんがい過酷な「文化的」であること− ジョセフ・ヘンリック著『文化がヒトを進化させた』を読む(2)
ジョセフ・ヘンリック氏の『文化がヒトを進化させた』を引き続き読む。
ヘンリック氏によれば「文化」と「遺伝子」は共進化するという。
文化と遺伝子の共進化
共進化とは、文化と遺伝子、どちらかが一方的に他方を生み出す原因であるとは考えず、相互作用を通じてそれぞれ変化、進化していく、という考え方である。
遺伝子の進化の選択圧となる環境としての文化
文化は、遺伝子の進化を方向づける「環境」になる。
ここでヘンリック氏がいう文化とは、特に「社会規範」である。何かの「タブー」であるとか、儀式や婚姻に関する規則などがそこに含まれる。
「ヒトの遺伝子を取りまく環境を変化させたのが、文化が生み出した社会規範だった。[…]食のタブーを無視する、儀式をないがしろにする、姻戚に狩猟の分け前を与えないといった規範破りを犯すと、評判を落とし、陰口を叩かれ、結婚の機会や仲間を失うはめになった。」(『文化がヒトを進化させた』p.24)
社会規範を破る人は「評判」を落とし、「婚姻の機会や仲間を失う」という。なかなか人間というものは大昔から変わらず、気苦労が尽きないものである。
文化の中でも特にヒトとヒトとの関係のあり方を規制するのは社会規範であるという。なすべきこととなすべきではないことを区別する規範は、ヒトの行動を左右し、強く「規制」する。そしてある社会、ある文化において望ましい「なすべきこと」をなすヒトが、その社会で子どもを残すチャンスをより多く得るというのである。
これを繰り返しているうちに、ある社会規範のもとで、より好まれる遺伝的性質を持った人の子孫が数を増やし、結果的に集団の遺伝子の統計的なパターンまで変化していくことになる、という筋書きである。
そして社会規範こそが「自己家畜化という遺伝的進化の駆動力」であり、「ヒトの社会性を急速に高めていった」とヘンリック氏は書く。
社会規範
ヘンリック氏によれば社会規範には集団内の「調和」や「協力」を促す効果がある。社会規範があり、個々の個体が社会規範を考慮して行動することで、対立や争いを回避したり、調停したりする(『文化がヒトを進化させた』,p.249)。
現代の自由な社会では「規範」というと、なにやら個人の自由を束縛するもののように思われることもある。けれどもしかし、今日でも、「礼儀正しいこと」「他人を愚弄しないこと」などなど、さまざまな規範のおかげで、私たちは初対面の相手とも殴り合いではなく挨拶でコミュニケーションを始めることができるようになっているし、「借りは返すこと」「義理を通すこと」といった規範のおかげで継続的に互いを信頼することができるという側面もある。
ちなみに、社会規範は、個々人が生まれながらに”遺伝的に”持っているものではないとヘンリック氏は考える。
「ヒトの脳は、増大しつづける文化的情報を収集、蓄積、整理、伝達する能力が決定的な選択圧となる世界のなかで進化し巨大化していった。ヒトの文化的学習能力は、自然選択の作用と同様に、何世代にもわたって「黙々と」作用し続けて、一個人もしくはグループでは生み出し得ないような賢い習慣を生み出す。(『文化がヒトを進化させた』p.34)
社会規範を含む「文化」は、世代を超えて形作られ、伝承された「習慣」である。
人々の間で伝承されることで再生産され、受け継がれ、時に変容する「習慣」としての規範は、人々の遺伝子に遺伝的に書き込まれているわけではない。ある人が何を規範として獲得するかは、生まれ落ちた場所で、誰と、どのような人々と暮らし、学習をするかによって左右される。
もちろんそれは、人が他者によって完全に決定されているとか、完全に受動的な存在だという話ではない。社会規範はあくまでも「各個体が他者から学ぶ能力を発揮するうちに」つど新たに生まれてくるものである(『文化がヒトを進化させた』,p.248)。
ヒトの知能のように思えるものの多くは、天性の知力でも、本能でもない。実は、先祖代々文化として受け継がれていた膨大な知的ツールやスキル、概念、分類体系などによってもたらされている。」(『文化がヒトを進化させた』p.34)
ここでヘンリック氏は興味深いことを書かれている。「ヒトの知能のように思えるもの」は「文化として受け継がれてきた」概念や分類体系だというところである。
当たり前のことのように思われるかもしれないが、この分類体系、分類、分類すること、分けると共にまとめること、は人類の文化現象のおそらく核心にあるアルゴリズムである(この辺りのことについては、下記の記事にも書いていますので参考にどうぞ↓)。
分けることとつなぐこと。
これこそ、C.S.パースのいうインデックスでもイコンでもない、シンボルの体系としての言語を発生させる秘密なのである。この話は下記の記事に書いていますので参考になさってください。
「言語」=シンボルによる分節体系を創造し学習する能力。その進化を促した「文化」とは!?
ヘンリック氏は「言語」のルールもまた社会規範の一つであるという。
人間の高度な思考を可能にする「脳」の進化もまた、この言語、「言語ルールを含めた社会規範の影響を受けながら鍛錬され、形成され」たものであるという。
即ち、社会規範の影響のもとで、海馬が大きく、脳梁が太い、つまり他者との協調的な行動や協力に強い個体がより多くの子孫を残す結果になった、という説である(『文化がヒトを進化させた』,p.27)。
親族構造が言語を生む?!
言語という多数のシンボルの組み合わせからなる体系は、何かと何かを分けることとつなぐことを自在にできるようになったところから発生した、と推定される。
そうだとすると、この何かと何かを自在に分けたりつないだりする能力の進化を促した文化的な規範とは一体何だったのだろう、という話になる。
* * *
ここでヘンリック氏が注目するのが「親族構造」である。
親族構造といえばレヴィ=ストロース氏の構造主義の出発点であるが、今はヘンリック氏の話をしよう。
ヘンリック氏によれば、他の動物にみられないホモ・サピエンスの文化、社会規範のうち、特に注目に値するのが親族関係についての規範、人類学でいう「近親相姦のタブー」である。
「ヒトの社会は、どれもど小規模な社会であろうとも、霊長類の社会と違って、親族関係に関する一連の規範のもとに成り立っている。」(『文化がヒトを進化させた』p.215)
親子関係、夫婦関係、兄弟関係。
親 対 子
夫 対 妻
上の子 対 下の子
男性 対 女性
「つがい」になることができる / できない
親族構造は、互いに別々に区別されつつも一つに結びついた二つの項のペアである。項と項の関係、ペアとペアの関係の組み合わせによって、複雑な親族関係が構造化される。
そうしてある二人の個体が親族構造のどの位置にあるかによって、「つがい」になることができるか、できないかを分別する規範が出来上がるのである。
この婚姻のタブー、婚姻の規則を理解し、従うことができる個体が、群れの中で有利に子孫を増やすことができたとすると、この「分けつつつなぐ」ことを自在にするアタマの使い方が他の個体よりほんの少しだけ「できる」者たちが徐々に増えていく事になる。これが何万年、あるいはことによると何十万年と、世代を継いで反復されたとすると、この特長がますます選び抜かれていく。
そして、群れの個体の多くが「分けつつつなぐ」ことを自在にできる頭を持つようになるにつれ、少しづつ、多様なシンボルの自在な組み替えと構造化が進んでいくことになるだろう。
そこに、互いに異なるものを異なったまま結びつける「意味する」ということが可能になる。言語の始まりである。
レヴィ=ストロース氏は、後に人類にとって抜き差しならない切実な「意味」の世界の出来上がり方を「構造」の運動として捉えようとするであるが、その初期の探求は、親族構造を巡って繰り広げられたのである。
※
親族構造というと、遺伝的な親子関係から発生するもので、遺伝子の世界の話だと思われるかもしれない。親族構造は文化とは無関係な遺伝の話であると。
しかし、そうではない。
人類の親族構造は、生物学的な親子関係を超えて織りなされる。
なにより「遺伝的なつながりがなくても親族名称で呼び合う」ことは様々な文化で行われていることである(『文化がヒトを進化させた』p.236)。
親族構造という社会規範は、言語につながる「シンボル化」する脳の力を強化するよう促す。
◇
参考に、神経生物学者・進化人類学者のテレンス・ディーコン氏の説も見てみよう。
ディーコン氏は、親族関係を表すための「シンボル」こそが、言語に先行し、ヒトの祖先の言語=シンボル化能力の進化を促すよう圧力をかけたのではないかという仮説を提示している。
ヒトの祖先は、言語に先立って、まずシンボル(記号)を使わざるを得なかった、というのがディーコンの説である。
ディーコン氏の説によれば、ヒトがシンボルを使うようになった理由というのは、一夫一婦制の夫婦という関係を「群れ」の中で再生産し続けるために、関係を互いに&他のメンバーに示し続けるために、記号の体系が便利だったのではないかという。
群れの中のある個体とある個体のペアに対して、一方に他方の「夫」あるいは「妻」であるとの記号を与えること。
個別的な二人の個体の関係を「夫」と「妻」という記号のペアで象徴(シンボル化)すること。
シンボルを使うことで、実際に「夫」や「妻」と呼ばれることになる個体のヒトのあいだの無数の違いを超えて、抽象的かつ一般的に記号の関係として二者の関係を意味づける。個別のつがい関係をシンボルの関係へと変換することで、関係を特定のものから一般的なものに変換できるのである。
記号というのは他の記号との関係を表明するものである。
夫とは、ある妻に対する夫であり、妻とはまたある夫に対する妻である。こちらが夫でこちらが妻である、と仲間皆が呼ぶことで、その二人は夫婦になる。
この記号によって、本来、他の類人猿と同じように同時に複数にありえるはずのペアの可能性を、長期的に特定の組み合わせに限定することで、特定のペア関係を持続的に維持するよう、群れの構成員に圧力をかける。
そうすることが、例えばオスが、小さな子どもを抱えて自分で狩猟採集することができないメスに食べるものを運ぶよう促す結果につながり、結果として、群れ全体の生存率を高める上で有利であった(のではないか)ということ。この点で、シンボルの能力に秀でた個体がより生き残りやすく、言語の進化のきっかけになったのではないかというのがディーコンの説である。
文化がヒトをコントロールする
ヘンリック氏に戻ろう。親族構造のような社会規範にみられるように、文化には「ヒトの行動を自在にコントロールする」力がある。
「近親相姦のタブーはつがい形成や結婚に強い影響力を及ぼしうるものであり、また社会規範によって血縁個体に対する利他行動を強化することが可能なのである。つがい形成や結婚を掌握できれば、さらに大きな社会組織を牛耳ることができ、ヒトのさまざまな認知機能や動機までもコントロールすることができる。」(『文化がヒトを進化させた』p.232)
社会規範は、社会組織からヒトの認知機能や動機までコントロールする。
社会規範のような「文化」は、世の中でよく言う意味での「文化的」な「趣味の世界」というよりも、強くヒトを駆り立てる価値の体系、切実で容易に譲ることのできない価値の体系なのである。
そうした意味での文化は、伝搬し、部族を超えて広まっていく。
ヘンリック氏は、豊かな部族、争いに勝った部族の文化は、急速に周囲の他の部族へと広まっていくとする。
そうして文化は広まれば広まるほど、より大規模な意味と価値のネットワークを構築するようになり、その意味と価値を再生産しつづけるための細かな社会規範や儀式を無数に生み出し、ヒトビトの立ち居振る舞いから物腰、モノの言い方ひとつにまでいたる細かな規制をおよぼす。
ここに始まるのが人間の「自己家畜化」であるという。
続く
関連note
◇
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
