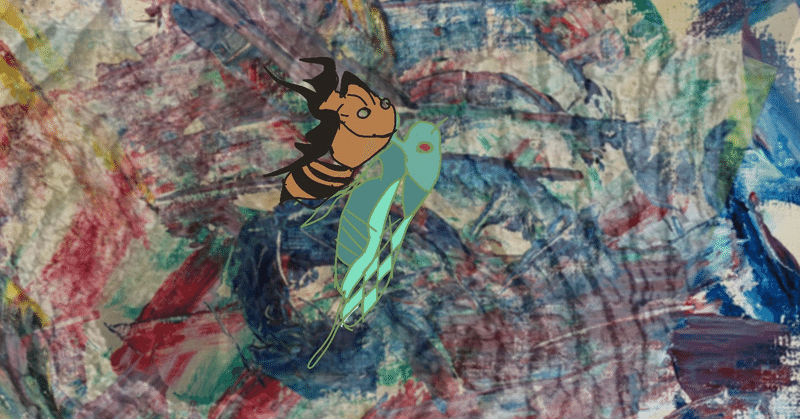
蝉の断章の記憶 第3話
わたしの孤独な性格は、大人になるまで変わらなかった。孵化してから成虫になるまで無変態の生き物みたいだった。
どんな人間にも出会いはある。わたしも例外ではなく、高校時代に、女の子に声をかけられ、デート(?)に誘われた。気難しい本好きの、殆ど笑わない人間も、好奇心の対象としては価値があったのかも知れない。わたしの初めてのデートは、百貨店を一周しただけで終わった。二回目、別の女の子とのデートは映画館だったが、映画は開始時間を過ぎていた。並んで座った二人の目に入った最初のシーンは、放尿だった。主人公が顔にそれをかけられていて、それがスクリーン一杯に映し出された。
中学で初恋をし、ポップスやロックやラップに夢中になり、高校でクラブ活動に打ち込み、青春という登竜門を潜り抜け、肉体も表情も大人になってゆく周りの人間を見て、わたしは羨ましさや妬みより不思議な感覚に捕らわれた。それが自然なのだろうか? 人間として? わたしの読んだ物語では、そういったことは重要ではなかった。それは何かの香りのようなもので、淡くて軽やかな記憶に過ぎない気がした。結局、わたしは逃げていたのだろう。世界から。現実から。人生から。
それは、大学に進学して少しだけ改善された(ように見えた)。生活費を稼ぐため、カフェでアルバイトをするようになったからだ。他人との接点を言葉で繋ぐのは苦痛だった。が、マニュアルの決まり文句を繰り返すだけで時間が過ぎた。休憩時間にオーナーや同僚に話しかけられても、簡単な返事だけで済んだ。つまり、誰も、他人にはそれほど関心がなかったのだ。アルバイトという仕事の性質上、深く相手を詮索するのはタブーだったのか? それでもわたしは、人間が環境の動物であると、知らず知らずのうちに証明していた。いつの間にか表情筋が動いて簡単な愛想笑いや冗談が言えるようになった。読んだ本の表現をそのまま引用したりすると面白がられたりした。
だが、わたしの本質は生まれた時から変わらなかった。わたしは物語の世界を現実に投影し、そうなることを望んでいた。しかし、そんな理想的な人生は、現実には存在しなかった。苦しい時に励まし合い、時には人生の道標となり、喧嘩するほど仲良くなる親友。命をかけたくなる恋人。生涯、師と仰げる先輩。そんな人間と出会う場面を見つけられなかった。現実の世界は美しくも楽しくもなく、わたしの心はいつも物足りない状態が続いた。自分が変わらなければならないことに気付けなかった。いつまで経ってもわたしは孤独だった。唯一の親友は本だった。人とうまく付き合うことができないまま外側だけ成長した。やがて、巣立つ時が来た。
人間の波の中をうまく泳ぐ器用さも体力も知恵も無いまま就職したわたしは、社会で生き延びるにはおとなし過ぎたし、会社組織の権力のピラミッドの中で優位に立つずるさも器量も持たなかった。わたしはいつも最低限の業務をこなし、あとは映画や本や美術館を巡ったりして人生を消費した。わたしが五十歳の時、父が癌で死んだ。母はすでに、父と離婚していた。残された家は、一人暮らしには十分な広さだった。
数年後、会社が不景気になり、リストラを始めた時、わたしは真っ先に候補に上がった。わたしは抵抗も絶望もしなかった。ささやかな手切れ金とともに会社を後にしたわたしは、かえって安堵した。不特定多数の人間を相手に、気を使いながら毎日を過ごさなくても良いという開放感に満たされていた。
すでに人生の折り返し地点を過ぎていた。だが、わたしは本当の自由を手に入れた! 自由とは? それはわたしにとって贅沢な暮らしをし、世界一周の旅に出ることではなかった。邸宅に住み、高級な車に乗り、予約の取れないレストランで食事をすることではなかった。何からも束縛されない一日があるなら、それでいい。わたしは翌日から近くの公園へ行き、ベンチに寝転んで本を広げた。タブレットで読んでも良かったが、わたしは本の紙の匂いや感触が好きだった。それに眠くなったら、本は枕にもできたから都合が良かった。
時代の流れで物品は宅配が常識になっていた。本も例外ではなかった。近所の書店は次々と姿を消した。わたしは新刊を漁りに、大きな書店のある隣町のT町まで電車で出かけた。人と出会いたかったからだ。誰かに話しかける訳じゃないが、周りに人間がいるだけで心が安らいだし、静かなBGMが気分転換になった。駅前で何気なく受け取ったチラシを見ると、
《スプリングフェスティバル開催し! フリーマケットも! T町緑公園! 明日から三日間!》
と書いてあった。面白そうだ。わたしは行くことに決めた。
緑公園はその辺りで一番大きな公園だった。公園を囲むように散歩道ができていて、ゆっくり歩くと二時間はかかった。ジョギングする女子高生に追い抜かれ、ウォーキングをする中年夫婦や犬を散歩させる老人とすれ違い、内側に隣接して広がる森のようなエリアを通り抜けると芝生が一面に広がっていた。
陸上競技場ほどの広さは壮観だった。空に聳える高層ビル群の凹凸が遠景に見え、視線を下げると、ぐるりと樹々の壁が続き、その下に花壇が点在している。チューリップが原色の花をつけて塗り絵のようだった。
公園の中央に大きな池が見えた。池は大きな瓢箪型だった。そのくびれた部分に架けられたアーチ型の橋をスキップで渡る子供。乳母車を引く家族連れ。橋の欄干にもたれて寄り添う恋人達。間欠泉みたいに姿を見せる噴水が春の陽光を受けて虹色に輝いていた。
晴れた空に花火の音が響く。誰かが歌っているバンド。マイクの音量が大きい。歓声。走り回る子供。シャボン玉が伸びたり縮んだりして風に乗り、それを追いかける幼児、アイスクリームを手に、嬉しそうな学生、芝生にシートを敷いてサンドイッチを食べている家族連れ。鳥の声。雲の色、緑の空気、風船が空の高いところで静止。突然、8の字を描きながら落下。その先にカラフルなテントが集まっている一角が有った。そこが催場だった。連休の初日だからか、大勢の人々が屋台や出店に群がっていた。一番奥の地味なテントが落ち着けそうだ。わたしは中に入った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

