
<閑話休題>私と林達夫
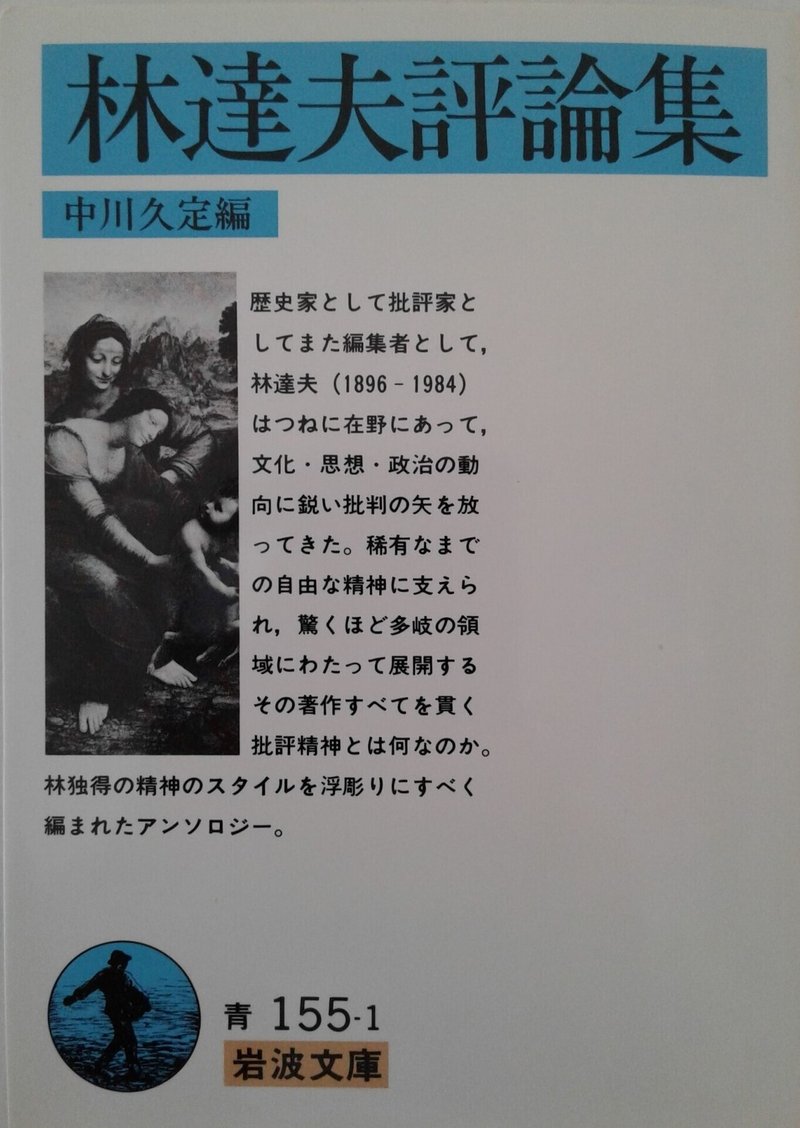
林達夫の『精神史』は,1969年に発表されているが,僕が読んだのは20歳の頃だったので,1979年になる。発表してから10年が経っていたが,当時は今よりも世の中が変わる速度が遅かったから,少しも古びた感じはなく,むしろ絵画の下絵をX線で読み取るという話題は,非常に新鮮なものがあった。
『精神史』については,たまたま読んでいた大学の友人は,その冒頭に書かれているバロックやらレトリックという言葉に翻弄されてしまい,難解過ぎてよく分からなかったという感想だった。しかし,当時の僕は,書かれていることの意味を十分に理解できたとは思えないながら,林達夫の学術論文らしからぬ闊達な文章のうまさに,大きな喜びを感じていた。まるで,優れた詩を読むように,文章そのものを読む喜びに浸ることができたのだ。
学問的な文章で,ここまで読者に読ませてしまう知的エンターテイメント性を持ったものに,僕は生まれて初めて出会ったことを興奮していた。また,そのペダンチックかつ時間(歴史)と空間(国境)を自由自在かつ縦横無尽に飛び回り,言葉の一つ一つに深い造詣と意味を含みながら,20歳の若造にもスラスラと読めてしまうことが楽しかった。そして,読み込めば読み込むほど,そこには非常に高度で難解な思想や概念を職人技の如く表現しがあることに気づき,自ずと自分の教養レベルを試されることになるが,それでもそれなりに学問と知識さらに思考することの最上の快感があった。
これは,自分の目指すべき最高のお手本であり目標だと,強く自覚した僕は,その時「何年かかっても良いから,将来この林達夫の『精神史』のような文章を書けるように,勉強をし,文章力を磨こう!」と心に誓ったのだった。
そして,もう40年以上が過ぎた。途中『精神史』とは少しずれている映画鑑賞(それはそれで,20世紀を代表する「精神」でもあったのだが)に夢中になり,小説(特に短編小説)の技法に大きな魅力を感じて,『精神史』の勉強からは少し逸れる時期もあった。それから,何よりも生活するため,生き延びるためとはいえ,サラリーマンとして生活を始めたことは大きく影響した。
大学で学んだことと『精神史』で得たことは,現実のサラリーマン(公務員)生活にはまるで役に立たなかった。むしろ害が多い『精神史』の世界から一刻も早く抜け出して,ドロドロしたストレスの多い現実社会に適応しなければならなかった。大学で学んだ教養が役に立つことがわかったのは,ずいぶん経ってから(特に海外勤務してから)だったが,それまではもっと下世話な実社会の芸能人などの話題を知っていることが,何よりも重要だった。
そのため,僕はひたすら己の心を押し殺し,上司や周囲からの命令や指示に従順に従うこと,そして自分の頭で考えることはしないことで,今までの人生を生き延びることができた。そう,自らを望んで偽っている仮面の人生だ。そんな人生が楽しいはずはない。年齢を重ねるに従って,自らの意見を求められることも数回あったが,その度に「自分の意見」を開陳すると,すぐさま「理解できない」と全否定され,一笑に付される繰り返しだった。ある時は,自分なりに一所懸命に書いた文章を,「こんなのは役人の書く文章ではない」とゴミ箱に捨てられたときは,自分の人格を否定されたような気持ちになり,その後の文章を書き分ける術を学ぶことにつながったと思う。
そもそも「自分の意見」が採用されることを期待して,僕は何か述べる気持ちはなかった上に,「個人の意見」という前提条件を示されたから,全体の調和とか文脈とは関係なく,僕自身が考えることを述べたに過ぎなかった。だから,僕の意見が採用されなかったのは当然だったし,むしろ採用されない方が良かったと思う(採用されていたら,僕はもっと仕事に忙殺されたことだろう)。僕の考えることは,世間一般の多くの考え方と同調する意識はさらさらなく,正に20歳の頃から目指した林達夫の「反語的精神」に満ちたものだったのだから,周囲から異端視されることは,むしろこうした「反語的精神」を維持していることの確認作業でもあった。
そして,ついに定年退職を迎え,上司や同僚の「一般的・前例踏襲・理解しやすい」意見に従うことや,それに無理矢理合わせる必要はなくなった。もう自分の本当の姿を,心の奥底に押し込んで,その上にサラリーマンという非常に居心地の悪い仮面を付け続けて,したくもない演技をする必要はなくなったのだ。それは,僕の言葉では「自由の再獲得」,「魂のルネッサンス」と表現したい。
こうして忍耐の連続だった40年が経ってから,林達夫の『精神史』の世界に再び浸りきるチャンスを得た。今や,生きるために自分自身を心の奥底に隠し,仮面を被りながら無理矢理に押し殺す必要がない,言葉通りの意味で自由な環境にいるのだ。この環境を得るまでに40年を要したわけだが,ではその間に得たものは,ただこの自由という環境だけだろか。仮に『精神史』という巨大な目標に辿り着くための,必要な勉強や教養の積み重ねまでも排除してきたのでは,それはあまりにも悲しく,空しい。
幸い,サラリーマンとはいえ,余暇ともいうべき時間がある。その時間をどう使うかは,その人それぞれになるが,僕はこの余暇をなるべく勉強と教養の積み重ねに費やすことに努めてきたつもりだ。もちろん,他人に自慢できるような勤勉さに欠ける僕は,40年前に想定したものよりはるかに質・量ともに期待外れの低い数値になったが,それでも例えばフィレンツェのウフッツィ美術館やルクソールの古代エジプトの遺跡を見るという,書物では得られない体験を重ねることもできた。特にイタリア旅行は,林達夫のみならず和辻哲郎(『イタリア古寺巡礼』)の追体験へ昇華できるものがあったと思う。また強がりを言わせてもらえば,世界のあちこちで,地元の酒を飲んだり,地元の料理を食べたりしたことも,「教養」の一部になっていると思う。
思えば,「教養」という言葉は非常に奥深いものがある。それは「経験」にも似ている。たとえば,森有正が述べるように,ただ何かをすることが「経験」とはならない。「経験」になるためには,その「経験」に先立つ「先験的経験」(簡単に言えば,予習みたいなものだ)がなければ「経験」という果実は実らない。「教養」も同じで,ただ知識を得ることや,試験で正答率が高いことが「教養」とはならない。「教養」としての真の果実を得て,心身の滋養となるためには,「教養」が「経験」と連携することが必要だ。さらに,「教養」と「思索」が連携することも欠けてはならない。
私の社会人生活40年で,こうした「教養」と「経験」を十分に研鑽できたとは言えないものの,少なくともこれから生物としての死を迎えるまでの間,林達夫の『精神史』に少しでも近づける足がかり(モノに例えるならば,これからの長い道程を歩くための,靴や杖)を,得ることはできたのではないか,と思っている。
そして,これからはそうした足がかりを頼りにしつつ,一歩一歩,遅く小さい歩幅ながら,遙か彼方の至高の存在を目指して,自らの脚で歩き続けられる喜びに浸ることにしたい。もう,僕の足を引っ張る邪魔者は誰もいないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
