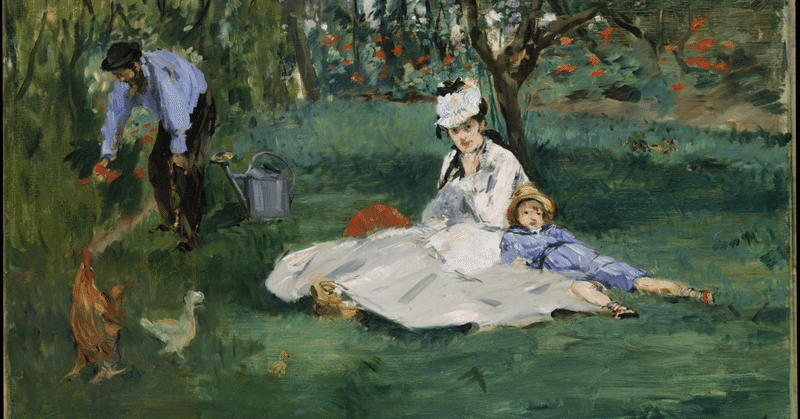
<閑話休題>「オカルティズム」(「ユリイカ」別冊1974年)から
<書評>というものではないが、雑誌「ユリイカ」別冊のオカルティズム特集号(1974年)を読んでいて、面白かった、あるいは参考になったことが三ヶ所(以下に雑誌のページで表示)あったので、<閑話休題>として紹介したい(また、各項目の後段に私の感想を付けた)。

なおこの特集は、文芸雑誌であるため、疑似科学のようにオカルティズムの具体的な方法や実例を面白半分に紹介するのではなく、オカルティズムと深い関係がある作家や研究者などについての論文を紹介する特集となっている。従って、三面記事的な内容を期待するのであれば、完全に裏切られるだろう。
そういうわけで、日本からは泉鏡花や日夏耿之介らが取り上げられている他、(もちろんこちらが本流なのだが)海外からはフランソワ・ラブレーやT.S.エリオットなどが紹介されている。これらの諸論文を読み込んでいくにつれて判明していくのは、文学という人の行う創造行為が、人類の集合的無意識そのものであるオカルティズムから無限のイメージと素材を獲得してきた歴史そのものであった。つまりオカルティズムとは、本来的に文学的なイメージであるのだ。
以下に、雑誌の該当ページとその抜粋、そして私の<感想>を紹介する。
〇 P.209
言語について、先の論文(『詩人と言語』1970年)でレイモン(マルセル・レイモン)は、なかなか上手いことを言っている。仮に言語を単なる記号体系と見なすことに賛成したとしても、言語というこの無法則記号は、「徐々に必然性を孕む傾向にあり、単に記号であることをやめる。」この、偶然性が必然性へ転化する、あるいは、偶然だからこそ必然となる、という不条理性こそ、言葉が持っている永遠の力であり、詩の言葉はまさしくその力への信頼の上にのみ立っている。
<感想>
ウィトゲンシュタインは、『論理哲学論考』で言語表現の限界を指摘したが、その後は「哲学探究」などで、それを乗り越えるためにはどうすべきかを研究しているうちに、亡くなってしまった。
残された草稿(多くが理解するのに難しい文章となっている)を研究する学者によれば、(1)限界を乗り越えられない(『論理哲学論考』の深化)、(2)限界を乗り越えるものがある(『論理哲学論考』の進化)、という二つの見解が出ているようである。
一方、もし(1)の結論となるのであれば、言語表現を生命線にしている文学は死を迎えるしかないだろう。しかし、文学に希望を託す私のような者は、なんとしても生き残るために、(2)の結論を信じたくなる。そして、そのための(理論的根拠ではなく)エネルギー源として、このレイモンのいうところの「偶然性が必然性に転化する」という不条理性が生きてくるのではないか。そしてその不条理性とは、そのまま集合的無意識における不条理性であり、同時に詩の言葉となるのではないか。
〇 P.220
・・・パラケルスス(本名は、テオフラストゥス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイム 1493-1541年)は錬金術という語を彼以前の人々や同時代の人々とは違った意味に用いたが、これは彼が、他の言葉についてもよく行ったことで、時には気まぐれに新しい言葉を造ってしまうこともあった。例えば彼はアルコールという言葉を、本来の目蓋を染める化粧品(al-kohl)という意味から勝手に酒精という意味に変えてしまい、以後こちらの意味の方が定着した。
注:コホル(al-kohl、alはアラビア語の定冠詞)は、古代エジプト人も虫除けとしても使用した目の周囲に塗る薬品・化粧品で、現代でいうところのアイシャドーである。アラブ社会では、多くの女性が現在でもこれを使用しており、また『アラビアン・ナイト』の中でも、美しい女性となるため必須の化粧方法として数多く描かれている。
<感想>
パラケルススは、錬金術師=魔術師として相当な変人だったらしいが、現代にまで残る言葉を多数残している点を考えれば、人類史へ立派な貢献をしている偉大な人物だったと言える。
なお、アルコールを酒精と日本語に訳した人物や経緯は知らないが、パラケルススに劣らない妙訳ではないだろうか。そう、酒の中にはグノームのような妖精が住んでいるのだ。それを酒精と称して、何か異論があるだろうか。そして妖精らしく、この酒精は良いことも悪いことも、その時の気分によって、酒を飲む人に作用してくる。酒精とはうまく付き合いたいものだ。
〇 P.224
象徴の原義は<繋ぎ合わせる>を意味するギリシャ語(SYMBALLO)に由来している。そしてそれは<認知の徴>を意味する(SYMBOLA)と関係がある。古代に於て主人は客を迎える時に器を壊してかけらを客に与え、再び会う時にそれを繋ぎ合わせて認知の印としたと言われている。従って象徴とはもともと秘密の符牒のようなものであった。そしてこの秘密の符牒が不可知で神秘的なこと、宇宙の神秘への奥義の徴となり、ひとつの体系をなす時、既にシンボリズムはオカルティズムなのである。
<感想>
カッシラーの『シンボル形式の哲学』は、著者の死もあって結論が出ないまま終わっているが、ここにその結論に結びつく一つのヒントがあるように思う。つまり、シンボルとは宇宙と人との間を結びつける符牒であり、人はシンボルを通して宇宙の摂理を知る。
そして、そのシンボルは何かといえば、たぶん自然の中に普通に存在しているが、普段の生活から人が意識することがないものだと思う。それを一般的な言葉で表現することは難しい。可能なことは、詩的文学的表現でその周辺をなぞるだけだ。あるいは、視覚的芸術や聴覚的芸術によって、そうしたイメージを喚起させることだろう。
そのシンボルを意識し、また宇宙との対話の架け橋だと自覚することが、禅でいうところの「大悟する」ということではないだろうか。また、大悟するための手段(方法)として、つまりこうしたシンボルを意識できるように、あるいは感知できるようになるものは、「無心になること」だと私は考えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
