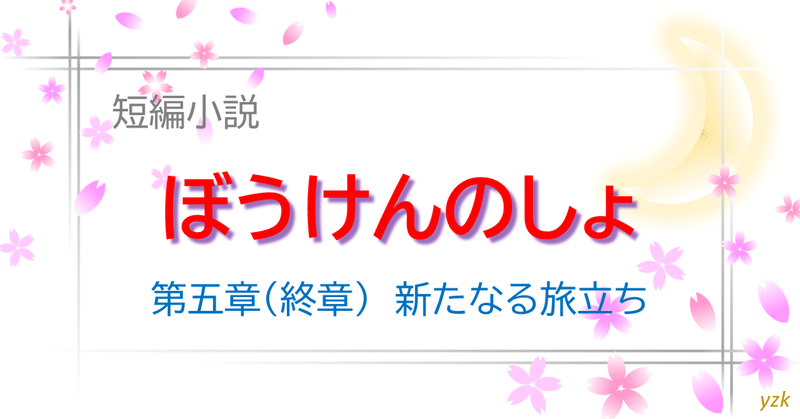
【短編小説】ぼうけんのしょ 第五章:新たなる旅立ち(最終回)
※これまでの物語は、こちら↓
第五章(終章) 新たなる旅立ち
魔王は昔話を始めた。
先の戦争、つまり、戦士が隣国の女性たちを騙して慰安所という名の性虐待所に連れて行った、あの戦争のとき、魔王は家族とともに征服地で暮らしていた。魔王の一家は、国が斡旋してその征服地に送りこんだ開拓民だった。周囲には、同じような開拓民がたくさんいて、いくつかの村ができていた。
国が戦争に負けると、開拓民を守るはずの軍はあっという間に国へ逃げ帰り、魔王たちのような一般住民は取り残された。
その土地に戦勝国である北方国の軍が進駐し、それまで征服されていた現地民とともに略奪や虐殺を繰り返した。後ろ盾を失った開拓民たちは、なすすべがない。
「あるとき、集落のリーダーだった男が北方国軍の幹部と交渉した。軍の将校に若い女を差し出すから、兵士や現地民の暴虐を取り締まって守ってくれ、とな。私はちょうど二十歳だったが、選抜された中には私より一つ二つ年下もいた」
数人ずつが交代で毎晩、北方国軍の施設に行かされた。施設といっても粗末な掘っ立て小屋で、床に少女たちが並んで寝かされた。食事の相手や酌をするような平穏な時間はなく、ただ将校たちに凌辱されるだけだ。
「私より少し年上の、すでに夫のいる女たちは“接待係”から外された。なぜだか分かるか? 彼女たちは夫である男の所有物で、夫に貞操を誓ったからだ。村のリーダーたちは、そんな女を敵国に差し出して、夫である同胞の男たちの体面を傷つけるわけにいかなかったのだよ。私たちは未婚で、つまりまだ誰のものでもなかったが、父親の所有物ではあった。だから、“接待係”として差し出すメンバーを選ぶとき、説得されたのは私たちではなく父親たちだった」
当番の夜、魔王のとなりに年下の少女が寝かされたときは、その日の地獄が終わるまで、少女の手を握っていてやった。そして、子どもの頃から一緒に歌ってきた故郷の歌を口ずさんでやったのだという。
「私は、何をされても絶対に泣き叫ばなかった。それが気に食わなかったのだろう。一人、ことさらサディスティックな奴がいてな。私は生まれつき、左手がこうなんだが」
魔王はマントから左手を出して見せた。その手は、中指と小指が欠損しており、指が三本だけだった。
「そのサディスティックな奴が、それじゃあ左右のバランスが悪いと言って、右手の中指と小指を切り落とした」
右手も出して、勇者に見えるように差し出す。左手と同じように、指が三本しかない。しかし、同じようにといっても、先天性の欠損と、あとから暴力で痛めつけられ奪われたのとでは、意味がまったく違う。
勇者は思わず左手で口を覆った。
魔王は淡々と語る。その淡々さゆえに、かえって勇者は魔王から流れ出る憎しみに取り込まれそうになるのを感じた。
右手でゆうしゃのつるぎを握り締め、切っ先を魔王に向けたまま、いったい自分は、なぜこんな話を聞かされているのだろう。
魔王はテーブルに置かれたティーポットからカップに茶を注ぎ、「飲むか?」と聞いてくる。無言で首を振った。毒が入っていないとも限らないし、悠長にお茶を飲む場面でもないだろう。
「略奪も虐殺も減った上に、食料や身の回りの品も少ないながら提供された。私の父親は抜け目のない人間でな、裏で相手方と取引して、村へ施される品々の他に、こっそり懐に蓄えていた。私は当番の回数が多かったが、おそらく父と敵の将校とで密約でもあったのだろう。私が将校たちに差し出されたのは、集落の人間たちを守るためだけでなく、父親が私腹を肥やすためでもあったのだよ」
魔王はティーポットとカップの絵柄をうっとりと眺めるように、目を細めた。ポットもカップも、白磁に大きな薔薇が絵付けされている。
「開拓地にとどまっていた間は、集落の人間に腫れ物に触るように扱われたが、感謝もされた。当然だな。私たちのおかげで生き延びたのだから」
ところが、一年近く経ってようやく帰国が叶うと、状況は一変した。心を殺して集落を守り抜いた魔王たちは、中傷にさらされたのだ。事情を知らない外部の人間ではなく、まさに“接待係”の女性たちによって守られていた同じ集落の人間たちが、彼女らを蔑み、二重にも三重にも痛めつけた。
曰く、「あの女どもは敵の将校に身を売っていい思いをした」「男たちが戦って大勢死んでいった中で、ちょっと体を提供したくらいで減るもんじゃなし、でかい顔するな」「外国の大男と交わるなんて貴重な経験できてよかったじゃないか。どうせ、自分だって喜んでたんだろうよ」云々……。
「私たちはまだ二十歳そこそこで、世間というものを知らなかった。国へ帰れば、裕福な暮らしはできなくても、開拓地でともに苦労した仲間たちに労られ、生涯感謝されるだろうと思っていた。まさか、命を繋いでやった人間たちに蔑まれ、後ろ指を指されるなどとは思いもしなかった。とんだ甘ちゃんだったな」
魔王は、ふん、と過去の自分を鼻で笑った。
「将校どもにいいようにされている間、私が手を握ってやった年下の子は、国へ帰って一年もしないうちに自殺した。私は……ご覧の通りだ」
言いながらマントのフードを脱ぎ、顔の下半分を隠している黒いマスクも外した。
おそらく40歳を少し過ぎたくらいだろうが、髪は一本残らず真っ白だ。そして、顔の左側の頬から鼻、口、顎にかけて、火傷したようにひどくただれている。
魔王はティーカップのお茶を一口飲んだ。
シャープな輪郭に、アーモンド型の目と通った鼻筋。白い髪と顔の火傷があっても、それ以前の顔立ちが想像できる。若い頃から器量が良かったのだろう。魔王が美しいからこそ、北方国の将校は父親との取引に応じたのかもしれない。
「この顔の傷は、国に帰ったあと、開拓地の集落で近所に住んでいた男から酸をかけられた痕だ。命惜しさに敵国の男と寝るような女に、きれいな顔は似合わないとさ。命惜しさに、同胞の女を敵国の男におもちゃとして献上した奴が、そう言うのだよ。こんなに笑えることもあるまい」
魔王の口元が歪む。
「ところで、その頃、私の父は何をしていたと思う。私を道具にして蓄えた富を使い、最初は村を、次に都市を、気づけばいつの間にか国を牛耳り、しまいには王になった」
勇者は剣を落としそうになった。
愕然とした。
王宮で会ったときの、王の下卑た笑いを思い出す。
「父は、国王になった途端、私を城の地下牢に閉じ込めた。あいつにとって、私の存在は脅威だったのだよ。自分が何を元手に王の座を手に入れたのか、民に知られることを恐れたのだろう」
勇者は王を好きになれなかったが、あの爺は爺なりに国や世界の安寧を願ったからこそ勇者に魔王討伐を命じたのだと、信じ込んでいた。だが、実際は、勇者を使って自分の娘を抹殺したかっただけなのだ。
「地下牢での何日目だったか、髪が白くなり、それから私は強大な魔力に目覚めた。牢を抜け出し、国を脱出し、魔物の族長たちの力を借りてここに城を築いた。ここは、北方国の領土だ。かつて私たちを蹂躙した奴らは、私のことなど覚えてはいないだろう。奴らはここに魔王がいることを知っていながら、手も足も出せずにいる。まだ私の方から奴らに攻撃を仕掛けたことはないが、勝手に怯えているのだよ」
かつての将校たちは、自分たちの行いも、自分たちの慰み者でしかなかった異国の女のことも、きれいさっぱり忘れているに違いない。ましてや、その女が、山頂に魔物を従えて居座っている魔王その人であるとは思いもしないだろう。
「私は人間を滅ぼそうと思ったが、父の国で勇者が生まれたと聞いてな、会ってみたくなった。そのうち父が勇者を寄越すだろうと思った。案の定というわけだ」
魔王はまた一口、お茶を飲んだ。
「これで私の話は終わりだ。面白かっただろう? どうする、勇者よ。王の命に従い私を倒すと言うなら、相手になってやろう。あのケチな父でも、私の首を持って帰れば何かしらの褒美をくれるだろう。実際、私はまだ人間どもに何もしていないのだから、私を殺したところで世界は何も変わらないだろうが、勇者としての役目は立派に果たしたことになる。親の子殺しを代行しただけとは誰にもバレるまい」
もしも今ここで勇者がやられて全滅したとしても、何度も挑戦すれば、いずれは魔王を倒せるだろう。
しかし、魔王を倒して、だからどうだというのか。
そのあと、どうなるというのか。
魔王の言う通り、魔王を倒しても世界に平和が訪れるはずもない。ただ、自分が英雄として祭り上げられ、偽の物語を背負わされるだけだ。世界は相変わらず碌でもないまま回っていくだろう。
だが、魔王に背を向けて立ち去ったとしても、どうなるというのか。
偽の物語を放棄して、この碌でもない世界を漂い続ければいいのだろうか。髑髏の痣のある身体で。
「それとも、私と一緒に来て、本当の悪を討つか?」
魔王が自分の迷いにつけ込んでいるのは分かっていた。それでも、魔王について行くのもいいかもしれないとも思うのだった。
本当の悪とは、何だろうか。本当の悪と、本当の悪ではない悪に違いはあるだろうか。
もしかすると、世界を滅ぼすことになるかもしれない。あるいは、やはり途中で魔王との対決が避けられなくなり、どちらが死ぬことになるのかもしれない。
けれども、そうなったらそうなったで、かまわないではないか。
勇者は、魔王に向けていた剣を下ろした。そして、二つ頼み事をした。
一つは、戦士が騙して“慰安婦”にした隣国の女性たちを探し出し、何らかの償いをしたいということ。金銭的なことなのか、それとも他に何か手立てがあるのかは分からない。時間を巻き戻せない以上、本当の意味での償いなどできるはずもないのだが、とにかく探し出して何かをしなければならない。
二つ目は、あの貧しい漁村で出会った男の子を手元に引き取りたいということだ。あの子は古文書で予言された勇者ではないが、育つ環境によっては真の勇者になれるかもしれない。例えば、立派な漁師に。
「そうか。その男は、そんなことをしていたのか」
魔王は、絨毯に転がっている戦士を、汚い虫でも見るような目つきで睨んだ。
「分かった。女性たちは探し出して、何らかのことをしよう。だが、偽勇者をやらされている男の子を引き取ることはできない。私はもう、憎しみの渦の中にいる。そなたも、憎しみをすでに知っておろう。そのような我々のところに幼い子どもを巻き込むわけにはゆかぬ。然るべき者に預けて養育を任せることはできるかもしれないがな」
勇者は少々がっかりしたが、魔王の言うことも一理あるかもしれない。あの子の年齢なら、まだ、憎しみに浸からずに生きることを学べるかもしれない。だから、汚染してはいけない。
魔王は、壁に向かって右の手のひらをかざした。三本の指から、黄金の光が発せられる。三本の光が壁に円を描くように走ると、光に囲まれた部分が消失し、人が通れるくらいの大きさの窓が現われた。
「鳳凰を呼んでくれ。この山頂からふもとまで、一気に急降下しようぞ」
勇者は世界中を旅してきたから、たいていの場所に行ったことがある。つまり、たいていの場所に移動魔法で瞬間移動できる。というか、魔王だって、魔王であるからにはそれくらいできそうなものだが。それをわざわざ鳳凰を召喚しろというのは、もしや、絶叫系が好きなんだろうか。
ま、いいや。
勇者は聖なる鈴を鳴らした。どこからともなく七色の鳳凰がやってきて、窓の前で悠然と羽ばたく。
勇者は、仲間だった三人の死体を見下ろした。生き返らせてやろうかとも考えたが、MPがもったいないのでやめておく。三人の道具袋から貴重なアイテムだけ頂いて行くことにしよう。
「行くぞ」
魔王が声を掛け、窓を開けた。
そして、思い出したように振り返って尋ねる。
「そうだ、そなた、名前は何という?」
闇が世を覆う時、光もまた生まれん
左の小さな鍵の骨に髑髏をぶら下げし勇者
三つの光と共に立ち上がり
世に清浄と凪をもたらさん……
〈完〉
最後までお読み下さり、ありがとうございました。
以下、参考記事です。
作品を気に入って下さったかたは、よろしければサポートをお願いします。創作の励みになります。
