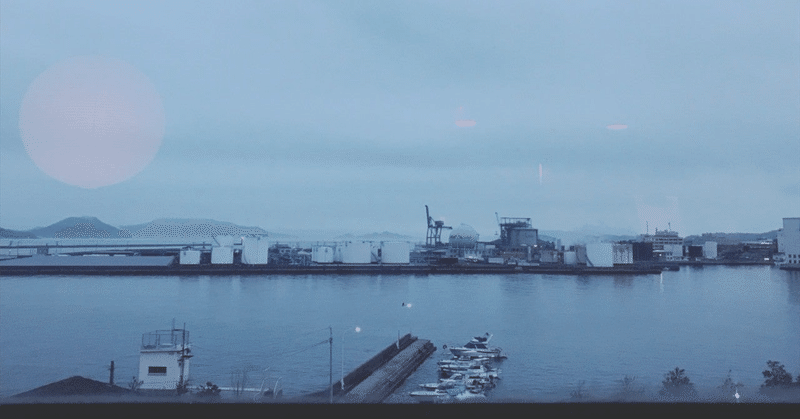
短編小説:港を眺める犬
普段は田舎で暮らしているから、都会に出るとそれだけで疲れてしまう。
行き慣れない都会での用事を終えた私は、寄り道もせず駅に向かった。その途中で大きなホール(所謂大規模な市民ホールというところだろうか)の前を通りかかったのだが、歩道に面した掲示板には、近々行われる芝居や演奏会のポスターがずらりと並んでいた。
いつもなら気にも留めないはずなのに、一枚のポスターが、はっと目を引いた。
そこに、君がいたのだ。
華やかな笑顔を浮かべる君が。
なんて、なんて明るい笑顔なのだろう。
最後に会ってから何年も経つというのに。少しも歳をとっていないどころか、若返っているようにさえ見える。
そういう事実が、私と君がもう二度と会うことはないと確信させるのだ。
君は、私の家が好きだった。
詳しく言うと、私の家の、二階の部屋から見える小さな港が好きだった。
舞台俳優を目指していた君は、オーディションに敗れるたびに港のベンチに座り込んでいた。私の散歩道に、この世の終わりのような顔で沈んでいるものだから、心配になって声をかけたものである。
「海を見ていると、少しだけ心が晴れる気がして。こんなに大きいから、きっと許してくれる、って」
とある寒い冬の日、やはり何の役も貰えなかった君は、マフラーに顔をうずめて言った。
「海は寛大ですからね」
君が沈んでいる時、私は君の言葉を肯定するようにしていた。
「そう、寛大。…でも、寒い」
君の頬と鼻は紅いのに、吐息は白かった。だから、だろうか。
「私の家から、この港よく見えるんですよ」
などと口走ったのは。
君は私を見上げた。
「ここよりは、あたたかいです」
私の言葉に、君は戸惑ったような笑顔を浮かべた。
君はすぐに私の部屋を気に入った。
「ここなら、雨の日も、寒い日も、港が見られますね」
「いつでも来て良いんですよ」
私が言うと、君は遠慮しなかった。
よく、思い付いたように私の家を訪れた。
「一部屋くらい。住んでもらっても良いくらいです」
実際、この広い家をひとりでもてあましていたから、君が住んでも良いと本気で思っていた。だからさりげなく、港が見える東の部屋は、いつも綺麗に整えていたものである。
「それは…」
君はその日、答えを出さなかった。
しばらく経って、君は犬のぬいぐるみを持ってきた。
「私はまだ住まないから、代わりにこの子に住んでもらいます」
港が見える窓辺に、その犬を置いた。
明るい茶色の、耳がぴんと立った瞳の綺麗なその犬は、どこか君に似ていた。
そんな日々がずいぶんと続いた。そんな日々というのは、私はのんびり、海を眺めながらぬいぐるみの犬と暮らし、君はオーディションを受けては、結果を出せず、私の家に来る、という日々だ。
穏やかな不安をほんのりと抱くそんな日々は、あまりにも心地が良かった。君もそうだと思っていた。
しかし君は、ある日突然、姿を消したのである。
私はいつも、君が気まぐれに訪れるのを待つばかりだったから、君を探す方法を知らなかった。何もできなかった。風の噂で、君はある寒い日の朝早く、港から出る船に乗ってどこかに行ったのだと聞いた。
しばらくは、また君が気まぐれで帰ってくると信じていた。東の部屋を整えて、犬に港を見せていた。
それでも、何ヵ月も経つと、私は待つのを辞めた。あの部屋を使うのは何だか気が進まなくて、月に一度、掃除をするほかは入らなくなった。
あたたかいと言うよりも、暑いと言う方がふさわしくなった頃、君から手紙が届いた。真っ白な封筒に、私の住所と名前が書かれていた。君は、こんな不器用な字を書くのかと初めて知った。
私は、封筒を開けなかった。
君のどんな言い訳も、受け入れられる気がしなかったのだ。
封をしたままのそれを、窓辺の犬の下に敷いた。そうするとなおさら、その部屋に入るのは億劫になった。うっすら埃が溜まるようになれば、悪循環は加速する。あの部屋はもはや『開かずの間』だった。
それから、君のことは、覚えているような、忘れているような、曖昧な意識の下に追いやっていた。
しかし、何年も経った今、芝居のポスターの隅で弾ける君の笑顔が、当時の記憶を激しく呼び戻したのである。同時に、封をしたまま置いた手紙のことも。
今なら、君のどんな言い訳も受け入れられるだろう。
家に着いた私は、まっすぐあの部屋に向かった。
埃まみれで、蜘蛛の巣も見えるそこに、犬と、手紙は相変わらずいた。日に焼けた犬は少し色褪せていたが、ビー玉のような目は変わらずらんらんとしている。
真っ白だった封筒は、犬の影を残し、どこか黄ばんでいるような気がした。埃が積もったままの椅子に座り、港が見える窓の前で、封を切る。君からの短い手紙。不器用な字が並んでいた。
--突然いなくなって、ごめんなさい。
茶色っぽいインクは、もともとそういう色なのか、褪せてしまったのか。
--でも、どうしてもあなたを、驚かせたかった。
--実は、ようやくオーディションに合格したのです。せりふは多くないけれど、そこそこ重要な役だと思います。
合格したのか。いつも港でふさぎこんでいた、君が。
--今は毎日、お稽古をしています。とっても楽しいです。とっても楽しいけれど…。
そこで、数行空いている。
--足りないのです。寂しいのです。あの港と、あの部屋が恋しいのです。
--やっぱり私、あの港のそばで生きていきたい。だから、もしも、もしもあなたが許してくれるのなら、迎えにきてくれませんか。そしたら私、これっきりでお芝居をやめて、あの部屋に、帰りたいのです。
封筒には、とっくに日付の過ぎた芝居の券と、あの港から出る船の切符が入っていた。
私はしばらく、動けなかった。
港の向こうに、日が沈んでいく。
目を落とした先には、手紙の裏側。小さな字で何か書いてある。
--あなたに、会いたいのです。
私は、手紙や券を、丁寧に封筒の中へ戻した。埃まみれの部屋で、大きく息を吸う。
薄暗い港を眺めながら、私の脳裏に浮かぶのは、あのポスターで弾ける笑顔を浮かべる君なのだ。あの港で、ふさぎこんでいた君ではなく。
君のいるべき場所は…、言うまでもない。
私は封筒を窓辺に置き、その上に犬を座らせた。せめてお前は、ここから港を見守っていておくれ。
そっと撫でた犬の頭は、柔らかかった。
※フィクションです。
山根あきら様の企画『青ブラ文学部』に参加いたしました。初参戦です。よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
